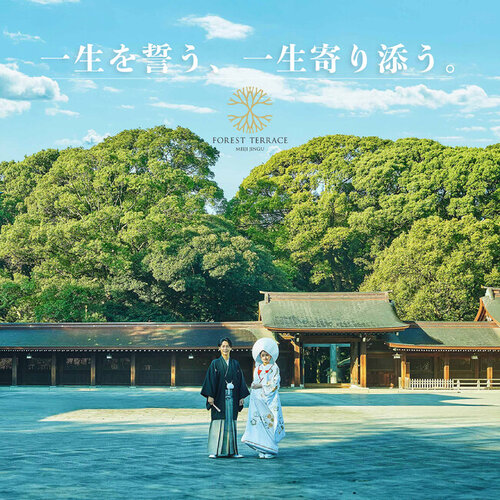《じょうずに頼る介護》家族や親族のいない「シングル高齢者」の気軽に頼めない「連帯保証人」「身元引受人」「緊急連絡先」は誰に?
2025年4月14日(月)12時30分 婦人公論.jp

入院の保証人、誰に頼む?(写真提供:Photo AC)
これからは〈自分介護〉の時代へ。2040年には、単独世帯が900万世帯に達するという予測があります。特に、65歳以上の単独世帯数の増加が推測されています。日本の家族構造は大きく変容して、これまで頼りにしていた家族相互助け合いシステムが崩壊しています。高齢者を包括的に支援/実践している団体「リボーンプロジェクト」が、介護の事例と、専門家のアドバイスを編集した『じょうずに頼る介護 54のリアルと21のアドバイス』より一部を抜粋して紹介します。
* * * * * * *
家族、親族のいない人の入院保証人は誰?
シングルの保証人:入院の保証人問題で「ん?」2度目の発作で「んん?」
「あっこは俺の姻族だっけ?」齢70を過ぎた立派な大人がなんて無知なのかしら、と明子さん(73歳)は思った。
「何言ってるの?姻族なわけないでしょ。私はあなたの先輩で、ミキの友人で大学の同窓生。赤の他人でしょ」
和明さん(72歳)が倒れて緊急入院した際、連絡先として明子さんの名前を書いたところ、看護師さんから確認されたのだという。
「ご家族ですか?」「いいえ」「ご親族ですか?」「いいえ」「じゃあ、姻族の方なんですね?」「そうかな」というやりとりがあったのだそうだ。和明さんは、姻族とは婚姻を結んだ相手の3親等以内の親族のことというのを知らなかったらしい。
姻族だって親族だから、看護師さんの質問も変なのだが……。明子さんは、誤解されたままでもいいやと思った。
というのも昔、友人から、同棲していた彼が入院するとき、保証人の欄に友人と書いたら「ご夫婦じゃないんですか?」としつこく聞かれ、事実婚にしたかったのに仕方なく婚姻届を出したという話を聞いたことがあるからだ。
いまだに入院の際は「家族保証」「戸籍主義」が幅を利かせていることに明子さんは驚いた。
和明さんの病気は「心不全」だった。妻のミキさんを亡くしてから5年、男一人の生活は不摂生そのもの。寝たいときに寝て、起きたいときに起きる。
食事もコンビニ弁当で済ませたり、ビールに少々のつまみでおしまいにしたり。不健康になるのも無理はないが、心不全とは驚いた。
即入院。投薬治療の後は、循環器リハビリで生活改善の日々を送ることになったのだ。
退院後の生活改善と人生の後始末
退院後の喫緊の課題は生活改善だ。まずは介護申請をして要支援2をもらい、食生活の改善には宅配のお弁当を頼み、週1回のデイサービスでリハビリを継続することにした。
警備会社のシステムを利用して安全確認契約を結び、自宅マンションで倒れたときの備えも万全、だったはずなのだが……。
「宅配の弁当を受け取るのが面倒でねえ。毎日、1階の玄関ドアを開けるのが負担で断ってしまったんだよ。自由に出かけられなくなったから」
マンションはオートロック方式で、お弁当を受け取るためには在宅して玄関ドアを居室から開ける必要がある。
そのために外出時間が制限されるのがどうにも我慢できなかったようだ。この頃まではどうにか近くのコンビニまでは足を運べていたが、だんだん億劫になっていった。
そしてとうとう2度目の発作を起こしてしまう。ほんの50メートルの距離を歩き切れず、道端にしゃがみこんでしまったのだ。
「以前入院していた循環器の専門病院に駆け込んで、もう1度入院させてもらおうと思ったんだけど、断られてしまったよ」
要介護生活と、人生の後始末を考える
2024年の4月に始まった「医師の働き方改革」の影響で、アルバイトやパートの医師が補充できなくなったため、近隣の病院の循環器内科が軒並み診療を中止。
和明さんの主治医のいる病院に患者が殺到し、とうとう新規の入院を受け付けられなくなったという。
「驚いたね。世の中とは無関係に生きたかったけど、そうはいかないことを思い知らされたよ。遅ればせながらこれからの要介護生活と、人生の後始末をまじめに考えようと思った」
なんとかなるさで暮らしてきた和明さんだったが、やっと重い腰を上げて行く末を考える気になったようだ。
友人たちも年をとり、あちこち不調で頼りにならない。親戚付き合いも避けてきたし、後を託す親族もいない。
「確か、亡くなった姉の息子がいたはず。初めて連絡を取ってみようかと思ったけど、ほとんど初対面の甥に何かを頼むのも違うかなと思うしね」
まずは、入院できる病院探しから始めて、一人暮らしが難しくなったときのための施設探し、自宅マンションの売却、残った財産の遺贈先探し、死後の後始末を誰に託すか……。やることは山積みだ。

入院や介護になった時に、不便をかこつことに(写真提供:Photo AC)
入院時の連帯保証人と身元引受人
専門家のアドバイス:入院、介護を前提に思い立ったが始めどき。まずは緊急連絡先を決めておこう
自由気ままな一人暮らしを謳歌していた人も、いざ入院、介護となると、がぜん不便をかこつことになる。
ほとんどの病院では、入院の際に「連帯保証人」と「緊急連絡先」や「身元引受人」の記入を求められる。
連帯保証人は、万一入院費用が支払えない事態に陥ったときに代わりに支払ってくれる人で、「患者と生計を一にしない支払い能力のある成人」という条件がついていたりする。つまり、同一生計だと、同居の家族は連帯保証人にはなれないということだ。
一方、身元引受人や緊急連絡先は、「不幸にも本人が亡くなったときに遺体を引き取ってくれる人」という意味があるので、妻や夫や子ども、親やきょうだいなど家族の名前を書くことが多かったが、親族のいない単身者が増えてくると、病院では誰に頼めばいいのか迷ってしまう。
病院によっては、患者本人以外に手術の同意書へのサインを求めることがあるかもしれない。手術中の急変など、いざというときの救命措置、延命措置への判断を即時に求められることもあり、友人に気軽に頼めるものでもない。
しかしこれらは、院内ルールとして慣習的に行われていることで、厚生労働省は「身元保証人等がいないことのみを理由に入院を拒否することは、法律(医師法第19条第1項)の規定に抵触する」という旨の通達を出している。
治療を受ける権利は患者本人にあり、医療機関は治療する義務があるということだから、たとえ家族、親族であっても、患者本人の意向に反して手術同意や救命措置の判断ができるはずはない。
ましてや、身元保証サービス会社と金銭契約を結んでお任せにする類のルールでもない。
※本稿は『じょうずに頼る介護 54のリアルと21のアドバイス』(太田出版)の一部を再編集したものです。
関連記事(外部サイト)
- 《じょうずに頼る介護》配偶者と死別、未婚、子無し、きょうだいも少ない…、2040年には「単独世帯数」が900万世帯に。「自分を救うのは自分だけ」という時代
- 相続はしたものの持て余す実家…。「空き家対策」に先延ばしは厳禁。体力、気力のあるうちに情報収集と決断を
- <ここには隠しカメラがあるの>老人ホームの入居者が気づいていた秘密。知らないはずのことを知っていた施設長は笑顔を見せて…
- 70代女ひとり、母の介護施設を振り返る。罵声をあびせる認知症患者と穏やかに話す介護職員。彼女は元ホステスだった
- 「子どもに下の世話はさせたくない」と言っていた親の気が変わることも。それでも「家族の介護をやってはいけない」と介護のプロが断言する理由