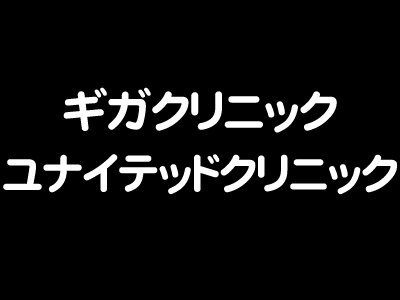瀬戸内にたたずむ“本州最後のナゾの途中駅”「児島」には何がある?
2025年5月5日(月)7時0分 文春オンライン
日本のいいところは、よほどの飛行機嫌いでも日本中あちこちを旅できることだ。沖縄など離島部はさすがに難しいが、本州・北海道・四国・九州にはおおむねくまなく鉄道ネットワークが張られている。
たとえば、四国。東京駅から新幹線「のぞみ」に乗れば、3時間20分ほどで岡山駅に着く。で、そこから瀬戸大橋線の快速「マリンライナー」に乗り継げば高松へ、また特急「しおかぜ」なら松山、特急「南風」なら高知まで。
四国に限らず、国内の主要都市のほとんどは東京駅から多くても3〜4回ほどの乗り換えで行くことができる。アメリカやロシア、中国といった広大な大陸に国土を持つならともかく、日本のような島国ではなかなかスゴいことなのではないかと思う。
いや、もちろん飛行機と比べたら時間がかかりすぎるといった問題はある。けれど、できる限り飛行機は避けたいという人も一定数はいるわけで、そういう人たちも安心して旅できるということは、やっぱり日本はいい国なのである。
さて、ここで四国の話に戻ろう。といっても、今回の目的地は四国ではなくその手前、児島駅だ。

岡山駅から瀬戸大橋線に乗り換えて20分ほど、いざ瀬戸大橋を渡らんとするその直前、つまり瀬戸大橋のたもとにあるのが児島駅である。この駅を出たら、あとは瀬戸内海を渡って四国に上陸するから、本州最後の駅でもある。
“本州最後の駅”「児島」には何がある?
で、この児島駅、言うなれば四国に行く途中、気がつけば通り過ぎてしまうような存在だ。ところが、快速「マリンライナー」はもちろん特急「しおかぜ」「南風」、そして寝台特急「サンライズ瀬戸」までご丁寧に停車するのである。
そして、これがまた意外とお客の乗り降りが多い。岡山発の各駅停車も、児島行きが大半。と、まあなかなかに気になる存在なのだ。
そういうわけで児島駅にやってきた。開業したのは1988年、瀬戸大橋の開通と同じ年。そもそもこの区間の線路は瀬戸大橋を渡るために建設されたものだから、まるで新幹線でも走りそうなくらいに立派な高架線になっている。
児島駅も高架の2面4線、目隠しして連れてこられたら、新幹線がやってくると勘違いしてしまう人もいるかもしれない。それくらい、立派な駅だ。
高架の下の改札を抜けて西口に向かう。駅前広場に出ると…
新幹線によく似ているのは、駅だけではない。高架の下の改札を抜け、駅の西口に出たらここもまたまるで新幹線駅の駅前広場。
何があるわけでもなくとにかくだだっ広い駅前広場。目の前の通りを渡った先には駅前広場と地続きのような公園があるし、よく区画整理された道はどれも幅が広い。
駅前広場を挟むようにエディオンとヤマダデンキというふたつの家電量販店が並んでいるあたりは興味深いが、どちらも大きな駐車場を備えている。
反対の東口。こちらには駅前広場はなく、目の前がすぐに国道430号。「マリーン通り」と名付けられた国道沿いには観光港があるほか、ローソン、ジョイフル、かっぱ寿司、コメダ珈琲、そしてパチンコ屋。
駅を取り囲むように駐車場がたくさんあって、このあたりも新幹線の駅とよく似た特徴だ。
いずれにしても、悪くいえば殺風景、無難な言い方をすれば人工的、少し前向きな捉え方をすると真新しい。そういう、新幹線の新しい駅前とまるでそっくりな風景が、児島駅前には広がっている。
事実、この児島駅周辺は1988年の児島駅開業と瀬戸大橋線の開通にあわせて開発された一帯だ。国道にはマリーン通りといういかにもといった名が与えられ、駅周辺の地名は「児島駅前」。
古い地図や航空写真を見ても、児島駅があるあたりはまったく何もなかったことが一目瞭然だ。まさに、児島は瀬戸大橋とセットで生まれた新参の町といっていいのかもしれない。
駅前から離れ西に向かう。公園を抜けると様子に変化が…
が、いくら駅の開業から40年近く経ったとはいえ、瀬戸大橋一本槍の駅では特急の停車駅になろうはずもないし、お客の乗り降りもこれほど多くはないはずだ。そこで、駅前から少し離れて西に向かって歩を進めてみよう。
すると、駅前の児島公園を抜けた先、南北に通る鷲羽山通りを越えたあたりから少しずつ様子が変わってくる。
鷲羽山通り沿いには中学校やドラッグストアといった施設が並び、その脇を抜けると開放感のある駅前の風景が一変、細い路地に古い住宅などがひしめくようになるのだ。
その中には、かなりの違和感を放ちながら、というかどうしたって廃線跡にしか見えない遊歩道もあった。遊歩道の脇は道路になっていて、その道沿いには昭和の商店や旅館のような建物も並ぶ。
どうせ遊歩道になっているのだからと廃線跡を北に辿ると、覆いが被さってホームのような施設も残された、つまりは廃駅へ。
そこを抜けた先には、先ほど見た児島駅前からすると二回り、三回りくらい規模を小さくしたような広場があった。きっと、件の廃駅の駅前広場だったのだろう。
幻の駅前広場の向こうにはずいぶん“ブルー”な光景が…
幻の駅前広場の向こうには、倉敷市の児島市民交流センターがあって、傍らの広場の端っこには瀬戸大橋で用いているケーブルがオブジェとしておかれていた。瀬戸大橋のたもとの町だけに、こうしたアピールにもぬかりなし、といったところか。
交流センターの西側に目を向けると、実に昔ながらの昭和の商業エリアといった町が待ち受けていた。飲食店など古い商店が並び、角には大きなジーンズをかたどったオブジェが掲げられている。
その道に入ると、ビッグジョンの児島本店。突き当たりの通りは頭上に吊るされたジーンズがはためく「児島ジーンズストリート」だ。
微妙にクネクネと曲がっているジーンズストリートには、小さいながらも洗練された雰囲気のデニム専門店が軒を並べる。
そんな店々を冷やかしながら散策している人も何人か。どうやら観光客向けの一角のようだから、彼らは地元の人ではあるまい。ジーンズストリートを中心としたこのエリア、いわゆる“デニムの聖地”のような位置づけになっているという。
ジーンズストリートの北の端には、かつてこの地で塩田を営んで財を成したという野崎家の邸宅が文化財として残っている。ジーンズストリートと並ぶ児島の観光スポットなのだろう。ちなみに、駅近くからこの昔ながらの市街地へと続く道は野崎家の当主・野崎武左衛門にちなんで武左衛門通りと名付けられている。
ともあれ、児島駅前から少し離れた廃線と廃駅を囲むこの一帯は、駅前とはまったく違った昔ながらの市街地なのである。そして、実は……などと振りかぶるまでもなかろう、ここが古くからの児島の中心であった。
あの廃駅が「児島のターミナル」だった頃
例の廃線跡は下津井電鉄というローカル私鉄で、廃駅は下津井電鉄の児島駅。1988年に瀬戸大橋線の児島駅が開業するよりずっと前から存在していた、元祖・児島のターミナルである。
なんと開業は1913年。そのときは、周辺の地名にあわせて「味野町駅」と名乗っていた。この下津井電鉄児島駅を中心に、児島、また味野の市街地が形成されたというわけだ。
古く、児島は陸続きではなく瀬戸内海に浮かぶ正真正銘の島だった。それが江戸時代初めに岡山と陸続きになって、さらに干拓事業も進められてゆく。
ところが、干拓で生まれた土地は塩気が強くておよそ稲作などには不向きであった。
そこで、土地をそのまま塩田にする一方で、塩にも強い栽培作物として綿花が盛んに栽培されるようになる。
そうして塩田では野崎家が財を成し、また綿花栽培ではそれに紐付く繊維産業が盛んになった。これが、児島の町の成り立ちである。
江戸時代には足袋や帯地、真田紐などを製造していた児島だったが、明治に入ると紡績工場が進出して工業化。その後は日本有数の機業地に成長し、学生服の製造で日本一のシェアを誇っていた時代もあるという。
しかし、戦後になると学生服の素材が綿から合成繊維に変わり、児島の繊維業も厳しい局面に立たされる。そこで目をつけたのが、デニムだった。
1960年代半ば、児島は日本で初めて国産ジーンズを製造する。はじめはアメリカから輸入したデニム生地を縫製したものだったが、のちに生地の製造から手がけるようになり、すっかりジーンズの聖地へと成長していった。児島は、ジーンズ日本一の町なのである。
1988年、瀬戸大橋の開通。1990年、下津井電鉄廃止。そして…
一方で、児島は瀬戸内海の真ん中という地理的条件もあって、古くから交通の要衝でもあった。
児島半島の南西、下津井港は江戸時代には西廻り航路の寄港地で、また本州と四国を結ぶ航路の拠点になっている。下津井電鉄は、そうした要の港とかつての国鉄宇野線・茶屋町駅を結ぶ鉄道として開業したのだ。
瀬戸大橋が開通する頃になると、いささか事情は変化する。かつての塩田跡に設けられた瀬戸大橋線児島駅が新たな地域の玄関口となり、駅周辺の開発が進む。
それと共に、旧中心市街地は衰退傾向になってしまった。役割を失った下津井電鉄も、1990年末をもって廃止になった。
そうした中で、2009年には“ジーンズの聖地”として存在感を高めるべく、ジーンズストリートが誕生する。長く地域を支えてきた繊維産業が、またいまでも地域の要を担っている、というわけだ。
こうして、さまざまな歴史が交錯する現在の児島の町ができあがったのである。
古代から続く“特別な場所”「児島」を見下ろす“ヤバい場所”
実は、児島地域は古代より特別な存在として認識されていた。
というのも、『古事記』には伊邪那岐命と伊邪那美命は大八洲を生んだのち、続けて吉備の児島を生んだといったことが書かれている。『日本書紀』では、児島は大八洲に含まれており、いずれにしても古代の日本でも重要な位置づけの島だったのだ。
まだ岡山と児島が陸続きではなかった頃、瀬戸内海の真ん中に浮かぶ巨大な島・児島はあらゆる意味で存在感があったのだろう。
瀬戸内航路では児島を避けては通れず、源平合戦の舞台にもなったという。また、陸続きになってからは、塩田と綿花栽培、四国への玄関口として名を成した。
そういうわけで、こうした児島の町をただ通り過ぎるだけでは少々もったいないのではないか、と思うのである。デニムが好きでもそうでなくても、少し途中下車して駅の周りを歩き回ってもバチは当たるまい。
もし、もっと本格的なレジャーを楽しみたければ、山の上の遊園地、「鷲羽山ハイランド」に足を延ばしたっていい。ずいぶん昔、一度だけ行ったことがありますが、なかなかハイレベルの絶叫マシンが揃っていますよ……。
写真=鼠入昌史
(鼠入 昌史)