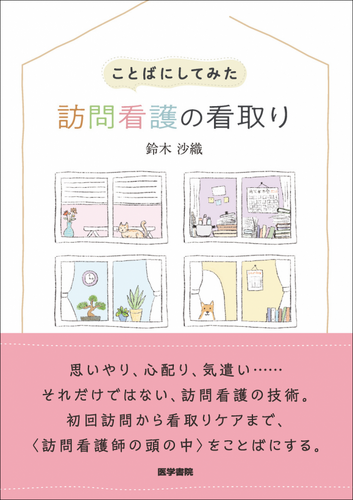83歳のパワフル訪問看護師、故郷の山村で介護事業を拡大。後方支援してくれていた夫が認知症になり、くじけそうになったけれど…
2025年5月5日(月)12時29分 婦人公論.jp

元春さんのハーモニカコンサートは、すみかの入居者から大人気(撮影:藤澤靖子)
長野県のとある山間部に、一人の女性が立ち上げた介護施設がある。介護というとネガティブなイメージもあるが、ここでは毎日笑い声が絶えない。その明るさの秘密は、一体どこにあるのか。施設を開所した当事者であり、現在も訪問看護師として働く江森けさ子さんを訪ねた(撮影:藤澤靖子、寺澤太郎)
* * * * * * *
<前編よりつづく>
病に倒れて気づいた「今」を楽しむ大切さ
地域で医療系のケアマネジャーを望む声が高まったことから、江森さんは04年に在宅介護の相談やケアプランの作成を引き受ける居宅介護支援事業所を開設した。
08年にはグループホーム「すみか」を開所するなど、「5年で終わり」どころか、介護事業はさらに拡大していく。
「すみかを始める時、周りには『また夫婦で大変な仕事をやるだかい』という声もあれば、『ボケ老人集めて、金稼ぎするつもりだかい』という声もありました。それも当然だと思う。私たちみたいな年金生活者が故郷に帰って事業を始めようなんて、普通ではないですからね」
しかし、四賀の認知症の高齢者は右肩上がりに増えていた。在宅介護に苦しむ家族や、当事者が不安から引き起こす行動を見るにつけ、「認知症の人たちが家族のように暮らせる居場所」が必要だという思いは、ますます強くなったという。
故郷に戻って以来、介護の経験をそれなりに積んできたつもりでも、すみかの開所当初は緊張の日々だった。
「新しい環境におかれた不安で取り乱す人や、スタッフに暴言を吐いて噛みつく人……。私も心配で職場を離れられなかったし、夜の様子を知りたいからと夜勤にも加わりました」
そうして入居者一人ひとりの状況を把握し、スタッフと支援の方法を統一する。たとえば、認知症で不安が強く、耳も遠いため会話が成立しにくい当時88歳のあきさんの場合はこうだ。
「合図のために肩をポンと叩くだけで、『何するだー』と大声で怒鳴る。でもそのうち、大声を出すのは、何をされるかわからない不安と緊張から来る自己防衛とわかってきて。
必ず顔を見てゆっくり話すなどの配慮を続け、だんだんと平穏に暮らせるようになったのです。これは紛れもなく、《人の力》でしかできないことだと感じました」

峠茶屋では、スタッフが見守りながら自然の中の散歩も楽しむ(撮影:寺澤太郎)
もう一つ江森さんが大事にしたのは、相手への敬意を忘れないこと。すみかでは、施設で出す料理の準備を入居者にも手伝ってもらっているのだとか。「もともと働き者で、仕事がないと生活に飽きがきてしまう皆さんですから、手仕事をすると生き生きしてくるの。山菜や野草の下ごしらえなんて、見事なものですよ」と、江森さんは嬉しそうに笑う。
そうした経験をもとに、笑いあり涙ありの人形劇を創作し、認知症を正しく理解してもらう出前講座も各地で300回以上開催。地元紙でコラムの執筆も始めるなど、活動の幅も広がった。
そんな江森さんに転機がやってきたのが、71歳の時。突然、強いめまいに襲われた。脳腫瘍だった。10時間に及ぶ手術は無事成功し、幸い後遺症も残らなかったが、心には大きな変化があったという。
「私が長く看護の仕事をしてきてよかったと思うのが、人を生物学的に見て『いつか必ず死ぬ』と客観的にわかっていたこと。実際に自分が病に倒れ、『いつ死ぬかわからない』という覚悟もできた。
ですから私、高齢者の前でも平気で『今晩寝たら、もう目が覚めないかもしれないよ。だから今日を楽しく生きないとね』なんて話ができる。言われたほうも、『ああ、そうだいね』と納得してくれます(笑)。毎日、笑いの中で『死への準備教育』をしているんです」
自分が死と向き合った経験から、「看取り」ができる場所を作りたいという思いも湧いてきた。そして闘病から2年後の14年、デイサービスの移転に伴い、自宅前の土地に住宅型有料老人ホーム「にしきの丘」を開所。
同じ敷地内に、デイサービスと訪問看護ステーション、ヘルパーステーションも併設した。自宅近くに施設を集約したことで、利用者や入居者とのコミュニケーションもより密に。
見学させてもらったにしきの丘では、江森さんと100歳の女性が手を取り合い、しみじみと言葉を交わす姿が心に残った。
近年は、少子高齢化と過疎化が進む地域の高齢者のケアを続けていくために、後継者へ事業の権利を承継することも進めている。江森さんが務めていたNPOの事務理事職と夫・元春さんの理事長職は、峠茶屋のメンバーが受け継いでくれたという。
「ありがたいことです。介護保険制度が変わり、峠茶屋のような小規模の介護事業所はどんどん経営が厳しくなっているので。新理事長を始め、皆さん本当にがんばってくれていますよ」

真剣な眼差しでフキの下ごしらえをする、すみかの入居者たち(撮影:寺澤太郎)
曲を間違えても気にしない
江森さんはつねに、仕事用とプライベート用のスマートフォンを肌身離さず持ち歩いている。現在も週5日は峠茶屋の事務所に出勤し、訪問看護師として利用者の健康管理にも対応するためだ。プライベートでは、松本市内に住むシングルマザーの長女一家をサポートしている。
「娘は乳がんの既往があるうえ、職場まで片道1時間かかる。だから3人の子どもの面倒をみるのは大変。真ん中の子は自閉症を抱えているので、朝は私が娘の家に行って孫の学校の支度をさせ、スクールバスに乗せるまでを担当しています。
その養護学校が素敵でね。孫もいろんなことができるようになったし、学校の子どもたちの笑顔を見るのも私の癒やしなの!」
そんなふうに人生の山あり谷ありを明るく語ってくれる江森さんだが、「実は今、人生で一番落ち込んでる。八方ふさがり。初めてよ、こんなピンチ」と声を落とすのだ。
視線の先には、夫の元春さん。企業で長く総務や経理を務め、「どんぶり勘定でおおざっぱ」という江森さんの介護事業を、ずっと後方支援してくれていた。それが数年前から目と耳の衰えを感じ、運転免許証を返納。

すみかでは80代の調理スタッフも元気に働く(撮影:藤澤靖子)
また、24年に事務所のすべての役割から退いた頃から、認知症の初期症状が表れ始めた。この日、元春さんが打ち合わせからずっと同席していたのも、江森さんの姿が見えないと不安になってしまうからだという。
「私は仕事柄、夫の頭の中がどうなっているかわかるでしょう。だから先走って、あれは危ない、これはダメって言いたくなる。出かける支度など、今まで10分でできたことが20分かかると理解していても、つい『早くして』とドアの前で足踏みしちゃう。
ああ、認知症の方の家族はこういう生活を送ってきたんだと。これまで当事者でもないのに偉そうなことを言って、申し訳なかったと思います」
もちろん、経験が役立つこともある。たとえば、今日の日付がわからず時間の感覚も薄れてきた元春さんのために、巻物状のカレンダーを作って、「病院の受診」「雑誌の取材」など大きな予定だけ書き込む。
「それ以外に、私と夫の一日のスケジュールも1枚の紙に書き出し、《見える化》しています。でも3時から外出と書いたら、時間ぴったりに荷物を背負って待ってる(笑)。予定が変わると混乱してしまうので、どんなに忙しかろうと私も予定通りに行動しないといけないの」
最初に渡された細かい予定表には、そんな背景もあったのか——と考えていた時、江森さんのスマートフォンがピピピと鳴った。どうやら訪問看護の利用者さんの容体が変わったらしい。
江森さんは「ごめんなさい。3時になったら『すみか』で『ハーモニカ』ですから」と事務長の木村さんに言い残すと、駐車場へと駆け出して行った。
ハーモニカとは、元春さんが小学校1年の時から続けてきた趣味。それを峠茶屋やすみかのお茶会などで演奏するのが、長年の楽しみだった。その習慣は、認知症を発症した今も変わらない。元春さんは、ハーモニカを吹くことが生きがいだと、照れくさそうに話してくれた。
しかし移動の支度をしながら、元春さんが「僕は操り人形のピエロなんですよ」とぽつり。木村さんが「えー、昨日はけさ子さんに感謝してるとおっしゃっていたじゃないですか」と返すと、「感謝はしつつ、でも踊らされてる」。そんなつぶやきにも、元春さんの不安ややるせなさが感じられた。
会場の食堂には、三々五々、入居者の皆さんが集まってくる。83歳のきよ子さんは、お茶の時間に合わせて服を着替えるおしゃれさん。「ここでの生活はとても楽しいわよ」と、笑顔で教えてくれる。
89歳のみねこさんは、スタッフを手伝って除菌スプレーと布巾でテーブルを拭いて回る働き者だ。皆のお茶の準備まで率先して行う。
そして入居者9人の観客を迎え、元春さんのステージが始まった。唱歌の「お正月」や「早春賦」の懐かしいメロディが流れると、皆さん手でリズムを取る。先ほど声をかけた時は会話がおぼつかなかった人も、きれいな声で一緒に歌っている。「ふるさと」では涙を流す人もいた。
元春さんは、リクエストされた「里の秋」をとっさに思い出せなかったのか「北国の春」を吹き始めるなど、おやっと思うところもある。
しかし会場の皆さんは、気にすることなく笑顔で拍手。その優しく温かな雰囲気が、とてもいいなあと私は思った。加齢も認知症もお互いさま、皆で今を楽しもうよ、という和やかなつながり。
緊急の仕事を終えて戻って来た江森さんに私のつたない感想を伝えると、「そうなの! だから私、次は初期の認知症の人が集える場所を作りたいと思って。介護保険とか関係なく、のんびり過ごしてもらったり、上手に生活できる知恵を伝え合ったり。いいと思いません?」
と、きらきらした目で語り始める。落ち込んだ時は、新しい目標を考える。
「年齢なりに衰えてできないこともあるけれど、万が一できなくても気にしない(笑)。それが人間の自然の姿だと納得しているから。地域の皆さんと支え合って生きてきた今、老いも認知症も障害も、きっと乗り越えられると思っています」と語る江森さんの笑顔は、これからも多くの人に生きる力と勇気を与えていくだろう。
関連記事(外部サイト)
- 83歳のパワフル訪問看護師。看護学校教員として1000人以上の看護師を世に送り出し、60歳で故郷の山村にUターン。介護施設を次々と立ち上げて
- 脳梗塞で倒れた夫のため、自宅介護ができるよう分譲団地を改装。自分も脳梗塞、乳がんと診断されながら、声楽家の活動は続けて
- 胃ろうから4ヵ月で食べられるようになったケースも。口から食べられないときこそ、歯科医の出番。食べることは生きることそのもの
- 高齢化が進む都内の大規模団地で生まれた「暮らしの保健室」は全国60ヵ所に。医療の専門職が駐在、お茶を飲む気軽さで相談できる
- 58歳・祐美さん「同世代との会話は子や孫、介護、病気に偏りがち。うんと年下の友だちは根掘り葉掘り聞いてこず、一緒にいるだけで元気に。若いって尊い」