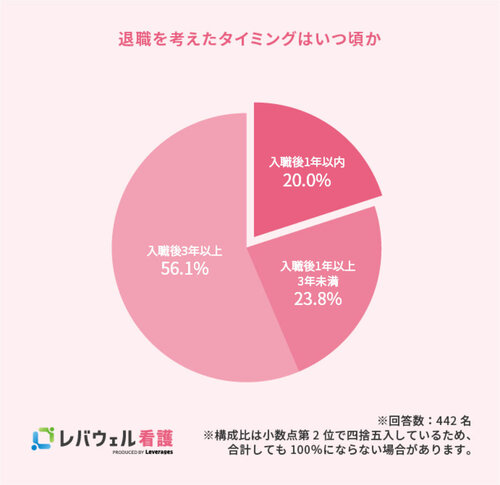83歳のパワフル訪問看護師。看護学校教員として1000人以上の看護師を世に送り出し、60歳で故郷の山村にUターン。介護施設を次々と立ち上げて
2025年5月5日(月)12時30分 婦人公論.jp

住宅型有料老人ホーム「にしきの丘」に入居する100歳の女性と楽しそうに話す江森さん(右)(撮影:藤澤靖子)
長野県のとある山間部に、一人の女性が立ち上げた介護施設がある。介護というとネガティブなイメージもあるが、ここでは毎日笑い声が絶えない。その明るさの秘密は、一体どこにあるのか。施設を開所した当事者であり、現在も訪問看護師として働く江森けさ子さんを訪ねた(撮影:藤澤靖子、寺澤太郎)
* * * * * * *
貧しい農村に生まれ、看護の道へ
長野県松本市の北東部にある四賀(しが)地区。標高1000m級の山々に囲まれた盆地に広がるのどかな田園地帯を、1台の車が軽快に飛ばしていく。「けさ子さんは運転速いから、追いかけるのが大変なんです」と、後続の車を運転するNPO法人「峠茶屋」事務長の木村美和さんが、笑いながら教えてくれた。
江森けさ子さん、83歳。60歳で故郷にUターンして介護事業を次々と立ち上げ、現在も訪問看護ステーションの管理者、訪問看護師として働いている。
車から降りて早々、「私は行きあたりばったりの人だから、予定表を作っておかないと皆さんが困ると思って」と話す江森さんは、昨夜パソコンで作ったという取材の予定表を配ってくれた。屋外での移動はつねに小走り。人懐こい笑顔と、全身から発する明るいエネルギーが印象的だ。
取材の打ち合わせをするために訪れた蕎麦店は、江森さんの小学校の同級生だという女将が1人で切り盛りする地元の人気店。
「村の人は、年取っても働き者。特に女性がそうだいねえ」「小さい頃から家を手伝ってきたから」と話す2人が生まれた頃、このあたりは養蚕でなんとか生計を立てる貧しい農村だったそうだ。小中学校時代は「野山で遊んでいた思い出しかないです」と、江森さんは笑う。
7人きょうだいの4番目。女の子を進学させる経済的余裕は家にない。女性が手に職をつけて生きていくには、と考えて選んだのが看護の道だった。中学卒業後は県立病院付属の養成所に入り、18歳から准看護師として働き始める。
打ち合わせに同席していた夫の元春さんとは、「結婚しても働き続けられること」を条件に23歳で結婚。
夫の転勤に同行して移り住んだ広島では被爆者医療にも従事し、診療所で働きながら正看護師の資格を取得した。その地で長女と次女が生まれ、夫婦で協力しながら仕事と子育てを両立してきたという。
「周りの人に助けられましたね。実は夫が、その後の転勤先の静岡で、詐欺まがいの事業に巻き込まれてしまって。私は子どもと印鑑を抱えて、取り立て屋から逃げ回っていた時期があるんですよ。その時も、保育所の先生や職場の仲間が、『変な人が訪ねて来たらすぐ警察を呼ぶから』と守ってくれました」
静岡では、37歳から看護学校の教員という新たな活動もスタート。後進の指導に生きがいを感じて定年まで勤め上げ、1000人以上の看護師を世に送り出した。

宅老所「峠茶屋」は和やかな雰囲気(撮影:藤澤靖子)
村人の助けで事業が軌道に乗り
そんな看護一筋で生きてきた江森さんが介護事業を始めたのには、どんな経緯があったのだろうか。
江森さんが故郷の四賀に足を運び始めたのは、子育てが一段落した50代半ば。兄夫婦が継いだ実家の農作業を手伝うという名目で、村で過ごす休日を楽しみに通うようになったのだ。
「農作業の手を休めて眺める景色は、ため息が出るほどきれいでね。馴染みのあるお国言葉で会話ができるのも、嬉しいものだなあと思ってしまって」
江森さん夫妻はしばらくすると四賀に小さな山小屋を建て、借りた畑で週末農業を楽しむようになる。そこで出会ったのが、年齢をものともせず農作業に励む元気な高齢者たち。
農業初心者の江森さんを気にかけ、トラクターで硬い土を耕したり、余った苗を分けてくれたりと、親切にしてくれた。自分の愛する田んぼの風景や整備されたあぜ道は、この人たちが営々と守ってきたのだと実感し、感謝の気持ちが湧いてきたという。

宅老所「峠茶屋」(撮影:藤澤靖子)
一方、村では高齢化や過疎化が急激に進み、介護の問題が深刻になりつつあった。
「私は看護師だから、医療や介護が手薄な田舎で、少しは役に立てることがあるかもしれないと思って。最初はほんの道楽の気持ちですよ。5年もやったら終えるつもりで、自宅の山小屋を小規模宅老所(デイサービス)にして、村のお年寄りをお預かりしてみようと考えました」
そこで江森さんは、仕事の合間を縫って訪問介護の体験や介護支援専門員(ケアマネジャー)の資格取得などの準備を重ね、2001年暮れに夫婦で四賀への移住を決める。江森さん60歳、元春さん64歳の時だった。
その頃、当時の長野県知事が「住み慣れた地域に小規模の宅幼老所を作る」方針を打ち出し、建物の改修や新築に助成金が出るようになったことを江森さんたちは知る。
「ちょうど実家のある集落に、空き家同然となった旧公民館がありました。昔から地域の人が寄り合いに使ってきた場所だから、お年寄りにも馴染みがあるかなと思って、ここを宅老所にしようと決めたんです」
改修費には江森さんの退職金を充て、宅老所「峠茶屋」は完成した。現在もNPOの名称として使うこの名前には、「山あり谷ありの人生を乗り越えてきた人たちに、ここらで一服してほしい」という願いが込められている。
しかし03年の開設当時は、認知症の親を預けることも、親を預けたと周囲に知られることも避けたい家族が多かった。定員以上の介護スタッフを揃え、地元産の米と野菜を使った食事を用意したにもかかわらず、オープンした月は利用者ゼロ。翌月も2人という厳しい状況だった。
そんな時に頼りになったのは、ご近所さんだ。峠茶屋で、村の老婦人に旧満洲仕込みのギョウザの作り方を教えてもらう会を開いたり、地域の人が制作したキルト展を開催したり。江森さんを心配してか、「ちょっとお茶を飲みに来たよ」と気軽に寄ってくれる人たちも増え、口コミで峠茶屋の様子やデイサービスの魅力を広めてくれた。
「朝出勤すると、玄関先に野菜や山菜が届けられているのが峠茶屋の日常になりました。頑固で村人から疎まれていた男性を預かって、スタッフが根気よく寄り添ううち、『あのじいさんが穏やかになった』と村で噂になったこともあったねえ。そういう毎日が嬉しくて楽しくて。介護という仕事は人を幸せにするのだと気づき、すっかり私、ハマってしまったんです」
<後編につづく>
関連記事(外部サイト)
- 83歳のパワフル訪問看護師。看護学校教員として1000人以上の看護師を世に送り出し、60歳で故郷の山村にUターン。介護施設を次々と立ち上げて
- 独身女性、老後の家問題。92歳の父、89歳の母との3人暮らし。持ち家があって正社員、自分は難病で週3の透析、老後は大丈夫?【2024年下半期ベスト】
- 依存心が強い78歳の母親の世話を「家族代行サービス」へ。昼夜問わない愚痴の電話、お金の無心「親の面倒をみるのは当然」の態度に耐え切れず
- 脳梗塞で倒れた夫のため、自宅介護ができるよう分譲団地を改装。自分も脳梗塞、乳がんと診断されながら、声楽家の活動は続けて
- 高齢化が進む都内の大規模団地で生まれた「暮らしの保健室」は全国60ヵ所に。医療の専門職が駐在、お茶を飲む気軽さで相談できる