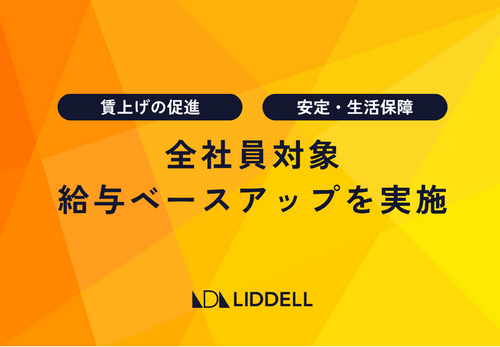「34年ぶりの高賃上げ率」でも喜べないワケ、大企業がカネを巻き上げる「強欲インフレ」のメカニズム
2025年4月21日(月)7時0分 ダイヤモンドオンライン
「34年ぶりの高賃上げ率」でも喜べないワケ、大企業がカネを巻き上げる「強欲インフレ」のメカニズム
写真はイメージです Photo:PIXTA
今年の春闘の平均賃上げ率は5.46%と、34年ぶりの高水準である。しかし恩恵を受けるのは主に大企業の社員に限られる。賃上げ分の原資は価格上昇による利益であり、中小企業に勤める多くの消費者がその負担を強いられている。大企業の賃上げのカラクリを暴く。※本稿は野口悠紀雄『日銀の限界 円安、物価、賃金はどうなる?』(幻冬舎新書)の一部を抜粋・編集したものです。
大企業が給料アップしても中小企業は賃上げできない現実
国民経済計算(編集部注/国の経済状況について生産、消費・投資などのフロー面、資産、負債などのストック面を体系的に記録することを狙いとする国際的な基準)における家計消費は、ほぼ減少を続けている。また、鉱工業生産指数もほとんど停滞している。
このように経済活動が停滞して、物価が上昇しているのだから、これは典型的なスタグフレーション(編集部注/景気が後退していくなかでインフレが同時進行する現象)だと言える。
「賃金が上昇すれば、消費が増えるだろう」という考えがあるかもしれない。しかし、賃金を増やすための必要条件は、粗利益が増加していることだ。大企業の粗利益は増加しているが、中小零細企業の粗利益は、そうではない。したがって、中小零細企業は、そもそも賃上げをする力を持っていないと言える。
政府は、人件費の上昇分を販売価格に転嫁して中小零細企業も賃上げができるように指導しているが、こうした転嫁がスムーズに実現できるとは考えられない。