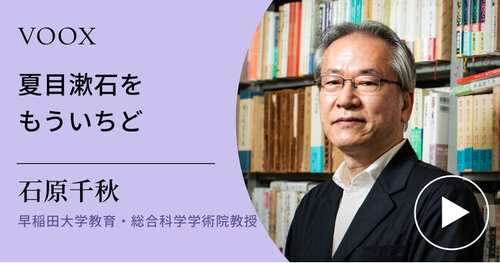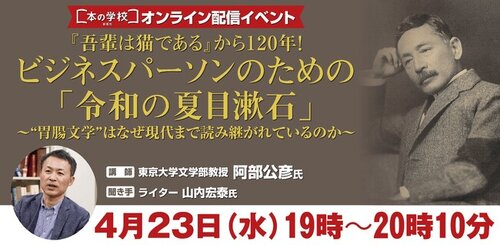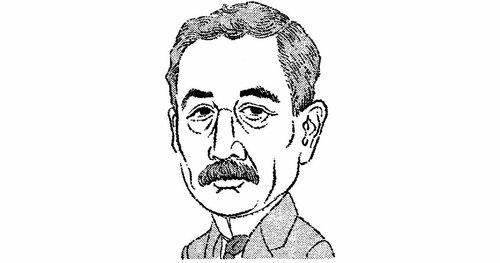【実話ベース】40年間、置かれた…生きることを許されなかった女の人生
2025年4月23日(水)6時15分 ダイヤモンドオンライン
【実話ベース】40年間、置かれた…生きることを許されなかった女の人生
正気じゃないけれど……奥深い文豪たちの生き様。42人の文豪が教えてくれる“究極の人間論”。芥川龍之介、夏目漱石、太宰治、川端康成、三島由紀夫、与謝野晶子……誰もが知る文豪だけど、その作品を教科書以外で読んだことがある人は、意外と少ないかもしれない。「あ、夏目漱石ね」なんて、読んだことがあるふりをしながらも、実は読んだことがないし、ざっくりとしたあらすじさえ語れない。そんな人に向けて、文芸評論に人生を捧げてきた「文豪」のスペシャリストが贈る、文学が一気に身近になる書『ビジネスエリートのための 教養としての文豪』(ダイヤモンド社)。【性】【病気】【お金】【酒】【戦争】【死】をテーマに、文豪たちの知られざる“驚きの素顔”がわかる。文豪42人のヘンで、エロくて、ダメだから、奥深い“やたら刺激的な生き様”を一挙公開!
イラスト:塩井浩平
病気に自由を奪われた青春時代の10年間
高知生まれ。小学校校長だった父のもとに生まれる。高知県女子師範学校中退。代表作は『婉という女』『アブラハムの幕舎』など。高知県女子師範学校は全寮制の学校だったが、入寮中の18歳時に喀血し、結核で入院。学校も中退せざるを得ず、以後約10年間を療養に費やす。故郷で病気の治療をしながら小説を書くようになり、昭和7(1932)年、20歳のときに初めて投稿した『姉のプレゼント』が、『令女界』という雑誌に入選。以後も執筆活動を続け、29歳のとき創作に集中するため上京。48歳で講談社から刊行した『婉という女』がヒット。亡くなるまで、精力的に執筆活動を続け、数々の文学賞を受賞した。平成12(2000)年、87歳で心不全により死去。
結核との闘いが作家人生の原点に
大原富枝は、平成12(2000)年に87歳で亡くなりました。長生きして多くの作品を残しましたが、若いころに結核を病んだ経験があります。
18歳からの10年間にわたり療養生活を強いられ、青春期の自由を奪われたことが、大原の作家人生に深く根ざしているのです。
自由を奪われた主人公・野中婉と大原の人生の重なり
代表作であり、俳優・岩下志麻主演で映画化された小説『婉という女』は、土佐藩執政の父・野中兼山(良継)が失脚したのち、わずか4歳から40年にわたり幽閉された実在の女性に焦点をあてた歴史物語です。
大原の故郷・土佐(現・高知県)を舞台にしており、狭い場所で自由を奪われ、どこにも行けない主人公・野中婉の葛藤や苦しみは、若いころに病気で自由を奪われた大原自身と重なります。
印象的なのは、こんな描写です。
「置かれた」存在を否定されたような40年
「門外を一歩を禁じられ、結婚を禁じられ、40年間をわたくしたちはここに置かれた」「他人との面会を許されず、他人と話すことを許されないで、わたくしたち家族はここに置かれた」「わたくしたち兄弟は誰も生きることはしなかったのだ。ただ置かれてあったのだ」——『婉という女』(『婉という女・正妻』講談社文芸文庫に収録)
「暮らしていた」ではなく「置かれた」
このように、大原は「置かれた」という表現を繰り返し使っています。「生きていた」でも「暮らしていた」でも「いた」でもなく、「置かれた」なのです。
つまり、人間が暮らすのではなく「モノが置かれる」のと同じような扱いをずっとされていたと感じているわけです。主人公の切実な訴えが、胸を締めつける作品です。
封建的な社会での女性の立場、自由の追求とその限界、それに対する深い絶望を描いた同書は、昭和35(1960)年、大原が48歳のときに発表され、大きな話題を呼びました。
派手な時代の裏側にいる人々の孤独に光を当てた『アブラハムの幕舎』
ほかにも社会に居場所がなく、宗教的コミュニティに惹かれてしまう若者たちを描いた長編小説『アブラハムの幕舎』は、1980年代のバブル期に派手な社会の表舞台からは見えない、孤独や弱さを抱えてとり残された人々の姿に光を当てており、とても読み応えがあります。
※本稿は、『ビジネスエリートのための 教養としての文豪』(ダイヤモンド社)より一部を抜粋・編集したものです。