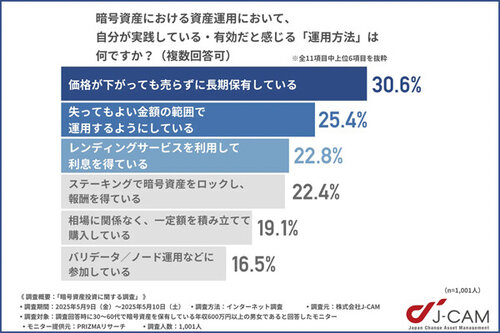"I love you"の和訳はなぜ「月がきれいですね」がハマるのか…「ただの景色の描写」が美しい愛情表現になる理由
2025年4月30日(水)7時15分 プレジデント社
※写真はイメージです - 写真=iStock.com/Tero Vesalainen
※本稿は、小野純一『僕たちは言葉について何も知らない 孤独、誤解、もどかしさの言語学』(NewsPicksパブリッシング)の一部を再編集したものです。
写真=iStock.com/Tero Vesalainen
※写真はイメージです - 写真=iStock.com/Tero Vesalainen
■“I love you”を訳すと「月がきれいですね」
漫画やアニメの中で、「月がきれいですね」が「あなたが好きです」の意味で用いられることがあります。
夏目漱石が英語を教えているときに、学生がI love youを「私はあなたを愛する」と訳しました。すると漱石は、日本人はそんな言葉を口にしない、明治時代の男女なら、せいぜい「月がきれいですね」くらいだろう、と注意した、というエピソードが元になっています。
※ただし、豊田有恒『あなたもSF作家になれるわけではない』(徳間書店、1979年、p.141)には「月がきれいですね」ではなく「月がとっても青いなあ」とあります。
どうして「月がきれいですね」と言語化することが、二人にとって「愛している」と口にするのと同じくらい意味をもつのでしょうか。この点こそ、言葉の力を示すと思います。
言い換えれば、没個性的な言葉の並びが、個人の感情そのものになる、ということに関わるでしょう。
■「月がきれいですね」と確認できる関係性から見えるもの
今ここに互いを大切に思う二人がいると想像してください。その二人が月を眺めて、「月がきれいだね」と言うなら、その二人はあらかじめ、自分たちが同じものを同じように感じることができることを確信しています。二人は、相手が何を素敵だと思うのかをよくわかりあっている。
そのようなことが可能なのは、仲の良い家族の誰かか、親友か、恋人かもしれません。だからこそ、この言葉を口にできるとき、そこにいる二人はすでに互いをよく知っていて、信頼していて、何を考えるのかが手に取るようにわかる、ということだと思います。
写真=iStock.com/zagi89
※写真はイメージです - 写真=iStock.com/zagi89
たとえ離ればなれでも、同じ目標や理念をともに見ている関係性です。誰かがそばにいて孤独じゃないという安心感を与える状況や、たとえ遠く離れていても同じものを見て同じ気持ちを共有する具体的な誰かがいる状況で、自分は孤独ではない、わかりあえる人がいると感じている状態です。この関係性は、友愛や家族愛を含むようなだれか具体的な大切な人がいて、その人とは同じ目的をもち、ほとんどの利害が一致するものでしょう。
だから、この二人が「月がきれいですね」と同意しあうということは、自分たちが利害の一致した最も親密な関係であることをわかった上で、言語化して再確認している状況です。したがって「月がきれいですね」は、人類愛のような普遍的な愛の形を表していません。
むしろ「あの人ではなく、この人が好き」という、それ以外のすべての人を排除して選び取った恋人や、他のだれでもない愛しい我が子のような特定の対象への愛(あるいは執着)の関係性を指し示すと理解できます。
■誰かと心が通じ合っている情景が浮かんでくる
さらに範囲を広げましょう。私が独り月を見上げて「きれいだな」と思ったとき、何百キロか離れたところにいる自分の大切な人も、同じ月を見上げて「きれいだ」「一緒に見られるとよかったのに」と思っていると想像できるならば、それは、自分の大切な人だからこそ、その人が何に心を動かすのか、よく知っているということです。
心が誰かと通じあう状態を、「孤独」と呼ぶことは難しいのではないでしょうか。
■相手が歩んできた人生への敬意が込められている
もっと範囲を広げましょう。ふと満月を見上げて遠吠えをする犬の気持ちまでわからなくとも、私たちは、人間ならたぶん誰でも月を美しいと思うだろうと確信しています。
それは、真っ暗な夜空に無数の稲妻が光って、世界が揺れるように雷が響くとき、ほとんどの人が美しいと思うと同時に、恐ろしさや圧倒される感覚を持つと予想できるのと同じでしょう。高い山の頂を遠くから眺めるときにも、その山の姿に圧倒され、畏敬すら感じるでしょう。この感覚を「崇高」として考察したのは、ドイツの哲学者カントです。
その瞬間こそ「月がきれいですね」が特定の対象への愛(あるいは執着)のような利害関係を超えて、深い愛のありかを示すときだと思います。
「月がきれいですね」が執着や利己的な愛を超えた深い心としてとらえられるとき、そこにはその人の歩んできた人生という「物語」への敬意や共感、そしてその人が存在するに至るはるかな時の流れへの畏敬を込めた「まなざし」が感じとられているでしょう。
■「月がきれい」は人類に普遍的な感覚
「月がきれいですね」と同意しあう二人は、圧倒的に高い山よりも手の届かない宇宙に大きく輝く月に崇高さに似た感情を抱いて驚嘆し、ため息をついて、これ以上言葉が出てこないかもしれません。無限の宇宙に魅惑されながらも、深淵を覗くときの恐怖に似た驚きを感じると思います。それは決して到達できず、ちっぽけな自分がますます小さく感じるような感覚です。
それは「月がきれいですね」の「きれい」や「美しい」のように文化や個人で基準が変わる価値観ではなく、おそらく人類に普遍的な感覚です(犬や猫にも共有されているのかもしれません)。それは月の荘厳さ、宇宙の計り知れなさに圧倒される感覚の表現に他なりません。
■損得勘定もビジネスも関係ない存在としての「月」
空に浮かぶ月は、あらゆる人の利害関係からも、打算や損得勘定からもビジネスからも無関係です。利害や損得を基準にするビジネスは、消費の対象を扱います。消費対象であれば、ファッションか何かのように「これが今年の秋の『美』の先端です」といって月が浮かんできたり、「ちょっと今月は月にたくさん行きすぎちゃった」などということになるでしょう。でも月はそういう消費の対象ではありません。
だから、月を美しいと言うのは、特定の人や物を「美しい」と呼ぶのとはまったく違います。何の打算も、利害関心もない状況で、「きれいだね」と感情を出すことができる相手は、お互い相手を利用しようとしていない関係です。利害関係がなければ、実は自分の知っている人だけではなく、見ず知らずの人でも同じ感動を共有することができるといえます。
■無意識に「この料理は美味しいね」と語りかける意味
小野純一『僕たちは言葉について何も知らない 孤独、誤解、もどかしさの言語学』(NewsPicksパブリッシング)
何の打算も、利害関心もない「まなざし」が月とその背後に広がる無限の宇宙に向いているとき、「きれいですね」が向かう先は、誰かと交換可能な消費対象としての「あなた」ではありません。その「まなざし」は、他の誰でもないあなたしか紡いでこなかったはるかな時の流れの「物語」、そのような「物語」が誰にでもあるという普遍性への深い畏敬や崇敬、共感をしっかりととらえています。
このような自覚なしに、私たちは愛する人に、月、花がきれいだ、この料理は美味しいね、と語りかけます。
このような交流を可能にする言葉、このような慈しみの心情を結晶させる言葉は、それ自体がはるかな時の流れの「物語」を背負う「まなざし」であり、無数の人々の関わりなしには存在しえなかったものです。私たちは一瞬一瞬のかけがえない経験を愛おしむのと同じ細心の注意で、言葉と関わる必要があると思います。
----------
小野 純一(おの・じゅんいち)
自治医科大学准教授
1975年、群馬県生まれ。自治医科大学医学部総合教育部門哲学研究室准教授。専門は哲学・思想史。東京大学大学院人文社会系研究科博士課程修了。ベルギー・ゲント大学文学部アジア学科研究員、東洋大学国際哲学研究センター客員研究員などを経て現職。
著作に『井筒俊彦 世界と対話する哲学』(慶應義塾大学出版会、2023年)などがある。訳書にジェニファー・M・ソール『言葉はいかに人を欺くか』(慶應義塾大学出版会、2021年)、井筒俊彦『言語と呪術』(安藤礼二監訳、慶應義塾大学出版会、2018年)。
----------
(自治医科大学准教授 小野 純一)