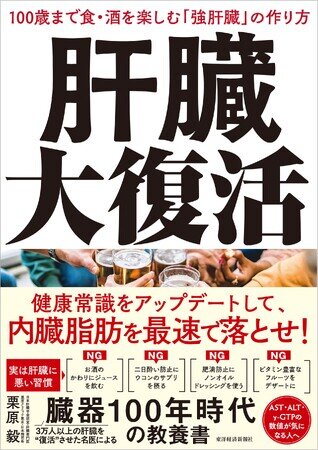一度は同意したもののドナーを拒否する妻…「臓器提供」をめぐる夫婦間トラブルの“実情”が生々しかった《最悪のケースでは…》
2025年5月19日(月)12時0分 文春オンライン
〈 「人を意図的に脳死させる『脳死マシーン』を開発した」数千万円の金が飛び交う“臓器売買”で行われている“まさかのやり口”とは 〉から続く
臓器移植を受けるにはさまざまなハードルがあり、提供を希望する人のなかには親族に頼る人も少なくない。しかし、親族だからといって、臓器を提供することに納得できるかというと……。
ここでは、高橋幸春氏の『 臓器ブローカー すがる患者をむさぼり喰う業者たち 』(幻冬舎新書)の一部を抜粋し、夫婦間の臓器提供を巡る諍いを紹介する。(全3回の3回目/ はじめから 読む)

◆◆◆
臓器移植法が施行される前、移植医療の黎明期では、移植手術は医療と患者側の合意の上で進められた。医師が移植についての説明をし、レシピエント、ドナーの意思確認も行っていた。
移植手術を受けたいという夫婦が相談にやってくる。夫が慢性腎不全で人工透析治療を受けていた。ドナーになるのは妻だ。
「妻もドナーになるのに同意している。移植をしてほしい」
夫が来院の意図を告げた。
妻も夫に頷きながら話を聞いていて、すでに夫婦の間で話し合いが行われ、妻も腎臓提供に同意していると思われた。
「白血球の血液型」HLAの適合
医師が移植に向けてHLA(Human Leukocyte Antigen =ヒト白血球抗原)検査、血液型などいくつかの検査について説明した。HLAが不適合なら移植はできない。
1954年、フランスの免疫学者ジャン・ドセーによって、HLAは「白血球の血液型」として発見された。HLAは白血球だけにあるのではなく、様々な細胞に存在し、組織適合性抗原として働いていることがわかった。
HLAが遺伝子の第6染色体にあることもわかり、このHLAが人間の免疫システムをつかさどっている。HLAは両親からその半分ずつを受け継ぐため、親子や兄弟の間でも一致する確率は低いが、一卵性双生児同士の場合には、このHLAがすべて一致しているために、拒絶反応は起きないことが証明されている。
非血縁者間ではHLAが一致する確率は数万分の1程度と言われている。HLAが合致しなければ、移植された臓器はレシピエントの体内で異物と認識され免疫システムが攻撃を開始する。
このHLAの適合数がなるべく多い者同士間での移植なら、拒絶反応も最小限に食い止めることが可能になり、当然、移植の成功率は高くなる。とはいえ一卵性双生児同士の移植でもない限り、拒絶反応は必ず現れる。
免疫反応は、移植臓器だけではなく、ウイルスなどの侵入に対しても反応し、人間の体はこの免疫システムによって健康が維持される。臓器移植はこの免疫拒絶反応をいかにコントロールするかの闘いでもある。
1970年代の腎臓移植は、まだ医療としては確立されていなかった。1980年代に入り優れた免疫抑制剤が日本に導入されるようになり、揺るぎない医療となった。
臓器提供したくない妻と、そんな妻に財産を残したくない夫
ところが検査の数日後、臓器の提供を了解していると言った妻から病院に電話が入った。
「先日していただいた検査の件でご相談があるのですが……。私の腎臓は、適合性に問題があるという検査結果にしてもらうわけにはいかないでしょうか」
夫の説明では、妻が腎臓を提供すると同意したので、移植の相談に来たという話だったが、実際はそうではなかった。妻は納得しないまま、夫に連れられて来院したのだ。
ドナーの意思確認ほど困難なものはない。夫婦だから「一心同体」などと思い込むことがいかに危険をはらむか。当時の移植医は少なからずこうした経験をしている。
このようなケースは今日でも起こり得る。夫が妻に提供を求めても、妻が拒否する。それでも夫は妻に提供を求める。
「俺が死んでもいいのか」
激しい言葉で妻をなじる。
資産がある場合はさらに問題は複雑になる。
「そんな妻に俺の財産を譲りたくない」
臓器提供をめぐり、離婚に至ることもある。
あるいは夫に隠れて妻が臓器斡旋組織を訪れ、「夫に海外で移植してやってほしい」と訴えるケースさえある。
(高橋 幸春/Webオリジナル(外部転載))