「資本主義とは恐慌やハイパーインフレの危機に常にさらされている不安定なシステム」経済学者・岩井克人が読み解く《アメリカの不平等化の元凶》
2025年5月23日(金)7時0分 文春オンライン
アメリカが「不平等」な社会となっている元凶はどこにあるのか。経済学者の岩井克人氏が解説する。
◆◆◆
自由放任主義と株主主権論の「理論的誤謬」
アメリカが「ディストピア」となったのは、その資本主義が自由放任主義的であり株主主権論的であることによるのは明らかです(その民主主義がポピュリズムを招きやすい大統領制であることも、大いに寄与しています)。
だが、ここで強調したいのは、自由放任主義も株主主権論も「理論的誤謬」であるということです(それは、『不均衡動学』や『貨幣論』や『会社はこれからどうなるのか』などで長年にわたり論証してきました)。
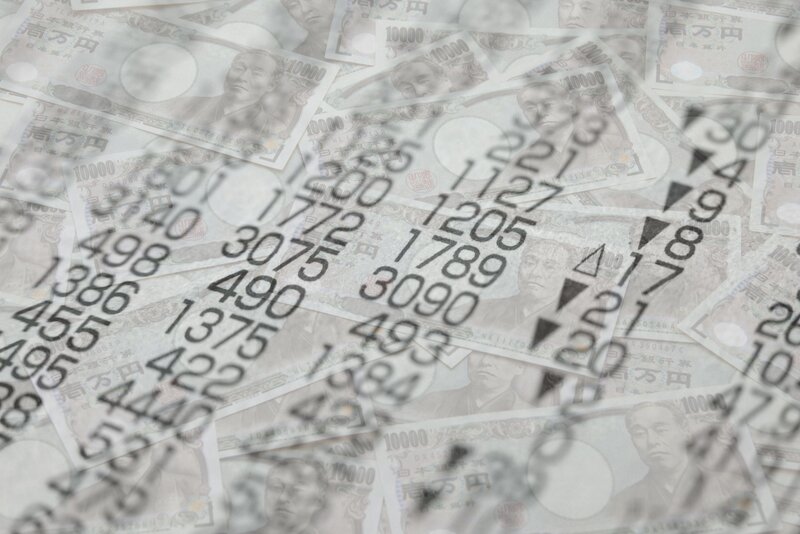
まず、自由放任主義は資本主義経済が貨幣経済であることを無視した誤謬です。人が貨幣を受け取るのは、モノとして使うためではありません。他の人もそれを貨幣として受け取ると予想しているからです。その意味で、人はそう意識していなくとも、貨幣を受け取るたびにまさに投機をしているのです。そして、投機にはバブルが伴い、バブルは破裂します。貨幣のバブルとは人がモノより貨幣を欲しがる不況であり、貨幣バブルの破裂とは人が貨幣から逃走するインフレです。不況が悪性化すると恐慌となり、インフレが悪性化するとハイパーインフレとなります。すなわち資本主義とは貨幣経済であることによって、恐慌やハイパーインフレの危機に常にさらされている本質的に不安定なシステムなのです。
さらに、株主主権論も、会社が法人であることを無視した誤謬です。オフィスや工場を所有し、従業員や仕入先や銀行と契約を結ぶのは、株主ではなく法人としての会社です。その会社を現実にヒトとして動かすのも、株主ではなく経営者です。いつでも株を売り逃げできる株主と違い、経営者は会社に対して忠実義務を負っている存在です。それは、ひとたび会社をヒトとして動かす役を引き受けたならば、会社を自己利益の道具としてはならないという倫理的な義務に他なりません。
資本主義は市場だけでは自立しえない
ところが米国の会社システムは、株主利益を最大にするには経営者も株主にすればよいとして、株式オプションを中核とする報酬制度を導入しました。不幸にもそれは経営者を忠実義務から解放し、会社をみずからの利益追求の道具とする機会を与えただけでした。そして、その機会に乗じて、大会社の経営者は平均的労働者の350倍にまでその報酬を吊り上げたのです。アメリカでは上位1%の高所得者層が全所得の20%を手にしていますが、その内訳を調べると、資本所得の割合は小さい。起業家の所得も大きいのですが、それ以上に大きな割合を占めているのは他ならぬ経営者の報酬なのです。米国の不平等化の元凶はまさに株主主権論という誤謬にあるのです。
ところで、自由放任主義が誤謬であるならば、資本主義経済は市場だけでは自立しえません。政府や中央銀行の規制や介入、社会保障や相互扶助などと組み合わさってはじめて安定的に機能することになります。資本主義それ自体も、市場とそれ以外の制度をどう組み合わせるかによって「多様性」をもつことになるのです。
株主主権論が誤謬であるならば、会社とは株主の利益のための道具ではなくなります。それは人的組織としての自律性をもち、株主だけでなく、従業員や他の関係者の利益、さらにはSDGsのような社会的貢献すらもその目的の中に含むことが可能になります。会社システムそれ自体も、その目的をどう設定するかによって「多様性」をもつことになるのです。
※本記事の全文(約10000字)は、月刊文藝春秋のウェブメディア「 文藝春秋PLUS 」に掲載されています(岩井克人「 2つのディストピア 米中に呑み込まれるな 」)。全文では、下記の内容をお読みいただけます。
・クズネッツの法則とモンテスキューの法則
・「希望の星」から転落した中国
・習近平vs.ジャック・マー
・日本の「世界史的な使命」
・近代の多様性を示せ
(岩井 克人/文藝春秋 2024年6月号)













