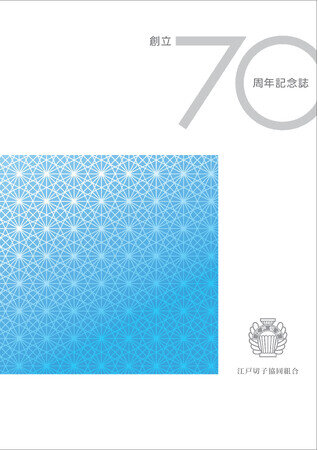天皇が「万世一系の継承者」と定義した…江戸時代を終わらせた明治維新が「革命」にならなかった国家的事情
2025年3月2日(日)9時15分 プレジデント社
明治天皇の肖像(画像=Uchida Kuichi/CC-PD-Mark/Wikimedia Commons)
※本稿は、上念司『保守の本懐』(扶桑社)の一部を再編集したものです。
明治天皇の肖像(画像=Uchida Kuichi/CC-PD-Mark/Wikimedia Commons)
■軍事政権からの「民主化」だった
明治維新による社会の変化は「革命」と言っていいぐらいの大きなものでした。身分制度はなくなり、年貢は地租に変わり、憲法が制定され議会もできて選挙も行われるようになったからです。
江戸時代は言ってみれば徳川家と大名が連合した軍事政権であり、一定の身分がなければ政治には参加できませんでした。また、身分は基本的に世襲であり、生まれた瞬間に将来その人がどのような職業に就くのかもほぼ決まっていました。
もし、フェートン号事件から安政の開国に至る外圧がなければ、江戸時代はもっと長く続いていたことでしょう。しかし、世界はそれを許さなかった。日本は欧米列強との国交を開かざるを得ない圧力を受け、不平等条約を飲まざるを得ない状態に追い込まれたのです。
■日本の遅れに気付いた改革派vs守旧派
なぜ欧米列強に勝てなかったのか? 理由は簡単です。まずは軍事力の差。そして、その差をもたらす科学技術が最大の問題でした。
私有財産制度が確立していない国ではイノベーションは起こりません。古代中国は羅針盤を発明しても、大航海時代はこなかった。同じことが封建時代の日本にも言えるわけです。
明治維新の原動力となった下級武士たちはこのことにいち早く気付き、社会改革の必要性を訴えました。しかし、当時の徳川幕府はこれをたびたび弾圧しました。
改革派は同盟を組んで戦い、大政奉還から最後は戊辰戦争という暴力によって守旧派を粛清。明治新政府が立ち上がったわけです。このあたりの歴史についてはこれだけで本が何冊も書けてしまうので省略します。
■新政府が「革命ではなく維新」とした理由
問題は、明治維新において伝統や正統性が思想的かつ理論的にどのように確保されたかという点です。維新は維新であって決して革命ではない。
そもそも、明治維新という呼称自体、維新が終わった後に後付けされた名称です。やっている最中には「御一新」と呼ばれていました。御一新、つまり何かが大きく変わるというニュアンスでしたが、終了後それは革命ではなく維新であると定義付けられました。
明治維新において最も重要なこと、それは明治天皇が古代から続く万世一系の継承者として、国家の正統性を象徴した点にあります。
天皇は日本の歴史における「万世一系」の象徴であり、国家の正統性を維持する中心的な存在でした。幕末の混乱期においても、その権威は失われていません。幕末も例外なく歴代将軍は天皇の任命で就任していますし、むしろ条約勅許問題など朝廷の権威をさらに利用する動きすらありました。
そのため、維新期において「王政復古」のスローガンが浮上したのは、その正統性から言えば当然のことでした。
■天皇は改革に欠かせない存在だった
この考え方の萌芽は水戸黄門でお馴染みの徳川光圀がまとめた『大日本史』という歴史書の中に見て取れます。それを発展させた水戸学、特に後期水戸学は明治維新の理論的な支柱の1つになりました。
新政府は、多くの改革を実施するにあたり、その正当な理由を日本の伝統的価値観に結び付けて説明しました。もちろんかなり苦しい説明もありますが、伝統と結び付けて解釈するという点がとても大事です。この点で、天皇は新しい時代の象徴でありながら、古来の伝統とも連続性を持つ存在でした。
特に大事なのは、五箇条の御誓文(1868年3月)です。御誓文は明治新政府の基本方針を明確化する文書であり、その内容には革新性と保守性が共存しています。明治新政府が目指したもの、それは当時の欧米のような自由主義、言ってみれば「自由で開かれた社会」でした。
■社会の維持には「メンテナンス」が必須
自由で開かれた社会とは、保守思想が目指す漸進的な改革を実現するための基盤となるものです。個人の自由が最大限に尊重され、同時にその自由が社会全体の利益と調和する形で保障されるからこそ、自由に議論ができ、その結果として衆知を集めることができる。
そして、一定の結論が出た後で常にそれを振り返り効果を確認しながらまた次の漸進的な改革に着手する。保守という言葉は英語で言えば「メンテナンス」です。私たちの社会は古い自動車みたいなものですが、新車に買い替えるわけにはいかないのです。
急進的な改革には大きなリスクが伴うため、古いポンコツでも修理しメンテナンスしながら乗り続けるしかない。そのためには、当事者すべてが整備士としてこの修理に参加する必要があります。
自由な議論を通じて、みんなで決めていく社会。何を隠そうこれこそが五箇条の御誓文にある一節「廣(ひろ)ク會議(かいぎ)ヲ興(おこ)シ萬機(ばんき)公論ニ決スヘシ」そのものなのです。
五箇条の御誓文の原本(画像=DCyokohama/PD-Japan-oldphoto/Wikimedia Commons)
■天皇自らが先頭に立って近代国家への道を歩む
左翼系の歴史学者には明治天皇による御誓文を茶番だとか、単なるスローガンだとバカにする人たちがいます。しかし、それがいかに愚かしい批判か。読者のみなさんはもうすでにご理解いただけるかと思います。
保守思想の観点からすれば、日本の歴史、伝統を重視し、その形式に従って明治天皇がこのような布告を出すことは極めて重要なことです。
近代国家への道を歩むということは日本にとって未曽有の大改革であり、天皇自らその先頭に立って努力すると宣言されたわけです。それも天地神明に誓って。
その目指すものの第一に掲げられたのが「廣ク會議ヲ興シ萬機公論ニ決スヘシ(広く人材を集めて会議を開き議論を行い、大切なことはすべて公正な意見によって決めましょう)」という項目です。いわゆる保守思想と自由主義の融合、保守自由主義は明治維新から始まったのです。
■当時の日本は侵略の危機に晒されていた
明治天皇が自ら先頭に立ってこういう社会改革を行う必要があったのは、日本をいち早く欧米並みに近代化し日本を守るためです。欧米諸国は「自由で開かれた社会」であると同時に、同じ基準を持たない国々を文明国とは認めていませんでした。
「自由で開かれた社会」と言っても、あくまで当時の基準。フランスもついこの間まで身分制度があったような国だったわけです。それが無くなって自由になった。でも、文明国と認めない国は「教化」の対象であり、侵略して植民地にしてもいいという倫理観がまかり通っていたわけです。
分かりやすく言えばこれは「令和の世から昭和のテレビドラマを振り返って、その酷さに絶句する」みたいなものです。当時のドラマではセクハラも暴力の描写も今では絶対に考えられないぐらいえげつないものでした。でも、当時はそれでよかったのです。
今から見れば、欧米諸国のダブルスタンダードにしか見えないこの行動も、当時としては当たり前。だからこそ、左翼の人たちはこの時代を帝国主義の時代とネガティブなイメージで呼ぶわけです。
■伝統を守りながら改革もする難題をクリア
欧米列強によるアジアの植民地化から日本を守るためには、江戸時代の古い仕組みでは対抗できない。だからこそ、維新の志士たちは日本を近代化させ、近代国家として生まれ変わった日本を欧米列強に認めさせようと立ち上がりました。外的環境の変化に適応しつつ、日本の社会を守るためには、歴史的な連続性に配慮しつつも大胆な改革が必要でした。
写真=iStock.com/KeithBinns
※写真はイメージです - 写真=iStock.com/KeithBinns
伝統を守り、しかし、改革もする。どう考えても完全に矛盾しているこの難ミッションを課せられたのが明治新政府であり、それをクリアしたのも明治新政府でした。
例えば、五箇条の御誓文第一条にある「広く会議を興し」という部分は、封建制的な専制支配を否定し、議論を通じた開かれた政治を目指す意思を示していますし、第四条の「天地の公道」に基づく行動とは、西洋的な普遍的価値観を取り入れる意思を表しています。
■市街戦を繰り返したフランス革命との違い
ポイントはそれらが、明治天皇による宣言だったという点です。五箇条の御誓文は、明治天皇が自ら発した、歴代天皇および天地神明に誓うという形式が取られました。これは、天皇という伝統的権威を基盤に新しい体制を構築しようとする保守思想的なアプローチと言えるでしょう。
フランスのようにパリで市街戦を何度も戦うことなく、最初からこのような設定をした点に私たち日本人の先人たちの智慧を感じませんか?
明治維新の成功は、伝統と改革のバランスを取ったことにあります。天皇と五箇条の御誓文は、伝統的な価値観、特に万世一系や日本の文化的アイデンティティを基盤にしながら、必要な改革を進めるということを明確にした宣言でした。これは保守思想において重要な社会秩序の維持のためには、天皇の存在が不可欠であったことを意味します。
■混乱を最小限に抑えることができた
公儀(幕府のこと)は天皇から征夷大将軍に任命されることで日本を統治する権限を与えられている。だから、公儀といえどもそれは「幕府」に過ぎない。この理論は徳川光圀が明治維新の200年前に主張したものです。
上念司『保守の本懐』(扶桑社)
明治新政府の歴史解釈は少なからず徳川光圀に始まる水戸学の影響を受けています。この天皇を中心に据えた歴史観が、激動の時代における混乱を最小限に抑える役割を果たしました。
ただ1つだけ余計な話をさせてください。水戸学は時代が下るにつれてあまりにも過激化しすぎて一部はトンデモ論、陰謀論に走るヤバい学派になってしまいました。そのため、明治新政府も水戸学のすべての理論を採用したわけではなく取捨選択が行われています。
また、旧水戸藩の人材は過激な人が多すぎたので明治新政府からは排除されました(「水戸学がトンデモなので明治新政府もトンデモ」という左派の批判は的外れです)。
----------
上念 司(じょうねん・つかさ)
経済評論家
1969年、東京都生まれ。中央大学法学部法律学科卒業。在学中は創立1901年の日本最古の弁論部・辞達学会に所属。日本長期信用銀行、臨海セミナーを経て独立。2007年、経済評論家・勝間和代氏と株式会社「監査と分析」を設立。取締役・共同事業パートナーに就任(現在は代表取締役)。2010年、米国イェール大学経済学部の浜田宏一教授に師事し、薫陶を受ける。金融、財政、外交、防衛問題に精通し、積極的な評論、著述活動を展開している。
----------
(経済評論家 上念 司)