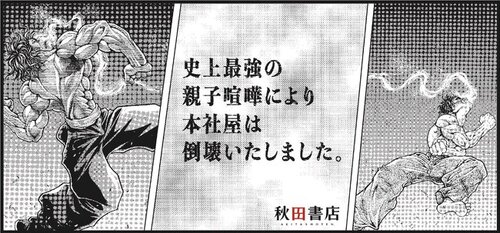「殴る蹴る」よりも脳の一部が16.6%萎縮する…「激しい夫婦喧嘩」を目撃した子どもの脳に起きる深刻なダメージ
2025年3月12日(水)18時15分 プレジデント社
※写真はイメージです - 写真=iStock.com/Kiwis
※本稿は、友田明美『最新脳研究でわかった 子どもの脳を傷つける親がやっていること』(SB新書)から抜粋し再編集したものです。
写真=iStock.com/Kiwis
※写真はイメージです - 写真=iStock.com/Kiwis
■体罰は「百害あって一利なし」
マルトリートメント(以下マルトリ)とは、虐待やネグレクトに限らず、「子どもへの避けたいかかわり」を指す総称です。マルトリを経験すると、こころの傷(トラウマ)が生じ、認知の障害(IQ低下)、健康に害を及ぼす行動(薬物やアルコール依存)やさまざまな疾病リスクが高まる可能性があり、最終的には早世につながる可能性があります。
まず、身体的マルトリについて解説します。どんな理由があろうとも、体罰は「百害あって一利なし」です。逆に、「望ましくない影響しかない」ことが研究により明らかになっています。
ハーバード大学のマーチン・タイチャー氏とともに研究をし、最初に報告をしたのが「身体的マルトリによって脳の前頭前野が縮む」ということでした。18〜25歳のアメリカ人男女約1500人に聞き取り調査を行い、次のような体罰を受けた経験のある23人を選び出しました。
・体罰の内容:頰への平手打ち、ベルト・杖などで尻を叩かれるなど
・体罰を受けた年齢:4〜15歳の間
・体罰を受けた相手:両親や養育者
・体罰を受けていた期間:年に12回以上で、3年以上
■「前頭前野」の萎縮につながる
こうした厳格な体罰を受けた経験のある23人のグループに対して、利き手、年齢、両親の学歴、生活環境要因をマッチさせた「体罰経験のない」22人にも協力してもらい、両グループの脳を調べて比較しました。その結果、体罰経験のあるグループの脳は、体罰経験のないグループに比べて、次のような変化が見られました。
・感情や思考をコントロールし、行動の抑制にかかわる「(右)前頭前野(内側部)」の容積が平均19.1%小さくなっていました。
・物事の認知にかかわる「(左)前頭前野(背外側部)」の容積が14.5%小さくなっていました。
・集中力や意思決定、共感などにかかわる「(右)前帯状回」の容積が16.9%小さくなっていました。
前頭前野が萎縮すると、犯罪抑制力の低下や素行障害、うつ病のリスクを高め、強い攻撃性があらわれることもあります。さらに、6〜8歳頃に身体的マルトリを受けた場合、脳への影響が特に大きいこともわかっています。体罰は子どもの脳の発達に深刻な影響を与えるのです。
■暴言は子どものコミュニケーション能力を下げる
暴言による心理的マルトリは、子どもの「聴覚野」にダメージを与えることがわかっています。聴覚野は言語の理解にかかわる領域で、他人とのコミュニケーションを円滑に行う働きを持っています。過去に身体的マルトリによる脳へのダメージを調査したときと同様のやり方で、18歳までに暴言によるマルトリを受けた人たちと、そうでない人たちの脳をMRIで比べました。
すると、大声で怒鳴られる、ののしられる、責められる、脅されるといった言葉の暴力によるマルトリを受けてきたグループは、そうでないグループと比べて、左脳にある聴覚野の一部である上側頭回の容積が14.1%も肥大していることがわかりました。
聴覚野が肥大するとは、端的に言うと、必要な情報を効率よく得るための「シナプスの刈り込み」が正常に行われていないということです。子どもの脳は乳児期に、情報を伝達するシナプスが爆発的に増えます。その後、代謝が活発になるにつれてエネルギー消費が過剰になるため、脳の中では木々の剪定のように余分なシナプスを刈り込んで、神経伝達を効率化していくのです。
■「母親からの暴言」は影響が大きい
しかし、この大切な幼少期に暴言を繰り返し浴びると、正常なシナプスの刈り込みが進みません。その結果、シナプスがまるで伸び放題の雑木林のような状態になり、脳の容積が肥大すると考えられます。特に、聴覚野への影響が出やすいのは4〜12歳頃に暴言によるマルトリを受けた人たちで、この時期はちょうどシナプスの刈り込みが進む時期と重なります。聴覚野のシナプスが正常に刈り込まれていない状態では、人の話を聞き取ったりする際に余計な負荷がかかります。その結果、心因性の難聴を引き起こしたり、情緒不安定になったり、人とのコミュニケーションを恐れるようになったりすることがあるのです。
脳へのダメージは、「一人の親からの暴言」よりも「両親からの暴言」のほうが大きく、「父親からの暴言」よりも「母親からの暴言」のほうが影響が大きいこともわかりました。つまり、両親からの暴言や、子どもと接する時間が長いと考えられる母親からの暴言のほうが、脳に与えるダメージという点でより深刻であるわけです。また、暴言の頻度が高く、その内容が深刻であればあるほど、脳への影響が大きいという結果も確認されています。
■子どもの前で夫婦喧嘩をするとIQや記憶力が低下する
いつも夫婦が仲良くいられればいいですが、家事や育児の分担から親の介護などさまざまな課題に直面する中では、ときには夫婦喧嘩をすることもあると思います。ただ、子どもの前で激しい喧嘩をするのは避けたほうが良さそうです。
両親の激しい喧嘩を見聞きして育つと、子どもの脳は傷つき、IQや記憶力に悪影響があることがわかっています。18〜25歳のアメリカ人男女を対象に、小児期に両親間のDVを長期間(平均4.1年間)にわたり目撃した22人と、そうした経験のない30人を比べたところ、DVを目撃したグループは脳の視覚野の容積が平均6.1%減少していました。大脳皮質の中でも、視覚に直接関係する部分が萎縮していたのです。視覚野が萎縮すると、他人の表情を読み取りにくくなり、対人関係でトラブルを抱えやすくなります。
実は、言葉のDVを目撃するほうが、身体的DVを目撃するよりも脳へのダメージが大きいのです。具体的には、視覚野の一部である舌状回の容積減少の割合が、身体的DVを目撃した場合は3.2%であったのに対し、言葉のDVを目撃した場合は19.8%にまでなっていました。言葉のDVが身体的DVの約6倍もの影響が見られたのです。
これは非常に驚くべき結果ではないでしょうか。多くの親が、子どもの前で配偶者を叩くなど暴力を振るうのは良くないとわかっていると思います。でも、怒りに任せて怒鳴ったり、ネチネチとしつこくなじったりする言葉の暴力が、これほどまでに子どもの脳に悪影響を与えるとは思っていないでしょう。もっと多くの方に知っていただきたい事実です。
写真=iStock.com/sorn340
※写真はイメージです - 写真=iStock.com/sorn340
■性的マルトリで視覚的な記憶力が低下する
こんなことも性的マルトリにあたります(例えば、思春期に入る頃の子どもに親が入浴を強いる、子どもの前で親の下着姿や裸を見せるなど)。では、性的マルトリが子どもの脳へ与える影響はどのようなものでしょうか。小児期に性的マルトリを受けた経験のあるアメリカ人女子学生23人と、そういった経験のない女子学生14人を対象に脳を調べたところ、性的マルトリを受けたことのあるグループは、そうでないグループに比べ、左半球の「視覚野」の容積が8%減少していました。
視覚野は、単に目の前のものを見て認識するだけでなく、映像の記憶形成に関連する重要な領域です。ここが縮んでいるということは、「視覚的なメモリ容量が減少している」と考えられます。この調査では、視覚による記憶力を測定するテストも行いましたが、視覚野の容積が小さい人ほど、視覚的な記憶力が低いこともわかりました。性的マルトリを経験した人の脳は、メモリ容量を減少させることによって、苦痛を伴う記憶を脳内に長くとどめておかないようにしているのではないかと考えられるのです。
■親の脳も傷ついている
友田明美『最新脳研究でわかった 子どもの脳を傷つける親がやっていること』(SB新書)
私たちの脳は、さまざまなストレスによって傷ついています。特に子どもの脳は傷つきやすいですが、大人の脳も同様に影響を受けます。たとえば普通のお母さんでも、周囲の協力が得られず孤独に子育てを頑張っている中で、育児ストレスや不安な気持ちが強まったとき、感覚処理能力が低下することがわかっています。感覚処理能力が低下すると、赤ちゃんの泣き声などの感覚刺激に対して反応しなかったり、逆に過剰に反応したりといったことが起きます。このような脳の状態が、マルトリを引き起こす可能性も推察できるのです。
マルトリは多くの親が経験することであり、マルトリをしてしまった親を責める気持ちはまったくありません。「またやってしまった」と思ったら、次は同じことを繰り返さないように気を付ければいいのです。もしコントロールできないと感じたら、専門家に相談することをおすすめします。脳を癒やすことで、改善します。傷ついた脳は修復できるのです。
----------
友田 明美(ともだ・あけみ)
小児精神科医
医学博士。福井大学子どものこころの発達研究センター教授。熊本大学医学部医学科修了。同大学大学院小児発達学分野准教授を経て、2011年6月より現職。福井大学医学部附属病院子どものこころ診療部部長兼任。2009〜2011年および2017〜2019年に日米科学技術協力事業「脳研究」分野グループ共同研究日本側代表を務める。著書に『子どもの脳を傷つける親たち』(NHK出版新書)、『新版 いやされない傷』(診断と治療社)、共著に『虐待が脳を変える 脳科学者からのメッセージ』(新曜社)などがある。
----------
(小児精神科医 友田 明美)