お金儲けのためではなく、会社の利益のためでもなく…フリージャーナリストが投げかける「社会人の正しい目的」とは
2025年4月13日(日)7時0分 文春オンライン
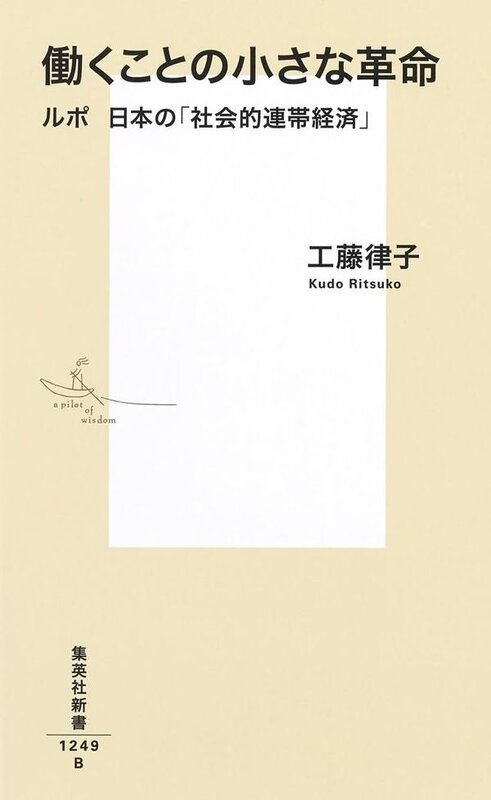
「私自身が選択を迫られた約40年前と、日本における働き方の基準があまりに変わっていないことに驚きます。バブルや就職氷河期、あるいはコロナ禍を経て世の中は大きく変わったはずなのに、“目指すべき正しい社会人”像はなぜかずっと更新されない。とても不思議だし、本当にそれでいいの? と思っています」
このたび、『働くことの小さな革命』を上梓した工藤律子さん。大学院在学中から取材活動を開始して、「自分の書きたいことを自由に書くためには、この方法しかない」と、フリーのジャーナリストの道を選んだ。以来、スペイン語圏やフィリピンの社会問題を中心に取材、発信し続けてきた。
「同世代はともかく学生からも、フリーで働くなんて不安じゃない? と言われます(苦笑)。じゃあ、そもそも働くってどういうイメージ? と尋ねると、多くが“会社に入ること”だと答える。そして“これがやりたいと言えることがまだないし、あっても自信がない”と。で、会社に入ってやることは何かといえば、結局は自社の利益を生むための活動になってしまう」
いわゆる途上国や新興国での取材経験が豊富な工藤さんならでは、の視点もある。それらの国々でも企業の利益追求を優先し実現した「経済成長」が、必ずしも人々を幸せにしているようには見えないというのだ。
「本当に貧乏だった頃は互いに助け合っていたのに、だんだんそうじゃなくなって……。今では精神的な貧困度はむしろ上がったとすらいえる状況です」
そんな実感の積み重ねが、働き方や経済のあり方に目を向けるきっかけとなった。
さて、本書のサブタイトルは、「ルポ 日本の『社会的連帯経済』」である。この社会的連帯経済とは何か? いわく、〈企業間の競争による利潤の追求とそれを基盤とする経済成長よりも、社会的利益のために連帯して、人と(地球)環境を軸にした経済〉のこと。Social and Solidarity Economyの略でSSEとも称され、欧州諸国では近年、推進の機運が高まっている。具体的には、さまざまな協同組合やNPO、共済組合、財団、フェアトレード、社会的企業、有機農業、地域通貨のような「補完通貨」の運営など。
工藤さんは、このSSEにこそ新しい時代の働き方のヒントがあると考え、現在、日本各地でSSEを実践している人、団体、会社などを訪ねて実態を取材した。そこには、お金儲けや生活費を稼ぐことばかりが目的ではなく、あくまで自分らしく、仲間と地域やコミュニティのために働き、生きようとしている人たちの姿があった。
「ただ、自分たちのやっていることがSSEだと自覚している人は、少数でした。また、形は異なっていても近しい発想で活動している人もたくさんいるので、本書がみんなをつなげるものになればと願っています」
ところで、工藤さんのユニークな活動の一つにSSEスタディツアーがある。
「毎年、6人ほどの参加者を引率して、SSEが盛んなスペインの事業組織を見学して回ります。やっぱり、直接出会うことでしか伝わらないものがあるので。例えば、海外のSSEの実践者は、自分たちの活動の理念や理想について、実に熱っぽく語るんですよ。いい大人が目をキラキラさせて。日本の若者にはそれがとても新鮮で魅力的みたいで(笑)。その熱の伝播を期待しているところです」
終章では、SSEの普及のためには主体的で共感力のある市民を育てることが肝要だと考察する。つまり工藤さんもまた、小さな革命の種を播く人なのだ。
くどうりつこ/1963年、大阪府生まれ。東京外国語大学大学院在学中からメキシコ貧困層の生活改善運動を研究するかたわら、フリーのジャーナリストとしての取材活動を開始。著書に『マラス 暴力に支配される少年たち』など多数。
(「週刊文春」編集部/週刊文春 2025年4月17日号)













