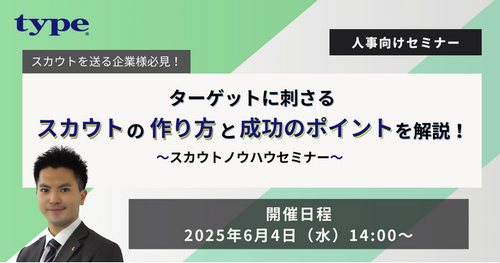ターゲットは1キロ8分ペースの「スローランナー」18~34歳を狙っていたナイキは、なぜ高齢アスリートに目を付けたか
2025年4月9日(水)4時0分 JBpress
日本をはじめ世界各国で進む超長寿化社会。これまで「老後」「シニア」とひとくくりにされてきた世代は、今や多様な価値観とライフスタイルを持つ「新しい消費者層」と再定義されつつある。本稿では『超長寿化時代の市場地図 多様化するシニアが変えるビジネスの常識』(スーザン・ウィルナー・ゴールデン著、佐々木寛子訳/ディスカヴァー・トゥエンティワン)から、内容の一部を抜粋・再編集、3200兆円規模とも言われる、長寿市場におけるビジネスの可能性を論じる。
スポーツシューズメーカーのナイキや、アイウェアのD2C(ダイレクト・トゥ・コンシューマー)企業ワービー・パーカーは、長寿マーケットの需要をどう取り込んだか?
事例2
高齢アスリートを発見したナイキ
企業の戦略は、18歳から34歳の層ばかりを狙いがちだ。かつてのナイキもそうだった。スポーツシューズとアパレル販売で世界一となり、370億ドルの帝国を築いたナイキも以前は、主にこの層に向けて商売をしていた。
2019年、ナイキは、高年齢層アスリートのニーズに対応する戦略の拡大を決定した。この層は同社の売り上げの10%を占め、他の層よりも購入単価が高い。ただし、同社は高齢者向けのスニーカーではなく、「年齢を重ねるアスリート」のためのスニーカーを作ろうと決めた。
カテゴリー・プロダクト担当役員(当時)のマイク・スピレインは、ナイキの長寿カスタマー像を理解するための作業に着手した。ターゲットは現役ランナーだ。競技大会にも出続けており、今では「スローランナー」になってきた人である。
スピレインは、多くの高齢者が健康のためにウォーキングをしていることも知っていた(米国では健康のためのウォーキング人口は1億1000万以上、ジョギング人口は6000万とされている)が、それでもナイキは「ウォーキングをする高齢者」をターゲットにはしなかった。
狙いはあくまで、「ウォーキングをする高年齢のアスリート」である。スピレインは、ナイキが長年培ってきた商品へのロイヤリティを、「自分はまだまだアスリートだ」と考えている人たちから獲得する方法を見つけようとしていた。ナイキが目指したのは、「永遠のアスリート」「アスリートであり続ける人」を取り込むことだった9。
9 Robert Chess and Jeffrey Conn, “Nike: Sport Forever,” Case E690(Stanford, CA: StanfordGraduate School of Business, 2020)
ナイキは新しいスニーカー、クルーザーワン(CruzrOne)の設計を始めた。ナイキ創設者フィル・ナイトを念頭に置いた特別デザインだ。フィル自身が「アスリートであり続ける人」のステージにいるカスタマーであり、彼との会話から、スニーカーデザインのレジェンド、ティンカー・ハットフィールドがデザインした。
1キロ8分ペースかそれ以上の「スローランナー」をターゲットとして、ヒール、ミッドソール、前足部を再設計し、着地時の体重がかかとの後方にかかるようにして前転運動を促すことで、ゆっくり走り続けやすい構造にした。
このように設計したものの、ナイキはメッセージとして、具体的な特徴や、購入者であるスローランナーの分析については強調しなかった。ナイキのマーケティングは「アスリートであり続ける人」というステージに焦点を当てた。自分にサポートが必要だとは思っていないが、サポート機能のある製品は高く評価するであろう人に向けて商品を開発したのだ。
クルーザーワンは試験的にオンライン限定で1足150ドルで販売された。現在は別部門を立てず、ナイキブランドとして販売されている。「アスリートであり続ける人」を理解し、マーケティングを開始したナイキは、自社戦略を進化させ続けた。2020年7月、ナイキは消費者セグメントをシンプルにした。メン、ウィメン、キッズの3カテゴリーだ。
スピレインは、この3部門を統括するコンシューマー・クリエーションの責任者に就任した。メン、ウィメンのカテゴリーでは、「アスリートであり続ける人」を全生涯に広げた戦略に取り込んでいる。「永遠のアスリート」マーケットの拡大は著しく、これから20年ほどでカスタマーの3分の1がこのカテゴリーに入ると予測しているためだ。高年齢の消費者は商品へのロイヤリティが高いとされており、ナイキはそれを獲得するために動いたのだ。
ナイキの勝因は、対象マーケットを広くとらないことだった。「ウォーキング人口」や「おしゃれな人」を広く狙おうとはせず、特定のステージ、特定のサブドメインに焦点を絞っていた。
「高齢者がシューズに求める要素はこれだ」などという思い込みや偏見に囚われることもなく、カスタマーが自己をどのように定義しているかに耳を傾け、それを生かして戦略を実装した。「その消費者になる必要はないが、理解する必要はある」とスピレインは言う。「しっかり声を聴くことは、良いマーケティングの本質だね」
ナイキは現在、スポーツの定義とアスリートの定義を広げ、「スポーツ・フォーエバー」「アスリート・フォーエバー」のテーマを盛り込み、さらに高年齢層が活発でいられるための施策にも着手している。
同社は、ダンスやヨガをスポーツとして捉えるなど、将来のフィットネスをめぐる商品戦略を深化させ、この層に向けたアパレル戦略を展開している。同社はまた、アクティブなライフスタイルを通じて人びとの健康寿命を延ばすサポートに関する保健・医療領域の政策議論に積極的に貢献していきたいと考えている。
・企業名:ナイキ
・ドメイン:フィットネス、アパレル
・サブドメイン:「アスリートであり続ける人」
・市場規模:40億ドルを超えて成長中のシューズ市場
・対象ステージ:方向転換、再生、健康状態の見直し
・ベストプラクティス:高年齢層向けのマーケティングを行わず、コアターゲットであるアスリートに向けて商品を販売したこと。若年層ターゲット戦略を超えて、アスリートから長期のロイヤリティを獲得した点。特定のステージとセグメントに絞ったこと
事例3
「おしゃれな若者ブランド」を乗り超えたワービー・パーカー
アイウェアのD2C(ダイレクト・トゥ・コンシューマー)企業、ワービー・パーカーは、当時の社会貢献型ベンチャーでよく見られた「1つ売れたら1つ寄付」を掲げて、2010年2月に創業した。
創業当初、共同設立者のニール・ブルメンタールとデイヴ・ギルボアは、マーケティングの王道である18歳から34歳の層をターゲットにして、単焦点の度付きレンズを手頃な価格で提供した。500ドル相当の商品を95ドルで売るのが同社の基本路線で、品揃えを絞ることで低価格を実現した。一般的な眼鏡店では1000SKU(商品単位)を扱っているが、ブルメンタールによると、同社は3色×30デザインの90SKUで事業を始めたという10。
2年目にはサングラスと度付きサングラスを商品ラインナップに追加し、3年目には異素材の新フレームを加えた。
創業から4年、ECからリアル店舗へ進出する際に、ワービー・パーカーは累進レンズの販売に踏み切った。累進レンズとは、1枚に複数の焦点があるレンズで、上部と下部に異なる度数が入ったものだ。上で遠景を見て、下で手元の本を読むなど、遠近両用に使える。年齢が上がると2つ以上の眼鏡を使い分けている人が多いが、その不便を累進レンズは解消してくれる。
同社はすぐに、累進レンズ市場は非常に大きいと気づいた。米国のアイウェア市場の50%以上を累進レンズが占めており、平均価格は500ドルだった。
10 ニール・ブルメンタルへの著者インタビューより(2020年9月実施)
創業以来3年、流行に敏感な若者のブランドとして運営してきた同社は、4年目にして長寿マーケットに踏み出した。とりわけ、ユーザーが初めて累進レンズを作るタイミングが商機になると考えた。そこで、長寿カスタマーが来店なしでオンラインの視力測定ができる仕組みを開発した。
また、今の処方が合っているのか、処方の更新前にチェックできるアプリも開発しており、これは米国では65歳以上には未承認だが、認可が下り次第、提供できるよう準備してある。同社は、ECでもリアル店舗でも、新たなカスタマー層に良い購買体験をしてもらえるよう尽力した。
もう1点、ワービー・パーカーが重視したのは、年代層に合わせて眼鏡をデザインしないことだった。流行りのフレーム、売れている型番にそのまま累進レンズをはめた。若者だけでなく、さまざまなステージの人がおしゃれな眼鏡を欲しがっているとわかったためだ。累進レンズへの切り替えの際には特にこのアプローチがベストだと同社は考えた。切り替える年齢も人によって異なるわけだし。
同社の全体戦略である「低価格」は、このマーケットでも貫く必要があった。長寿マーケットやヘルスケア市場のB2Cビジネスでは顧客獲得コストが高くなりがちだが、ワービー・パーカーは、テレビCMを絞って投下したりFacebook広告を使って、累進レンズへ切り替える人に効率よくリーチした。こうして、累進レンズの眼鏡を平均295ドルで販売できたのだ。
このマーケットを取り込むためには、広告戦略にも細かい変更が必要だった。たとえば、広告に中高年のモデルを加えることがある。広告モデルの年齢のダイバーシティは、現在の広告業界全般の課題の1つだ、とブルメンタールは主張している11。
長寿マーケットへのピボットは大成功を収めた。今や、ワービー・パーカーは流行に敏感な若者だけに縛られない、多世代向けの製品を提供する企業だと自認している。2014年から2019年で100万本以上の累進レンズ付き眼鏡が販売され、現在では同社の売り上げの約30%が累進レンズとなっている。
遠隔診療が承認され、保険適用化でその利用が増加する中、ワービー・パーカーは自社の長寿マーケット戦略を見出した。若者向けブランドとして人気を得ながら、ブランドの対象を高年齢層まで広げ、さまざまなニーズに対応した製品を提供している。同社の現在の目標は、何十年も同ブランドを愛用してくれるカスタマーを幅広い年齢層で獲得することだ。
11 ニール・ブルメンタルへの著者インタビューより(2020年9月実施)
<連載ラインアップ>
■第1回「富の80%を持つ65歳以上」をターゲットに 金融業界初の老年学の専門家を採用した旧メリルリンチの戦略とは?
■第2回 ターゲットは1キロ8分ペースの「スローランナー」18〜34歳を狙っていたナイキは、なぜ高齢アスリートに目を付けたか(本稿)
<著者フォロー機能のご案内>
●無料会員に登録すれば、本記事の下部にある著者プロフィール欄から著者をフォローできます。
●フォローした著者の記事は、マイページから簡単に確認できるようになります。
筆者:スーザン・ウィルナー・ゴールデン,佐々木 寛子