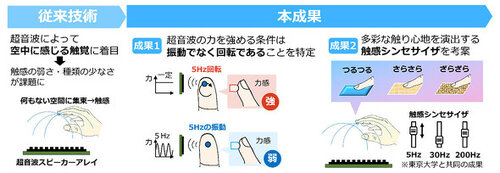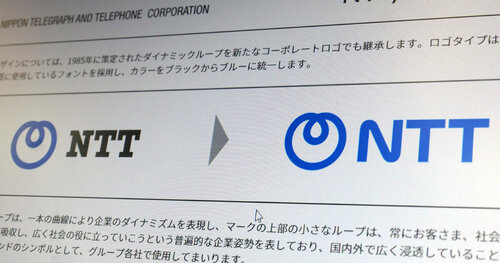NTTのNTTデータTOBで高まる、成長への期待
2025年5月14日(水)9時20分 財経新聞
●NTTデータグループを完全子会社化
国内通信大手のNTTが、NTTデータグループを完全子会社化し、親子上場を廃止すると発表した。
【こちらも】上場維持基準引き上げでどうなる? 東証グロース
約1カ月でTOB(公開買い付け)を開始し、約57%の保有比率を100%にする。取得費用は2兆3712億円の見込みだ。
2020年にはNTTドコモを完全子会社化しており、統合によって意思決定の迅速化と海外事業の競争力を高める狙いがある。
5月9日には、7月1日付で社名を日本電信電話株式会社からNTT株式会社に変更することも発表したが、島田明社長が目指す「世界で勝てる、強いNTT作り」は実現するのだろうか?
●AIにも重要な役割?NTTデータGとは?
NTTデータグループは、データ通信やシステム構築を行うNTTの子会社である。
ITサービス企業としては日本最大であり、世界6位の売上高を持つ。
かつては中央官庁からの大量天下り受け入れや、2007年の年金記録問題での杜撰な契約などが問題となったことがあった。
近年は海外事業に力を入れており、今年4月下旬にChatGPTの開発元である米オープンAIとの提携も発表している。
子会社化により、AI需要に対応したデータセンターの拡大及び高度化、自治体や中小企業向けの営業体制の強化、社内のDX化の推進を目指すとしている。
親会社NTTの財務基盤を活かし、データセンターなどへの巨額投資へと迅速な決定が期待される。
●さらなる成長に立ちはだかるNTT法
1985年に旧日本電信電話公社が民営化され、NTTが設立された時に制定されたNTT法が、今後の課題となる。NTTデータGの完全子会社化はNTT法の対象外だった。
市場支配力が強いNTTに競争の公正性を確保するため、規制が強く、それが研究開発の自立性や技術革新の促進を妨げて律という指摘が前からあった。
ただし規制緩和によって、NTTの寡占状態が進み、地方や過疎地でのサービスの悪化という懸念もある。競合他社であるKDDI、ソフトバンク、楽天の3社は規制緩和には反対している。
2023年には、自民党の特命委員会から防衛費増額の財源として、3分の1以上を保有する政府のNTT保有株を売却する提案があったが、反対意見が多く、棚上げとなった。
政府が発行済み株式3分の1以上を保有していたり、役員人事や年度ごとの事業計画で総務大臣の認可を得る必要がある現在のNTT法の、廃止を含めた議論の活発化は、”強いNTT”を目指すには避けられない。
国内通信大手のNTTが、NTTデータグループを完全子会社化し、親子上場を廃止すると発表した。
【こちらも】上場維持基準引き上げでどうなる? 東証グロース
約1カ月でTOB(公開買い付け)を開始し、約57%の保有比率を100%にする。取得費用は2兆3712億円の見込みだ。
2020年にはNTTドコモを完全子会社化しており、統合によって意思決定の迅速化と海外事業の競争力を高める狙いがある。
5月9日には、7月1日付で社名を日本電信電話株式会社からNTT株式会社に変更することも発表したが、島田明社長が目指す「世界で勝てる、強いNTT作り」は実現するのだろうか?
●AIにも重要な役割?NTTデータGとは?
NTTデータグループは、データ通信やシステム構築を行うNTTの子会社である。
ITサービス企業としては日本最大であり、世界6位の売上高を持つ。
かつては中央官庁からの大量天下り受け入れや、2007年の年金記録問題での杜撰な契約などが問題となったことがあった。
近年は海外事業に力を入れており、今年4月下旬にChatGPTの開発元である米オープンAIとの提携も発表している。
子会社化により、AI需要に対応したデータセンターの拡大及び高度化、自治体や中小企業向けの営業体制の強化、社内のDX化の推進を目指すとしている。
親会社NTTの財務基盤を活かし、データセンターなどへの巨額投資へと迅速な決定が期待される。
●さらなる成長に立ちはだかるNTT法
1985年に旧日本電信電話公社が民営化され、NTTが設立された時に制定されたNTT法が、今後の課題となる。NTTデータGの完全子会社化はNTT法の対象外だった。
市場支配力が強いNTTに競争の公正性を確保するため、規制が強く、それが研究開発の自立性や技術革新の促進を妨げて律という指摘が前からあった。
ただし規制緩和によって、NTTの寡占状態が進み、地方や過疎地でのサービスの悪化という懸念もある。競合他社であるKDDI、ソフトバンク、楽天の3社は規制緩和には反対している。
2023年には、自民党の特命委員会から防衛費増額の財源として、3分の1以上を保有する政府のNTT保有株を売却する提案があったが、反対意見が多く、棚上げとなった。
政府が発行済み株式3分の1以上を保有していたり、役員人事や年度ごとの事業計画で総務大臣の認可を得る必要がある現在のNTT法の、廃止を含めた議論の活発化は、”強いNTT”を目指すには避けられない。