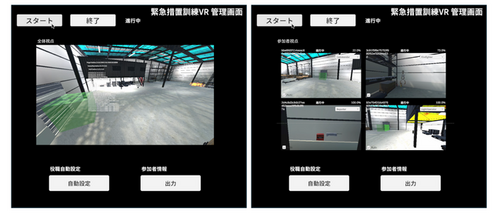将来モンスター化する新人は「5つのP」で見極める…学歴や頭の良さは関係ない、研修期間中に観察すべきこと
2025年5月23日(金)9時15分 プレジデント社
※写真はイメージです - 写真=iStock.com/maroke
■研修期間中は実務より先に「資質」を見る
新年度がはじまって早くも2カ月がたとうとしています。
4月当初は、希望と不安を胸に新たな一歩を踏み出した若者たちがいる一方で、そんな彼らを受け入れる先輩たちも、いったいどんな若者なのだろうか、コミュニケーションはうまくとれるのだろうか、仕事はできるのだろうかなどと、期待と不安が入り混じった複雑な心境だったのではないでしょうか。
そして今、職場ではその期待や不安はどうなっているでしょうか。すっかり互いになじんでスムーズな滑り出しとなったところもあるでしょうし、なかなか互いの壁を越えられずにギクシャクしているところもあるかもしれません。
先輩たちはこの2カ月のあいだに、新人たちを観察してきたと思いますが、いったいどのような点に着目して観察し、評価してきたのでしょうか。もちろん、最初から期待どおりにタスクをこなせるはずなどないのですから、いきなり仕事の「出来・不出来」を評価することはないでしょう。一般的には、まず彼らに内在するコンピテンシー(資質・能力)の確認、観察評価から始められることが多いのではないでしょうか。
写真=iStock.com/maroke
※写真はイメージです - 写真=iStock.com/maroke
■医師に求められる「5つのP」とは何か
当然ながら多くの組織では、入社前にこれらは一定程度、見きわめられていることでしょう。しかしじっさい組織の一員としてともに仕事を始めるにあたっては、あらためて再確認しておく必要があります。
この重要性は一般企業でも医療機関でも同じです。新人医師を受け入れた場合、できるだけ速やかにコンピテンシーの観察、把握が望まれます。なぜなら、その実情しだいでは早めの対策を講ずる必要が生じ得るからです。
私がとくに気をつけて観察するのは、Peacefulness(穏やかさ)、Politeness(礼儀正しさ)、Punctuality(時間厳守)、Priority(優先度)、Proactiveness(主体性)という5つの「P」。
医師として必要な知識や技術を有していることはもちろん重要ですが、それ以前にひとりの社会人として備えているべき、これら5つのPを欠いていたままでは、持っている知識や技術を有効活用できないばかりか、かえってこれらのスキルを使うこと自体が危険になる場合すらあり得るからです。
本稿では、医療現場で研修医を教育する者としての視点から、これらの医師にかぎらず社会人として有しているべき基本的なコンピテンシーについて私見を述べるとともに、これらに問題を抱える新人に接した場合に、いかなる方略を講ずるべきかについても考えてみたいと思います。
■穏やかさから主体性まで、新人に求める資質
まずPeacefulness。穏やかで温和な人物であるか、これは病める人を対象とする私たちの職業ではとくに重要ですが、顧客や、同僚・チーム内での人間関係を考えれば、医療機関にかぎらずすべての業種に必要とされるものでしょう。
つぎにPoliteness。礼儀正しく丁寧、態度や言葉が乱暴でないということも、あらゆる職業において共通して必要とされる重要なコンピテンシーといえるでしょう。
そしてPunctuality。「○○時から始めます」といわれた場合に、遅れるのは論外ですが、○○時に登場するのでも間に合ったとはいえません。遅くとも開始時刻の10分前には現場に到着していなければ、業務を円滑に始めることはできないとの意識を持っておくことが望まれます。
これらはまさに基本の「き」といえるものですが、これらができていても、じっさいの業務で欠いていると困るのが、Priority。今すぐ着手せねばならないことを放っておいて、今やらなくてもいいことにこだわり続けるのは、非効率であるばかりか、ときとして危険な場合すらあります。状況を俯瞰して、今なにが大切かの優先順位を見きわめられる能力は非常に大切です。
■「指示待ち」ではなく自ら行動する姿勢を
最後にProactiveness。優先順位にも関係することですが、つねに状況を俯瞰するなかで、自分で対応可能なことについては「指示待ち」ではなく、自ら能動的かつ主体的に行動することが望まれます。もちろん独断による暴走は論外。ホウレンソウをこまめにおこなう必要があることは言うまでもありません。
一般の企業と同じく、医療機関でも新年度から新人医師が配属されてきますが、現在の状況と比較するために、私が新人だった30年前の状況に軽く触れておきましょう。
当時は医学部を卒業して国家試験に合格すると、すぐに自分の希望する診療科の大学医局に入局する者が大多数でした。私も卒業してすぐに大学の外科医局に入り、「研修医」として、学習者と労働者双方の立場で勤務を開始しました。
当時の研修医を指導する先輩医師たちの多くは「昭和時代卒」であり、外科のなかでも私が所属した医局はかなり封建的でした。現在であればSNSなどでパワハラとして問題になってもおかしくないような「指導」が普通におこなわれていましたが、それでも先輩たちは「今の研修医たちは甘やかされすぎ、昔はもっときつかった」と口をそろえて言っていたものです。いわゆる「先輩の背中を見て学ぶ(真似ぶ)」という典型的な徒弟制で、ていねいなフィードバックはほぼ皆無であったといってもよい状況でした。
■たった4週間で新卒を見極める
一方、昨今の医学部新卒者は、まず2年間、初期臨床研修医となり、将来どの診療科に進むにせよ、ひと通りの診療科を一定期間ずつローテーションする(詳細は紙幅の都合もあり割愛)ことになっています。つまり、行く先々で短期間かつ異なる指導環境に身を置くことになるわけです。
私が研修医の教育指導をおこなっている医療機関も、ゼロから一人前の医師にまで育て上げるという長期的スパンでの医師養成をおこなうことはありません。医学部卒業後2年目の初期臨床研修医の地域医療研修を受け入れていますが、彼らの当院での研修期間は一人あたり4〜5週間。出会って、なじんで、慣れてきたところで研修期間は終わってしまいます。
つまり、この短期間のあいだに、彼らの有するコンピテンシーを見きわめ、課題(学習目標)を提示しおこなわせ、観察し、フィードバックをし、再びおこなわせて、評価するという作業を繰り返しやらねばなりません。
したがって研修医の5つのPについては、研修開始初日の出会ったその瞬間から、私の持つすべての感覚器官を駆使して観察していくことになります。その観察をもとに、学習目標到達への道筋を個々に合わせて微調整していくわけです。
写真=iStock.com/west
※写真はイメージです - 写真=iStock.com/west
■最初に「あなたはお客様ではない」と伝えること
研修期間がほんの1カ月しかない研修医であっても、患者さんからみればひとりの医師。まず研修医には「あなたはお客様ではありません。うちのチームの一員として患者さんに接してください」と一番最初に伝えます。そしてじっさいに患者さんと主体的かつ積極的にコミュニケーションを持つよう指導していきます。
この方略により、Peacefulness、Politeness、Punctualityについては、最初の数日でほぼ把握できます。一方、Priority、Proactivenessについては、もう少し把握と評価に時間が必要です。
山本五十六の「やってみせ、言って聞かせて、させてみせ、ほめてやらねば、人は動かじ」という言葉をご存じの方も多いでしょう。旧日本軍の軍人の言葉ではありますが、これは今もいかなる現場でも通用する、指導者・教育者の心得の基本の「き」といってもよいと思います。
医学教育の現場では、一人前の医師として独り立ちさせることが大きな目標であるので、どこまで任せられるかということを評価しなければなりません。とはいえ、なにも知らない新人に、説明も指導もせぬまま初めてのタスクを課して、「なんだやっぱりできないじゃないか」と言うのでは、評価になりませんし、とても教育にはなりません。
■プロ意識に欠けるベテランが誕生しないために
まずは指導者が手本となる行動を示して、その行動についての説明をしたうえで、じっさいに新人にさせてみるというステップが必要なのです。そしてこの「させてみる」も、まずは指導医の直接監督のもとおこなわせ、そこである程度のレベルに達していると評価できれば、つぎはいつでも困ったときには指導医が駆けつけられる状況で「させてみる」。さらにそのステップがクリアできた場合には、同様のタスクについては単独でおこなわせる、という手順を踏みます。
これは医療現場以外の職場でも、おおむね同様ではないでしょうか。
さて、このような新人教育のなかで、もし彼らのプロフェッショナリズムにもとる行為(アンプロ行動)に気づいた場合、指導者がどのように行動するのが望ましいかも考えてみたいと思います。(医師のプロフェッショナリズムについては過去記事〈女児の陰毛を診察した「専門医」は、なぜ「今後も見る」と開き直ったか…元大学教授がトンデモ行動に出る根本原因〉を参照)
アンプロ行動とは、おもに医療現場で働く専門職について問題とされるもので、医学教育の分野で多くの論文のもと議論されていますが、医療機関にかぎらず一般企業における新人教育指導の現場においても、少なからず同様の問題を抱えているのではないかと思われますので、ヒントにしていただければと思います。
■欠席や遅刻も「アンプロ行動」の一つ
医学教育学のある論文によれば、アンプロ行動は「4つのI」、Involvement(関わり)、Integrity(誠実さ)、Interaction(相互関係)、Introspection(内省)に分類されます。
具体的に例示すると、Involvement(関わり)には、欠席や遅刻、チームワークがない、自主性の欠如などが、Integrity(誠実さ)には、データ改竄や捏造、同意取得なしの行動や、規則の不遵守、Interaction(相互関係)には、差別やセクハラ、不適切な服装、SNSの不適切使用など、そしてIntrospection(内省)には、フィードバックを受け入れない、自己の限界を認識しない、自分の不備ではなく外部要因を非難するといった行動が、それぞれ挙げられます。
このように見ると、医療現場でアンプロ行動と言われるものが、必ずしも医療業界にかぎったものではないことに気づかれるのではないでしょうか。問題は、指導者・教育者がこれらに気づいたときに、どのように対処すべきかということです。
■「見て見ぬふり」がもたらす悪循環
新人指導をおこなっていくなかでは、誰でも、できれば口うるさいことは言いたくないと思うことでしょう。かりにアンプロ行動を見てしまっても「とりあえずもう少し様子をみよう」と考えてしまうこともあるかもしれません。もっと過激に「できないやつの指導に時間は使えない。切り捨てるのみ」と考える指導者もいるかもしれません。じっさい医学教育者の20%が学習者のアンプロ行動を観察しながら、報告するのは3〜5%とする論文も存在します。
そもそもマイナスの評価を下したり、注意や警告したりすることは、指導者にとってもかなりの精神的なストレスになり得ます。しかし、だからと言って、指導者が見て見ぬふりなど反応しなかった場合、さらには指導者自身が同じようなアンプロ行動をするなどしていた場合、新人はその行為が容認されうるものと受け止めてしまい、行動変容さえも無意味で不要と考えてしまうことになってしまいます。
もちろん、今すぐこれらに対処するのはひとりでは困難でしょう。まずは組織としてプロフェッショナリズムとはなにかという共通認識をもったうえで、それにもとる行為とはなにか、つまり「アンプロ行動とはなにか」との定義を共有しておくことが大切です。
写真=iStock.com/b-bee
※写真はイメージです - 写真=iStock.com/b-bee
■2年目、3年目になるとすっかり「お医者様」に…
そして「アンプロ行動のような行動」を確認したときも、単独の評価者による拙速な決めつけや、思い込みによるレッテル貼りをおこなうことなく、できるだけ複数の人間で、可能であれば多職種をまじえた多角的視点からの観察評価が望ましいと考えます。
なぜなら「アンプロ行動」には、その要因として、そのひと個人の問題だけでなく、個人間、外的要因や状況的な要因もあるうえに、そもそも本人がプロとなることを前にして、一時的にスキルや適切な態度を欠いているに過ぎない場合もあるからです。そのような行動をとった理由や状況を、まず本人から十分聞きとり一緒に考える姿勢が、指導者に求められると思います。
逆に、新人のころにはあったPeacefulness、Politenessが、2年3年と経過するにしたがって失われ、傲慢な「お医者様」になってしまうケースも少なからず目にします。残念ながらそのような医師は、先輩医師のアンプロ行動を「規範」として身につけてしまったと思われ、新人の場合よりも、さらに行動変容が困難となります。
学習者のみならず教育者であってもアンプロ行動をとり得るということ、プロフェッショナリズムというものは、学習者と教育者が同じ標準のもと協働して高めていくべきものという認識を先輩たる教育者自身が持っておく。この謙虚さこそが、アンプロ行動を予防するために先輩が後輩たちに見せるべき「背中」と言えるかもしれません。
----------
木村 知(きむら・とも)
医師/東京科学大学医学部臨床教授
1968年生まれ。医師。東京科学大学医学部臨床教授。在宅医療を中心に、多くの患者の診療、看取りをおこないつつ、医学部生・研修医の臨床教育指導にも従事、後進の育成も手掛けている。医療者ならではの視点で、時事問題、政治問題についても積極的に発信。新聞・週刊誌にも多数のコメントを提供している。著書に『大往生の作法 在宅医だからわかった人生最終コーナーの歩き方』『病気は社会が引き起こす インフルエンザ大流行のワケ』(いずれも角川新書)など。
----------
(医師/東京科学大学医学部臨床教授 木村 知)