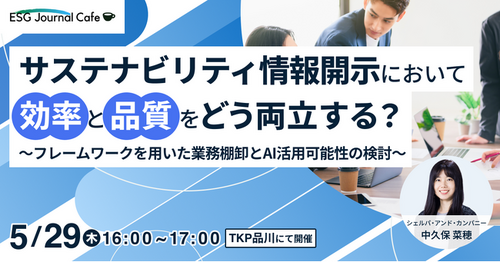迫る、「サステナビリティ2026問題」 ~日本企業のSXの加速を支援する~
2024年11月28日(木)12時0分 PR TIMES STORY

2027年3月期から、サステナビリティ情報の開示が義務化される見込みであると、サステナビリティ基準委員会の発表で明らかになりました。対象企業は2026年度から、SSBJの制度開示に向け、グループ連結でのデータの信頼性、網羅性を担保する内部統制とそれを支えるIT統制の整備を行い、サステナビリティ関連情報の収集・集計・開示が求められ、財務影響分析やマテリアリティープロセスの見直しなども求められます。CSRDにおいてはダブルマテリアリティであることから、非財務開示内容、ストーリーとの一貫性、評価とそのプロセスの一貫性が、制度保証で確認されます。一方、上記対応に向けコーポレートだけでなく、ビジネスサイドとの連携に向けた体制構築や情報開示のためのプロセス等、準備が充分でない企業が多いのが現状です。
そこで、サステナビリティERP「booost Sustainability Cloud」を提供するbooost technologiesは、状況を変えるため、2024年11月にプロジェクトを発足。情報開示への対応が2026年に迫っている問題を「サステナビリティ2026問題」と名付け、伊藤忠商事株式会社、BIPROGY株式会社、パーソルビジネスプロセスデザイン株式会社など、賛同企業とともに、解決のための取り組みを始めました。
「サステナビリティ2026問題」とは何か、プロジェクトの概要をbooost technologiesの代表取締役の青井 宏憲に聞きました。
サステナビリティ情報の開示義務化で、より厳密な情報管理が求められるように
ーーあらためて、「サステナビリティ2026問題」とは何かを教えてください。
青井
「サステナビリティ2026問題」とは、サステナビリティ情報の開示義務化にあたって、多くの企業で着手が遅れており、その危機感も不足しているため、このままでは企業価値の低下につながってしまう懸念がある状況のことです。
背景には、サステナビリティ情報の国際的な開示基準を策定するISSB(国際サステナビリティ基準審議会)が2023年6月に国際開示基準を公表し2024年1月に発効されたことを受けて、2024年3月、サステナビリティ基準委員会が、日本版のサステナビリティ情報開示基準の草案を公表したことにあります。2027年3月期から、時価総額3兆円以上のプライム上場企業を対象に適用され、その後、順次、対象企業が拡大される見込みです。これまでも任意開示としてサステナビリティ情報の開示は行われてきましたが、2027年3月期よりサステナビリティ情報も制度開示となるため、これまで以上に厳密なサステナビリティ情報の集計・開示体制を整えて2026年度を迎える必要があります。
「情報開示の項目を増やしエクセルやForm等で挑めれば良い」程度に考えている企業も多いですが、そのままの理解でいることは経営における大きなリスクです。制度開示が適用されることでとくに重要な点は、サステナビリティ情報開示の信頼性向上に寄与する第三者保証とその水準として、合理的保証を見据え、いかに財務同等水準のIT統制を担保するのかという点です。
これまでは、サステナビリティ情報の開示については第三者保証が任意であったため、監査法人等の第三者による任意での保証(会社が定めたルールへの準拠性の確認)がおこなわれていれば、問題はありませんでした。しかし今後は、限定的保証、合理的保証と上場企業の財務情報の監査と同レベルで、監査法人等の専門機関による第三者保証の対応を行う必要があります。データの網羅性や正確性について厳しく見られ、情報収集のプロセスやIT統制が効いているか等も確認されます。
これまでExcelやForm等で、承認ワークフローや権限設定等のIT統制を利かせず実施していた、グループ会社間のバケツリレーのような情報収集では対応が充分ではなく、保証期間の長期化とそれに伴う保証コストの増大につながります。そのためグループ連結で、より正確で、厳密なIT統制を整えなければならないのです。

本質的なSXへの取り組みに挑戦する企業を増やしたい
ーープロジェクト立ち上げのきっかけや、背景にあった思いを教えてください。
青井
きっかけは、私たちのお客様から、制度開示への対策や、制度保証を見据えたIT統制の整備、サステナビリティ情報をどのように経営に活かすのかといった問いが増えたことです。
サステナビリティ関連情報を開示し経営に活かす取り組みが、すでにESGリスクプレミアムを踏まえた企業価値や株価に直結しています。私たちが支援する企業のなかには、サステナビリティ経営に真摯に向き合い続けた結果、高いESGスコア(投資家が企業価値を把握するために用いられる指標)を獲得したことで、機関投資家からのESG投資が1,000億円以上なされている事例も多々あるのです。
DXと同様、経営のSX(Sustainability Transformation)が求められています。しかし、制度開示が求められる規模の大きな会社ほど、グローバルに組織のサイロ化が進み、「サステナビリティ推進の担当部署に規制対応だけしてもらえばいい」という考えに陥りがちです。SXへの取り組みは全社で進めなければうまくいかず、「経営=サステナビリティ」と言えるレベルまで、到達しなければならないのです。
このままだと日本の多くの企業が、本当に取り組むべき企業価値向上やSXへの議論ができず、その結果、規制対応もうまくいかないのではないかと危機感をおぼえました。すでに、サステナビリティ情報の開示が始まっている欧州では、SX推進のための経営、変革がおこなわれています。日本が世界から取り残されてしまうという危機感も強くありました。
上記、規制に対応した開示をゴールにするのではなく、規制対応を一つのきっかけに、事業を含め、真のSXに挑戦する企業が増えなければ、日本のみ失われた30年が継続してしまうという危機意識から「サステナビリティ2026問題」として日本全体の問題であると打ち出し、産官学で広くその普及を通した理解の促進と解決につながるアクションを日本全体で実行するためのプロジェクトを始めたのです。「サステナビリティ2026問題」として社会課題化することで、業務負荷が高いと感じる担当者の方々が声を挙げやすくしたいという狙いもあります。
サステナビリティ2026問題に危機意識を持つ産官学の一体となった共同体の組成と変革のための学びのための機会提供
ーーサステナビリティ2026問題を解決するための本プロジェクトでは、具体的に何をするのか教えてください。
青井
今予定しているのは、大きく2つです。1つ目は、サステナビリティ2026問題に危機意識を持つ産官学の一体となった共同体の組成です。
本プロジェクトは第一段階として、日本企業のSXの動向と課題について社会に提起する狙いがあり、そのために、私たちの考え方に賛同してくださる産官学の皆さまを広く募ろうと考えています。
賛同いただく皆さまには、SXを推進する企業はもちろん、日本企業のSXを共に支援したいと考える企業も含まれます。企業のSX推進のために必要な支援は多岐にわたりますので、コンサルティングファームや非財務情報も取り扱う会計監査法人など、あらゆる分野の企業や各省庁、大学等にもご賛同いただき、一緒に日本企業のSXに貢献できればと考えています。
2つ目は、学びのための機会提供です。
CEOやCFOなど各部門の責任者にお集まりいただき、SXリーダーの話を聞く勉強会の開催を考えています。欧州ではすでに当たり前になりつつある、CSO(Chief Sustainability Officer)と同じレベルまで知見を高め、サステナビリティ経営について活発に意見交換できる場を提供できればと思っています。
実務ご担当者向けには、会員数500名を超える日本最大級のサステナビリティリーダーの集うコミュニティ「Sustainability Leadership Community(SLC)」とも連携し、情報開示に特化した勉強会やワークショップを実施し専門性の高いSX人材の創出に取り組む予定です。

あらゆる環境、社会の課題が解決した未来を目指して
ーーbooost technologiesとしての今後の展望について教えてください。
青井
まずは、あらゆる企業に目前に迫る「サステナビリティ2026問題」を乗り越えてもらうことが目標です。そのために、引き続き「サステナビリティ2026問題」の理解促進に力を入れると同時に、グローバルにIT統制を利かせた膨大なサステナビリティデータの収集・管理ができる体制づくりの支援ができればと考えています。
そのうえで、収集したデータをベースにした、データドリブンのSX、サステナビリティ経営の実現まで伴走したいと考えています。各種の規制を守ることは当たり前であり、環境や社会に対してどれほどプラスの影響を与えられるのかを追求するつもりです。
また、SX推進を担える人材がまったく足りていません。今回のプロジェクトを通して企業や組織のSX、GX人材育成を急ぎ、教育機関と連携し、プログラミングや投資と同じようにサステナビリティに関する社会的な教育も、推進していければと考えています。
本質的なSXに取り組む企業が増えると、社会問題とされているあらゆる点が自ずと解決していくはずです。環境破壊が引き金となって起こる生態系の破壊や食糧不足はもちろん、児童労働や差別といった人権問題も含め、「サステナビリティ」に包括されている数々の問題が解決され、より良い社会に近づけると考えています。
このような世界の実現を目指して、私たちは引き続き、挑戦していきます。

行動者ストーリー詳細へ
PR TIMES STORYトップへ