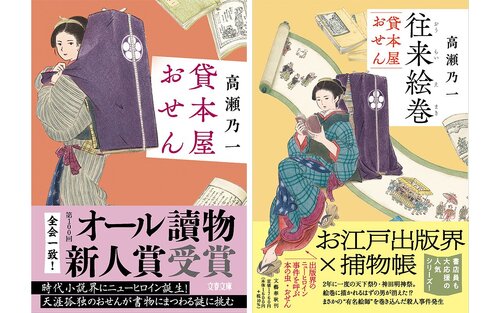業界最注目の著者による人気シリーズ、ついに文庫化! 「これを読んで胸をわしづかみされない本好きはいないのでは」書店員さんによる解説を全文公開!
2025年5月20日(火)7時0分 文春オンライン
文化年間の江戸。女手ひとつで貸本屋を営み、高荷を背負って江戸の町を巡るおせん。坂木盗難や幽霊騒ぎ、幻の書物探しなど読本に係わる事件に立ち向かう、異色の「ビブリオ捕物帳」——『 貸本屋おせん 』シリーズ。
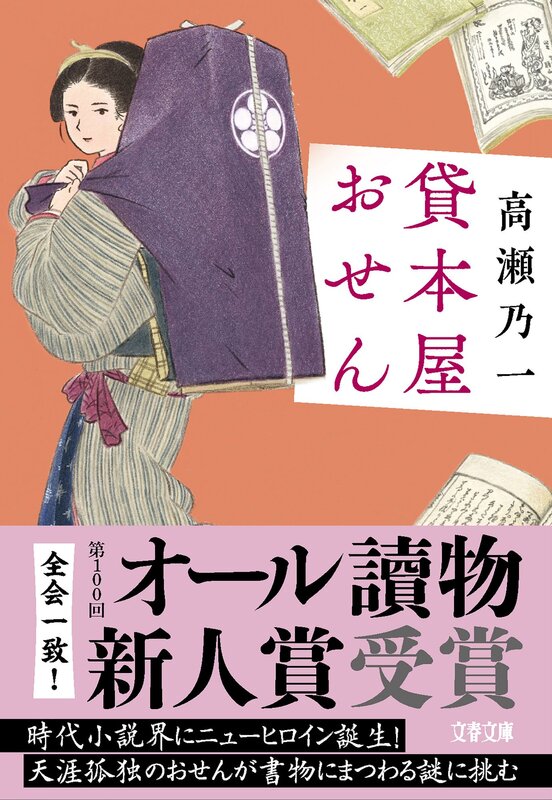
デビュー時から話題沸騰、いま歴史時代作家業界で再注目の著者による本書が、ついに文庫化、発売即重版となりました! さらにシリーズ2作目となる『 往来絵巻 貸本屋おせん 』も5月14日に発売です。
2冊の刊行を記念して、文芸書評などでも活躍する精文館書店中島新町店の書店員・久田かおりさんによる、『 貸本屋おせん 』文庫解説を全文公開します。本書の魅力をぜひ堪能してみてください!
◆◆◆
江戸のメディア王蔦屋重三郎が主人公の2025年NHK大河ドラマ「べらぼう」にも出てくるが、貸本屋というのは江戸時代に始まった見料を取って本を貸し出す商売で、1960年代初頭までは続いていたらしい。今で言うレンタルコミックの先駆けである。日本の識字率は世界に類を見ないほど高かったという説もあるが、確かに江戸時代に庶民相手の貸本屋が成り立つくらい文字を読み、本を楽しむ人が多かったのだろう。横浜流星演じる「べらぼう」蔦屋重三郎は高荷を背負って店を訪れ吉原の女郎相手に、相手の好みそうな本を見繕って貸し出している。「読書」は苦界に生きる女たちにとっていっときの現実逃避だったのかもしれない。
高瀬乃一とは何者なのか
そんな蔦重もちらりと出てくる『貸本屋おせん』は文化年間の浅草を舞台にした「ビブリオ人情捕物帖」だ。作者の高瀬乃一は第一話として収録されている「をりをり よみ耽り」で第100回オール讀物新人賞を受賞しこの連作短編集でデビューした。その後も、来世の地獄か今の欲かを選ばせるファンタジックかつブラックな『無間の鐘』(講談社)、ミステリ仕立ての医療時代小説『春のとなり』(角川春樹事務所)、そして幕末を舞台に時代の波に飲まれていく下級幕臣を描いた『梅の実るまで 茅野淳之介幕末日乗』(新潮社)と、趣の違う作品を発表し続ける期待の時代小説家だ。
『貸本屋おせん』は2023年本屋が選ぶ時代小説大賞にノミネートされたが、残念ながら大賞は逃している。実はその選考委員として不肖私も参加させていただき、選考会の会場で最初から最後まで、ただただひたすらにおせんを推し続けておりました。「本屋としてこんなに本への愛に満ちている小説を推さずに何とする!」と。今回その「おせんLOVE」がご縁で解説依頼につながったのかも知れないですね。僭越ながらおせんの魅力をお伝えできたら、と思っております。
主人公のおせんは浅草の長屋に一人で住んで貸本屋を営む二十四歳の娘だ。父親は「後れ毛平治」の異名をとる腕のいい版板彫り職人だったが、おせんが十二歳のときに自死している。平治が彫っていた板が御公儀を愚弄した内容だという咎で罰せられ、その後、おせんの母親は若いツバメと駆け落ちし、平治は自暴自棄になり自らの命を絶ってしまった。この父親の死が、いろんな意味でおせんの人生を形作ることになる。
幼い娘が一人で生きていくのは容易ではない。けれど長屋にはたくさんのおせっかい焼きの「おかあさんたち」が、町にはおせんの仕事を見守ってくれるたくさんの「おとうさんたち」がいる。彼らの温かい目と手がおせんを育ててくれたのだろう。この第一話には、そんなおせんの生い立ちや、貸本屋になったきっかけ、「本を貸す」ことの意味、そして何より貸本屋としてのおせんの矜持がつまっている。「本を貸すだけじゃない。守るんだよ」という言葉。これを読んで胸をわしづかみされない本好きはいないのではないだろうか。
あの「べらぼう蔦重」も登場⁉
第二話からは、そんなおせんのもとに転がり込んでくる「事件」の謎解きと顛末がテンポよく描かれていく。
「板木どろぼう」はおせんを見守るおとうさんのひとり、地本問屋喜一郎の持つ板木が盗まれたところから始まる。しかもそれが今を時めく曲亭馬琴の作だというから大事件だ。ここで登場するのがべらぼう蔦重だ。いや、事件にはかかわりはないのだが、喜一郎が仲の悪い同業者の伊勢屋と相板(お金を出し合って合同で出版をすること)してまで馬琴の本を出そうとした理由が「にくにくしい蔦屋耕書堂」に打ち勝つための大勝負だったというわけだ。
地本の草分け的老舗問屋で江戸一番の本屋にまで上り詰めた蔦屋耕書堂に喧嘩をふっかけようとしたのに、肝心の板木が盗まれたとあっては大恥だ。そこで江戸中の書肆に顔の出せる貸本屋であるおせんに白羽の矢が立ったのだ。おせんは足を使った聞き込み捜査を始めることとなる。このあたりから出版関係の専門用語がたくさん出てくる。今も使われている言葉もたくさんあり、いちいち感心してしまうのだが、本書の正しい読み方としてはいろいろ出てくる知らない言葉を一読目はスルーしてひたすらおせんの謎解きに浸るのがいいだろう。
そして読み終わった後、二読目三読目で思う存分辞書を引いたり検索したりして出版豆知識を増やしていっていただきたい。というのも、『貸本屋おせん』の魅力の一つに「テンポの良さ」というのがある。物語の展開も、登場人物たちの会話も、とにかく心地よいテンポで流れていくのだ。まずはその流れを遮らず波に身を任せて最後まで読み終えて下さいまし。
さてさて板木どろぼうはどうなったのでしょう。誰が何のために盗んだか。おせんの幼馴染み青菜売りの登の大活躍で明らかになったその理由と結末に、なるほどこれは「人情」捕物帖だわと納得する。そして転んでもただでは起きない江戸商人のしたたかさに思わずニヤリとするだろう。
第三話「幽霊さわぎ」は本ではなく錦絵が主役で「書入れ」というひとつの文化が描かれる。それは本来読物に歴代の持ち主が書き込んだ注釈のことでよくある落書きとはわけが違う。書かれた文字は本の一部となり新たな読者への道標となるのだ。今でもさまざまな書入れは「マルジナリア」と呼ばれ一部ファンにとってはたまらない宝物となっているようだ。気になる方は山本貴光著『マルジナリアでつかまえて 書かずば読めぬの巻』(本の雑誌社)をどうぞ。誰かが書き込んだ文字、それをたどる本の旅、唯一無二の存在、それが「書入れ本」なのだ。
そんな書入れが施された美人絵を手に入れたおせん。モデルはあまりの美しさに亭主が家の奥に囲い込んでほとんど誰もその顔を見たことがないという美しき女将。その亭主の頓死と通夜の伽での手代と女将の房事。そこから起こったよみがえりと幽霊さわぎ。我らがおせんが解き明かす、書入れの秘密と幽霊の謎。大人気の錦絵への書入れに込められた思いが切ない。
幻の源氏物語「雲隠」をさがす恋物語も
第四話「松の糸」は全五話の中で一番軽やかで一番清々しい。「うぶけ八十亀」という名古屋人ならちょっと反応してしまいそうな名前の刃物屋の、惣領息子の恋のから騒ぎ。名の知れた色男公之介が惚れたのは料理屋の出戻り娘お松。誘いに乗らないお松が出した一緒になる条件がなんと源氏物語の幻の書「雲隠」を探してくれたら、というもの!
この「雲隠」というのは源氏物語の「幻」と「匂宮」の間に存在すると言われているが誰も見たことがない幻の帖なのだ。この世にないものを探してくれたら一緒になるなんて、まるで竹取物語ではないか! とワクワクしながら読んでいくと、どうやら探しているのは亡くなった元夫による「雲隠」の写本だという。恋煩い中の公之介に捜索を頼まれたおせんは人脈をフル活用して調査を始める。
もしも幻の「雲隠」が手に入ったら大儲けだという下心もありつつ、本当に写本が存在するのなら一目見たい読んでみたい、という本好きの虫も騒ぎ出す。気になりすぎて夢に光源氏まで出てきちゃったというのだから相当だ。でもまぁ、そりゃそうだろう。そんなものがあるのなら源氏ファンならずとも読みたくなるってもんですよ。
そしてこの雲をつかむような探し物の探し方にも注目されたし。人が亡くなったとき、その持ち物はどうなるのか。ゴミとして捨てるものもあるし、今でいうリサイクルに出すものもあるだろう。では、本はどうするか。まぁたいていは古本屋、書肆、好事家に売るだろう。おせんも当然そう考える。けれど、本に全く関心のない人が本を処分するなら……。
なるほどそっちか、と妙に感心してしまった。さて「雲隠」の写本はあったのかなかったのか。その結末と共に、夫が亡くなったあとその両親に追い出されたお松が夫の遺した写本をどうしても取り戻したかった理由、そして公之介とお松の恋のから騒ぎの顛末をどうぞお楽しみに。
第五話「火付け」はラストを飾るにふさわしい物語。吉原と火事というお江戸とは切っても切れない題材をもとにおせんと登の幼馴染みコンビがまたまた大活躍する。
火事で焼け出された妓楼での足抜け騒ぎ。大門の外での仮宅に出るよう命じられたお針の小千代がとある策でまんまと妓楼を脱出。執拗に必死に後を追う破落戸たち。たかがお針一人に、という疑問。何か裏が?と、ここまでならおせんには何のかかわりもない話なのだけど、小千代はおせんから借りた式亭三馬の「両禿対仇討」の写本を持ったままだという。
おせんの手による写本なのでそれほど値打ちはないのだが、おせんにはこの写本をどうしても返して欲しい理由があるのだ。おせん&登チームは破落戸ヤカラたちより先に小千代にたどり着けるのか。まさに手に汗握る展開と第一話につながる写本の秘密に思わずうなるだろう。いやぁ、うまいねぇ。ちゃんと伏線回収されました。おせんの中にある本への、父親への思いの深さが心にしみる。
おせんのキャラクターの妙
『貸本屋おせん』の魅力の一つがそのテンポの良さだと先に書いたが、もう一つ忘れちゃいけないのはおせん自身のキャラクターだろう。けなげでいじらしい、と描かれがちな不幸な生い立ちの少女を、クレバーでタフで、ある意味図太さも持つ自立した女性として描くところに作者の女性観が見える気がする。何度転んだって何度でも立ち上がるしぶとさと、自分の人生は自分の足で歩いて行くんだという強い思いを持つおせんの魅力がたっぷり詰まっている。
明けない夜はない、けれど暮れない朝もない。目先の明るさを見せるだけじゃない、現実の厳しさと、また夜が来る悲しみの世をそれでも自分の力で渡っていく逞しさが何よりの魅力なのだと思う。
(久田 かおり/文春文庫)