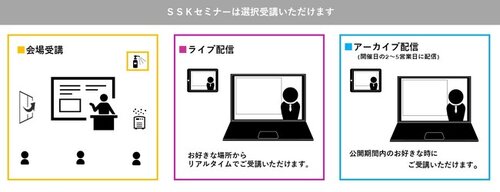“悪者”の水素が金属の強度・延性向上の鍵だった! - 原子力機構など発表
2025年4月2日(水)17時26分 マイナビニュース
日本原子力研究開発機構(原子力機構)とJ-PARCセンターは4月1日、金属に侵入した水素が強度と延性を低下させる「水素脆化(すいそぜいか)」を引き起こす一方で、特定の条件下では強度と延性を同時に向上させる可能性も示唆されていたことを背景に、水素が金属の変形過程に及ぼす影響を詳細に解析した結果、金属内に侵入した水素が原子の配列を歪ませ、線状の欠陥である「転位」の動きを阻害することで強度が向上すると同時に、面状の結晶欠陥の一種である「変形双晶」ができやすくなることで延性も向上するという新たなメカニズムを解明したと発表した。
同成果は、原子力機構 J-PARCセンターの伊東達矢博士研究員、同 マオ・ウェンチ博士研究員(研究当時)、同 ゴン・ウー研究副主幹、同 川崎卓郎研究主幹、同 ハルヨ・ステファヌス研究主幹、物質材料研究機構(NIMS)の小川祐平研究員、同 岡田和歩研究員、同 柴田曉伸上席グループリーダーらの共同研究チームによるもの。詳細は、ナノ構造を含む無機材料の全般を扱う学術誌「Acta Materialia」に掲載された。
水素エネルギー社会の実現には、安全な水素貯蔵・輸送材料の開発が不可欠だ。しかし金属は水素との相性が悪く、内部に侵入されると脆くなる水素脆化が引き起こされてしまう。その一方で近年になって、特定の条件下では水素が金属の強度と延性を改善するということが報告されていたが、その詳細なメカニズムは未解明だった。そこで研究チームは今回、中性子回折を用いた変形試験中のその場観察を実施し、水素が金属の変形過程に及ぼす影響を詳細に解析したという。
今回の研究では、「Fe-24Cr-19Niステンレス鋼」(以下、SUS310S)を270℃・100MPaという高温・高圧の水素環境下に200時間曝露した後、合金重量に対し1万分の1.4程度の水素が導入された。そして中性子回折により、“引張変形中の水素を添加したSUS310S”(以下、水素添加材)と“通常のSUS310S”(以下、母材)の構造変化を観察。その結果、水素が強度と延性を向上させるメカニズムが明らかとなったという。
水素添加材と母材の中性子回折の結果、原子配列が作る格子(結晶格子)の方位や結晶面間隔に応じ、異なる位置に回折ピークが確認された。水素添加材では全方位で結晶格子が膨張しており、SUS310Sへの水素の侵入により、格子がわずかに広がり歪んでいることが判明したとのこと。金属の結晶格子に歪みが生じると、転位の移動が抑制され、変形開始時の抵抗が増加して強度が高まる「固溶強化」が生じる。なお転位とは、金属などの結晶性材料が外力で変形する際に生じる原子配列の欠陥が線状に連なったものである(同じ結晶性材料でも、金属はセラミックスに比べ、外力によって転位が生じやすく移動しやすいため、脆性破壊せずに変形できる)。
.