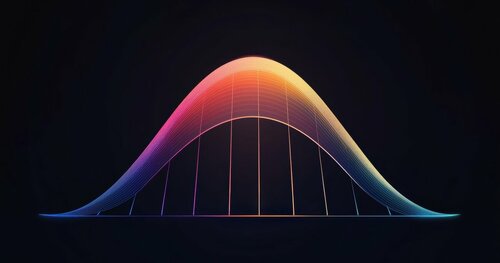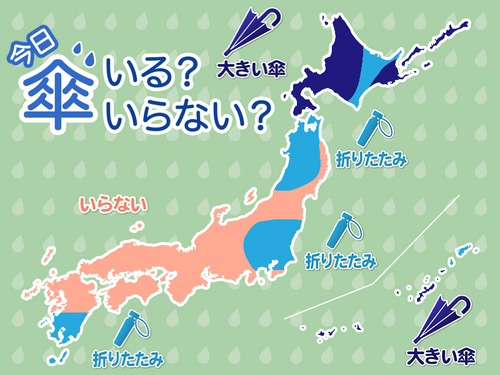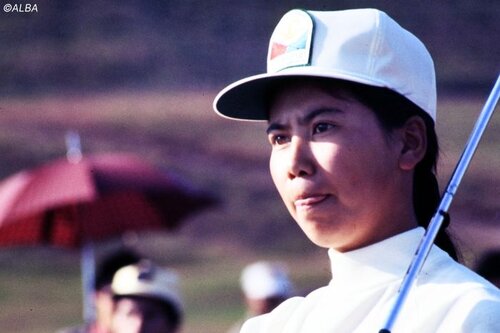メーカー担当者が解説! 自作PCパーツの“あるある”トラブルを避けるためにできること
2025年4月21日(月)11時10分 ITmedia PC USER
ゲスト登壇者の皆さん。上段左から日本AMDの佐藤氏、ASRockの原口氏、GIGABYTEの川村氏。下段左からMSIの富原氏、ASUS JAPANの市川氏、ZOTACの圓井氏
この記事では、4月12日に開催されたステージイベントのうち、筆者が特に気になったものの模様をお伝えする。
●今後のPCパーツのトレンドは?
ステージイベントの1発目は「次世代PCパーツ最新トレンド発表会」だ。読んで字のごとく、これからのPCパーツのトレンドをパーツメーカーの担当者が語るという趣向で、日本AMDの佐藤氏、ASRockの原口氏、日本ギガバイト(GIGABYTE)の川村氏、エムエスアイコンピュータージャパン(MSI)の富原氏、ASUS JAPANの市川氏、ゾタック日本(ZOTAC)の圓井氏をゲストに迎えて行われた。司会はアスクの徳田氏が務めた。
お勧めの自社製品は?
最初のお題は自社の“一押し”製品の紹介だ。
ZOTACの圓井氏は「AMP Extreme INFINITYシリーズ」シリーズのグラフィックスカードを一押しした。これは同社のグラフィックスカードにおいて“最上位”に位置するものだ。
ASUS JAPANの市川氏は「Prime」ブランドのグラフィックスカードを挙げた。Primeは汎用(はんよう)性を重視したブランドで、市川氏は同ブランドのグラフィックスカードは比較的コンパクトであることを強調していた。
MSIの富原氏は、同社のマザーボード「EZ DIY機能」がもたらす“ユーザーフレンドリーさ”をアピールしていた。EZ DIY機能は組み立てプロセスを簡略化するための工夫だ。
GIGABYTEの川村氏は「全部」と少しズルい回答をしていた。同社はCPU以外の各種PCパーツを“全て”取りそろえているというメリットを強調した格好だ。
ASRockの原口氏は「Radeon RX 9070 XT Taichi 16GB OC」をイチオシした。本製品は、Radeon RX 9070 XTを搭載するグラフィックスカードとしては珍しく、GPU補助電源コネクターに新規格の「16ピン(12V2x6)」を採用している。これにより、性能を高められたのだという。
そして日本AMDの佐藤氏は“変化球”として、AI向けGPU「Instinct」と回答した
気になる他社製品は?
次のお題は、“他社の”気になる製品を挙げるというものだ。
ASUS JAPANの市川氏は、サムスン電子のPCI Express 5.0対応超高速SSD「Samsung SSD 9100 PRO」をイチオシ製品として挙げた。ZOTACの圓井氏は各社のマザーボードが格好良くなったことを褒めていた。
日本AMDの佐藤氏は、ITGマーケティングが展示していた、レノボ・ジャパンのワークステーション「ThinkStation P8」に「Samsung SSD 990 PRO」を16枚搭載した構成のストレージ速度を褒めていた。そしてASRockの原口氏は、同じくITGマーケティングが展示していた「トレポン(※1)」を挙げたところで、時間の都合で終了となった。
(※1)軍や警察の訓練に使う電動エアガン「プロフェッショナル・トレーニング・ウェポン」のこと
●ASUS製グラフィックスカードの魅力は?
その後、同じステージを使ってASUS JAPANによるPRステージが行われた。先ほどのステージにも登壇した市川氏が、同社の「GeForce RTX 50シリーズ」「Radeon RX 9000シリーズ」搭載グラフィックスカードの魅力を紹介した。
ASUSのグラフィックスカードには複数のブランドが存在するが、GeForce RTX 50シリーズの登場に合わせて最上位ブランドとして「ROG Astral」が加わった。
シリーズは水冷を採用した「ROG Astral LCシリーズ」と、空冷のみのとなる「ROG Astralシリーズ」に大別できるが、現時点ではROG Astral LCシリーズではGeForce RTX 5090搭載の「ROG Astral LC GeForce RTX 5090」のみが存在する。
ROG Astral LC GeForce RTX 5090の水冷システムは360mmラジエーターと3基のファンが採用されており、高い冷却性能を実現している。
一方、空冷のROG Astralシリーズは、GeForce RTX 5090搭載の「ROG Astral GeForce RTX 5090」モデルに加えて、GeForce RTX 5080搭載の「ROG Astral GeForce RTX 5080」を用意する。いずれも4連ファンを搭載し、羽根(フィン)の間隔を最適化し、ヒートパイプを沈みこませるベイパーチャンバー構造を取ることで高い冷却性能を実現したという。
GPUのヒートスプレッダーを“磨く”ことで、熱効率を向上させるMaxContactヒートスプレッダーやグリスの代わりに相変化素材GPUサーマルパッドなどのASUS独自技術が採用されている。
信頼性や耐久性を重視する「TUF Gaming」ブランドでは、GeForce RTX 5070/5070 Ti/5080/5090搭載モデルの他、Radeon RX 9070/9070 XT搭載モデルが用意されている。今後、GeForce RTX 50シリーズ搭載モデルは追加予定がある。
本ブランドのグラフィックスカードでは、部品に「ミリタリーグレード」のものを採用することで高い信頼性と長寿命を実現している。3連ファンは両端の2基は反時計回りに、中央の1基は時計回りに回転させることで「乱流」を減らしている。
メインストリームを担う「Prime」ブランドでは、GeForce RTX 5070/5070 Ti/5080搭載モデルの他、Radeon RX 9070/9070 XT搭載モデルが用意されている。こちらも、GeForce RTX 50シリーズ搭載モデルの追加予定がある。2.5スロット設計で、コンパクトなケースに収めやすい「SFF(Small Formfactor) Ready」であることが大きな特徴だ。ベイパーチャンバーやMaxContact Designなど、上位モデルで利用されている技術の多くが使われているのも魅力だ。
●自作PCのトラブルでよくあることとは?
ASUSのPRセッションの後は、再び主催者によるステージイベント「自作PCあるある! トラブル解決テクニック座談会」が開催された。司会を務めるアスクの徳田氏が、ゲストのASRock原口氏、GIGABYTE岡田氏、MSI豊田氏、ZOTAC圓井氏に質問を投げかけるという形式で進められた。
なお、本セッションでは開始前に「パネリストの発言はメーカーを代表して回答しているわけではない」ということが念入りに伝えられた。
封印シールが剥がれていても保証は受けられる?
最初の質問は「製品に付いている各種シールを剥がしても保証が受けられるのか?」というものだった。
これに対してASRockの原口氏は「当社のスタンスとしては、ちゃんと読めればいいというのがあります。シールが剥がれた場合でも、読めればできるだけ対応しています。また、製品を買ったらすぐに、パッケージと本体に書かれているシリアル番号を撮影して保存しておくこともお勧めします。そうすれば、後でシールが汚れたりかすれたりして読めなくなっても、販売経路を割り出せます」と回答した。
GIGABYTEの岡田氏も「基本的には(ASRock)と同じで、製品パッケージのシリアル番号と購入証明があれば、基板のシールが剥がれていても対応はできると思います」と答えた。
MSIの豊田氏は「製品に付いているシールは剥がさないでいただきたいということが前提ですが、パッケージと本体のシリアル番号を事前に撮影していただいて、もし剥がれた場合は(事前に)相談してください」という。ZOTACの圓井氏は「基本的にはシリアル番号の写真を撮っておいて、レシートと一緒に『Gmail』などで自分宛に送っておけば、後で検索しやすいと思います」と回答した。
共通しているのは、シリアル番号などが記載されているシールは、買ったらすぐに撮影して保存しておくべきという点だ。ここは留意したい。
改造やオーバークロックはメーカーにバレる?
次の質問は、「改造やオーバークロック(OC)などをしたら、メーカーにバレて保証が受けられなくなるのか?」というものだった。改造はさておき、オーバークロックについてはメーカーが“ウリ”として訴求することも増えている反面、設定したら保証が無効になる場合もある。どこまでが「保証範囲」なのかという点は、確かに気になる所である。
まず、MSIの豊田氏は「マザーボードの保証という点だけでいうと、『Intel XMP』『AMD EXPO』といったCPU/チップセットメーカーが提供するOC機能、あるいは『Game Boost』『AI Boost』といった当社が提供するワンクリックOCであれば保証いたします。一方で、UEFI(BIOS)または『MSI Afterburner』を使った(手動の)OCは保証対象外です。
ここで徳田氏が「ワンクリックOCをしたのか、マニュアルOCをしたのか分かるのですか?」と突っ込んだところ、豊田氏は「基本的には(UEFIやアプリの)ログを見ないと分からず、工場まで持っていかないと分からないです。ただ、見方を変えるとマニュアルOCで壊れた場合は工場ではバレるということですので、(修理依頼時は)正直に申告していただいた方がありがたいです」と答えた。
ZOTACの圓井氏も「MSIさんと同様に、ワンクリック系のOCは保証対象です。『FIRESTORM』(ZOTACのユーティリティーアプリ)内でいじれる範囲であれば、そもそも壊れることはないという前提ではあるので『バレて保証がなくなる』かどうかは分からないというのが正直なところです。しかし、“ギリギリの”チューニングをすると、基板にダメージが及ぶことがあり、それは工場に持っていけば分かりますので、結局は不正なOCをすると保証がなくなることもあります」と回答した。
ASRockの原口氏は「当社の場合は検査装置が優秀なので、多少でも(OCを)やっていたら速攻で分かります。確実にバレます。『何もしていないのに壊れた』と言われるというと『うーん』という気持ちにはなりますが、あえてグレーな回答をさせていただきます。(OCを)やってるかやってないかはバレますが、サポートしないとは言ってない」と回答。
原口氏は続けて「ただ、普通は無理なOCをすると、マザーボードよりも先にメモリかCPUかGPUが死ぬんですよね。マザーボードが死ぬというのはあまりないですが、OCをするとパーツの寿命が加速度的に縮むので、結局は分かります。なので、動かなくなったら(サポートに)送ってみてという感じですね。物理的な物損がない限り、基本的には交換するといった措置は行っています」ともした。
GIGABYTEの岡田氏は「一応、(申告時に)『改造をした』と書かれてしまうと保証できないですね。当社は堅いメーカーですので。ただ、基板自体の設計をしっかり作り込まれているので耐久性には自信があります。ワンクリックOCに関しては耐えられる範囲で作られていると思いますが、それは保証とはまた違うと思います」と答えた。
据え付けのヒートシンクやファンカバーは自分で外して掃除していい?
続いて「マザーボードのヒートシンクやグラフィックスカードのファンカバーなどは外して清掃してもいいのか?」という質問が行われた。
ZOTACの圓井氏は「すごく答えづらい質問です。自作PCなのかBTO PCなのかでも変わりますが、自作PCならグラフィックスカードをマザーボードから取り外して、『液だれしない』というエアダスターで吹いていただくくらいがちょうどいいと思います。よく『ヒートシンクを外したい』という話も聞きますが、それは完全に保証外の行為となります。エアダスターか、手動のプシュプシュやるやつ(エアブロアー)をお勧めします」と回答した。
ASRockの原口氏は「みんな話しにくいと思うのであえて話しますけど、エアダスターに関しては『ガス式』とか『エア式』とかいろいろあります。特にガス式だと(何らかの理由で)引火する可能性もありますので、圓井さんからもあった通りカメラのレンズなどを清掃する手動のものを含めて、ファンをしっかり押さえた上でエアブロアーで清掃するのがいいと思います」とした。
さらに原口氏は続けて「分解に関しては各社さん一緒だと思いますが、『ネジを外してヒートシンクを外してグリスを塗り直したい』というユーザーさんもいらっしゃると思いますが、基本的に(グラフィックスカードの)サーマルペーストは耐久性に優れた5〜10年くらいは持つ仕様のものを使っているので、正直塗り直す必要はないと思います」とも語る。
パーツがそろいきってから組み立てた方がいい?
次の質問は、「安いタイミングで個別にパーツを購入して、まとまってから組み立てるのはアリか?」というものだった。
MSIの豊田氏は「販売店さんが困りますので、できればパーツを購入したらすぐに動作確認の意味で使ってほしいと思います。初期不良なら販売店でも対応しやすいと思います」と回答した。
ZOTACの圓井氏は「今、特にGeForce RTX 50シリーズを中心にグラフィックスカードの値段が上がっています。グラフィックスカードを買って(資金的に)力尽きて、『クレジットカードの枠が回復するまで待ちたい』という話も聞きます。動作確認が取れるのであれば問題はないんですが、初期不良の保証期間はどうしても店舗によって異なりますし、『動作確認だけをしておいて、来月か再来月に組みましょう』というのはまだいいですが、1年越しとか『月刊でパーツをそろえていくプラモデル』的な買い方をするくらいなら、極力まとめて買うことを強くお勧めします」と答えた。
ASRockの原口氏は「マザーボードなども、1年もたてば新しいのが出たりします。正直、『月刊でパーツをそろえていくプラモデル』的なやり方はしない方がいいと思います」とした上で「ただ、どうしてもそういう買い方をしてしまった場合、『1年越しに組み立てよう』となったタイミングで(パーツの)不具合が発覚して、保証期間がギリギリ切れているみたいなこともありがちです。そんな場合は(発売元の)代理店に相談してみて下さい。厳密にいうと、パーツの保証期間は(原則として)2年間ですが、代理店さんと私たちの間では、店舗在庫を考慮したマージン(余裕)を持っているんです。保証期限から1〜2カ月過ぎてしまい『これ有償だよなぁ……』思っている人は、代理店に相談すれば何とかなる可能性がなきにしもあらずです」と回答した。
基本的にパーツはまとめて買うか、それが難しい場合でも買ったらすぐに動作確認を行うことは心掛けた方が良さそうだ。
「正規販売店」の見分け方は?
最後に「正規販売店の簡単な見分け方は?」という質問が行われた。
MSIの豊田氏は「お客さまがセラー(販売元)の名前をしっかりと確認するのがいいと思います。(Amazon.co.jpなら)絶対的に安心なのは販売元と出荷元の両方が「Amazon.co.jp」である場合です。それ以外のセラーは、メーカー直販か所在が明確な場合を除き避けるのがいいと思います」と回答した。
GIGABYTEの岡田氏は、「セラーさんと代理店が“正規”であれば、保証はちゃんとできます。それ以外の所から買う場合は『届いてみないと分からない』面もあります。ただ、国内向け製品なら、パッケージに保証書シールが貼ってありますから、それが一番分かりやすいです。購入する際は、シールをしっかり見ていただければと思います」と答えた。
ZOTACの圓井氏は「大事なのは、パーツ類の売買契約は『メーカーや代理店とお客さま』ではなく『販売店とお客さま』との間で締結しているということです。販売店の保証体制として『初期不良も含めてメーカーと交渉してください(問い合わせてください)』と書いてるところは絶対にやめた方がいいです」と説明した。
ASRockの原口氏は「セラーなら住所を調べるのが一番ですね。お店の住所で検索して一軒屋だったら結構怪しいとか」と付け加えた。