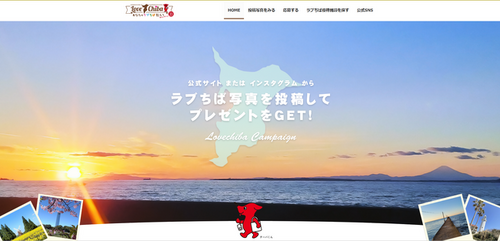SNSフェイク情報にだまされやすい高齢者の特色 テレビ見て新聞読む人にも落とし穴
2025年5月24日(土)16時0分 J-CASTニュース
SNSのニセ情報、ウソ情報を一度信じると、自分の判断の間違いを容易に認めようとしないという調査結果が2025年5月13日に公表された。
総務省が全国の15歳以上を対象に行った「ICTリテラシー、偽・誤情報の拡散に関する実態調査」で、過去に流通した偽・誤情報を見聞きした人に、内容の真偽を尋ねたところ、今でも「正しい情報だと思う」「おそらく正しい情報だと思う」という回答が47.7%で、「誤った情報だと思う」「おそらく誤った情報だと思う」の26.7%を大きく上回った。半分近くがだまされたとは思っていないか、思いたくないのだ。
「自分がだまされるはずがない」
なぜ偽・誤情報を信じてしまうのか。全体では「公的機関が発信源・情報源である」という回答が最多なのだが、60歳以上は「自分で論理的・客観的に考えた結果」「自分の意見や信念と一致していた」という回答が目立つ。「自分がだまされるはずがない」「自分の考えていた通りだ」と思い込む傾向が強いということである。
NHKのシリーズ番組「フェイク・バスターズ」が、「60代の母親が陰謀論にはまってしまった」「夫がこの世界はディープステート(闇の組織)に支配されていると信じてしまった」といった年配者の「被害」を紹介すると、「うちの家族も......」という声が数多く寄せられたという。
高齢層がニセ情報、ウソ情報を信じやすいのには、理由がある。総務省の調査は「偽・誤情報だと気づいた経緯」についても質問していて、4割近くが「テレビ・新聞(ネットを含む)で誤った情報として報じられていたから」と答えている。テレビや新聞を見たり読んだりしている人ほど情報のウソや間違いに気づくということで、高齢層は新聞をよく読むし、テレビのニュースも見ているのだ。
ただ、他の世代と違うのは、退職があったり、パート・アルバイトをやめたりで、人と会うことが減る。そうすると、「そんな情報は嘘!」と言われる機会も減り、特定の情報ばかりに接して、自分の中で妄想をどんどん膨らませてしまうということはないだろうか。
複数の情報源を比較確認すること
マインドコントロールやカルト宗教に詳しい専門学者は、だれでもニセ情報、ウソ情報にはまるという。では、「信じない」「ウソに気づく」ための注意点はあるだろうか。
当たり前のことだが、まず「複数の情報源を確認する」こと。同じ事実でも、メディアによって伝え方は違うので、比較すれば真実かウソ・ニセか判断しやすい。
2つ目は「拡散しない」だ。真偽がわからないまま拡散すると、拡散したことを正当化しようとして、あとで間違いとわかっても認めようとしなくなる、という。
調査では35.2%が「自身はICTリテラシーが高い」と思っていて、「私はだまされない」が一番の落とし穴かもしれない。
(シニアエディター 関口一喜)