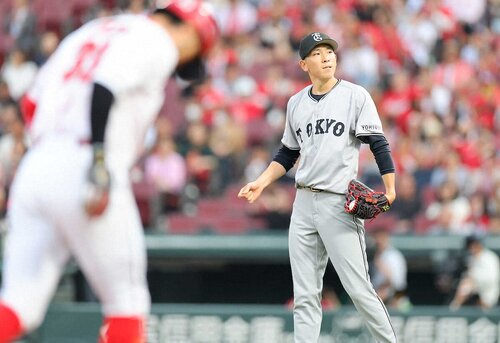東洋大・酒井監督が語る第101回箱根駅伝の真実、エース欠場の大ピンチを乗り越えて掴んだ「20年連続シード」
2025年1月31日(金)6時0分 JBpress
(スポーツライター:酒井 政人)
石田と梅崎の4年生エースが故障
今年の箱根駅伝で継続中としては最多となる“20年連続シード”を成し遂げたのが東洋大だ。4校によるアンカー決戦に競り勝ち、総合9位でフィニッシュ。重圧のなかで10区を務めた薄根大河(2年)はゴール後、涙が止まらなかった。
今季は11月の全日本大学駅伝で13位と惨敗。12月にふたりの4年生エースが戦線離脱する。そして本番では最多6人の選手を入れ替えた。厳しい状況のなかで東洋大はいかに連続シードを死守したのか。酒井俊幸監督が苦しんだ第101回箱根駅伝を総括した。
まずは4年生エースの状態だ。5月の関東インカレ1部10000mで28分08秒29の自己ベストで6位に食い込んだ石田洸介(4年)は12月に入ってから継続したトレーニングが難しくなり、「12月18日頃に本人と話し合い、『出場は厳しい』という結論に至りました」と酒井監督はいう。
さらに梅崎蓮(4年)は12月30日に以前から気になっていたという左アキレス腱に痛みが発生。本人から「足が痛くて、走るのは難しい」という“告白”を受けて、酒井監督は主将を外す決断を下した。
「石田は感覚の良い選手なので当日まで起用の可能性を残すため1区に登録しましたが、起用する予定はありませんでした。梅崎は過去3年間の活躍を見ても、2区で大きな期待を寄せていました。そのなかで本人が言いにくい言葉を絞り出して、自分の状態を伝えてくれました。梅崎の日誌を見ても、自分への憤りがあり、悔し涙を流したそうです。20年連続シードがかかっているなかで、ふたりとも起用できないことは想定しておらず、それが大きなプレッシャーとなっているのも感じました」
石田に続いて梅崎の起用を見送ることになり、予定していたオーダーを大きく動かすことになる。当初は緒方澪那斗(3年)が1区、小林亮太(4年)が3区、迎暖人(1年)は7区を予定していたが、小林を1区にまわして、緒方を花の2区に、迎を3区に抜擢するかたちになった。
「正直、チームに動揺はありました。でも急遽、区間変更をした選手たちは、『どこでも行きます』と言ってくれたんです。石田と梅崎の気持ちを全員で受け継いでいこうという雰囲気がありました。小林も故障からの復帰途上で不安はありましたが、往路の選手たちは落ち着いて臨んでくれたと思います」
1区は中大・吉居駿恭(3年)が抜け出すと、小林が大集団を積極的に引っ張った。11位での中継になったが、2位の駒大と13秒差というまずまずのスタートになった。しかし、エース区間を託された緒方は厳しい戦いが待っていた。花の2区は超ハイレベルとなり、緒方は1時間08分50秒でまとめるも区間20位。19位まで順位を落としたのだ。
ここから鉄紺が意地を見せる。まずは3区の迎が区間8位と好走。続いて、前回10区区間賞の岸本遼太郎(3年)が4区を区間3位と快走して、16位から9位まで順位を押し上げたのだ。5区の宮崎優(1年)も踏ん張り、往路を9位でフィニッシュ。シード圏内で折り返した。
「小林は第2集団を引っ張って、自分の走りやすいペースを作っていきました。1区の展開をうまく考えて走ってくれたと思います。2区は出場メンバーのレベルが非常に高く、区間記録を見て驚きました。緒方は結果的に区間20位でしたが、8分台で収めており、彼にとって良い経験になったと思います。3区の迎は、『もう行くしかない』と覚悟を決めて、10kmを28分30秒ほどで通過して、前回の小林と遜色ない入りを見せました。後半の粘りは改善の余地がありますが、この経験が彼にとって大きな成長になるでしょう。4区の岸本は『見える選手はすべて抜く』という気持ちで走り、しっかりと巻き返してくれました。5区はU20世界選手権後にヘルニアの手術を受けた松井海斗(1年)の起用も考えていましたが、1月2日の朝に変更を決めました。宮崎は途中でケイレンが起きたこともあり、ラップに浮き沈みがあったものの、元箱根から芦ノ湖までは区間2位のタイムを記録しました。1年生ながら最後までよく頑張ってくれたと思います」
復路も2人の選手を変更
東洋大は往路でマックスとなる4人の選手を交替したが、復路でも2人の選手を投入。今大会唯一となる“フル交替”を実施した。6区のリザーブだった内堀勇(1年)を7区、アンカーの起用プランもあった網本佳悟(3年)を8区に起用したのだ。
「内堀は大腿骨疲労骨折のため 11月は練習ができておらず、当初は起用予定がありませんでした。6区のリザーブとして芦ノ湖に宿泊をしていたので、そこから小田原中継所まで移動したくらいです。8区は永吉恭理(4年)を2年連続で登録していましたが、網本の調子が上がってきたので7、8、10区のどこかで起用しようと考えていました」
復路は6区の西村真周(3年)が8位の立大に3秒差まで接近するも、7区の内堀が12位に転落した。しかし、8区の網本が区間2位と踏ん張り、9位に押し戻す。そして9区の吉田周(4年)で8位に浮上した。
「6区の西村は3回目の山下りなので、あと30秒ほどタイムを縮めてほしかったですね。7区の内堀は区間順位(12位)こそ良くありませんが、スタミナ面で不安があったなかでよく頑張ってくれました。8区の網本は遊行寺の上りで帝京大との差を広げるなどイメージ通りの走りで期待に応えてくれたと思います。前回9区2位の吉田には『区間賞を狙おう』と話して、少し気負わせてしまったのは反省です。それでもラスト3kmで追い上げて、帝京大を抜き返して、5秒差をつけてくれた。この5秒がアンカーの薄根にとっては大きかったと思います」
鶴見中継所のタスキリレーは東洋大が8位で、帝京大が9位、順大が10位。東洋大と11位の東京国際大は31秒差しかなかった。この4校が壮絶なシード権争いを繰り広げることになる。
集団に明確な動きがあったのは22km付近。東京国際・大村良紀(3年)がスパートすると、東洋大・薄根大河(2年)と帝京大・小林咲冴(1年)が競り合い、順大・古川達也(2年)が少し遅れる。大手町のゴールは8位が東京国際大、1秒遅れで9位の東洋大、さらに2秒遅れで10位の帝京大。順大はシード権に7秒届かなかった。
ラスト1kmちょっとの争いが注目を浴びたが、その前にレースを動かしていたのが薄根だった。
「理想は最初の5kmである程度ペースを作り、そのまま逃げ切って、前の創価大が見える位置まで到達することでした。最初の1kmを2分50秒切りのペースで入らせたんですけど、薄根はかなり後ろを気にしていましたね。30秒ほどあった差がわずか3kmで縮まり、本人も驚いたと思います。あそこまで集団でレースが進むと、最後まで力を温存する方が有利です。しかし、薄根はラストスパートが得意ではありません。馬場先門(約20km地点)での声がけは私が最初に行い、『どこかでスパートを仕掛けないといけない。行くしかないぞ!』と伝えました。その声に薄根はすぐ反応して、スッと前に出たら、帝京大・小林選手も続いてスピードを上げていきました。ゆっくりしたペースで進み、ラスト1kmの勝負になったら難しかったと思います。うまくロングスパートにつなげることができて良かったです」
1秒をけずりだして、20年連続のシード権に到達
大ピンチを乗り越えて、東洋大は総合9位でフィニッシュ。継続中の記録としては最長となる“20年連続シード”に到達したことになる。エースを欠いたなかで、シード権を確保できた理由はどこにあったのだろうか。
「往路でシード圏内に入っておくことは非常に重要で、復路の選手たちが心の準備を整えるためにも必要なことでした。往路を終えた時点で9番にいたことは、とても大きな意味を持っていたと思います」
酒井監督はまず往路の健闘を挙げた。そして、東洋大のチームスピリットである「その1秒をけずりだせ」を選手たちが体現したのが大きかったという。
「今回は各区間のラストスパートで1秒をけずりだすような走りができたと思います。2区の緒方は区間20位でしたが、戸塚の壁で前との差を詰めました。6区の西村もラスト3kmは昨年より力強い走りをしたと感じています。 エース不在にもかかわらず、シード権を確保できた理由はここにあると思いますね」
一方で箱根駅伝のレベルが高騰していることも強く実感したという。
「箱根駅伝の全101回大会のうち約5分の1が連続シードにつながっていることになります。ただ今回は『4位以内』を目標に掲げていました。そのなかで緊急事態が重なり、最低限シード権だけは確保しなければならないと強く思っていました。チームとしての意地もありましたし、再び上位に進むためにもシード権を確保することが不可欠だと、選手たちも理解していたと思います。ただ今回はシード権の獲得ラインも高かったですし、今後トップスリーを目指すには、10時間45分という総合タイムが必要になってくるでしょう。今回(10時間54分56秒)から各区間で約1分ずつ詰めなければ、3位以内は現実的ではありません。それくらいの意識を持って、再び、優勝争いに加わっていきたい」
箱根駅伝で20年連続シードという節目を迎えた東洋大。エース不在の窮地を乗り越えたことで、鉄紺はさらにたくましくなり、今後はもっと強くなるだろう。
筆者:酒井 政人