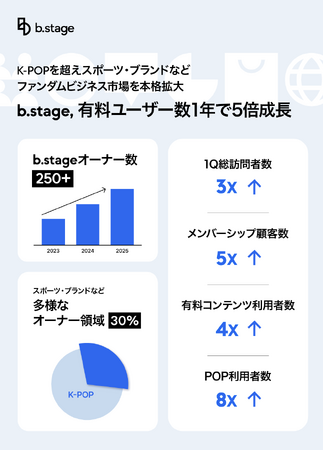大人のインフラ紀行 第15回 東京の一番奥。奥多摩に鎮座する小河内ダムと白丸ダムを巡り感じた自然と技術が交わってきた年月
2025年4月22日(火)11時0分 マイナビニュース
インフラツーリズムとは、公共施設である巨大構造物のダイナミックな景観を楽しんだり、通常では入れない建物の内部や工場、工事風景などを見学したりして、非日常を味わう小さな旅の一種である。
いつもの散歩からちょっと足を伸ばすだけで、誰もが楽しめるインフラツーリズムを実地体験し、その素晴らしさの共有を目的とする本コラム。今回は東京の奥座敷、奥多摩にある大小2つのダムを見学した。
—————
四月上旬のある晴れた土曜日。車を走らせて東京の西端、奥多摩へ向かった。
地図で見る東京は南北よりも東西に長く伸びているので、場所による気候差はそれほどないように思うかもしれないが、そんなことはない。標高の違いやヒートアイランド現象など、様々な条件が重なり、東京都の東と西では気候にかなりの差がある。概ね、東に行くほど暖かく、西に行くほど平均気温が低い。
それを特に実感できるのは、雪が降ったときと、桜が咲くときだ。この日、東京都心の23区では桜がほぼ満開。僕が暮らす多摩地区では7〜8部咲きに差しかかる頃だった。しかし標高の高い奥多摩では、桜はようやくちらほらと咲き始めたばかり。
道沿いにはみずみずしい新緑と控えめな桜が交じり合い、車の窓から入ってくる春浅い山の空気は清々しかった。
今回の目的地は、小河内ダムと白丸ダム。
いずれも多摩川上流に築かれたダムだが、成り立ちも機能も異なる。お隣同士にありながら違った個性を持つ2つのダムを、半日かけてじっくり訪ね歩くつもりだ。
これまで「大人のインフラ紀行」シリーズでは様々な施設を巡ってきたが、やはりダムを訪れる際には特別な高揚感がある。山あいに忽然と現れる巨大な構造物──その存在感は圧倒的で、いつ見ても胸が高鳴るのだ。
○小河内ダム——東京に暮らす人々の水を蓄える巨大な壁
車がたどり着いたのは奥多摩湖。多摩川を堰き止めて作られた人工湖で、正式名称は“小河内貯水池”である。
湖の東側にあるのが、この日の最初の目的地、堤高149メートル、堤頂(ていちょう)長353メートルという堂々たる規模を誇る小河内ダムだ。戦後復興期の首都圏の水需要に応えるため、1957年(昭和32年)に完成した重力式コンクリートダムである。
奥多摩湖は、春の光を受けて深く静かな青を湛えていた。
山並みを映し、時折り水面に光を散らすそのたたずまいは、人工湖であることを忘れさせるほど自然に溶け込み、美しい。湖の周囲には遊歩道や展望スポットが整備され、季節ごとに桜や紅葉が楽しめる観光地にもなっている。
一方で、ダム建設にあたって移転を余儀なくされ、湖に沈んだ旧集落(小河内村など)の歴史があることも忘れてはならない。
片側に湖、もう一方にダムの谷底を望める堰堤の上は、自由に歩くことができる。
幅広い堤頂道路を進んでいると、自然と人工の境界を歩いているような、少し不思議な感覚にとらわれた。
堰堤を渡りきった先の山の木立の中に、10数頭のサルと2頭のシカの姿を見つけた。
この辺り、奥多摩町や檜原村にかけては、ニホンザルとニホンジカが広く生息している地域である。特に春から秋にかけては、群れで移動するサルや、山道沿いに姿を見せるシカに出会うことも珍しくないらしい。
また、ここ奥多摩一帯はツキノワグマの生息域にもあたる。実際、ダム周辺には「クマ出没注意」の注意書きが多数見られた。春から秋にかけて山間部では目撃例もあり、自然と深く共存していることをあらためて感じた。
そんな小河内ダムと奥多摩湖をあとにして、再び車を走らせた。次の目的地は白丸ダムである。
○白丸ダム−—流れを守る静かな働き者
小河内ダムから車で十数分。白丸ダムに到着した。
小河内ダムと同じ1957年に完成したこのダムの正式名称は、“白丸調整池ダム”。小規模な水力発電も行っているが、主たる役割は流量調整にある。小河内ダムからの放流による急激な流量変動を抑える機能を持たされた、いわば多摩川の穏やかな流れの守り手だ。
堤高30.3メートル、堤頂長61.2メートルという比較的小型のダムは、白丸湖と呼ばれる調整池とともに、静かに山の懐に抱かれていた。
この日は、白丸ダムに設けられた“魚道”の開放日だった。
一般見学者が白丸ダムの魚道を見ることができるのは、4月〜11月の休日や夏休み期間のみだ。
魚道とは、アユやヤマメといった川に棲む魚たちが、ダムの上流と下流を行き来するための人工の道。言うなれば、お魚さん専用のバイパスだ。
淡水魚は産卵のために川を遡上するが、ダムのような人工物があると、そこで行き止まりになってしまう。その対策として、緩やかな傾斜の水路を作り、魚がさらに上流へと進めるよう設計されているのだ。
魚道には、自然河川に近い流れを再現する「連続池式」と呼ばれる構造が採用されていて、水が段差を越えて流れ落ちることで、魚たちが無理なく少しずつ上れるようになっている。段差のサイズや水の流速も細かい計算の上に設定されていて、様々な魚種に対応しているのだそうだ。
白丸魚道の見学コースへ進むと、まず目に飛び込んでくるのが、深く掘られた巨大な縦穴だった。深さは20メートルほどだろうか。
コンクリートの壁に沿って螺旋階段が設けられ、見学者はその階段を降りて魚道へと向かう仕組みになっている。上から見下ろすと、暗がりの底へと吸い込まれるような視界が広がり、そのスケールに思わず息をのんだ。
螺旋階段をぐるぐると降りた先には、水が勢いよく流れる魚道があり、手すり越しにのぞき込めるようになっていた。
遡上する魚の姿こそ確認できなかったが、野生の営みを支えるために設けられたインフラ設備には、確かな人の意思を感じた。
白丸湖では、SUP(スタンドアップパドルボード)を楽しむ人たちの姿も見えた。
山あいにひっそりたたずむダムとダム湖は、声高に語ることもなく、黙々と仕事を続けていた。
○自然と技術が交わる場所で静かに積み重ねられた時間
奥多摩のダムたちは、大昔からある山の風景に割り込みながら、それでも違和感なくそこにあった。人の手で建てられた構造物が、時間を重ねるうちに、自分の居場所を得たように見えた。
小河内ダムの堰堤の周辺には、サルやシカ、ツキノワグマが暮らしている。白丸ダムの流れには、小さな魚たちの気配があった。自然と技術が、折り合いをつけながら築いてきた時間があることを感じられたのが心地よかった。
まだ知らぬインフラにも、きっとそれぞれの物語があるのだろう。またどこかへ足を向けてみたくなった。