【水野誠一 連載】竹中直純(中)目に見えない文化貢献とさりげなく手に取らせるリベラルアーツの必要性
2025年4月22日(火)7時0分 ソトコト
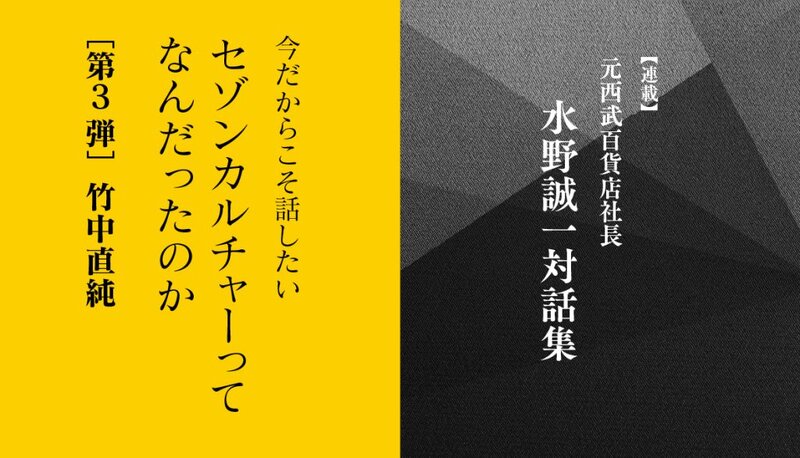
西武百貨店の社長から米国のIT企業の顧問へ。水野誠一の世代を超えた交流から、今回は実業家でプログラマーの竹中直純がゲストとして招かれた。
竹中はまさにセゾンカルチャーが日本の文化に影響を与えているのを体験している世代。博覧強記な資質の原点にもつながっているようだ。
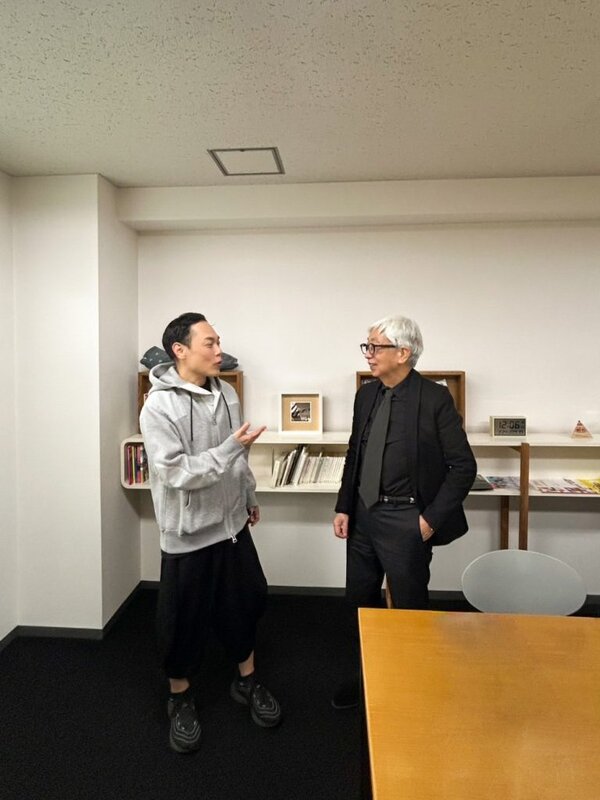
竹中少年が影響を受けたセゾンカルチャーとは
水野 僕がいつも驚くのは、竹中さんは実に博覧強記で、何を問いかけても必ずちゃんとしたカウンターパンチが出てくるところです。
すごい人だという同時に、いろんな世代層に対しても、ちゃんと付き合い方をわかってるっている人なんだよね。
竹中 ありがとうございます。
水野 そういう竹中さんにぜひお伺いしたかったのはね。西武というか、セゾングループというのは、どういうに見えていたのかということなんです。
会社として評価できるのか、それから、ダメになったのはなぜだったのかっていう。
知り合った時も、もうすでに僕は西武じゃなかったし、そんな話をしたい時期ではなかったんですよ。
竹中 はい。僕は年代的にはそのカルチャーに触れてきた世代だとは思います。
育っていく中で会社、組織、社会というものと自分が最初に対峙する年代は、小学生とか中学生の頃ですよね。
僕は福井の出身なので「だるまや西武」という地元の百貨店のだるま屋さんと西武百貨店がくっついた百貨店があったんです。
そこへ行くと、看板なんかにCIカラーの青を使っていて、西武のブランディングみたいなものが薄く入ってくるんですね。
その中で覚えているのは、無印良品の存在です。でも元々は西武じゃなくて西友なんですよね。
でも、田舎だと全部が一体になっているんですよ。
それでポップアップコーナーみたいなところで、すごくシンプルに「ブランドを作らないということがブランドです」というようなかっこいいポスターがあった。
それを読んだとき、今で言うアニメとか映画のメタ展開の如く、僕はすごくしびれたんですよ。
つまり、小説の中で小説家が出てきて読者に言及するとか、漫画やアニメの中で、視聴者を意識したセリフを登場人物が喋るように。
子供ながらに頭の中でブランドっていう概念ができかけだった時期に、それをいきなり壊されたんです。それがすごく印象に残っています。
ひとつのイニシェーションと言える体験でした。
水野 それが小学生から中学生にかけての頃ですか。
竹中 それが中学生です。それから5、6年して僕は大阪に出ます。
素直に大学に行かずに、なんか時代遅れの反体制みたいなね、よくわからない若気の至りで、一旦就職しますみたいなことを言って、ファッションメーカーに就職しました。当時は今に比べて実に様々なところ書店があるわけですよ。
その中の一つ、江坂駅に東急ハンズがあって、入口奥に、リブロだと思うんですが、西武系の書店がありました。
そこに、例えばマガジンハウスで出してる「POPEYE」「BRUTUS」とか、なんかそういうかっこいい雑誌が並んでる。他にもかっこいい本が並んでる。かっこいい塊だったんです。
もちろん、受験用の参考書とか、地図とか、実用上絶対に必要なものもあるんだけれど。まずは今の言葉で言うとキュレーションして、かっこいい本を面出しして、こんな本が売れてますよとか、この本おすすめですよって言ってくれるっていう機能が、地元の書店よりもはっきり出てるんですよ。
つまり、文化を紹介する、かっこいいものを紹介する、ブランドを紹介するっていう機能は、販売店にあるんだということを、生まれて初めて意識した瞬間でした。
水野 編集されているんですよね。
竹中 そうですね。店の見た目を編集するということですね。
ブランドなきブランドというイニシエーション

水野 リブロとか、それからディスクポートというレコード、CDの販売店も、僕たちはそういうふうに編集の感覚でやってきました。
そういうものが必要だと思ったから。
いわゆる普通の百貨店からいかに脱するかということを必死になって考えていた。
もちろん企業だし、百貨店本体もちゃんとしなきゃいけないけど、独自のブランドのあるものへと変えていかなきゃいけないと、絶えず自己否定しながら動いていく企業だと感じていたんだと思います。
竹中 構造的には、百貨店自体にはブランドはないわけですよね。だから、外から持ってきた何か、たとえばルイヴィトンとかエルメスとか、そういうものをきちんと揃えて、雰囲気をつくっていく。それは本質的に編集なんですよね。そして「どうでしょう」って提案するのが百貨店という構造であって。
でも学生当時の僕は「メタ構造」のような言葉はもってなかったけれど「無印良品」が現れたことで、この企業はわかっているんだということがわかったんですよ。
だから、そこから「西武」というのは僕には特別な存在になりましたね。
水野 「無印良品」は、確かにブランドっていうものを否定するブランドですからね。
僕の好きな否常識という言葉にぴったりなんだけど。
僕はあのとき、堤清二さんが「無印良品」を西友でやるっていうのに対して、なんで百貨店でやってくれないんだって思ったんだけど、今にして思えば、百貨店はブランドに溢れているのだから、百貨店で無印良品をやったら、自己矛盾になると考えたんでしょうね。
竹中 田舎では区別がついていませんでした。西武内に「無印良品コーナー」があったので(笑)。
水野 そういう見え方もしたんですね。セゾンカルチャーに対してっていうのはどんな印象をもっていましたか。
竹中 いろんなことに広がっていますよね。たとえばセゾン美術館があったり。僕は都市圏に出てきてから百貨店が本体だと気づきました。
その百貨店構造を壊すような試みをきちんとしてきた会社だったんだな、というのは、今日水野さんと話していてわかりましたけど。
水野 Loftを作ってみたり。さっきお話があったLibroを作ってみたり。
竹中 WAVEもそうですよね。
水野 あれも僕がやっぱり現役時代に関わって、ネーミングも僕がしたんですよ。
ウェーブってのは波長とか波とかで、すごくいいんだけど、それだけではうちの偉い人たちは理解しないだろうと思ったので「WEの間にAV、オーディオ、ビジュアルがある」と言ってね。その後、家電メーカーのパイオニアがその商標を使わせてくれと言ってきたりしました。
竹中 ゲームの制作会社のSEDICもセゾングループですよね。六本木のWAVEの上にありました。
水野 そこの出身でけっこう活躍している人がいましたね。
竹中 ポケモンをつくったひとり、石原さんもSEDICにいましたよ。
SEDICで制作していた糸井(重里)さんの「Mother」の現場には、いろんなクリエイターが集結していました。プログラマーやゲーム作家やデザイナーがいっぱい出てますよ。
水野 そういう文化を生み落として、育てて、後世につながっている。
セゾンカルチャーは知らないところでも文化に貢献していたりする。
だけどね、西武の人の方が結構知らないんだよ、そんな事実をね。
誰もそうなるとは想像できていなかったしね。
リブロはリベラルアーツのある場所だった
竹中 僕は本が好きで、田舎の書店は品揃えの点で不満だったんです。リブロには田舎にはまずないような本がたくさんあるんですよね。90年代の初め頃で一つ挙げると、すごく印象的だったのは、澁澤龍彦なんです。
水野 最近紙幣のキャラクターになった栄一ではなく、龍彦さんの方だね。
竹中 はい。簡単に言えば、性的倒錯を中心に据えて文化を語る人なんですよ。
SMとか緊縛とか、そんなのを高校卒業したばっかりの人が読んだらびっくりします。
インターネットがないときですから、田舎にいると接しないことばかり。
で、田舎で接するとしても、大人しか入れない書店で買うSM雑誌とかでしょう。
そこには断片的に同じ情報はあるんですけど、切り取り方を見ると文化というよりは、即物的で煽情的なコンテンツになっているわけですよね。
子供には馴染まないんですよ。けど、文化のイニシャライズがされてないような子供が澁澤龍彦を頭から読むと、なんか生い立ちがあったり、日常のエッセイがあって、特に別に直にセックスとは結びついてないんですよ。
でも、そこから社会への問題意識とか、暮らしている日々に、つまり生きている日常の延長線上に湧き上がってくる生殖という概念や行為にどう向き合ってるかというのが、感受性豊かで、読める能力を持った人にはバンバン入ってくるんですよ。
これは結構ショックで。読み物の揃え方次第で読者が影響を受ける重要さが、リブロを通じてすごく身についた気がします。頭に入った気がしますね。
水野 僕も澁澤龍彦とか稲垣足穂とか、そういう人たちの本を読みながら高校時代は育ったね。
竹中 世代を超えてそういうところが同じですね。
どの本を選ぶのかは、地方だとその本屋のおじさんが知ってるかどうかにかかってくる。
だから、どんどん日本人の知性が下がったり、購買力が下がったりしてるのは、書店の影響もあると思う。地方の知性のキーマンになるような書店のおじさんのやる気がなくなってる、歳をとりすぎた、みたいなことが、その地域の中学生とか高校生に計り知れない影響を与えてるんですよね。
担任や各科目の先生も、授業中に豆知識みたいな話はあまりしませんよね。しかし脱線話をする先生が人気が出たりするということは、生徒はそういう知識を欲してるってことだと思うんです。
周縁の文化込みで学ぶ体系的に学ぶ知識は欧米だとリベラルアーツっていう言葉があって、日本だと教養といわれています。教養は、高校以下の頃から大学に行っても困らないようにバンバン積極的に頭に入れるのが良いっていう印象があるんですけども、日本ではそれが行われないところに問題があって。
30年前、40年前の日本の都市には民間の西武のような法人が、学校の代わりに実質的にそれを担っていたんじゃないかと思います。
それに刺激を受けた子どもたちは、自主的にさらに知識を広げていき、知的好奇心をガイドされることでいわゆるカルチャーが支えられたというふうに思います。
そういう役割が西武にあったと僕は思うんです。
どんな企業にもアップデートの継続が必要

水野 本についてはリブロだったし、音楽ではディスクポートも、民族音楽とかね、もう他では絶対置かないものが、ジャンルとしてきちんとありましたね。
しかもそこにちゃんとその音楽の知識のある店員がいるんですよ。
だからむしろ店員とお客の関係じゃなくて、仲間の関係であったり、さらに言えば、先生に学びに行くみたいなお客さんもいましたね。
そういう人間の関係論ができる店ということで、稀有だったと思います。
竹中 僕の主観の話なのですが、たとえばラディーノっていう、ラディーノ語で歌われるイベリア半島の音楽があるんですけど、ラディーノも日本で「発見」されたまま30年くらい経っていて、現代の歌手が主にヨーロッパでポップナイズして歌ったりしてそれは伝統文化なのですが、ラディーノ自体をちゃんと掘り起こして紹介するような、少なくとも日本の音楽評論家ってあんまりいないし。
南米方面は少しいます。南米音楽は『ブエナビスタ・ソシアルクラブ』という映画で有名になりましたけど、音楽評論家がずっと紹介し続けている。
ブエナビスタ・ソシアルクラブ自体は元々バンド名で、映画後20年くらい経って演奏者が高齢化してバンド活動をやめて、それが続編映画として公開されたあたりまでちゃんと続けている。なのに我々は紹介されないと知り得ない、だから文化が廃れてしまうように感じる現状があるんですよね。
なんかあそこで止まってるんですよ。
要するに当時の西武カルチャーはアップデートができてたんですよ。西武が一度紹介した文化をしつこく追っかけて届けてくれる。そういうことがわかっている経営者や企業が、今はないんでしょうね。
水野 そうですね。西武にもいなくなっちゃったんですよ。
そういう文化のある業態もね、みんな潰されちゃったし。
ちなみに僕は、今でも『ブエナビスタ・ソシアルクラブ』のファンですが。
西武の話ばかりしててもしょうがないので、竹中さんとこれからの話をしましょう。













