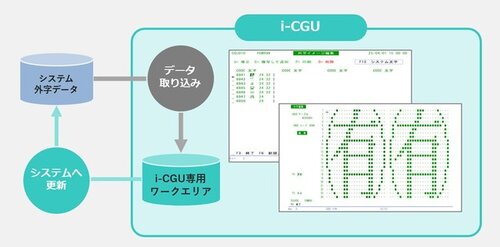<按察使>と書いて何と読む?ヒントはかつて存在した官職のことで…難読漢字で日本史を学ぼう
2025年5月20日(火)17時22分 婦人公論.jp

留まることなく流れ、現代の私達へとつながる日本史。
その間に起こった日本を変えた激変、事件、事変に制度、そして地名に加えて、活躍した人、悲劇の人物…。
あらゆるものが”漢字”で表記されています。しかし、中にはスラスラと読めない、いわゆる難読漢字で綴られているものも。
そこで本企画では難読漢字で綴られたキーワードを厳選。読み方の紹介とともに、その意味をあらためて解説します。
さあ、あなたも難読漢字で日本史を学ぼう!
さっそくながら問題です。

何と読む?
「按察使」
いったい何と読むでしょうか?
果たして正解は…
正解は…
正解は「あぜち」でした。
ーーーーーー
中国・日本・朝鮮・ベトナムにかつて存在した官職で、地方行政監察機関のこと。
日本では奈良時代に元正天皇の養老3年(719年)に設けられ、当初は地方行政を監督・監察する令外官として置かれた。
平安時代以降は陸奥国と出羽国のみに按察使が置かれ、他国については中央官僚である大納言、中納言、少納言と參議の兼任職となって形骸化した。
明治維新後、地方政治の監督官として明治2年に按察使が設けられたが、翌年には廃止された。
ーーーーーー
皆さんは正確に読めましたか? では次回もお楽しみに。
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より
関連記事(外部サイト)
- 本郷和人 なぜ上杉謙信の大領土は「あっ」というまに失われてしまったのか…関東平定を宿願にするなかで後継者問題を招いた「謙信の失敗」【2025編集部セレクション】
- 本郷和人 武田信玄の失敗は「北信濃10万石に10年も費やしてしまった」こと…信玄・晩年の領土規模<約60万石>を信長は20代で達成していたという事実【2025編集部セレクション】
- 戦国最強・上杉謙信が<唯一負けた>天才軍師は名前の読み方すら不明で…れきしクンも「何者なんだよ!」と唸る人物のナゾに迫る【2024年上半期BEST】
- 天下統一後の秀吉が「最後に」戦った東北の大名とは?鎮圧軍には政宗・三成・家康の名も…戦国史の終わりを彩った<みちのくの雄>【2025編集部セレクション】
- 93歳で関ヶ原に出陣した武将がいた!?信長、秀吉、家康に信頼された弓矢の達人の「マンガのような逸話」