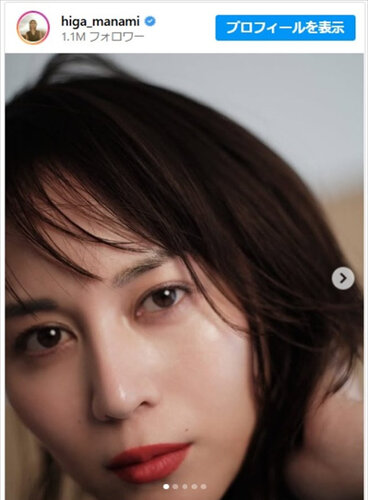国宝「曜変天目」と重文「油滴天目」の共演、信長、秀吉、家康と受け継がれた2つの茶入…静嘉堂の名物が一堂に会す
2024年9月23日(月)6時0分 JBpress
(ライター、構成作家:川岸 徹)
東京・丸の内の静嘉堂文庫美術館(静嘉堂@丸の内)にて茶道具をテーマにした特別展「眼福—大名家旧蔵、静嘉堂茶道具の粋」が開幕。静嘉堂が展示ギャラリーを丸の内に移してから初めての、静嘉堂としても実に8年ぶりの茶道具展になる。
“目垢まみれ”でも見たい珠玉の名品
静嘉堂所蔵の茶道具は三菱第2代社長の岩﨑彌之助(1851〜1908)とその嗣子で第4代社長の岩﨑小彌太(1879〜1945)の父子二代によって収集されたもの。その数およそ1400件に及び、本展ではその中から前後期あわせて79件が出品される。展覧会に先駆けて行われた報道内覧会で、安村敏信館長がこんな話を披露してくれたので紹介したい。
「骨董の世界には、“目垢がつく”という独特な言い回しがあります。たくさんの人に見せすぎると、目垢がついてその品の価値が落ちてしまう。ですから茶会などでは、1点くらいは目垢のついていない、うぶな品があったほうが喜ばれます。
ただし、大名物は別格。茶道具の名品のなかで、千利休が登場する前、特に足利義政の東山時代に名を馳せた茶器を大名物と言いますが、これはどれだけ目垢がついても価値は下がらない。お茶の世界は不思議なんです。
また、骨董の世界では“眼福”という表現も用いられる。これは目の保養になるような素晴らしい品々に与えられる言葉で、“いい作品に出会えて眼福を得た”などと用いられます。今回の展覧会が来館者にとって、眼福のひとときとなりましたら幸いです」
本展の出品作は“静嘉堂オールスター”といえるラインアップ。将軍家や大名家旧蔵の由緒ある茶入や名碗、千利休を筆頭に著名な茶人たちの眼にかなった風格あふれる名品がずらりと並ぶ。ただし、単に名品を揃えたというわけではない。静嘉堂の顔といえる国宝《曜変天目(稲葉天目)》などの「目垢はつき過ぎているが、やっぱり見たい」と思える名品はしっかりと抑えながらも、今回が初公開となる“うぶ”な品も含まれている。
唐物、高麗、樂、和物。名碗が勢揃い
では、本展の見どころをいくつか。見どころの1つめは「名碗の共演」。唐物、高麗、樂、和物と産地が多様で、それぞれの碗を見比べながら、個性や味わいを感じ取ることができる。
重要文化財《油滴天目》は、唐物茶碗の最高位「曜変」に次ぐ高い評価を受けてきた天目茶碗。産地は福建省建陽市水吉鎮にある建窯で、油の滴が水面に細かく散ったような斑文があることから「油滴天目」と呼ばれている。油滴天目は複数の美術館が所蔵しているが、静嘉堂所蔵の茶碗は朝顔の花びらのように大きく外側に開いた形が独特。厚く掛けられた黒釉の上に銀色に輝く大粒の油滴斑がびっしりと浮き上がり、その神秘的な美しさに引き込まれてしまう。
高麗茶碗ファンなら、重要文化財《井戸茶碗 越後》と重要美術品《井戸茶碗 金地院》の並びに惚れ惚れ。「越後」は大井戸に分類される大振りの姿、枇杷色を呈する表面に細かく生じた貫入(ヒビ)、胴を巡る柔らかなろくろ目が特徴。大きく割れを繕った痕が残るが、それも歴史を感じさせる味わい深い景色になっている。
「金地院」も大井戸に属する茶碗で、サイズは「越後」よりも大きいが、むしろおとなしく品のいい作行き。淡い枇杷色の釉が優美な雰囲気を醸し出している。ちなみに「金地院」という呼び名は、京都南禅寺の塔頭金地院の什物であったという伝承による。
信長、秀吉、家康が手にした「付藻」「松本」
見どころの2つめは「信長、秀吉、家康の手をわたった2つの茶入」。茶入とは茶の湯で抹茶の粉を入れる容器のこと。手のひらに収まるような小さな壺だが、戦国武将にとっては何物にも代えがたい価値ある品。権力の象徴として所持するほか、戦で手柄を立てた部下に褒章として与えたり、主従の信頼の印として贈り物に用いたり。
本展では織田信長、豊臣秀吉、徳川家康の手をわたった2つの茶入、大名物《唐物茄子茶入 付藻茄子》と、大名物《唐物茄子茶入 松本茄子(紹鷗茄子)》が公開されている。どちらも大坂夏の陣で罹災しながら修理され、大切に受け継がれてきた品。「付藻茄子」には若き日の岩﨑彌之助が、会社の給与を前借りして購入したとのエピソードも残されている。
狩野派絵師が継承した「猿曳棚」
3つめの見どころは「猿曳棚4点」。猿曳棚とは茶の湯で使われる紹鴎棚の形式にも近い大棚で、小さな引戸が付いた地袋が備えられている。この引戸に猿曳(猿回し)の絵が描かれていることから、猿曳棚と呼ばれるようになった。
展覧会では静嘉堂が所蔵する猿曳棚4点を一挙公開。古田織部と小堀遠州に学んだ茶人・清水道閑(伊達家・茶道頭)が代々に伝えた。本歌となる最初の猿曳棚の板戸絵は狩野元信が描いたと考えられている。その後、数度にわたって写しが制作され、板戸絵は狩野派の絵師が担当するのがならわしであった。
本展が初公開となる明治時代制作の猿曳棚は、狩野派の絵師・橋本雅邦の筆による可能性が高い。「作品そのものは小型で絵師の個性が見極めにくいことや、落款に比較材料がないことから雅邦作であるとの確証にはいたっていません。でも、雅邦の弟子・桃澤如水がこの棚を雅邦作として大切に所持してきたことなどから、雅邦作である可能性はかなり高いと思います」(安村敏信館長)
国宝指定の名碗から初公開の猿曳棚まで、静嘉堂の奥深さと底力を感じる茶道具展。あおるつもりはないが、「眼福」を得られる稀有な機会だと思う。
特別展「眼福—大名家旧蔵、静嘉堂茶道具の粋」
会期:開催中〜2024年11月14日(月・振休)
会場:静嘉堂@丸の内
開館時間:10:00〜17:00(毎週土曜日は〜18:00、第4水曜日、9月25日、10月23日は〜20:00) ※入館は閉館の30分前まで
休館日:月曜日、9月17日(火)、9月24日(火)、10月15日(火)(ただし9月16日、9月23日、10月14日、11月4日は開館)
※10月28日はトークフリーデーで開館
お問い合わせ:ハローダイヤル 050-5541-8600
筆者:川岸 徹