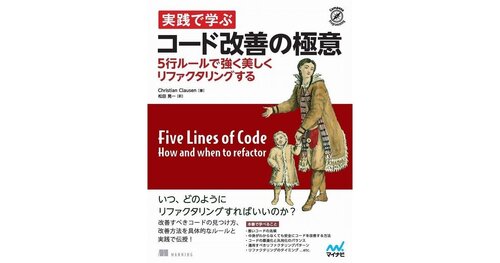“落ち込みやすい人”は「理不尽なルールに疲弊する」。では、メンタルが強い人はどう考える?
2025年4月23日(水)6時25分 ダイヤモンドオンライン
“落ち込みやすい人”は「理不尽なルールに疲弊する」。では、メンタルが強い人はどう考える?
自分の生き方や置かれた状況に「悩む人」がいる一方で、同じ環境にいても「悩まない人」がいます。ではどうすれば、「悩みやすい不幸体質」を卒業して、「絶対に悩まない人」になれるのでしょう。その方法を教えてくれるのが、書籍『不自由から学べること—思いどおりにいかない人生がスッとラクになる33の考え方』です。12歳からの6年間を「修道院」で過ごした著者が、あらゆることが禁止された暮らしで身につけた「しんどい現実に悩まなくなる33の考え方」を紹介。悲観でも楽観でもない、現実に対するまったく新しい視点に、「現実の見方が変わり、モヤモヤがスッと晴れた」といった声が多数寄せられています。この記事では本書より一部を抜粋・編集し、「理不尽なルールとの向き合い方」を紹介します。
Photo: Adobe Stock
あらゆることが「制限」された生活
修道院は携帯もテレビもダメ。 それなら「友達と仲良くするのはいいだろう」と思って手をつないでいたら、それもダメと言われました。
「一体何だったら許してもらえるのですか?」
さすがに耐えられなくなって、シスターに喧嘩腰で質問した記憶があります。
本当にそれくらい、あらゆることが制限された生活でした。 私は規則に従順に従いつつも、絶望と憤りを感じていました。
「なぜ、自分だけ…」という疲弊
同級生は毎日家に帰り、好きに放課後を過ごし、携帯もテレビも自由に見られるのに、私は「ルールだから」と禁止される。
束縛されることが大の苦手な私は、もういっそ脱走してしまおうかと、夜に部屋からベランダに抜け出して星空を眺めながら何度も考えました。
このルールという枠と、修道院の脇にある、よじのぼれないわけでもない壁が同じに見えました。
今思うと、あれは「何かに依存するな」ということだったのかもしれません。大人になった今であれば、何かに依存することの危険性はよく理解できます。
壁は「あって当たり前」と思えるとラクになる
今では、あのとき「壁」と向かいあえて良かったと感じています。
何かに挑戦したり、新しいステージに向かったりと前進するときも、必ずと言っていいほど、ルールという壁が立ちはだかります。 そのたびに戸惑ったり抗ったりしていては身が持ちません。
修道院での生活を送ったおかげで、その後の社会でも壁にぶつかったとき、「そりゃ、そうだよな」と、その存在を素直に認められるようになりました。
(本稿は、書籍『不自由から学べること —思いどおりにいかない人生がスッとラクになる33の考え方』の内容を一部抜粋・編集して作成した記事です。書籍では他にも、「悩まない人の考え方」を多数紹介しています。)