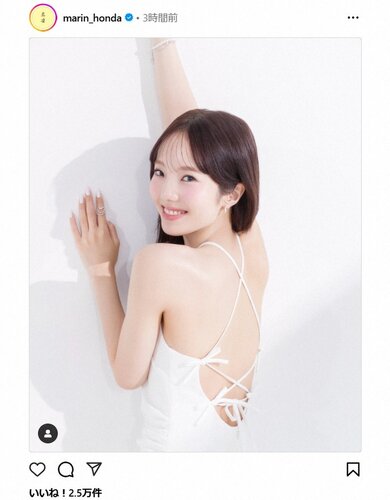昭和30年代まで活躍「氷冷蔵庫」を復刻…栃木の氷屋店主、万博でお披露目へ
2025年5月18日(日)17時7分 読売新聞
「日光杉などの材料にこだわり、環境にやさしい冷蔵庫」と話す山本さん(栃木県日光市で)
6月に大阪・関西万博で天然かき氷を提供する、日光市の蔵元「四代目氷屋徳次郎」が、今ではほとんど見かけなくなった「氷冷蔵庫」を造った。電気冷蔵庫が普及する昭和30年代(1955年頃)まで使われ、氷屋さんに届けてもらった氷を入れて食品を冷やした。4代目店主の山本雄一郎さん(74)は「日光杉や飾り金具など地元にこだわった、最も環境にやさしい冷蔵庫」と胸を張る。自信作は万博の県出展ブースでお披露目する。(伊藤学)
氷冷蔵庫は、夏場に生ものを保管するのが大変だった時代に普及した。明治後期、氷のわずかな冷気も見逃さず、知恵を絞った先人たちが木組みで製造したという。昭和になって洗濯機、白黒テレビと並ぶ「三種の神器」に数えられた電気冷蔵庫の登場で姿を消した。
今年に入って山本さんは、県の万博担当者から天然かき氷の出品を打診され、「県や日光のPRに役立つなら」と快諾した。「いのち輝く未来社会のデザイン」がテーマの関西万博。「環境」関連の出展も多いことを知り、「どうせならかき氷の出品だけでなく、環境にやさしい氷冷蔵庫も造ってやれ」と思い立った。
庫内の上部に氷の塊を入れ、その冷気で下段の食品を冷やす素朴な仕組みだが、氷の重さと湿気に耐える木工と板金の技術が不可欠。腕の確かな市内の建具店に製作を依頼した。
不用になった昭和時代の2ドア式タイプを参考に一から図面を引き、外観や扉のデザインをほぼ再現。材料は日光杉のほか、日光東照宮など社寺の造営で栄えた「金工」技術を生かした飾り金具を使い、取っ手や
一方、内張りのブリキはさびにくいステンレスに、保冷用のおがくずは断熱材にそれぞれ変更。冷気が効率よく流れ、解けた水が下段の受け皿にスムーズに落ちるなど細部にも工夫を凝らした。
約3か月かけて完成した氷冷蔵庫は高さ1メートル、幅、奥行き各60センチ。食品庫の容量は125リットルで、今なら一人暮らし向きサイズだ。上段の氷室には天然氷(縦横、厚さ各15センチ)が6個入り、ほぼ1日冷やすことができるという。
制作費は約80万円。同タイプの電気冷蔵庫は3万円台から購入できるが、「日光杉などの材料や、ものづくりにこだわった結果だから」と意に介さない。「『温故知新』という言葉があるが、今の課題を解決するヒントは過去に学べば見つかるかもしれない。レトロな冷蔵庫がきっかけになればうれしい」と笑った。
県の出展は6月27〜29日で、EXPOメッセ内にブースを開設する。氷冷蔵庫は飲食エリアで実際に使用する。万博後は、利用希望があれば貸し出す予定だ。