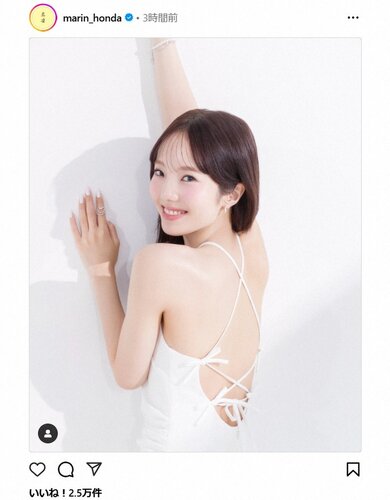南極の氷床に閉じ込められた気候の”化石”が伝える地球の未来
2025年5月19日(月)20時0分 カラパイア

photo by Mike Waszkiewicz.
南極の分厚い氷床の中には、先史時代の気候や氷の状態を今に伝える”化石”が残されている。それは気候変動が進む地球が、今後どうなるのかを知る貴重な手がかりでもある。
もしも南極西部氷床の氷がすべて溶けてしまうとしたら、世界の各地のとりわけ沿岸地域は甚大な影響をこうむることだろう。
だからこそ、気候学者たちは未来がどうなのるか知るために、まるでミッション・インポッシブルを思わせるスペクタクルな大作戦を敢行し、過酷な環境の中で氷床コアの採取に取り組んでいる。
より古い氷の記憶を求めて
南極の分厚い氷床に残されている”化石”とは、そこに閉じ込められた大昔の空気や氷そのものであり、地球の記憶でもある。
科学者たちは長年、できるだけ古い氷のサンプルを求めて南極を掘り続けてきた。これまでに採取された最古の氷は約80万年前のもので、それでも十分古いが、気候変動をもっと深く理解するには、まだ足りない。
とくに重要とされているのが「鮮新世(せんしんせい)」と呼ばれる時代だ。530万〜260万年前にあたるこの時期は、地球の表面温度や大気中のCO2濃度が現在よりも高く、現代によく似た気候だったとされる。
そこで注目されたのが、南極大陸を横断する「南極横断山脈)」の一角にあるオング・バレー[https://de.wikipedia.org/wiki/Ong_Valley]だ。研究チームはこの場所から約9.4mの氷床コア(氷の芯)を掘削することに成功し、その年代を調べた。
年代測定には、「宇宙生成核種(cosmogenic nuclide)」という技術が使われた。宇宙線によって地表の岩や氷に微量に生成される原子を数えることで、その物質がどれくらいの時間、地表近くに存在していたかを推定する方法だ。
そして彼らは驚くべき結果を手にした。採取された氷の上部層はおよそ295万年前、そしてその下層にはなんと430万〜510万年前の氷が存在していたのだ。

南極大陸 Photo by:iStock
鮮新世の氷河期の証拠
この年代はちょうど鮮新世にあたる。研究チームは、この氷が東南極氷床の拡大期に形成されたこと、さらには氷床が2回にわたってオング・バレーに進出した痕跡が保存されていることを突き止めた。
つまり、約295万年前と430〜510万年前の2回、氷河がこの地域まで進出してきた証拠が、氷の層やその周辺の堆積物にしっかりと刻まれていたのだ。それ以降、約1万年前を除いては大きな氷の移動はなかったという。
氷の化石から地球の記憶を調べる繊細な作業
氷床コアを掘り出し、それを調べる作業はとにかく大変だ。
気候学者は、ドリルで掘り出された氷床コアを砕くか溶かして、中に閉じ込められている太古の塵・気泡・海塩・火山灰・森林火災の煤といった痕跡を取り出す。
これを専用の容器に集め、質量分析計・走査型電子顕微鏡・ガスクロマトグラフなどの装置を用いて、当時の気候の様子を解析するのだ。
それはきわめて繊細な作業で、汚染を防ぐために、超高機能フィルターと換気設備で空気が清浄に保たれたクリーンルームで行われ、作業者もまた全身をクリーンウェアで包み、何重にも手袋をはめねばならない。
米国ダートマス大学のエリック・オスターグベルク氏は、「指紋ひとつで試料が台無しになりかねません」と語る[https://www.climate.gov/news-features/climate-tech/climate-core-how-scientists-study-ice-cores-reveal-earths-climate]。

グリーンランドの頂上から採取された氷床コア、年輪のように明るい帯と暗い帯が交互に現れている。これを取り扱う研究者は汚染防止のために手袋を何枚も重ねて着用する/Photo by Erich Osterberg
次の200年で地球の氷はどうなるのか?
そうやって過去の大気を十分に分析できれば、それぞれの氷床コアの”層”に対応する大昔の一定期間(多くは数週間から1年ほど)において、大気の組成や気温がどのように変化したのか推測することができる。
たとえば、サンプルに含まれる酸素の同位体の割合から、氷が形成された当時の気温がわかる。
比較的軽い「酸素16」を含む水蒸気が雨になるには、より低い温度が必要になる。だから、それが多ければ気温は低かったと考えられる。
過去100万年以上にわたって二酸化炭素量と地球全体の気温が連動していたことが判明したのは、氷床コアに閉じ込められた気体のおかげだ。

独自に設計された溶解装置に乗せられた氷床コア。この装置により、そこに含まれた汚染物質・海塩・ちり・火山灰・森林火災の煤といった太古の痕跡を検出する/Photo by Erich Osterberg
こうした過去の気温やそれに応じた氷の状態を知ることは、人類にとってきわめて重要なことだ。
オスターグベルク氏は、今後200年のうちに南極西部にある氷床が溶けるかどうかも、南極の氷が教えてくれると考えている。
そのとき達すると予測される気温が、12万5000年前の地球が経験したものだからだ。

西南極氷床(West Antarctic Ice Sheet)には、南極海に張り出す2つの巨大な棚氷がある。もし12万5000年前、南極横断山脈の西にある氷が完全に溶けていたとすれば、現在では海から数百km離れた氷も、当時は海の近くにまで迫っていたことになる/Imageby the NASA/GSFC Scientific Visualization Studio, based onLandsat Image Mosaic of Antarcticadata
氷を求めて極地を探索する研究者たちのミッション・インポッシブル
だからこそ、オスターグベルク氏ら気候学者たちは、より古い氷の記憶を求めて、氷床コアの採取を続けている。
彼らが目をつけた採取地点にある氷床の下のほとんどは、海面よりも低い。仮にかつて氷床が溶け去っていたのなら、そこで掘ろうとしているところは沿岸部だったはずだ。
オスターグベルク氏は、「当時そこが今より海に数百マイル近かったなら、氷床コアの化学組成に暖かい気温と高い海塩濃度が反映されているはずです」と述べる。
だが、そうした氷のサンプルを集めるには、ミッション・インポッシブルを連想させる大作戦を行わねばならない。
オスターグベルク氏らは現地へ向かう事前準備として、数回の夏の間に、氷床コアを採取すべきポイントを探した。氷の厚さはもちろん、できるだけ平らで、氷の変化が少ないことも重要だ。
さらにようやく現地に行けたとしても、長さ約200mの氷床コアを2本採取するのは、6〜8週間もかかる大掛かりな作業だ。
それを、この地球上でももっとも過酷な場所で、支援も補給もほとんど期待できない中、実行せねばならない。
「必ず何かしらのトラブルが起きます」とオスターグベルク氏。

コア掘削用のテント内で作業をする研究者/写真:ドム・ウィンスキーPhoto by Dom Winski
これらにくらわえて、嵐に襲われたり、危険な野生動物と遭遇したりすることもある。
オスターグベルク氏が2012年にグリーンランドで行った氷床コアの掘削ミッションでは、暴風雨に見舞われ、ホッキョクグマを避けるため、あえて危険な尾根を伝って避難したことがあったそうだ。
そうやって無事氷床コアを掘り出したとしても、これを研究所へ運び込むこともまた難題だ。
氷はだんだんと劣化するため時間との勝負になるからだ。
サンプルは通常、山の頂上からヘリで空輸されるが、空港では事前に税関手続きを終え、トラブルに備えて予備のトラックを用意しておくことも必要になる。
今私たちが知る気候の科学は、研究者が体を張った努力の末に培われたものだということだ。
References: Climate at the core: how scientists study ice cores to reveal Earth's climate history[https://www.climate.gov/news-features/climate-tech/climate-core-how-scientists-study-ice-cores-reveal-earths-climate] / 5-Million-Year-Old Antarctic Ice Core Contains Sample Of Air From The Pliocene Epoch[https://www.iflscience.com/5-million-year-old-antarctic-ice-core-contains-sample-of-air-from-the-pliocene-epoch-79192]