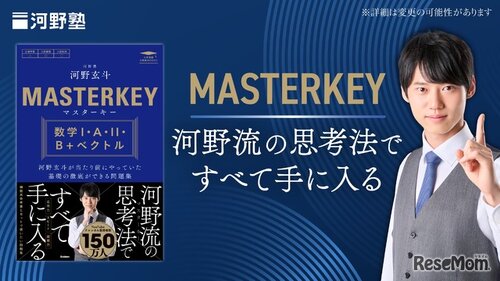数学の楽しさを教えたい!数学教師を目指して学ぶ玉川大学工学部「数学教員養成プログラム」
2025年2月18日(火)12時0分 PR TIMES STORY
<写真:2025年春、中学の教員として巣立つ取材メンバーと成川先生(中央)>
「教員養成の玉川」を掲げる玉川大学(東京都町田市)は、各学部や学科に専門領域を生かした多彩な教員養成カリキュラムを持ち、教員免許状の取得を目指す学生が多く学んでいます。なかでも特徴的なのが、数学教員を志す学生のために、工学部に設けられている「数学教員養成プログラム」(数プロ)です。最近では、この数プロのメンバーが中心となる数学の教職課程から、希望する学生のほぼ全員が中学校や高等学校の数学教員として巣立っています。
数プロの特色は、玉川が基盤とする「全人教育」のもとで、1年次から教職課程に必須の基礎科目を学ぶとともに、代数学や解析学といった専門教科の学修にも取り組むことです。1年次を終了し、GPA(成績評価)で一定レベルの成績を収めた学生のみが、2年次から数学教員養成コースへ進み、ベクトル解析や複素解析などのより高度な専門科目を学修します。
<成川先生>
元中学・高等学校の数学教員で、現在、数学教育を担当する工学部マネジメントサイエンス学科の成川康男教授は、「工学部の中に、数学教員を養成するプログラムを内包する大学は全国的にも極めて少ないのではないか」とし、「教育学部の数学専攻とは異なり、公理から出発する純粋な数学はもちろん、工学で用いるデータサイエンスや統計学に加え、ゼミや卒業研究における教育データの分析など幅広い内容を学べる」とその強みについて説明します。
数学教員養成プログラムでは、国が定める「学習指導要領」を理解し、数学科指導法などを通じて数学教員に必要な知識が身につけられるほか、参観実習や介護体験、教育実習、教育インターンシップ、教育ボランティアなどの教育現場における体験活動も充実しています。また、玉川大学教師教育リサーチセンターと連携し、現場経験の豊富なスタッフが採用試験対策として、面接や論作文、模擬授業の指導もしています。教職課程を履修する学生は、「ダブル免許プログラム」の受講により、中学校と高等学校の教諭免許状に加え、小学校教諭2種免許状の取得も可能です。さらに大学院まで進学すれば、専修免許状(数学・工学)を取得することができます。
今春から中学校の数学教員として就職予定の工学部マネジメントサイエンス学科、数学研究室の成川ゼミ4年生の夏目怜さん、川瀬泰雅さん、井村友哉さん、吉田桃華さんの4人の学生にその魅力などについて聞きました。
——玉川大学の入学の経緯と、数学教育を専攻した理由を教えてください。
夏目「中学校での数学の授業が楽しく、当時から数学教員を夢見ていました。高校で玉川大学の説明会に参加する機会があり、教員の養成に強いことを知って玉川大学を志望しました。教職課程に加えて、工学分野の専門的な科目も履修できる点に魅力を感じて決めました」
<夏目さん>
川瀬「私も数学が好きだったので、中学生の頃から中学校の数学教員になりたいと思っていました。大学選びの際、数プロで同じ夢を持つ仲間とともに学ぶことができたら、互いに励まし合い、より頑張れると考え、玉川大学を目指しました」
<川瀬さん>
井村「私は長く野球をやってきたのですが、高校3年生の時にコロナ禍になり、甲子園がなくなってしまったんです。その時に、教員になってふたたび甲子園を目指したいと思ったのが、教員への入り口でしたね。思い返すと、中学3年生の時の担任が数学の先生で、その先生が親身に教えてくれたことで、苦手だった数学の楽しさを知ることができました。そこから、大学でも野球を続けながら、数学の先生を目指すことにしました。数学教員として生徒たちに数学の楽しさを伝えながら、野球などの部活動の顧問の先生もしてみたいと思っています」
<井村さん>
吉田「私は中学の数学で一時、つまずいていた時期がありましたが、ある時、数学の問題を解くことが楽しいと思った瞬間がありました。自分で考え、問題を解き切ることに達成感を覚えたんです。大学受験については迷ったのですが、高校の担任の先生に、数学をきちんと学びたいのなら、専門的に学べる工学部の方がよいのではないかと背中を押してもらい、玉川大学の数プロを目指しました」
<吉田さん>
——卒業研究では、川瀬さんと吉田さんが「中学生からはじめる射影幾何学」、夏目さんと井村さんが「数学教育におけるICT(情報通信技術)の効果」について、それぞれチームでまとめられましたね。内容を教えていただけますか。
吉田「射影変換によって図形の性質を研究する射影幾何学は、本来、中学の数学では学ばないのですが、一部の学校では美術の時間に学んだり、海外のシュタイナー学校では取り入れられています。学校教育における数学では、生徒の空間図形に対する苦手意識が課題になっています。そこで、一般的には大学で学ぶこの射影幾何学を利用して、中学生でも理解できる教材を作りたいとの目的で研究を始めました。教材は、穴埋め形式にして書き込みながらルールを学べるようにしたり、苦手な生徒が多い証明問題なども、最後の方に空欄を多く設けたりするなどして工夫しました」
夏目「私も井村くんも高校で教育実習をしたのですが、私たちの頃と違い、今では生徒一人に1台タブレットなどのICT機器が普及し、授業の形態が変わりつつあります。そこで、従来のように紙に印刷された問題を解く場合と、タブレットで問題を解く場合とでは、どちらの方が学習効果が高くなるのかを、実際に高校生に解いてもらって調べることにしました。円の方程式の標準形を求める、やや複雑な今回の問題に限った結果ですが、正答率やスピードなど複数の項目で分析したところ、機器を利用した場合は操作時の時間のロスなどがある一方、紙に印刷された問題を解く場合では解答までがよりスムーズで、学習効果が高くなるとの結論に達しました」
——4年間の学びで、特に印象に残ったことは何ですか。
川瀬「やはり数学科指導法ですね。その中でも例えば、自分たちで期末試験を作る課題では、生徒たちのどのような能力を測るかによって、設問を選択するということを学習しました。これは自分がテストを受ける側だった時には分からなかったことです。試験を作成する過程で多くの学びを得ました。それ以外にも、数学教員に必須の知識や、授業の進め方なども体得できたように思います」
井村「私は、特別活動の授業で取り組んだ学級会の運営です。学級会とはクラスで決めごとがある際に数回にわたって開き、多様な意見をまとめ、合意形成を図っていくプロセスです。同級生を相手に私が教員役となり、『ある行事の最後の1時間にどんな遊びをするか』をテーマに3回ほど模擬学級会を行い、最終的にミニ運動会の開催をクラス全員で決定しました。教員側の理論や方法を実践しつつ、生徒たちの気持ちも汲んで進める、その一連の流れを楽しみながら経験することができました」
——数プロで学んで良かったことは何ですか。また、そこで培った経験や知識、能力を数学教員としてどう生かしていきますか。
吉田「限られたメンバーでずっと一緒に授業を受けたことで、互いに切磋琢磨しながら教員を目指すことができました。私のようにはじめは数学が苦手だったとしても、楽しい、達成感を味わえた、と思ってもらえるような授業をしたいと考えています。特に、女性で数学の教員を目指す人はまだ少ないと思うので、そうした意味でもよい影響を与えられたらうれしいですね」
井村「ここの良いところは、やはり同じ志を持つ仲間がいることですね。周りやゼミのメンバーに刺激をもらったからこそ、ここまで頑張ってこられたかなと思います。玉川大学はワンキャンパスなので、ほかの学部や学科で教員を目指す学生と交流できるのも良いところです。数学の魅力は何と言っても、答えが一つに決まるところ。一方で、数学は一つの問題に対し、さまざまな角度から解くことも可能です。この興味深い数学の分野で、生涯、教員でいたいと思いますし、できれば職員室にこもらず、子どもの近くで寄り添える先生でありたいです」
川瀬「私も同じで、教職の科目や教員採用試験に向けた勉強などは大変なことも多いため、一人だったら心が折れていたかもしれません。仲間に支えられたり、刺激をもらったりして、乗り越えることができました。同じ夢を持つ人が周りにいるというのは心強いですね。中学校の3年間は、身体だけでなく、精神的にも学力的にも、最も成長する時期だと思うんです。教員として、その時期に携われることがうれしいですね。数学は日常のさまざまな場面で使われているため、そうしたことも紹介しながら、一人でも多くの生徒が数学に興味を持ってくれたらうれしいです。私たちの腕にかかっていますね」
夏目「3人も言ったように、同じ目標を持つ仲間と一緒に勉強を頑張ったことは大きかったですね。一般的な大学の教職課程に比べると、数プロには学科の通常科目の中に教職科目が含まれており、1年生の頃から教職について専門的に学べることはメリットだと思います。算数から数学へ変わり、内容もぐっと難しくなる中学1年の数学は、『数学における中1ギャップ』として知られています。教育実習や塾のアルバイトなどを通して、生徒たちがどこで間違えるのか、どこでつまずくのかが少しずつ分かってきたので、それらの経験も生かし、これから数学の面白さや魅力を伝えていきたいです」
——最後に成川先生、これから玉川大学の数学教員養成プログラムを目指す学生さんへメッセージをお願いします。
成川「私は中学校と高校で数学教員を務めた後に、大学へ移りました。こうした経験も学生たちへ伝えていきたいですね。数学教員になりたいという志があれば、とにかく来てもらえばいいのですが、『数学検定』の関門がありまして、これを通らないと教職の免許が取れません。ですから、数学の力はあるに越したことはありませんが、数学への愛があれば、入ってからでも何とかなるでしょう。もちろん、教員にならなくても、研究者や技術者への道も開かれています。ITやデータサイエンスの分野で活躍したり、数学の学びや研究成果を広く教育分野で生かしたりすることも可能です。もっと言えば、数学は人類の発展に貢献できる学問です。工学部にあるからこそ、そうした幅広い選択ができることがこのプログラムの特徴と言えますね」
<山﨑浩一工学部長のコメント>
工学部の数学教員養成プログラムでは、中学校・高等学校の数学教員を目指しながら、工学系の専門知識を学ぶことで数学の応用力を養えます。これにより、実社会と結びついた魅力的な授業を展開する力を身につけることができます。
このプログラムは工学部の全学科で履修可能ですが、特にマネジメントサイエンス学科では、数学の専門性を深めるとともに、マネジメント理論を活かした学級運営の力も養うことができます。
<関連情報>
●玉川大学工学部
https://www.tamagawa.ac.jp/college_of_engineering/
●工学部 数学教員養成プログラム
https://www.tamagawa.ac.jp/college_of_engineering/teacher/
行動者ストーリー詳細へ
PR TIMES STORYトップへ