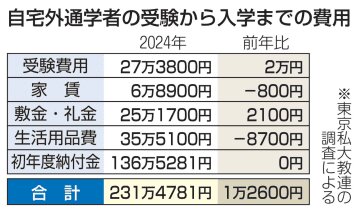2025年の秋が来ても「令和の米騒動」は続く可能性がある…コメ高騰は「市場に背を向け続けた」農水省の大失敗
2025年2月21日(金)10時15分 プレジデント社
政府備蓄米の放出について発表する江藤拓農林水産相=2025年2月14日、東京・霞が関の農水省 - 写真=時事通信フォト
■対応が後手に回ったことを認めた農水相
コメの価格高騰が続く中、ようやく政府が備蓄米21万トンの市場放出を決めた。2023年には記録的な猛暑と水不足でコメの収穫量が大幅に落ち込んだことから、コメ不足が表面化、価格も上昇したが、農水省は2024年産の新米が流通し始めればコメ不足は解消するとして静観を続けた。
ところが、2024年産のコメが出回り始める直前の8月になるとスーパーからコメが消えるなどコメ不足が深刻化した。南海トラフ地震臨時情報「巨大地震注意」が初めて発表されたことで、消費者がコメの買い占めに走ったことも品薄に拍車をかけたとみられている。
その後、新米が流通し始めても価格は下がるどころか上昇し続けた。2024年1月の東京でのコシヒカリの小売価格は5キロ2440円だったが、9月には3285円、2025年1月には4185円となった。こうした価格上昇に追い込まれる形で、政府は備蓄米放出を決めたわけだ。江藤拓農水大臣は、「この半年あまりの期間に、なんでもっと早く決断できなかったのかという批判は、甘んじて受け止める」と述べ、対応が後手に回ったことを認めている。
写真=時事通信フォト
政府備蓄米の放出について発表する江藤拓農林水産相=2025年2月14日、東京・霞が関の農水省 - 写真=時事通信フォト
■21万トンの放出は過去に例がない
放出量の21万トンは過去に例がない量だ。これまでの備蓄米の放出量は、東日本大震災の時の4万トン、熊本地震では90トンに過ぎなかった。これだけ大量の放出を決めたことで、果たして高止まりしているコメ価格は下落に転じるのだろうか。
2月18日、記者会見した江藤農水相は、「やはり流通市場は動いている。動き出したと受け止めていいのではないか」と備蓄米放出発表の効果が表れ始めたとの見方を示した。卸売業者から大手スーパーに対してコメの在庫を売り出す申し出が複数あったことや、コメの先物取引が活発化していることなどを受けたものだった。放出は3月中下旬とされるが、そこで大量のコメが流通し始めるとなれば、価格は下がるので、その前に売っておこうという動きがでているというわけだ。
だが、一方で、価格は大きくは下がらないという見方もある。今回、備蓄米が売り渡されるのは「集荷業者」つまりJA(農業協同組合)など農家からコメを買い付けている業者で、販売に当たる卸売業者ではない。JAはコメ価格の高騰で恩恵を受けており、価格を下げる動機はない。備蓄米の放出価格は集荷業者の入札で決まるので、価格を大幅に下げるような価格での入札はしないだろうとの見方もある。また、集荷業者に備蓄米が渡ったからといって、そのコメが全量、市場に流通するかどうかは確証がない。農水省は卸売業者への販売量などを報告させるとしているが、集荷業者が手持ちのコメをどの程度放出するかと関係する。
■コメの価格を高く維持しようとしてきた農水省
さらに、放出したコメは政府が1年後に買い戻すとしているため、来年もコメ不足が生じるのではないかとの見方が残る。そうなると価格は大きくは下がらない、というわけだ。
専門家の中には、農水省は高価格維持政策を採っていると見る向きもある。農水省が長年続けてきた減反政策も供給を減らすことで価格を維持することが目的だった。主食用米に代わって別の作物を生産する産地や農家に対し、補助金や交付金を支払ってきた。政府が市場に介入してきたのだ。
2017年度をもって減反政策は廃止されたとされる。もっとも、その後も都道府県が独自に生産数量目標を設け、市町村に配分している。また、飼料米に高い補助金を出すことで、食料米からのシフトを奨励し、食料米の供給削減による価格維持策を続けている。
江藤農水相は繰り返し「価格は市場が決めるものだ」と発言している。だが、実態は、市場価格をコントロールし、コメの価格をできるだけ高く維持しようとしてきたのは農水省なのだ。
写真=iStock.com/sigemin
※写真はイメージです - 写真=iStock.com/sigemin
■「コメ先物」へのJAの根強い反対
商品の価格は市場で決まるのが当たり前だと思われるだろう。だが、コメは集荷業者と卸売業者の相対取引で価格が決まっており、不透明だという批判が根強くあった。コメの取引市場を整備すべきだという声は根強くあったが、農水省の対応は二転三転してきた。
もともと、日本では江戸時代からコメの市場取引が行われていた。大阪堂島の米会所でコメの先物取引が定着していた。当時、コメは武士の俸給として使われるなど、一種の通貨の機能を持っており、世界最先端の金融取引所だったと見ることもできる。戦争に向けた国家統制経済が強まる中で1939年にコメの先物取引は廃止されたが、2011年に試験的に復活された。10年を経て大阪堂島商品取引所が「本上場」を申請したものの、農水省はそれを許可せず、2023年にコメ先物は上場廃止となった。
廃止の背景にはJAの根強い反対があった。JAは生産者から集めたコメの流通量を調整してきた。豊作で値崩れしそうなら、在庫を積み増して供給を減らし、高価格を維持してきた。当然、JAがコメを扱う手数料は取引価格に連動するので、コメの高価格維持はJAにとって生命線ともいえる。先物市場が本格的に機能すると、JAは価格決定権を失ってしまう。
■このタイミングでの先物上場が逆効果に
2023年のコメ先物廃止で、コメ価格の上昇に弾みが付いたと見ることもできる。先物取引では、現状の価格が高過ぎると思えば、先物を「売る」投資家が出てくる。先物市場がなくなれば、こうした売りが姿を消し、価格が高騰しやすくなる。
その反省があったのかどうかは分からないが、農水省は堂島のコメ先物の本上場を許可する方向に舵を切る。その上場が2024年8月、まさに令和の米騒動の真っ最中だった。
このタイミングでの先物上場は逆効果になった。というのも新しい商品が上場されると、一定の建玉を持つためにまとまった「買い」が入る。新規上場のご祝儀相場というのもある。つまり、コメ先物の上場がコメ価格を押し上げる要因になったとみられるのだ。もちろん、取引に厚みが出て、時間がたてば、価格は落ち着きを見せるはずだ。先物市場が適正に機能すれば、今回の政府備蓄米の放出が供給を増やすことにつながると市場が見れば、先物価格は下落傾向になるはずだ。
写真=iStock.com/kuppa_rock
※写真はイメージです - 写真=iStock.com/kuppa_rock
■コメは官僚による市場支配の典型例
伝統的に官僚機構は「市場」に背を向けてきた。政策実現のために価格決定権を握ることを重視し、「市場」に介入してきた。最近でもガソリン価格を引き下げるために石油元売会社に巨額の補助金を出し続けているのがいい例だ。だが、政府が強引に価格をコントロールしようとすれば、それには国民の多額の税金が投入されたり、高い価格によって実質的な国民負担が生じたりする。一方で、市場の中での切磋琢磨がなくなり、生産者が国際競争に耐えられなくなる。まさにコメは官僚による市場支配の典型例で、それが今も続いていると言っていい。
農水省は21万トンの市場放出をする論拠として、流通のどこかに21万トンが滞留している、つまり中間事業者が余分に在庫を抱えていると見ているようだ。だから、1年後に放出分を回収するという話になる。だが、実際に、供給量が足らないのではないか、という見方も出ている。インバウンド消費などもあり、コメの消費量自体が増えているのに供給が追いついていないのかもしれない、というわけだ。そうなると、長年の農水省の供給コントロール政策が失敗したという見方もある。
為替レートの円安が進んだことで、国際的に割高だった日本のコメが適正価格になり、輸出も増えている。日本食ブームで日本のコメに対する需要が拡大している。それでも実質的な減反政策を続けている意味があるのか。
もし、本当に生産量が足りなくなっているのだとしたら、令和の米騒動は2025年の秋が来ても収まらない。あるいは天候不順で不作となれば、さらに深刻なコメ不足に直面する可能性もあるということだろう。市場に背を向け続けた農水失政のツケを国民が払わされることになる。
----------
磯山 友幸(いそやま・ともゆき)
経済ジャーナリスト
千葉商科大学教授。1962年生まれ。早稲田大学政治経済学部卒業。日本経済新聞で証券部記者、同部次長、チューリヒ支局長、フランクフルト支局長、「日経ビジネス」副編集長・編集委員などを務め、2011年に退社、独立。著書に『国際会計基準戦争 完結編』(日経BP社)、共著に『株主の反乱』(日本経済新聞社)などがある。
----------
(経済ジャーナリスト 磯山 友幸)