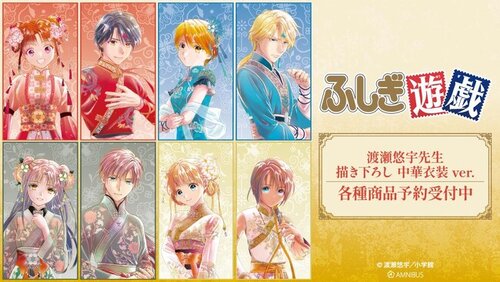Amazonとは「メニューの多い町中華」である…品数が多いほど「本日のおすすめ」が売れる行動経済学のセオリー
2025年2月27日(木)9時15分 プレジデント社
※写真はイメージです - 写真=iStock.com/bgton
写真=iStock.com/bgton
※写真はイメージです - 写真=iStock.com/bgton
■町中華は行動経済学のプロ
少し前にテレビ番組で、「メニューが多すぎる中華料理店」が取り上げられていました。顧客からのリクエストに応えたり、好評だったものをレギュラー化したりするうちに、メニュー数は年々増え、今ではなんと400種類以上! 1年以上通わなければ制覇できないくらいですね。
一方で、このお店の看板メニューは「ちゃんぽん」と決まっており、創業時から人気の一皿だそうです。
大量のメニューの数々と、おすすめの看板メニュー。
これ、実は行動経済学的にとても理にかなった戦略です。
出所=『世界は行動経済学でできている』
私たちは日常生活の中で、さまざまな条件を比較、検討しながら決断をしています。何かを選ぼうとするとき、選択肢が多すぎたりすると、「何を選べばいいのかわからない」「とりあえず、何も選ばないでおこう(決断を先送りしよう)」という選択をしがちになります。
行動経済学では、選択肢が多すぎることで、その選択を先送りにしたり、選択すること自体をやめてしまったりすることを「決定麻痺」と呼びます。
イギリス・ケンブリッジ大学の研究によれば、人間は1日あたり最大3万5000回もの意思決定をしていると言います。どんなルートで目的地に向かうか、いつどこで何を食べるかといった行動から、暇な時間に、ボーッとするか、スマホを見るか、景色を眺めるか、本を読むかという判断まで、自分や周囲の情報を整理、比較、検討し、ようやく決断にいきつくわけです。
■「選ぶ楽しみ」と「定番メニュー」の両輪
この処理が毎日3万5000回も脳内で行われているのであれば、消耗してしまうのは当たり前ですよね。
体を動かし続けていると疲れてしまうのと同じように、決断を続けていると脳が疲労し、徐々に決断の質が低下していきます。決断することが多すぎて嫌になってしまう現象を「決断疲れ」と呼びます。これは、「決定麻痺」の前段階として陥りがちな状態です。
商品やサービスを売る企業にとっては、「決定麻痺」や「決断疲れ」を見越して、素早く、そして自分たちに有利な形で顧客に判断させることが大切になってきます。
その一方で、顧客側が自分の意思で「選ぶ楽しみ」も消費活動では必要な要素です。
「大量のメニューの中から選ぶ楽しみ」と「迷ったときに外さない定番のおすすめメニュー」の両輪がそろっている町中華のお店は、まさにその2つの要素を兼ね備えているというわけです。
■私たちは「決断疲れ」に陥っている
コロンビア大学のシーナ・アイエンガー教授は著書『選択の科学』(文春文庫)の中で、アメリカの退職金積立(確定拠出年金・通称401k)に関する選択と決断の事例を紹介しています。
この制度は、退職後の生活費などをあらかじめ投資運用で準備するためのものです。勤務先の会社ごとに金融機関と提携して、さまざまな商品プラン(ファンド)を用意します。どれを選ぶかは、働く人が自分で自由に決めることができます。
このとき、金融商品の選択肢が多くなるほど、制度の加入者が減ることが明らかになっています。投資運用の選択肢の多さに圧倒されて加入の決断ができず、そのまま先送りして未加入のままという結果に終わっているのです。
また、多くの選択肢の中から選んだ人ほど、大きなリターンが期待しにくいプランを選んでいました。例えば、長期的に伸びそうな業界や会社の株式を探すのではなく、すぐに思いつきやすい会社の株を買うといった行動です。
数多くの投資運用プランを見比べるうちに「決断疲れ」が起きたのでしょう。決断そのものをやめてしまうか、よく考えずに答えを出してしまったのです。
出所=『世界は行動経済学でできている』
■「選んでいる」ではなく「選ばされている」
こうした現象は、結婚式や葬儀などの冠婚葬祭時にも起こりがちです。
基本プランの他に数多くのオプションが用意されており、「決断疲れ」に陥ってしまったところに、「一生に一度のお式ですから」「故人様のために」などの言葉に後押しされた結果、あまり必要のないオプションを付けてしまった……という話はよく聞きます。
あれこれ選べると、自分らしさを反映した豊かで価値のある買い物ができるというメリットもありますが、あまりに選ぶものが多いとすっかり疲れてしまい、売る側の「おすすめ」の思うつぼになっていることもある、というわけです。
私たちは自分の意思でさまざまな決定をしているつもりですが、実は与えられた選択肢の中で「選ばされている」ことも多い、ということですね。
アマゾンや楽天など、大手ショッピングサイトの「おすすめ商品」も「決定麻痺」を巧みに利用しています。
■品数が多いほど「おすすめ」が効いてくる
例えば、アマゾンで「ミネラルウォーター」を検索してみると、何百件もの商品がずらっと画面に並びます。事前に買う商品を決めていなかった場合、それぞれにどんな違いがあるのかを調べると思いますが、商品数が多すぎて早々に「考えるのが面倒くさい」「決められない」という「決断疲れ」状態になってしまいます。特に、急いで買わなければいけないなど、時間がない状況だと、なおさらでしょう。
その結果、たいがいは一番上の段に並んでいる商品の中から選んだり、「おすすめ」とか「ベストセラー」などのマークが付いているもの、コメントが多くて評価が高いものを選択したりします。
私たち消費者は、自分で考えたり選んだりしようとすると「決定麻痺」で先送りをしたり、「決断疲れ」で時間がかかり、結局買わないといった結果になりがちです。こうした結果を避けるために企業は、売りたい商品をどのように「おすすめ」するか考えているのです。
商談などでクライアントに商品やサービスを提案する場合も、このテクニックをうまく使えば、相手をこちらの思惑どおりに誘導することができるかもしれません。
【相手に決断させるコツ】
●多すぎない(3〜5個程度の)選択肢から選べるようにする
●選ばせたい「おすすめプラン」や「基本セット」などを他より目立つ形にして提示する
また、プラスαとして、「人気No.1」「お客様に一番選ばれています」といった補足情報を用意しておくと、「バンドワゴン効果」(他人が持っているもの、多くの人が持っているものだと、もともと興味がなかったとしても欲しくなる現象)も働くので、顧客を誘導しやすくなるでしょう。
■選択を誤らないために疲労と時間をコントロールする
一方、麻痺したり疲れやすくなったりする最大の要因は「時間」です。
一日中決定を繰り返してきた夜の時間帯は脳に疲労が溜まり、すでに「決断疲れ」になっている危険性が高いと言えます。そんなときに何かを決めようとしても挫折したり、「決定麻痺」に陥りやすくなったりします。
「大切なことは朝、決断せよ」……なんて言うと、エリート向けのビジネス書みたいですが、行動経済学的にも的を射ているというわけです。
裁判所で判決が下されるときに、裁判官の「決断疲れ」が被告人の人生を左右することもある、という調査結果もあります。イスラエルの裁判所で行われた、囚人の仮釈放審問と時間帯の調査によると、仮釈放が認められやすいのは、朝イチ、昼休憩後、午後休憩後の3つの時間帯だったそうです。
それ以外の時間帯は「決断疲れ」により、あまり考えずに済む判断(刑務所に入れたままにしておく)を選びやすくなる傾向が見られました。それほど、「決断疲れ」が私たちの選択に与える影響は大きいということです。
これをうまく利用すると、例えば、上司の決裁が必要だけど、粗探しや突っ込みはされたくない、とにかく承認のハンコだけ押してほしいという場合は、上司が「決断疲れ」に陥っている可能性の高い夕方の時間帯に案件を持ち込めば、深く考えずにOKを出してもらえるかもしれません。
出所=『世界は行動経済学でできている』
同じように、社内の役員会議などで稟議を通す、商談先に提案をするという場合も、相手が「もう考えるのが面倒くさい」という状態になっているタイミングを狙えば、通る可能性が高くなるかもしれませんね。
商売の売り手側から考えると、消費者に余計な判断をさせずにどんどんモノを買わせたいなら、セールのスタートを夜中に設定するといい、ということですね。アマゾンプライムデーの開始が夜中の0時なのも、そういった理由からかもしれません。
実際、仕事などで疲れて帰ってきて、深夜にスマホでついポチッと買い物をしてしまった経験がある方は多いと思います(私もそうです)。
■「選びたいこと」と「選ばなくていいこと」を決めておく
もう1つ付け加えると、「自分にとって価値が低いことは最初から選択や判断の手間を省く」というやり方もあります。
アップルの創業者、故スティーブ・ジョブズ氏が同じ黒のタートルネックとジーンズを何十着も保有して、いちいち着るものを選ばなかったのは有名な話です。これは、自分にとってあまり価値がないことを選ぶ無駄を減らし、減らした分の時間や思考のリソースを、より価値があることに使えるようにする方法です。
橋本之克『世界は行動経済学でできている』(アスコム)
例えば、仕事の合間のランチタイムをどのように捉えるかは、考え方が分かれるのではないでしょうか。
ほとんどの職場では、お昼休みは1時間くらいでしょう。その1時間の中で、職場からの移動時間がかかるとしても、毎日いろいろなお店を探して、おいしいものを食べたいと考えるのか。それとも、近場で簡単に食べられるお店にして、ランチの内容より休息時間を確保することを優先するのか。
時間も思考も有限ですので、その中で自分が「何を選ぶことに価値を感じるのか」を明確にし、より価値が高いものにリソースを使えるようにしておくと、自分にとってベストな選択と決断ができるようになると思います。
----------
橋本 之克(はしもと・ゆきかつ)
マーケティング&ブランディングディレクター
昭和女子大学現代ビジネス研究所研究員。東京工業大学工学部社会工学科卒業後、大手広告代理店を経て1995年、日本総合研究所入社。1998年、アサツーディ・ケイ入社後、戦略プランナーとして金融・不動産・環境エネルギー業界等多様な業界で顧客獲得業務を実施。2019年、独立。現在は行動経済学を活用したマーケティングやブランディング戦略のコンサルタント、企業研修や講演の講師、著述家として活動中。著書に『9割の人間は行動経済学のカモである 非合理な心をつかみ、合理的に顧客を動かす』『9割の損は行動経済学でサケられる 非合理な行動を避け、幸福な人間に変わる』(ともに経済界)、『世界最前線の研究でわかる! スゴい! 行動経済学』(総合法令出版)、『モノは感情に売れ!』(PHP研究所)などがある。
----------
(マーケティング&ブランディングディレクター 橋本 之克)