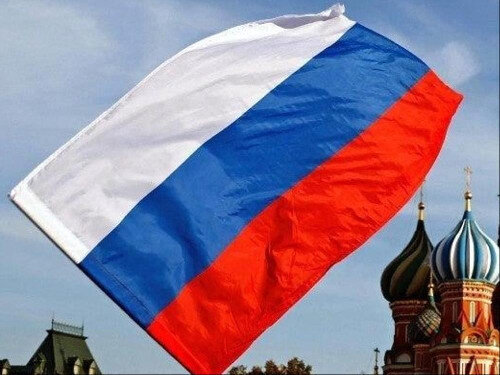ユニクロ柳井正氏や『人を動かす』のD・カーネギー氏も注目 なぜ東アジアの経営者は孔子の教えを重視するのか?
2025年2月25日(火)4時0分 JBpress
『論語』に学ぶ日本の経営者は少なくない。一方、これまで欧米では儒教の価値観が時代遅れとされ、資本主義やグローバル化には合わないと考えられてきた。だが最近になって、その評価が変わりつつある。本連載では、米国人ジャーナリストが多角的に「孔子像」に迫る『孔子復活 東アジアの経済成長と儒教』(マイケル・シューマン著/漆嶋稔訳/日経BP)から、内容の一部を抜粋・再編集。ビジネスの観点から、東アジアの経済成長と儒教の関係をひもとく。
経営不振に陥った企業、ストライキが行われた企業を立て直した『論語』の力とは?
■ 新孔子と儒教資本主義
山西天下滙宝(かいほう)文化伝媒(でんばい)有限公司の創業者、靳戦勇(きんせんゆう)は疲れ果てていた。同社は山西省の省都太原(たいげん)市で展示やイベントの企画運営を業務とする小さな会社だ。
従業員が仕事を怠けたり、口論が頻発しても、靳は自社が傾いていく様子を絶望的な表情で眺めているしかなかった。
ついには殴り合いが始まるほど、社内の不和は激しさを増していった。このような大混乱のせいで売り上げが低迷し、経営に大きな打撃を与えた。だが、彼には手の施しようがなく、途方に暮れるばかりだった。
あれこれ考えた末、彼は「孔子」を人事コンサルタントとして採用する。
実は、これまで聖人孔子をほとんど知らずに過ごしてきたが、2011年に地元の実業家から儒教を紹介されて認識が変わる。紹介者も自社の経営を立て直すために孔子に頼っていた。
まず『論語』を熟読し、紹介者が主催する定期的な会議に参加して刺激を受ける。
「儒教に感銘を受けた。儒教では、人に優しく、人に手を貸し、自分の家族のように接しなさいと説く」
彼は、このような考え方こそ自分の会社に必要だと確信した。孔子が彼の人生を指導してくれるなら、やる気のない従業員にも同じ影響を与えてくれるのではないかと考えたのだ1。
そこで、2012年後半のある日、彼は毎朝の会議で行う定例議題はひとまず横に置き、『論語』の言葉を紹介するビデオを従業員に見せた。その後も毎朝同じようにビデオを見せ続けた。
そして、彼は従業員に儒教の経書を読んではどうかと勧めた。ご褒美として、孔子の教えを最も覚えた者には報奨金を与えると提案する。
「儒教を採用したのは、従業員の生産性を管理して改善するのに役立つと思ったからだ。うまくいけばいいと期待したが、自信はなかった。ほんの試しにやってみただけだ」
ところが、すぐに驚くほどの効果が現れる。従業員間の不協和音が急に消え、以前より熱心に働き出した。
「彼らは本当に協力して働くようになった。他人に頼ることなく率先して仕事に取り組み、会社に対して積極的に貢献するようになった」
『論語』のビデオを見せてから3カ月も経たないうちに、会社の収益は倍増した。
孔子は、魯明羽(ろめいわ)にも同様の劇的な効果をもたらした。彼は山西省太原市の造園建設会社の共同創業者である。
幼少期から伝統的な中国文化に興味があり、2005年から従業員に儒教を教え始めた。毎朝の会議で儒教の教義を議論し、毎週専門家を呼んで講義してもらった。
「儒教の思想は従業員の心に染み渡り、行動に変化が起きるようになった。例えば、儒教を取り入れる以前、彼らは午前8時半に仕事を始め、午後5時半きっかりに会社を出た。職場には1分たりとも残りたくなかったのだ。それが今では、自主的に残業するようなった。時には、私が職場から追い出すことさえある」
魯はこの不可思議な力を孔子の言葉のおかげと考えている。2010年、彼は建設現場でストライキに突入した怒れる労働者数百人と対峙した。彼らの前に立ち、『論語』の言葉をいくつか暗唱してみるよう勧めた。すると、「まもなく、全員が自分の道具を拾い上げ、仕事に戻って行った2」という。
加えて、儒教を学ぶことで自社の経営慣行も改善できた。
1 2013年6月、著者がジン氏に取材した際の言葉である。
2 2013年、著者がルー氏に取材した際の言葉である。
「以前の私の関心は、私のために従業員がどれほど稼いでくれるかだけだった。今では、彼らのために良い仕事を与えたいと考えている。彼らは家族同然で、大事にしたい。収益を上げるだけでなく、自分や彼らの精神面を高めることも重視している。儒教を学び、自らを高めていけば、利益も自然についてくる、と従業員に説いている」
魯によれば儒教は職場を健全に発展させているだけでなく、従来以上の収益も生み出している。
東アジアの経営者は、孔子に経営的アドバイスを求めることを日課としている。
例えば、「ユニクロ」を世界的に展開するファーストリテイリングの柳井正代表取締役会長兼社長によれば、儒教は従業員の採用方法や昇進の仕組みに影響を及ぼしており、自分も各人の学歴や技能だけでなく、道徳的資質にも注目するようになったという。
「当社では、どれほど頭が良くても、周囲から人として尊敬されず、心からの信頼を得られなければ、出世の望みはない。当社の文化を理解できなければ、就職希望者がどれほど賢くても採用されることはない」
西洋では、孔子のビジネス感覚が注目されたことはないが、1936年初版の自己啓発書の元祖『人を動かす』(山口博訳、創元社)の著者デール・カーネギーは、冒頭で孔子の言葉を引用している。
「他人の欠点を直してやろうという気持ちは、たしかに立派であり賞賛に価する。だが、どうしてまず自分の欠点を改めようとしないのだろう?…自分の家の玄関がよごれているのに、隣家の屋根の雪に文句をつけるなと教えたのは、東洋の賢人孔子である3」
多くのアジア専門家にとっては、経済やビジネスに対する孔子の影響は一部の従業員を幸せにすることより遥かに大きい。ここ数十年、中国、日本、韓国、シンガポールなど東アジア諸国が相次いで工業化を果たしたが、大躍進の背景には孔子の存在があると指摘する経済学者もいる。孔子は急成長を可能にした東アジア社会の文化的基礎であると主張している。
考えてみれば、これは大きな皮肉だ。過去150年間の大半で、東西を問わず、孔子の批判者は孔子こそ東アジアの弱さの原点で、近代化を阻害する主な要因と指摘した。
ところが、これらの国々が経済成長の劣等生から優等生に一変する。すると、孔子の地位も東アジアの輸出、経済成長率、家計収入の上昇に伴って高まってきた。アジア没落の要因として指弾された文化的伝統が一転、アジア復興の背景として歓迎されるようになる。数世紀前から孔子に対する態度は変遷を重ねてきたが、その基準から見ても、これほどの評価の逆転劇はかつてなかった。
3 Dale Carnegie, How to Win Friends and Infl uence People(New York: Pocket Books, 1998), 12.
<連載ラインアップ>
■第1回ユニクロ柳井正氏や『人を動かす』のD・カーネギー氏も注目 なぜ東アジアの経営者は孔子の教えを重視するのか?(本稿)
■第2回 「儒教は資本主義に不利」の定説を覆した日本と「アジアの四小龍」 孔子の教えは、いかに起業家精神を引き出したか
■第3回 リー・クアンユー政権下のシンガポールを急成長させた「儒教資本主義」は、なぜ「縁故資本主義」に変質したのか?(3月11日公開)
■第4回 なぜ大韓航空機墜落事故が起きたのも孔子のせいと考えるのか? 儒教的資本主義を頭ごなしに否定すべきでない理由(3月18日公開)
■第5回 レノボ創業者の柳傳志は、なぜ中国人にCEOを任せるのか? 米国人社長の手法が中国企業には馴染まないと判断した理由(3月25日公開)
※公開予定日は変更になる可能性がございます。この機会にフォロー機能をご利用ください。
<著者フォロー機能のご案内>
●無料会員に登録すれば、本記事の下部にある著者プロフィール欄から著者をフォローできます。
●フォローした著者の記事は、マイページから簡単に確認できるようになります。
●会員登録(無料)はこちらから
筆者:マイケル・シューマン,漆嶋 稔