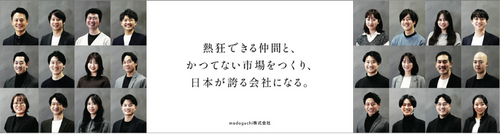本当に頭のいい人は「営業日報」の書き方が違う…「小さな1件」から大きな成果を生むための"さりげない一言"
2025年3月13日(木)8時15分 プレジデント社
※写真はイメージです - 写真=iStock.com/kazuma seki
※本稿は、石川明『すごい壁打ち』(サンマーク出版)の一部を再編集したものです。
写真=iStock.com/kazuma seki
※写真はイメージです - 写真=iStock.com/kazuma seki
■なぜ社内の会話は減少し続けているのか
ビジネスパーソンの基礎能力として「コミュニケーション力」が重視されるようになって、随分と時が経(た)ちます。今や、多くの企業が採用の基準で重視する基本スキルの一つです。
また、企業はITを活用して、社内のコミュニケーションを活性化しようとさまざまな取り組みを続けています。ですが感覚的には、データとしての「情報」は増える一方で、人と人との直接的な「対話」の量は減っているように感じませんか?
「組織を活性化したい」。この言葉をよく耳にします。では「活性化された組織」とは具体的にどんな状態を指すのでしょう。その定義は簡単ではありませんが、少なくとも「活発な対話が行われている」という要素は外せないのではないでしょうか。大事なのは、対話の量・頻度・幅の広さです。
現代の組織内の対話量が減りがちなことには、いくつかの理由が考えられます。
■デジタル化が奪った「ワイワイガヤガヤ」の場
現代のオフィスの風景を見てみましょう。多くの人が、黙々とパソコンの画面に向かって仕事をしています。かつては当たり前だった電話の呼び出し音も、同僚との会話も、めっきり聞こえなくなりました。最近では、「話をするなら会議室や打ち合わせスペースへ」が暗黙のルールになっているオフィスも増えています。静かに集中したい人への配慮という名目です。
もちろん、人々は決して孤立しているわけではありません。メールやチャット、ビデオ会議などを使って常にいろいろな人とやり取りはしているはずです。
それでも、パソコンが普及する前の職場で、フロアの中で皆がワイワイガヤガヤやっていた時代と比べれば、デジタル化が進んだ今では、人と人との直接的な対話は、確実に減っているように思います。
■「ちょっといいですか?」がなくなった弊害
コロナ禍は、私たちの働き方を大きく変えました。リモートワークが当たり前になり、多くの仕事がオンラインで進められるようになりました。通勤時間がなくなり、時間を効率的に使えるようになった人も多いでしょう。
しかし、この変化は人と人との対話の量を確実に減らす方向に働いているように思います。
オフィスにいれば、隣の席の人に「ちょっといいですか?」と気軽に声をかけられます。「最近どう?」といった何気ない一言から、自然と会話が広がることもあります。一方、オンラインではそういったカジュアルな声かけが、なんとなく面倒に感じてしまいませんか? 「わざわざ」連絡を取らなければならない感覚が、ついつい対話への一歩を遠ざけてしまうのです。
メールやチャット、ビデオ会議といったツールは、確かに便利です。工夫次第で離れた場所にいる人とも効率的にやり取りができます。けれども、一緒にランチを食べたり、雑談をしたり、何気ない時間を共有したりする機会は明らかに減っています。結果として、人と人との直接的な対話の総量は、やはり減少しているように思えます。
■状況把握しづらいが、面談するまでもないし…
さらに、近年の仕事のやり方の特徴として、「パーソナル化」が進んでいることも挙げられます。
もちろん、誰もが完全に独立して仕事をしているわけではありませんが、個人で処理できる仕事の範囲は広がっています。多くの作業がパソコンとサーバーの間で完結し、周りの人からは何をしているのかが見えにくくなっています。
かつては当たり前だった「全員集まっての会議」も、今では非効率の代名詞さながらにいわれるように……。ファイルの共有やメールの一斉送信で済ませることが、新しい常識になりつつあります。
確かに、これらの変化は組織の生産性を高めることに繋(つな)がっています。しかし、チームを率いる立場の人にとっては、新たな悩みの種となっているかもしれません。メンバーの様子が把握しづらい。かといって、わざわざ声をかけて状況を確認しようとすると、大げさな「面談」のようになってしまう。そんなジレンマを感じている管理職の方も多いのではないでしょうか。
■「風通しの悪さ」は組織を崩壊させる
組織の生産性や効率を追求した結果、対話の量が減っているのは、ある意味で自然な流れかもしれません。ただ、その変化が長期的には組織のパフォーマンスを低下させる可能性を、私は強く懸念しています。
特に懸念されるのが「風通しの悪さ」です。組織の風通しが悪くなると、上下の意思疎通が滞り、部門間(横)の連携も弱くなります。問題が表面化しにくくなり、「気づいたときには手遅れ」ということも起こりかねません。
風通しが悪い組織では、小さな気づきや、まだ形になっていないアイデアは、組織の中で声を上げにくくなります。リスクのある新しいことへのチャレンジや変革の機運も生まれにくく、組織は次第に保守的になり、停滞していきます。
こうした事態を避けようと、組織はさまざまな工夫を重ねています。かつての「飲みニケーション」やタバコ部屋(喫煙ルーム)に代わるものをと、さまざまな取り組みが行われています。
■1on1で何を話せばいいのか問題
オフィスにカフェスペースを設けたり、部署を超えたランチ会や「井戸端会議(よもやま会などとネーミングされる組織もある)」を企画したりしています。他にもオンライン上でのコミュニティづくりや、1on1ミーティングの制度化など、対話の機会を意図的に作り出そうとする動きも増えています。
写真=iStock.com/Masafumi_Nakanishi
※写真はイメージです - 写真=iStock.com/Masafumi_Nakanishi
これらの取り組みにも、確かに意味はあるでしょう。しかし、本当に大切なのは「場」や「機会」を用意することだけではありません。そこで「どんな対話を交わすのか」、その中身こそが重要なのです。実際のところ「1on1で何を話せばいいかわからない」という声はよく聞きます。
埼玉大学の宇田川元一氏の著書『企業変革のジレンマ』(日本経済新聞出版)では、組織内での「対話」こそが変革を進めていくための鍵と紹介されています。
拙著『すごい壁打ち』(サンマーク出版)では、そんな「対話」の一つの形として壁打ちというスタイルをご紹介しました。壁打ちは組織の風通しを良くし、活性化する効果的な方法の一つになり得ます。形式張った会議とは別に、組織の中で壁打ちが日常的に行われるようになれば、部署や立場を超えた対話が自然と増えていくはずです。
■壁打ちが組織にもたらす「風通しの良さ」
本書を読んでいただき、壁打ちを使いこなせるようになったみなさんには、率先して組織の中で壁打ちを行い、浸透させていくことにより、「風通し」の良い組織づくりに寄与していただきたいと期待しています。
読者の中にはマネジメントの立場にあり、組織の活性化自体をミッションにしている方もいるでしょう。
また、自分のミッションではなかったとしても、気持ち良く働ける職場、価値を生み出し続けられる強い職場を望んでいる気持ちはみなさん同じでしょう。
ここからは、壁打ちが浸透し風通しが良くなった職場には、どんな良いことがあるかご紹介します。壁打ちが実際に組織の中でどのように機能するかをイメージしてみてください。
どんな組織も、常に変化する環境の中で事業を営んでいます。その変化にうまく対応し続けることが大切だと、誰もがわかっているはずです。しかし、組織の中だけにいると、その変化を感じ取ることは難しいものです。
実は、環境の変化に最も早く気づきやすいのは、お客さんや取引先と日々接している現場の従業員です。真剣に仕事に向き合っていれば、外部の人との会話やその人たちの様子から、何かしらの変化を感じ取る機会があるはずです。
■営業日報をただの事務作業にしてはいけない
大切なのは、その「気づき」をいち早く組織の中に持ち込めるかどうか。「これは新しいビジネスチャンスかもしれない」「自社の競争力が落ちているかもしれない」など、最初は小さく、はっきりしない変化かもしれません。それでも、そこに可能性や危機を感じた人は、「これは社内で対応を検討すべきでは」と考え始めます。
多くの企業では「営業日報」の提出を義務付けています。私も仕事上、さまざまな企業の営業日報を見る機会があるのですが、正直なところ「もったいない」と感じることが多いのです。
確かに、一人ひとりはしっかりと日報を書いてくれています。ただ、その内容は結果や進捗の「数字」の報告ばかり。ただの結果数値の羅列で終わることがほとんどです。
本来、営業職の方はお客さんとの接点の中で、日々新しいビジネスチャンスの種に触れているはずです。しかし、数字だけの日報では、そのチャンスに気づくことができません。契約や受注に結びつかなかった案件は、数字で見ればどれも同じ「1件」でしかありません。けれども、その「1件」の中には、新しい価値を生み出す可能性を秘めた「特別な1件」が交ざっていることがあるのです。
■壁打ちこそが「予兆の早期発見」を可能にする
ただ、確信も具体策もない段階では社内で報告しづらいもの。上司に「ちゃんと考えてから報告しろ」と言われた経験があれば、まだ自分の中でも曖昧な段階の場合、「社内では黙っていよう」と考えてしまうのも責められません。
ところが、壁打ちが日常的な組織なら違います。「ちょっといいですか? 最近気になることがありまして……」と、誰かに話を切り出せるからです。最初はぼんやりとした話でも、良い「壁」が相手をしてくれれば、話しているうちに「何が問題なのか」「それはどれくらい重要なのか」が見えてきます。
正式な会議や報告書を待つまでもなく、小さな予兆の段階から組織として素早く動き出せる。壁打ちという気軽なコミュニケーションが認められているからこそ、組織は環境の変化の予兆をいち早く察知することができるのです。
私の本業は、ボトムアップで新規事業を生み出すお手伝いです。
ボトムアップにこだわる理由は、「経営者だけでなく、現場の社員からも新しいアイデアや改革案が生まれる組織こそ強い」と考えるからです。多くの経営者もそんな組織を目指したいと考えていますが、ボトムアップで声が上がる組織を実現するのは簡単ではありません。
写真=iStock.com/recep-bg
※写真はイメージです - 写真=iStock.com/recep-bg
■まずは「言い出す勇気」をつくる
まず大切なのは、社員が思いついたアイデアがたとえ小さかったり、曖昧だったり、未熟だったりしても、気軽に口に出せる雰囲気づくりです。
最近では「心理的安全性の高い組織」という言葉が広く知られるようになってきました。結局、誰かが「言い出す」ところからすべてが始まるのです。
もちろん、アイデアがたくさん出てくるだけでは不十分です。未熟なアイデアばかりが積み重なれば、「もっとマシな案はないのか」という声も出てくるでしょう。
大切なのは、出てきたアイデアを誰かが受け止めて、一緒に磨いていくこと。ただ、その「受け止める人」に必ずしも特別な企画力は必要ありません。最初は壁打ちの要領で、話を聞き、うなずき、時々質問を投げかける。それだけでも、アイデアは少しずつ磨かれていくものです。
「妄想ばかりでなく具体案を」「文句を言うなら代案を」。そんな指導をする管理職もいます。確かにその指摘は間違っていません。ただし、その一言で社員が萎縮し、妄想も文句も出なくなってしまう組織は危険です。
■優秀な管理職とは、「良い壁」となることである
本当に優れた管理職なら、良い「壁」となって、その「妄想」や「文句」に上手な問いかけを返し、より深い思考へと導いていくはずです。
石川明『すごい壁打ち』(サンマーク出版)
ただ良い案が出てくるのを待つだけでもダメ。かといって、研修でスキルを磨くだけでも、なかなか成果には結びつきません。
結局、最も大切なのは組織の中の対話の質であり、対話を育む風土です。新しいアイデアをボトムアップで生み出していくには、アイデアを口にする人と、それを受け止める人がセットでいること。そして、その二人の間で壁打ちが自然に行われるような風土が必要不可欠なのです。
スタートアップ起業の世界では「リーンスタートアップ」という考え方があります。小さく始めて、少しずつ大きく育てていこうという発想です。その意味で、壁打ちこそが、新しいアイデアを育てる最も小さな、でも確実な一歩なのです。
----------
石川 明(いしかわ・あきら)
インキュベータ代表
1988年上智大学文学部社会学科卒業後、リクルートに入社。リクルートの企業風土の象徴である、新規事業提案制度「New RING」の事務局長を務め、新規事業を生み続けられる組織・制度づくりと1000件以上の新規事業の起案に携わる。2000年に総合情報サイト「オールアバウト」社の創業に携わり、事業部長、編集長などを務める。2010年に独立起業。大手企業を中心にこれまで150社、3000案件、6000人以上の新規事業検討に伴走し支援してきた。「壁打ち」の相手になって新規事業の起案者の話を聴く回数は年間1000回を超える。早稲田大学ビジネススクール修了。大学院大学至善館特任教授、上智大学Sophia Entrepreneurship Network運営委員、明治大学専門職大学院グローバル・ビジネス研究科客員教授。経済産業省の起業家育成プログラム「始動」講師などを歴任。著書に『Deep Skill』(ダイヤモンド社)、『はじめての社内起業』(ユーキャン学び出版)、『新規事業ワークブック』(総合法令出版)がある。
----------
(インキュベータ代表 石川 明)