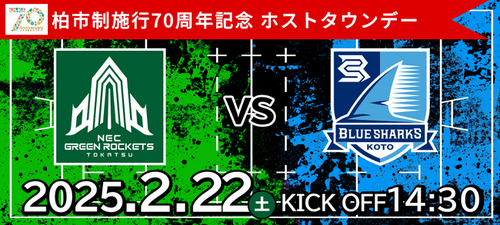清水建設は「麻布台ヒルズ森JPタワー」施工で500人を省人化 人間の代替にとどまらない「建設RX」の重要な目的とは?
2025年3月10日(月)4時0分 JBpress
日本のGDP(国内総生産)の実に22%を占める、建設・不動産・住宅の3業界。日本経済を支えるこれら巨大産業が、今「変革のタイミング」を迎えている。本連載では『「建設業界」×「不動産業界」×「住宅業界」Innovate for Redesign』(篠原健太著/プレジデント社)から、内容の一部を抜粋・再編集。異業種に比べてDXやGXの面で後れを取る3つの業界に求められている、産業構造の「リデザイン」について考える。
今回は、現場の省人化をはじめ建設業界の環境を大きく変革する「RX(ロボティクス・トランスフォーメーション)」をテーマに取り上げる。
建設業は製造業と比べて「真のDX」が進みにくい
では、真のDXとは、どんなことでしょうか? これは、過去データをベースに、より精度の高い意思決定ができるようにすることだといえます。
製造業の場合は、ボラティリティが少ない(使用する部品が固定、部品ごとの加工方法やコストなどもほぼ固定)ため、過去データの活用がしやすいという特徴があります。
一方、建設業は、どちらかというと1案件ごとに個別に適した対応が必要になってくるので、過去データの活用が難しいという状況になっています。また前述したように、施工工事の主体は職人である一方、モノの製造は工作機械が行います。そのため、どのようなモノがどのくらいの時間でできるかというのが、建設業よりも予測しやすいのです。
しかしながら建設業界において、個別性が高いからという理由でDXの道を諦めてもよいのかというとそうではありません。むしろ過去案件で溜まったデータをより多く集めて、モジュール化したナレッジを蓄積していく必要があるのです。
建設業での課題は、毎回、原価計算、発注先の選定、見積額の決定をゼロからやっていて、過去のデータがまったく反映されていないこと、もしくは、過去の経験を参考にしているものの、それが属人化してしまっていて、そのナレッジが会社に残っていかないこと、さらに、正確とはいえない意思決定が行われ続けていることになります。
前述したように、バリューチェーン上で出てきた書面などはデータ化し、追跡可能な状況にしておく、現場の実情は施工管理の担当者が回収する、ないしは、IoTやデバイスからの収集データなどで担保するというように、施工時点に発生したデータを蓄積していくというような作業は、DXを進める上で必須といえるでしょう。
また、在庫や部材管理の観点からいえば、設計〜現場〜調達までのつなぎ込み、原価管理の観点からいえば、受注〜設計〜部材ごと単価、協力会社コストの連動といったことになります。これをやらないと、QCDの担保や不健全な転嫁などがある現状は変わらないといえるのです。
こうしたDXを実際に進めていく中では、次の2点に注力することが必要です。
1つ目は業界知見や1次情報を正しく反映するようなツールの開発を、ベンダーなどと協力しながら実施すること(ただし、この際は業界知見とソフト化の際の技術知見を持った架け橋的な存在が必要)。
2つ目は、導入後の浸透を考え続けることです。活用現場においては一度の説明では受け入れられず、繰り返しの伴走が必要になります。心理的な壁に寄り添い社内・外の仕組みとして落とし込んでいくにはそれなりの時間とコストを要するということを押さえて推進していく必要があるのです。建設業におけるDXの推進には組織変革のストーリーメイキングがとても重要となるのです。
建設業では、これまで行われていた非合理的で「一発エイヤ」的な意思決定のしわ寄せが、労働時間や転嫁のような事象として現れています。だからこそ、社会的にそういったものが許容されない現在(2024年問題など)、過去データに基づいた、より正しい意思決定が求められているのです。
大手ゼネコンは「RX」へ積極投資を
建設業界のRX(ロボティクス・トランスフォーメーション)に関しては、2021年に「建設RXコンソーシアム」が大手ゼネコンを中心に立ち上がりました。
これは、人手不足の解消や生産性・安全性の向上、コスト削減といった課題解決を目的にしています。
たとえば清水建設は、ビルなど建築物の天井ボードを自動で施工するロボット「Robo-Buddy Ceiling」を自社開発し、実際の建築現場に適用しています。同社は次世代型生産システム「シミズ・スマート・サイト」を打ち出し、建築現場で建設ロボットを積極的に導入する方針をいち早く掲げました。そして、複数の自律型ロボットを組み合わせて生産性を高めるべく、技術開発と現場実証を重ねています。
2023年6月に同社の施工で竣工した高さ約330メートルの「麻布台ヒルズ森JPタワー」(東京都港区)では、溶接ロボットと耐火被覆吹き付けロボットを活用し、上棟までのプロセスで500人程度の省人化につながりました。
こうした先行事例が生まれている一方で注意すべきなのが、RXの目的を見失わないということです。通常、RXというと「省人化」、すなわち、これまで人がやっていた作業を機械によって代替することで、それまでに割いていた人的なコストを浮かせる、というような文脈でのみ言及されがちです。ただし、建設業におけるRXは、ほかの意味も持つということに注視すべきです。
まず1つ目が、労働環境の改善です。
建設RXと呼ばれるプロダクトの中には、単に人の作業を完全に代替するようなものではなく、人の作業をサポートするようなものも多く含まれます。たとえば、建設現場で使われるようなアシストスーツやクレーンの遠隔操作技術、バイタルセンサー、測量ドローンなどがその代表です。これらの技術は決して「業務を無人で遂行可能にする」ものではありませんが、紛れもないRXの技術の一つです。
こうしたRX技術は、建設業界にはびこる「高負荷で危険である」というイメージを払拭します。そのため、単なる人的工数の削減という文脈にだけ注目をするのではなく、就労環境の良化に役立っているという事実を明示し、求職人口の増加にまで効果を波及させるべきなのです。
2つ目が、工程管理のさらなる精緻化です。墨出しや資材の自動搬送、コンクリート施工などモジュール化しやすい業務は、現在、ロボットによる代替が進んでいますが、これをただ省人化の一手段として捉えるだけでは不十分です。人による作業が中心で、業務時間が読みにくいというのが常識であった建設業界において、一部の業務が精度高く所要時間を見込めるようになったというのは大きな進歩でしょう。
そのため、全業務のうちロボットによって行われる業務の所要時間はどのくらいなのか、逆に人でしか実施できない業務とは何で、それはどのくらいの所要時間が実際ベースでかかっているのかというデータを蓄積していく必要があります。
このように、ロボットの介入をきっかけに積極的に各業務の切り分けと各業務の所要時間の見込み数値を積み上げて記録していくことにより、将来的により正確なコスト予測が可能になっていくのです。
早急に生産性向上への改善が求められている建設業界において、先進技術を積極的に取り入れて、RXを推進させることが重要なのはもちろんでしょう。
ただ、その効果というものを単なる「省人化」にとどめるのではなく、求職者市場におけるプレゼンス増加や、工数管理の精緻化など別の課題解決をも見据えていくことが大切だといえます。
<連載ラインアップ>
■第1回 清水建設は「麻布台ヒルズ森JPタワー」施工で500人を省人化 人間の代替にとどまらない「建設RX」の重要な目的とは?(本稿)
■第2回 ビルの省エネ施策「ZEB」の付加価値をどう伝えるか? 東急コミュニティーの事例などを通じて見えた具体的な課題とは
■第3回 三井不動産レジデンシャル、野村不動産…地方でも加速する「コンパクトシティ構想」で不動産業界が直面する課題とは?(3月24日公開)
■第4回 イオン、アパ、星野リゾート、NTTデータ…続々参入する異業種企業が手掛ける不動産活用を通じた新しい価値創造とは(3月31日公開)
■第5回 大和ハウス工業を筆頭に進む大手ハウスメーカーの多角化経営、住宅市場の先細りに直面する工務店の生き残り戦略とは(4月7日公開)
※公開予定日は変更になる可能性がございます。この機会にフォロー機能をご利用ください。
<著者フォロー機能のご案内>
●無料会員に登録すれば、本記事の下部にある著者プロフィール欄から著者をフォローできます。
●フォローした著者の記事は、マイページから簡単に確認できるようになります。
●会員登録(無料)はこちらから
筆者:篠原 健太