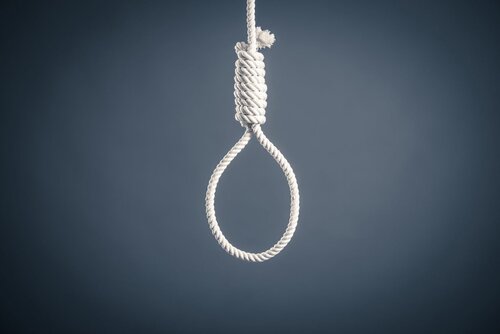「わしらは、処刑マシーンなんや」死刑囚の最期を看取る"白衣の刑務官"の知られざる業務内容
2025年3月21日(金)18時15分 プレジデント社
※写真はイメージです - 写真=iStock.com/bee32
写真=iStock.com/bee32
※写真はイメージです - 写真=iStock.com/bee32
■「心の準備だけはしとかんとな」
医務課の事務室内には、寺園清之ともう一人、平松卓がいた。デスクに座る寺園は、ひたすら手を動かし続けている。
名古屋拘置所の二階部分には、東館と西館とをつなぐ渡り廊下があった。その廊下に面して、病舎や診察室、薬局、そして医務課の部屋が並ぶ。
医務課の事務室に、夕暮れの光が射し込んでいた。光は鉄格子を通して、床に仄赤(ほのあか)い縞模様をつくる。
寺園は、隣にある薬局から戻ってきたあと、ずっと作業に没頭していた。渡された薬を手にし、その数や種類を確認しているのだ。薬は、収容者たちが服用するもので、これから西館のほうに出向き、各階の担当刑務官に手渡すことになっている。
「一応、心の準備だけはしとかんとな」
先輩刑務官である平松が、そう独りごちた。彼は、すでに白衣を脱いでおり、帰宅の準備に入っていた。ロッカーから取り出した私服を横に置き、ソファーに座ったまま、着替えている。
■拘置所で働く「白衣の刑務官」
寺園は、まだ仕事中である。一般刑務官と同じズボンを穿(は)き、上半身は白衣を纏(まと)う。それが、「保健助手」といわれる刑務官の、勤務中の姿だ。事務室の外では、制帽もかぶる。
寺園は、作業をしながら、平松を一瞥(いちべつ)する。すぐに視線を、壁にかけてあるホワイトボードに移した。医務課長の顔を思い浮かべ、心の中で頷く。
明日は長い一日になるのではないか。おそらくこの予感は当たっている。死刑が執行されるのだ。
ボードには予定表が掲示されてある。医務課に所属するスタッフの月間予定が書き込まれたものだ。医務課スタッフは、医務課長の米崎、新任医師の田所、保健助手の平松と寺園、それに看護師の吉浜秀子という、計5人のメンバーだ。ちなみに、刑務官が務める医務係長のポストは現在、空席である。
■吊るされた死刑囚は10〜15分で死を迎える
そういえば、先週のことだ。寺園に対し、吉浜秀子が、不安そうな表情で、こう尋ねてきたのだった。
「ここって死刑を執行したりするんですよね。やっぱりその時は、私みたいな看護師にも何か役割が振られるんですか」
「そうか、吉浜さんの着任後は、まだ死刑はやられとらんもんな。でも心配せんでええよ。その時に立ち会う職員は、医務課のなかじゃ、医務課長とわしら刑務官だけだもんで」
49歳の寺園であるが、すでに9回の絞首刑に立ち会っている。
執行時における保健助手の役割は、最期の看取りだ。刑場の地下にいて、落下してくる死刑囚を待つ。吊るされた死刑囚が目の前に現れたら、その体を支え、絶息するまで手首に指を当て、脈をとり続ける。
心肺停止に至る時間は、早い者で10分、平均だと15分くらいだ。脈が止まれば、次に、医師である医務課長が心音を確認し、死亡を告げる。そのあと保健助手は、警備隊のメンバーとともに遺体を清拭(せいしき)し、白装束に着替えさせる。
鼻や耳に脱脂綿を詰めたり、髭を剃ったりするのも、保健助手の役目だ。そして、納棺した遺体を、一階にある霊安室まで移動させれば、とりあえずの仕事は終了となる。
■通常業務は、収容者の健康管理や病気治療
「きっと、あしたやるんやろうな」
また平松が、独りごとを口にした。寺園は、それに反応せず、目を下に向けたまま、作業を続ける。チェック済みの薬を、白い布でできた手提げ袋の中に詰めていく。
寺園には、准看護師の資格がある。看護系の学校を出たわけではない。高校は鹿児島県内の剣道の強豪校に通い、3年時には、インターハイで好成績を収めた。高校卒業後、「武道拝命」という採用枠によって刑務官になる。最初は、名古屋拘置所の処遇部に籍を置いた。
夜間の巡回、および収容者の入浴や運動への立ち会いが主な仕事だった。そして、20代前半の頃だ。東京にある法務省の准看護師養成所において2年間の研修を受け、准看護師の資格を取得する。名古屋拘置所に戻ったあとは、医務課に所属。保健助手として、医師をサポートしつつ、収容者の健康管理や病気治療にあたっている。平松も、同様の立場だ。
二人はともに、「副看守長」という階級にあった。刑務官の階級は7段階あるが、副看守長は、下から3番目。管理職ではなく、二人は現在、監督権限のない係長待遇となっている。
医務課長の米崎は、寺園よりもひと回り下だった。2年前に、名古屋大学医学部附属病院から異動してきた外科医である。医師としての腕は確かだ。落ち着いた物腰で、的確な判断を下していく。寺園は、その仕事ぶりに、年下の相手ではあるが、頼りがいさえ感じていた。
■いつ死刑を執行するかは極秘事項
普段は冷静沈着な米崎が、一昨日から様子がおかしい。妙にそわそわしていて、どこへ行くのか、席を外していることが多かった。携帯型内線電話で連絡がつく状態になってはいるものの、今も行方知れずだ。米崎の予定表には、確か明日の水曜日、〈医学セミナーのため東京へ出張〉と書かれていたはず。だが、いつの間にか、それが消えている。
保健助手の刑務官に死刑執行が知らされるのは、当日の朝だ。二人が同時に欠勤することは、まずあり得ないからであろう。しかし、医務課長は一人しかいない。医務課長がいなければ、死刑自体が成り立たないのである。そうした事情もあり、医務課長には、3日ほど前に、刑の執行が伝えられるらしい。当然、その秘密事項を、他者に漏らしてはならない。
ほかにも、事前に刑の執行を知らされる者たちがいる。警備隊の面々だ。警備隊というのは、所内の規律維持活動や規則違反者への取り調べ、刑場の管理、さらには絞首刑執行の準備もする。そして、死刑執行時は、その中心を担う。
写真=iStock.com/st_lux
※写真はイメージです - 写真=iStock.com/st_lux
■前日にリハーサルを何度も繰り返す
明朝に執行だとすれば、すでに刑場の掃除は終えているだろう。警備隊にとって最も重要な準備作業は、清掃のあとに待っている。それは、絞首刑のリハーサルだ。
ロープの長さは、事前に調整しておく必要がある。死刑囚の体重と同じ重さの砂袋を用意し、実際にロープに括りつけて、執行ボタンを押す。地下に落下した死刑囚の足底が、床上30センチぐらいの高さにくるよう、何度も繰り返して実験するのである。
寺園の高校の後輩で、この拘置所の剣道部に所属する福留宏典も、警備隊員の一人だ。
昨夜、寺園は、拘置所内の道場で、福留と竹刀を合わせた。だが、まったく気合が入っていないし、心ここにあらず、といった体だった。それを質しても、なんでもありませんと、喉に何かが絡まったような声が返ってくるだけ。稽古が終わっても、ほとんど口を利かない。着替えたあとは、挨拶もなく、道場のある東館1階から、あたふたと出て行った。明らかに、いつもの彼とは違った。
26歳の福留は、今年、警備隊に配属されたばかりだ。きっと刑場の中に入るのも、初めてなのではないか。
■午前9時半頃の執行後、午後6時まで「隔離」
平松が、またつぶやく。
「あしたも、朝7時半ぐらいに呼び出しやな」
彼はもう、私服に着替え終わっていた。
平松の言葉を聞き流し、寺園は頭の中で、これまでの経験と照らし合わせて考える。
たぶん午前8時前に、執行に関わる者全員に集合がかかる。場所は西館2階、処遇部の会議室。20から30人が参加するミーティングだ。処遇部長の挨拶に始まり、続いて処遇首席が、タイムスケジュールや段取りについて説明する。刑の執行は、午前9時半頃だ。
〈執行後、その日の勤務は終了。死刑に関わった刑務官は、午前中で解放される〉
死刑を取り扱った書籍では、そんなふうに書かれていることが多い。ところが、名古屋拘置所では違う。確かに午前中で仕事は終了する。しかしその後、関わった者のすべてが市内の別の場所に集められ、午後6時過ぎまで、一緒の時間を過ごすことになる。
料理が出され、酒も振る舞われる。慰労会という名目もあるだろう。だが、本当の目的は、記者発表の前に情報が漏れないようにするための「隔離」ではないかと思う。
写真=iStock.com/mapo
※写真はイメージです - 写真=iStock.com/mapo
■血だらけの惨事を避けるための留意点
通夜のような会であるが、場の空気を変えようと、冗談を口にする者もいる。けれども、会場の雰囲気は、終始、陰鬱としていた。一方でそこは、個々の気持ちを整理したり、執行チーム全体の結束を高めたりする場にもなる。
25年前、寺園が最初に死刑に立ち会った日の会では、こんな場面があった。一人の警備隊員が立ち上がり、まわりに対し、「きょうのは、ほんま可哀そやった。次はもっとうまく逝かせなあかん。なあ、みんな、そうしよう」と檄を飛ばす。すぐさま、それに呼応して異口同音、「そうだ」「そうだ」の声が上がった。そして最後のほうは、実演も含めての、反省会となる。
執行に初めて加わったあの日──。思い起こせば、あれは悲惨だった。首縄のかけ方がうまくなかったらしく、執行された死刑囚は、本当に苦しそうな最期となった。血が飛び散った床に、遺体を横たえさせると、首が取れそうになっていた。
ベテラン刑務官が口酸っぱく言う留意点だが、首縄をかける時は、結び目を首の左側に持っていき、縄と皮膚の間に隙間ができぬよう密着させて、それから軽く締め上げるのだ。そうしなければ、落下の際、首の肉が裂けたりして、大量の出血をともなう惨事となる。
■絞首に失敗し、締め技で絶命させた例も
気づくと、事務室内に、咳払いが聞こえていた。殊更らしい咳である。平松が発しているのだ。着替えが終わっても、ずっとソファーに腰かけていた。
寺園は、彼のほうに目をやる。むこう向きに座っているが、その背中が何かを言いたげだった。平松とは、もう30年以上のつき合いだ。言葉を交わさなくても分かることがある。
平松は、柔道による「武道拝命」だった。その広い肩幅を見て、ふと思い出す。過去に他の拘置所で起きた、死刑執行時の出来事についてだ。
地下に落下し、宙吊りになった死刑囚が、もがき苦しみ続けている。ロープが首から外れかけていたらしい。やむなく死刑囚の体を下に降ろし、柔道高段者の刑務官が、締め技で絶命させたというのだ。執行後、その刑務官の子供が、不治の病に罹ったという話がまことしやかに語られている。
平松の息子は、9年前に、生死をさまよう大病をした。今もあまり体調は良くないようで、このところ、ずっと死刑執行には、寺園が立ち会ってきた。今回もそうしてくれ、と言うのだろうか。
寺園にとって平松は、「恩人」といってもいい存在だ。職場の先輩として、いろいろと教えられてきたし、私生活においても、種々相談に乗ってもらっていた。感謝しきれないほどの人物だ。その平松との間で、変な駆け引きはしたくない。
■12人の「死刑確定者」の顔が思い浮かぶ
平松が、寺園のほうに顔を向けた。寺園は即、平松に対し、その言葉を口にする。
「あした、あれがあったら、また自分が行きます」
平松の表情が、にわかに変わった。笑みが浮かぶ。が、すぐにそれを消して、頭を下げる。
「いつもすまんな」
「気にせんといてください」
寺園は、そう返して立ち上がった。制帽をかぶり、薬の入った手提げ袋を手にする。
「これから西館のほうに行って、薬を届けてきます」
「そうか。ほな寺園、わし、先に帰っとるわ」
軽く頷いた寺園が、そそくさと部屋を出る。
西館の上層階には、死確者が12人いた。そのなかの誰かが、明日、死刑を執行されることになる……。寺園の頭の中に、彼ら一人ひとりの顔が思い浮かぶ。
■「処刑マシーン」などにはなりたくない
死確者といっても様々だ。刑執行を前にして、刑務官の手を煩わせることなく、大人しく自ら前に進む者もいれば、徹底的に抵抗し、暴れだしてしまう者もいる。刑務官側からすれば、前者の場合は、自殺の手伝いをしているように思え、後者の場合は、よってたかっての殺人行為に及んでいるように思えた。
もちろん刑務官は、誰しも、好んで死刑を執行したいわけではない。きのうまでは普通に言葉を交わしていた人間が、突然、目の前で命を絶たれるのだ。いや、自分たちの手で命を奪うことになるのである。普通に考えれば、正気ではいられない。
「わしらは、処刑マシーンなんや。マシーンが何かを考えたらあかん」
かつて寺園は、ある先輩刑務官にそう諭されたことがある。けれどもやはり、マシーンなどにはなりたくない。自分は、血が通った、そして涙も流す、生身の人間なのだ。毎回、刑執行後は、しばらくの間、鬱状態が続き、酒の量も増える。悪夢にうなされたことも、一度や二度ではない。実際に、亡霊のようなものを見たことも……。
■指揮者である検察官は高みの見物
すぐにその記憶を消そうと、寺園は、頭を左右に振った。そして、西館2階のエレベーターホールへと向かう。
エレベーターから検察官が降りてきた。この階には、検事調べの部屋もある。調書を取りに来たのだろう。
寺園は、体の向きを変え、廊下を北のほうに歩く。
山本譲司『出獄記』(ポプラ社)
突き当たりにある窓から、外を眺めた。薄暗くはなっていたものの、近くの景色ははっきりと目に映る。名古屋城を背景にして、手前に法務合同庁舎のビルがあった。名古屋高等検察庁や名古屋地方検察庁が入る建物だ。
死刑執行を指揮するのは、処遇部長でも所長でもない。検察庁の検察官なのだ。法律的にそうなっている。しかし、指揮者であるはずの検察官が、立会人として拘置所に現れるのは、いつも執行の直前。そして執行時は、執行部屋の向かいの「バルコニー」から、高みの見物だ。
寺園は、睨むように、法務合同庁舎のほうを見た。
這っても行き来できるこの距離を、検察官は毎度、黒塗りの車に乗ってやってくるのだ。思っただけで、腹立たしくなる。
----------
山本 譲司(やまもと・じょうじ)
作家、元衆議院議員
1962年、北海道生まれ。佐賀県育ち。早稲田大学卒。菅直人代議士の公設秘書、都議会議員2期を経て、1996年に衆議院議員に当選。2000年に秘書給与詐取事件を起こし、一審での実刑判決を受け服役。出所後、433日に及んだ獄中での生活を描いた『獄窓記』(ポプラ社)が「新潮ドキュメント賞」を受賞。障害者福祉施設で働くかたわら、『続獄窓記』『累犯障害者』『刑務所しか居場所がない人たち』などを著し、罪に問われた障害者の問題を社会に提起。現在も、高齢受刑者や障害のある受刑者の社会復帰支援に取り組む。小説作品として『覚醒』(上下巻)『螺旋階段』『エンディングノート』がある。
----------
(作家、元衆議院議員 山本 譲司)