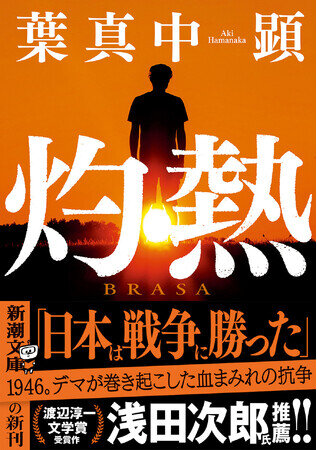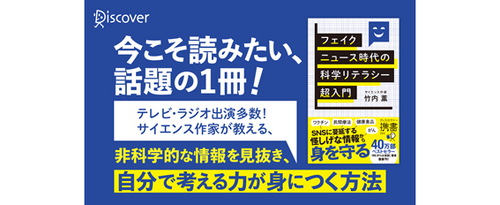「フェイクニュースに騙されるのは知性が足りないから」は大間違い…"大学の先生でも引っかかる"心理学的理由
2025年3月28日(金)8時15分 プレジデント社
※写真はイメージです - 写真=iStock.com/byryo
※本稿は、栗山直子『世界は認知バイアスが動かしている』(SBクリエイティブ)の一部を再編集したものです。
■人間には2つの思考経路がある
外部の要因など関係なく、そもそも人間の頭の中に存在する「考え方のクセ」。これが備わっていることで良いこともあれば、バイアスを引き起こしてしまうこともあります。みなさんの頭の中にはどんな考え方のクセがあるのか。知った上で、良い影響は活かし、悪い影響はうまく適応していきましょう。
写真=iStock.com/byryo
※写真はイメージです - 写真=iStock.com/byryo
まず、私たちの思考のクセの根っこにあるものが何かについてお伝えします。人間には2つの思考経路があります。ひとつが論理的に熟考し、判断する経路。もうひとつが直感的、感情的に判断する経路です。
ここでは、そもそもなぜ2つの思考経路があるのか、必要だったのかを一緒に考えます。また、直感的、感情的に判断する経路が認知バイアスを生むのですが、どのようなバイアスがあるのかをまとめ、それに関連する認知バイアスも紹介します。
なぜ、私たちは状況によって、誤った判断をしてしまうのでしょうか。問題の提示のされ方、表現の方法でなぜ判断を変えるのでしょうか。そして、ときに経験則に頼ってとても合理的とはいえない振る舞いをしてしまうのでしょうか。
■直感に従うと判断を誤りがちな理由
ダニエル・カーネマンがノーベル経済学賞を受賞した後の2011年に出版した世界的ベストセラー『ファスト&スロー』(“THINKING, FAST AND SLOW”)では、人には2つの思考経路が備わっているからだと説明しています。これを二重過程理論と呼びます。
ひとつは「システム1」と呼ばれる直感的、感情的な思考で、もうひとつが「システム2」と呼ばれる論理的な思考です。システム1はすぐに答えを出してしまう「速い思考」、システム2は答えをゆっくり出す「遅い思考」と捉えてもいいでしょう。
私たちは普通、システム1の思考モードで周りの状況を理解することが多いです。システム1が生存に不可欠なのは間違いありません。道を歩いていて自動車にひかれないように道路を渡れるのもそのおかげです。道路を渡るたびに、自分の置かれている状況を論理的に時間をかけて判断して行動していたら、逆に事故に遭いかねません。
私たちは常に情報や時間が限られる中で生きていて、瞬時の判断を迫られているのでシステム1に依存せざるを得ないともいえます。そのため意思決定や問題解決にシステム1を使う傾向があるのです。
ただ、そこにはいくつものクセ(認知バイアス)が潜んでおり、非合理的な行動を引き起こす可能性が高いとカーネマンは説きました。つまり、システム1は一般的にはバイアスの発生源になる可能性があり、ミスにつながる意思決定を招きかねないのです。直感に従うと、往々にして判断を誤りがちなのです。
■「理性的な判断」は「知能のスコア」と強くは相関していない
「私はそんな浅はかな判断はしない」と思われている人もいるかもしれません。確かに、人間は賢さにバラつきがあります。賢さ=認知能力に差があるのは事実です。誰もが認知バイアスの罠にはまるとは言い切れないという意見もわかります。
実際、認知能力と認知バイアスの関係を調べた人たちがいます。キース・E・スタノヴィッチとリチャード・ウェストは認知能力が高ければ、認知バイアスは起きないのではないかという仮説を立てました。
具体的には認知能力が高い人ほど合理的に考えられるのでシステム1に依存せず、システム2を働かせ、認知能力の低い人ほどシステム1に陥って、認知バイアスに左右されるのではないかと考えました。個人の認知の差が合理的判断に与える影響について関心を持ち、認知能力の違いが、物事の思考や推論、意思決定に与える影響を、実験をして明らかにしています。
その結果、認知バイアスは認知能力と負の相関関係があって、認知能力が高い人ほどバイアスを回避できる傾向が一定程度は見られました。賢ければ認知バイアスに引っかかりにくい傾向があるにはあったのです。ただ、他の実験では高い知能を持つ人々でも、しばしば直感的に考えてしまい、理性的な判断が知能のスコアと強くは相関していないことも示されています。
■陰謀論やフェイクニュースに引っかかる理由
たとえば、SNSの普及以降、世の中にはいろいろな陰謀論がはびこるような状況になっています。陰謀論とまで呼べなくても、政治や科学に関するフェイクニュースが毎日のように拡散されています。
写真=iStock.com/ViewApart
※写真はイメージです - 写真=iStock.com/ViewApart
みなさんの中には自分には無縁と思われている人もいるでしょう。「陰謀論やフェイクニュースに引っかかるのは、思慮に欠け、政治的に偏った人であり、教育や知性の問題」と感じているかもしれませんが、これは全くの誤りです。
陰謀論やフェイクニュースは確証バイアスのひとつのあらわれです。人は自分の意見の裏づけになる情報は無批判に受け入れますが、持論と対立する情報に対しては無視しようとするのが確証バイアスです。推論のミスを引き起こす原因のひとつです。
ソーシャルメディアのユーザーは、自分と興味・関心が似通った人の投稿をよく読みます。それらは自分の意見と一致しやすいので、自分の意見が肯定的に強化されます。判断を誤っていると誤りが増幅されてしまう可能性があるのです。自分の信念に合致するようなエビデンスだけを探し、評価し、仮説を検証するわけですから修正の術がありません。
スタノヴィッチなどの研究ではこのバイアスは知性とはほぼ無関係であることが示されています。ですから、大学の先生など知識階級の人がSNSで荒唐無稽なことを言い出してもそれはそれほどおかしな話ではないのです。
■なぜクレーンゲームはやめられないのか
他にもシステム1に陥って冷静な判断ができない例を紹介しましょう。
私たちは将来の行動を考えるときに、回収不能な過去のコストにこだわり過ぎて誤った選択をしてしまうことがあります。たとえば、誰もが、面白くない映画でもチケット代がもったいないから最後まで見た経験が一度はあるのではないでしょうか。
栗山直子『世界は認知バイアスが動かしている』(SBクリエイティブ)
見始めて、「これ、時間の無駄だな」と思っても、チケット代を払っているので、最後まで見てしまう。チケット代は映画館のシステム上、どう頑張っても戻ってきません。ですから、つまらないと判断した時点で映画館から退出した方が時間は無駄にならず、合理的な判断といえます。
人によっては、クレーンゲームを何回やっても景品が取れないのにやめられなかった経験もあるかもしれません。「もう1000円も使っているし、ここまでやったら何かを取るまでやめられない」と後に引けなくなって、さらに1000円以上使ってしまう。クレーンゲームも、今まで投資したお金は戻ってこないわけですから、何度かやって取れない時点で諦めた方が時間もお金も無駄にならず合理的です。
■「損切りしてやめる判断」ができずにズルズルと…
つまらない映画のチケット代や景品も取れずにクレーンゲームに投じたお金のように、支出されて回収不可能なコストをサンクコスト(埋没コスト)と呼びます。競馬や競輪などギャンブルで外し続けてもやめられず、予想を外すほど熱くなり、財布が空っぽになるまで続けてしまうのもサンクコストが膨らんでしまっている状況です。
このコストに基づいて意思決定すると経済的合理性に欠ける傾向にあります。すでにその時点では回収不可能なわけですから、こだわってもさらに損をする可能性だけが高まります。システム2を使えば、「今やめることで損失を最小に抑えられる」とわかるはずです。
回収不可能なものに関しては諦めて損切りする判断が合理的です。ただ、人間は投資した分を取り返したいという気持ちが強く働くため、損切りしてやめる決断ができずにズルズルと続けてしまいます。
----------
栗山 直子(くりやま・なおこ)
東京科学大学リベラルアーツ研究教育院/環境・社会理工学院 講師
専門は認知心理学、教育心理学、教育工学。青山学院大学文学部教育学科卒業、東京工業大学 大学院社会理工学研究科 人間行動システム専攻修士課程、同大学大学院同研究科 博士課程修了。博士(学術)。日本学術振興会特別研究員PDを経て、東京工業大学 大学院社会理工学研究科人間行動システム専攻助手。その後、同大学同研究科助教、改組により同大学リベラルアーツ研究教育院/環境・社会理工学院 助教、講師を経て、現職。2016年文部大臣表彰科学技術賞(理解増進部門)受賞。認知バイアスも含む人間の柔軟な思考、主に推論・問題解決に関心があり人の思考に関係する研究に従事。現在は論理的思考を育成するための研究を進めている。日本心理学会、認知科学会等会員。日本認知科学会をはじめ、海外のCognitive Science関連の学会で発表を多数行っている。
----------
(東京科学大学リベラルアーツ研究教育院/環境・社会理工学院 講師 栗山 直子)