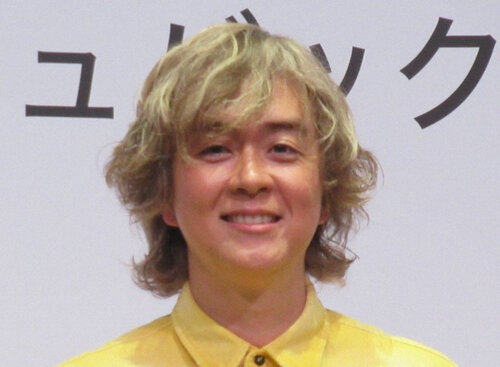一度乗ると価値観が変わる? 高級車同士の「優越感争い」を超えたテスラの「環境マウンティング」とは
2025年4月1日(火)4時0分 JBpress
SNSの普及で人々の承認欲求が肥大化する中、「他者よりも優れた自分を演出したい」という欲望が、今や消費行動の大きな源泉になった。「モノ」や「コト」の枠を超え、どうすれば優越感に浸れる「マウンティングエクスペリエンス(MX)」を提供できるのか。『「マウント消費」の経済学』(勝木健太著/小学館)から内容の一部を抜粋・再編集し、実例を挙げながら「マウント消費」のメカニズムに迫る。
電気自動車のパイオニアであるテスラと、米国での大ヒットを受けて日本にも上陸した缶入りの水「リキッド・デス」は、「自動車」と「水」をどう再定義し、MXを提供しているのか?
Tesla:従来の高級車の概念を覆し、「地球に優しく、革進的」という新たな体験を提供する電気自動車(EV)のパイオニア
『「マウント消費」の経済学』(小学館)電気自動車メーカーのテスラは、もはや地球環境を守りながら未来を切り拓くライフスタイルを提案する最先端のブランドへと進化を遂げている。
その背後には、世界的な起業家であり資産家でもあるイーロン・マスクの揺るぎないビジョンが息づいている。彼の卓越したリーダーシップのもと、自動車メーカーとして世界最大規模の時価総額を誇り、革新の象徴として不動の地位を確立している。
従来の高級車が提供してきた価値は、利便性や経済的余裕の象徴にとどまっていた。しかし、テスラが提示するのは、それらの常識を根底から覆(くつがえ)す新たな価値観である。
「環境に優しく、革新を追求する自分」というアイデンティティを所有者に対して付与することで、新たな次元のMXを提供している。同じ高級車でありながら、ベンツやフェラーリが象徴する伝統的なステータスとは一線を画した環境意識と先進性を核に据え、所有者に対してより深いレベルの持続的な満足感をもたらしているのだ。
テスラのオーナーになることは、車の所有以上の意味を持つ選択である。それは、「環境に配慮し、未来を自ら選び取る自分」を体現する行為であり、環境問題への貢献と最先端テクノロジーの享受を両立させる、他にはない体験である。この選択は、経済的余裕の証明にとどまらず、「未来を共に創造する一員である」という責任感と革新への参加意識を誇る行為でもある。
「一度乗ってみたら価値観が変わるよ」と多くのオーナーが口を揃えるのは、この体験が従来の車では得られない満足感と深い感銘をもたらし、「未来への第一歩」を実感させるからに他ならない。
さらに、「マウント競争」からの解放を象徴する存在としても際立っている。アップルウォッチが従来の腕時計が象徴していた「ステータス競争」を超越したように、高級車同士が繰り広げる「優越性の争い」を次元の異なる価値観で凌駕している。「環境を守りながら革新的な選択をする」という理念を体現することで、他の高級車では得られない独自の満足感を提供しているのだ。
テスラが提供するのは、「未来世代に対する責任」を果たしながら、「未来を所有し、育むライフスタイル」を具現化するという新たな価値観そのものである。環境配慮と革新を核に据えたこの提案は、「環境マウンティング」という価値基準を打ち立て、「所有」という概念そのものを根本から再定義している。
進化を続けるその姿勢と先進的な価値提案は、既存の枠組みに収まらず、他を圧倒する存在感を放っている。今後も、環境への配慮と革新を見事に融合させ、新しい所有体験を提供することで、未来のライフスタイルを牽引する象徴的なブランドとして、さらなる地位を確立していくだろう。
Liquid Death:普通の“水”を“クールな缶”で包み込み、「ダサくない水」として再定義。売上403億円を達成した米国発のスタートアップ
リキッド・デスは、「水」という極めてシンプルな商品に大胆なブランド戦略を持ち込み、飲料業界に新潮流を生み出したスタートアップである。その成功の原動力は、「水をいかにクールに見せるか」という挑戦を果敢に追求した点にある。
従来の「清潔さ」や「健康」といった水のイメージを打ち破り、誰もが当たり前に消費する「水」を個性や自己表現を映し出す象徴へと進化させたのだ。「水そのもの」に特別な価値と文化的意義を付与することで、飲料という次元を超越した存在として市場に君臨しているのである。
まず目を引くのは、挑発的で個性溢れるパッケージデザインだ。大きく描かれた不気味なスカルのロゴが印象的なアルミ缶は、「これが本当に水なのか?」と思わず二度見してしまう。
その強烈なビジュアルインパクトは「水は地味でつまらない」という従来のイメージを鮮やかに打ち破り、「クールでスタイリッシュな水」という新しいアイデンティティを創出した。このデザインがもたらす新鮮さと独自性は、リキッド・デスをバーやクラブといったナイトライフのシーンでも選ばれるファッショナブルなライフスタイルアイテムへと押し上げている。
しかし、その真価は挑発的なビジュアルだけにとどまらない。同ブランドのコミュニケーション戦略は、他に類を見ない独自性を放っている。SNSを駆使した広告キャンペーンでは、ユーモアとブラックジョークを大胆に織り交ぜることで、「清潔で健康的」という従来の水のイメージを根底から覆している。
たとえば、ハードロックの世界観を前面に押し出したプロモーション動画では、「水でありながら、ロックバンドのツアーTシャツのような存在感」をユーモラスに演出。この予想外のギャップがターゲット層の心を捉え、「リキッド・デスを選ぶ自分は他者とは異なるセンスを持っている」という特別感を消費者に対して提供している。
その結果、飲料というより自己表現とアイデンティティを象徴する文化的アイコンへと進化を遂げつつある。
さらに、リキッド・デスは環境意識を随所に取り入れることで、ブランドの魅力をより一層際立たせている。プラスチックボトルではなく、リサイクル可能なアルミ缶を採用することで、「地球に優しい選択」を消費者に対して提案している。この取り組みによって、リキッド・デスを飲むという行為そのものが「環境に配慮した意識的な選択をする自分」を体現する行動へと変容している。
環境問題への積極的な姿勢は、特に若い世代の消費者層から深い共感を集め、ブランドの差別化をさらに際立たせると同時に、その魅力を格段に高めている。ただの飲料ではなく、持続可能な未来を目指すライフスタイルを象徴する存在として、唯一無二の地位を築いているのだ。
こうした大胆かつ巧妙なブランディング戦略によって、リキッド・デスは2019年にスタートしてからわずか4年で売上403億円に達する企業へと急成長を遂げた。しかし、同社が提供しているのは単なる飲料ではない。その本質は「他者とは異なる自分」を表現するための選択肢としての価値にある。
「ダサくない水」という斬新なコンセプトを提示し、消費者に商品としての価値以上の意味を提供している。その結果、同業他社との競争とは無縁の独自のポジションを確立し、従来の飲料市場に新たな基準を打ち立てることに成功したのである。
シンプルな商品にそれ以上の価値を付加するという挑戦に対して見事な解答を提示している。水という普遍的な商品を「他者と異なる自分」を演出するためのツールへと昇華させ、消費行動そのものを特別な体験へと変貌させたのだ。この巧妙かつ洗練された戦略こそが、飲料業界でその存在感を際立たせている最大の理由であり、同時に同ブランドが創出したMXの象徴的な事例でもある。
リキッド・デスは、シンプルな商品に物語性を宿らせ、これまでにない市場価値を生み出すブランドとして高く評価されている。その存在は飲料業界にとどまらず、他業界においても「商品に意味を与える」マーケティングの未来像を提示するものだ。
この成功は、どんなに日常的な商品であっても、斬新な視点と物語を取り入れることで、独自のポジションを確立できることを力強く証明している。リキッド・デスの事例は、商品の枠を超えて、文化と価値を創出する可能性を明確に示しているのである。
<連載ラインアップ>
■第1回 なぜロレックスでなくアップルウォッチを選び、インスタで“匂わせる”のか?「マウント回避」と「特別感」の正体
■第2回一度乗ると価値観が変わる? 高級車同士の「優越感争い」を超えたテスラの「環境マウンティング」とは(本稿)
■第3回「俺は自由だ」ワルの愛車ハーレーダビッドソンは、ユーザーの自己肯定感をどう高め、新旧ファンを虜にするのか(4月9日公開)
■第4回他の同窓会とは一味違う「慶應三田会」 圧倒的な結束力と社会に張り巡らされたネットワークが持つ影響力とは?(4月16日公開)
※公開予定日は変更になる可能性がございます。この機会にフォロー機能をご利用ください。
<著者フォロー機能のご案内>
●無料会員に登録すれば、本記事の下部にある著者プロフィール欄から著者をフォローできます。
●フォローした著者の記事は、マイページから簡単に確認できるようになります。
●会員登録(無料)はこちらから
筆者:勝木 健太