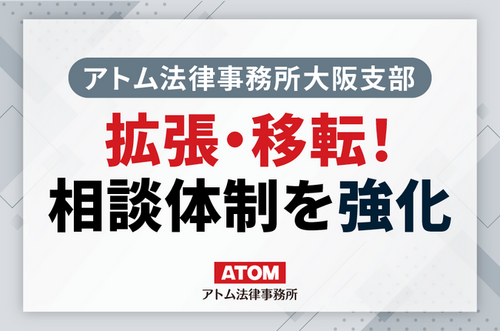多様化する消費のカタチ、「モノ」から「トキ・コト」へ…「持たない」豊かさ選択する人も
2025年4月30日(水)15時0分 読売新聞
モノを極力減らして暮らすミニマリストの男性(3月14日、福岡市中央区で)=中山浩次撮影
[戦後80年 昭和百年]経済<中>
日本経済は戦前から巨大なアメリカと向き合い、影響を受け続けてきた。米国の圧力に翻弄されるのは、トランプ政権が初めてではない。戦後はそれを何度も乗り越え、共栄の道を探ってきた。歴史を顧みつつ、日米貿易そして消費や雇用の現状と未来を問う。
福岡市内のワンルームマンション。広さ約30平方メートルの部屋には、ソファベッド、机、イス、洗濯機など、数えるほどしか家具がない。殺風景にも見えるが、部屋の主であるミニマリストの男性(30)は「モノがないと心身ともに自由になれる」と笑顔で語る。
ミニマリストとは、最低限しかモノを持たない暮らしを目指す人々のことだ。男性は1年を8枚の服で過ごし、部屋に布団はなく、ソファベッドに寝袋を敷いて眠る。部屋にあるモノは日用品も含め、段ボール1箱に入る程度という。
10年ほど前、一人暮らしを始めた際、初期費用がかかりすぎることに悩み、ミニマリストになった。冷蔵庫がないので食材は買う度に使い切り、洗濯はコインランドリーを頼った。むしろ狭い部屋を広々と使え、節約にもなる。当時は家賃を含め1か月約6万円で生活ができた。
今はミニマリストの生活を伝える動画投稿や執筆活動で生計を立てる。「生活費が安いと無理に働く必要もない。旅行や読書など好きなことに時間を使え、豊かに暮らせる」という。
クルマ離れ、ファッション離れ、酒離れ——。若者が消費をしなくなったとの指摘は、統計にも反映されている。総務省の全国家計構造調査によると、単身勤労者世帯(30歳未満)の「被服及び履物」への支出額は、バブル期の1989年には男性が月平均1万1445円、女性は2万1398円だった。だが2019年は男性が5106円、女性は9926円と、いずれも半分以下に落ち込んだ。
背景には、流行のモノを皆が一斉に買うという消費スタイルの変化がある。バブル期には高級車や高級ブランドを持つことがステータスとされ、モノを所有することが満足感にもつながっていた。
だがバブル崩壊をきっかけに消費が低迷すると、企業は高級な流行品よりも低価格商品を前面に出し、生き残りを図った。安価でも一定の品質を持つ商品が支持されたカジュアル衣料品店「ユニクロ」が代表格だ。
さらにスマートフォンなどデジタル機器の普及は、モノを所有しない消費を生み出した。音楽はCDからサブスクリプション(定額制)へ移り、偽造や複製が難しい「NFT」(非代替性トークン)アートなど、芸術品ですらデジタルで所有される。
個人がSNSで情報を簡単に発信できるようになり、消費者の関心は多様化した。コロナ禍を経て、体験を重視する「コト消費」や、その時その場でしか味わえない盛り上がりを楽しむ「トキ消費」も浸透した。食品ロスや大量廃棄へのアンチテーゼとして、人や環境に配慮した「エシカル消費」も注目される。
慶応大の白井美由里教授(消費者行動論)は、「SNSで消費のロールモデルが増えた。人々は自身の考えや価値観に合う商品・サービスを選んで消費している」と話す。