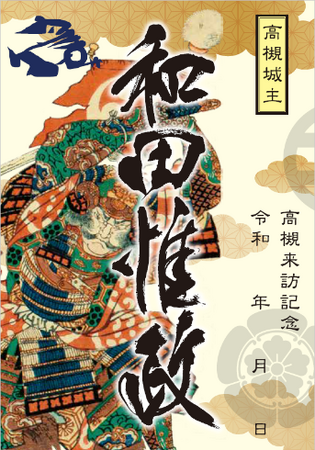武力でも知力でも財力でもない…応仁の乱後の乱世で活躍し非業の最期を遂げた武将が頼った"不思議な力"
2025年5月18日(日)9時15分 プレジデント社
※写真はイメージです - 写真=iStock.com/pictosmith
※本稿は、古野貢『オカルト武将・細川政元 室町を戦国に変えた「ポスト応仁の乱の覇者」』(朝日新書)の一部を再編集したものです。
■政元の魔法へのあこがれ
細川政元(ほそかわまさもと)には、男色(同性愛)に関係するエピソードが残っています。というのも、明応の政変後から、政元が内衆を殺す事件が起きてくるのですが、それを書き残した史料に「男色が云々」と批判的に書かれているのです。
もう少しあと、本格的な戦国時代に入ってきますと男色行為に対する見方も変わり、むしろ良いものであるというような印象が持たれるようになってきます。しかし、政元の時代では違っていたようです。
政元をめぐっては、史料に「飯綱の法など魔法を使うにあたっては女性と関わってはいけない、そうでないと魔法的な力がなくなってしまう」「だから四十歳までは妻帯しない」といった旨の記述が残っています。これらが政元の言動を強く規定している、とも考えられています。
彼が魔法などのオカルト的なものにハマっていった背景として、まず「空を飛びたい」などの具体的な願望は当然あるのでしょうが、加えて「人智を超えたものを大事にしたい、自分の基盤にしたい」という思いが根本的な行動原理としてあったのではないかと思われます。
写真=iStock.com/pictosmith
※写真はイメージです - 写真=iStock.com/pictosmith
■信念を貫くための呪術や修行
もう少し時代が下った戦国時代においても、合戦の前に占いをして勝利の可能性を高めようとしたり、上杉謙信が毘沙門(びしゃもん)天を信仰して勝利を神の加護によるものとしたりといった具合に、自分なりのよりどころを持ったものです。
政元の修験道への傾倒はその先駆けと言えるでしょう。しかし政元のそれは当時一般的だった仏教とか神道ではないものでしたから、日常生活の中においては「おかしなもの」であるという印象を与えたはずです。
しかし、政元からすれば筋の通ったことでした。
将軍との対立や自身が構想した政権を確立するという目標を設定した時、世間からどう見られようとも自分の信じるものを明確にしなければいけない、政元はそう考えたのではないでしょうか。
そこであらためて、政元が何を求めて呪術や天狗修行などのオカルトに辿り着いたのか、そしてその結果がどうなったのかを見てみましょう。
■悩んだ先のオカルトへの帰結
政元は幼くして家督を譲られ、その周囲は大人ばかりで細川氏の維持や幕政、戦争など大きな課題について「ああしろ、こうしろ」と指示(指導)されてきました。
また、元服した途端に拉致されてしまうという事件が起きて政治的な駆け引きの道具にされる経験もしています。
その中で聡明であった政元は、「どうして自分は細川氏の当主という立場であるのに、自分の意思で動くことができないのか。意思が立場に追いついていないのはなぜなのか」と考えたはずです。
そうなりますと、「自分の思いや考えていることを実現したいなら、このままでは駄目だ」と考えるでしょう。では、どんな手段を取り得るのか。正攻法としては年齢を重ねて出世し、より大きな力を持つことがあるわけですが、それとは別の武器が必要なのではないかと考え、その帰結として魔法を身につけるなどのオカルト的な方面へ向かったと考えられます。
■不気味さで支配した戦乱後の世情
実際のところオカルトへの傾倒はある程度目的意識があって演じていたのか、本物だったのかはよくわかりません。
ともあれ、彼が奇矯に見える行動を表に出していくのは青年期から壮年期にかけてのことで、その時期の前半には周囲から「こいつは不気味な力を身に付けているから、とりあえず言うことを聞いておいたほうがよさそうだ」と思われるような対応をしていたと考えられます。
また、ちょうどその時期は応仁の乱が終わった後の、世情が落ち着いていなかった頃です。政元がオカルト的なことをもとに行動したり発言したりして、周囲に「こいつは得体の知れない力を持っていて不気味だ」と思わせることで、むしろ世の中を安定させることに対してある程度効果を発揮し、一定の落ち着きを取り戻させた部分はあるのかもしれません。
変わった人間が変わった方法で力を振るうということが必ずしもハマったとは思いませんが、一定の機能を果たした、とは言えるのでしょう。
細川政元像(画像=京都国立博物館:龍安寺/CC-PD-Mark/Wikimedia Commons)
■「空を飛んで越後に行きます」が通用するか
十六世紀になり、政元の考える構想がそれなりに機能するようになってきたことで、世の中もある種の落ち着きをみせるようになります。落ち着いた状態で政権運営をする上では、政元が持っている「おかしさ」がマイナス方向へ働くことになってしまいます。
これは現代における政治家などでもそうですが、動乱や混乱時代に活躍できる人物と、平穏な時代に機能する人物は持ち味や適性が大きく違うわけです。自身の性質と世情が合致していればいいのですが、逆になってしまうとその人物にとっても世間にとっても大変不幸なことになります。
政元はやはり、雑然と混乱しているいろいろな物事を、不思議さ加減や変わっている性質から来るある種の腕力で強引に引っ張っていくというリーダーシップ的なものは持っていたと考えられます。しかし、フェイズが変わってしまうと、途端に周囲との関係が危うくなってしまいます。
状況が混乱している時には、政元の「空を飛んで越後に行きます」のような発言は、その能力に頼る形で、「おお、それができるのであれば早いほうがいいよね」「人知を超えた力を持ってる人はいいね」といった反応が平時よりも返ってきやすい状況でした。
しかし、情勢が落ち着き、安定した政治が求められるようなフェイズでは、政元の奇矯な行動に対して批判的な反応が集まり始めます。だからといって、オカルト的な考え方はすでに政元にとっては拠って立つところになってしまっているので、やめることはできないのです。
■オカルトの限界と革新性
結果、周囲には「もっとちゃんとしてください」と言われ、「烏帽子ぎらい」や「人に対して大声で呪詛を唱える」などの性質を抑えるように求められ、最後にはそれらを理由にして殺されてしまうのです。
古野貢『オカルト武将・細川政元 室町を戦国に変えた「ポスト応仁の乱の覇者」』(朝日新書)
この背景には後継者争いがあるわけですが、それだけでなく「政元のような時代にそぐわない人間が細川氏の(あるいは幕府の)代表であっては困る」と世間が要請しての暗殺なのです。
その意味で、生涯の前半ではオカルト的なものに拠って立ち、ポジティブな効果を発揮していったけれど、ネガティブに評価される面が生涯の後半に強く出てしまったため、最終的に後世で評価されないことになってしまったのだと考えられます。
しかし、彼が目指していた方向性は、時代の先取りとまでは言えないかもしれませんが、評価するべき部分は多々あったと思います。政元の時代は、これまであった常識やルール、価値観などがすでに制度疲労を起こしており、変えなければいけない時期に来ていました。政元はその危機感から、国を作り変えなければいけないという行動原理によって動いていたと考えられます。
■「変人」細川政元の存在意義
現代でもそうなのですが、何か新しいことをしようとしたら必ず反対されるものです。
しかも当時は現代よりもっと制度に対する規制が強かったでしょうから、そこでひとりだけで何かやったとしても、「変人だ」で終わってしまう可能性も高かったでしょう。
実際、政元はそれで命を落とすわけです。その意味では非常に革新的というか、時代と比べてちょっと早く生まれてしまった人間だったのではないか、と思います。
オカルト的な言動に周囲は振り回されましたが、彼のような少々変人ではあるけれど、ある種の筋を通して世の中を変えることにパワーを注ぎ込む人がいたからこそ、古い室町時代から新しい戦国時代という時代の扉を開けられたのだろうと思うのです。細川政元の存在は「時代を変え、動かす」という意味において非常に大きな役割を担っていたと言っていいでしょう。
写真=iStock.com/pictosmith
※写真はイメージです - 写真=iStock.com/pictosmith
----------
古野 貢(ふるの・みつぎ)
武庫川女子大学文学部歴史文化学科教授
1968年、岡山県生まれ。大阪市立大学大学院文学研究科後期博士課程単位取得退学。博士(文学)。武庫川女子大学文学部歴史文化学科教授。専門は日本中世史。14〜16世紀の政治史、権力論、室町幕府、守護、国人など。著書に『中世後期細川氏の権力構造』(吉川弘文館)、『戦国・織豊期の西国社会』(日本史史料研究会)などがある。
----------
(武庫川女子大学文学部歴史文化学科教授 古野 貢)