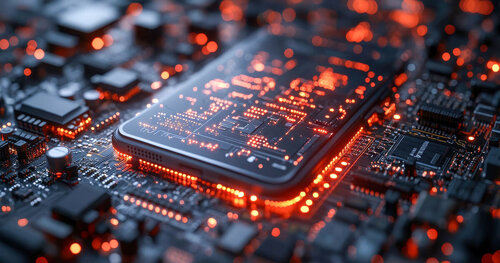〈空前の血税5兆円の行方は?〉半導体の国策プロジェクト「ラピダス」は失敗の歴史に学んでいるか?「使うのは国の金。成果が出なくても責任なし」の過去も
2025年5月21日(水)7時0分 文春オンライン
経済記者生活37年の大西康之氏による連載「 裏読み業界地図 」第4回。今回は北海道千歳市に設立された半導体メーカー「ラピダス」の抱えたリスクについて解説します。
◆◆◆
18兆4000億円の経済効果が期待できる?
北海道千歳市の地価が高騰している。国土交通省が3月に発表した公示地価ではJR千歳駅周辺が上昇率で全国の1位から3位を独占した。原因は2022年に設立された国策半導体メーカー、ラピダスの進出だ。世界最先端となる回路線幅2nm(ナノメートル)のロジック半導体の量産を目的とする同社には国が2024年度までに9200億円を拠出しており、3月31日には追加でさらに最大8025億円を支援すると発表した。
千歳市という小さな池に「2兆円の鯨」が飛び込み、水が溢れている。工事関連の出張者で市内のホテルは満杯。繁華街にはガールズバーが雨後の筍の如くオープン。地元不動産会社の社長は「賑わうのはありがたいが、昔から住んでいる人たちは固定資産税が上がって困っている」と困惑気味だ。

狂宴はこれで終わらない。
「2036年頃には18兆4000億円の経済効果が期待できる」
ラピダスの設立者の一人でもある東哲郎会長(半導体製造装置メーカー、東京エレクトロンの元社長)は2024年7月、道内の講演でこう語ったが、2027年を予定している量産開始までには総額5兆円の投資が必要とされる。
ラピダスが自己責任で資金を集めたのなら5兆円投資しようが10兆円投資しようが構わない。しかしラピダスに対する民間の出資は設立時で73億円しかない。
「使うのは国の金で、成果が出なくても責任は負わされない」
5兆円を分母にすると民間出資比率は0.15%。残りの99.85%は税金である。ラピダスの小池淳義社長(日立製作所出身で元ルネサステクノロジの技師長)は2025年3月「民間から1000億円の出資を受ける目処が立ちつつある」と語っているが、それでも民間比率は2%。ほぼ完全な「国策」である。
産業界では国策プロジェクトを「国プロ」と呼ぶ。半導体の「国プロ」は失敗の歴史である。
日本の半導体産業が国際競争力を失った2000年代、政府は数々の「国プロ」を打ち出し、かつて自動車と並ぶ外貨の稼ぎ頭だった半導体産業にテコ入れしようと試みた。
2001年に始まった「あすか」プロジェクトは、当時の最先端である回路線幅100nm〜70nmの微細化技術を使ったSoC(システム・オン・チップ)半導体の製造プロセス技術の開発に取り組んだ。NEC、東芝、日立製作所、三菱電機、富士通などの半導体大手12社から250名の技術者を集め、840億円の予算をつけた。
さらに進んだ70nm〜50nmの微細化技術を使ったSoC半導体製造プロセスに挑んだのが「MIRAI」プロジェクト。これには半導体大手24社とともに全国20の大学が加わった。集められた技術者は150名、200億円の予算が投じられた。
「あすか」と「MIRAI」が開発した製造プロセスで実際にSoC半導体を作るための製造システム構築を目指したのが「HALCA」プロジェクト。製造装置メーカーなど14社から35名の技術者が集められ、80億円の予算がついた。
半導体産業に対する国の支援は2001年から2007年までで総額1270億円に及んだ。しかし投じられた巨額の税金によって、日本の半導体産業が攻勢に転じることはなかった。
半導体の「国プロ」はなぜ失敗したのか。「あすか」に参加したNECの技術者はこう振り返る。
「集められた12社は日々、ビジネスの世界で熾烈な競争を繰り広げているわけですよ。エースを出せ、と経産省に言われても、競争の手は緩められないからエースは出せない。そもそも国プロなど、みんな仲良しクラブだと思っているから、本気にはなりません。国プロに送り込まれたのは、私を含め各社とも二番手、三番手の人材です。いろんな会社の人と働いて見聞を広めてきなさい、というレベルです」
使うのは国の金で、成果が出なくても責任は負わされない。技術者にとっては遠足みたいなものだ。国プロのために建屋を作るわけではなく、開発は各社の研究所で行われる。例えばNECの研究所を使う場合、NECの自前の装置と、税金で買った国プロの装置が混在する。
「国プロで買った装置には『あすか』とか『MIRAI』とかのシールが貼ってあるんですが、『減るもんじゃないし』とシール付きの装置を自社の研究でも使っていました」
企業の生き死にをかけた研究と、税金を使った「催促なし」の研究では、当事者意識が全く違ったのだ。
「このままでは日本の半導体産業が滅んでしまう」と危機感を持った東会長が経産省に掛け合って予算を獲得させたラピダスの生い立ちは、「あすか」や「MIRAI」と同じである。ラピダスが同じ道を辿れば、今度は5兆円という空前の規模の血税が無駄になる。
※本記事の全文(約8500字)は「文藝春秋」2025年6月号と、月刊文藝春秋のウェブメディア「文藝春秋PLUS」に掲載されています( 大西康之「NECと半導体 『電電ファミリー』失敗の歴史 」)。
■全文では下記の内容をお読みいただけます。
・半導体メーカー凋落の原因
・構造転換についていけなかった
・TSMCの勃興
・NECの西垣・関本紛争
・エルピーダとルネサスの苦戦
・目まぐるしい王朝交代
(大西 康之/文藝春秋 2025年6月号)
関連記事(外部サイト)
- 【さらにに詳しく読む】〈企業の裏側を徹底解説〉2025年版文藝春秋「業界地図」を一挙公開 製鉄、自動車、電機、半導体…【投資、就活、ビジネスに】
- 「結婚なら相手が怒って出ていくレベル」日産・ホンダ経営統合が〈誰かにやらされている〉と感じたワケ《記者歴37年ジャーナリストが裏読み》
- USスチールが、アメリカ人にとって「GMよりIBMよりも遥かに“特別な会社”」である理由とは?〈日鉄の買収計画はどうなる〉
- 有り金が底をつき、オフィスの水まで有料に…窮地のイーロン・マスクがテスラ社員に送った“一本のメール”「人類の未来のために…」
- 「チャットGPTを日本語にあわせたモデルにしたい」アルトマンCEOが日本を狙う“本当の理由”