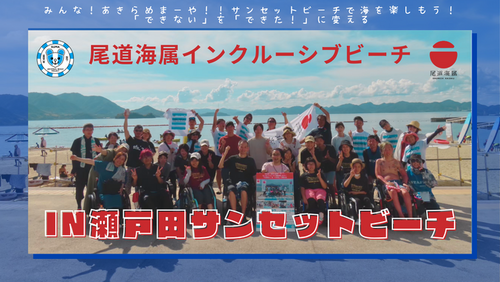なぜ一流は100ページ分の資料をたった1枚に凝縮できるのか…トヨタの残業年間400時間をゼロにした習慣
2025年5月26日(月)8時15分 プレジデント社
※写真はイメージです - 写真=iStock.com/Perawit Boonchu
※本稿は、佐藤美和『世界のハイパフォーマーを30年間見てきてわかった一流が大切にしている仕事の基本』(かんき出版)の一部を再編集したものです。
■結論を1枚に凝縮した資料
「この資料、一体何キロあるんだろう?」
図表、根拠となるデータ、使用したデータベース、分析手法の説明、結論に至るまでの検討の過程を詳細に記した分厚い資料は、迫力満点です。資料を受け取った人は、そのインパクトに感動してくれるし、資料を作ったほうも、努力のすべてを披露できたという達成感を得られます。私も駆け出しのコンサルタントだった頃は、クライアントとの定例プロジェクトミーティングには、毎回分厚い資料を提出していました。
ところが、コンサルタントとしての経験を積み重ねるうちに、気づいたことがあります。それは、一流のコンサルタントたちは膨大な資料の内容をA4・1枚にまとめられるということです。
「ミリオンダラーピッチ(Million Dollar Pitch)」というコンサルティング用語があります。お客さまから100万ドル(約1億5000万円)のフィーをいただける1枚の資料を作れるのが優れたコンサルタントだということです。
「資料1枚で100万ドルってどれだけ美味しい仕事なんだ?」と思う人がいるかもしれませんので、誤解のないように言っておくと、資料1枚というのは、手を抜いて構わないということではありません。資料作りなんかに時間をかけるな、ということでもありません。結論を端的に1枚にまとめられるまで、咀嚼(そしゃく)してお客さまに伝えるのが一流のコンサルタントだということです。
写真=iStock.com/Perawit Boonchu
※写真はイメージです - 写真=iStock.com/Perawit Boonchu
コンサルタントは、ひとつの結論を出すために非常に多くの時間をかけて分析や検討を行っています。だからそれをそのまま資料にすると、軽く数100ページの分量になります。とはいえ、その分量のものをそのままお客さまに渡すのは怠慢と言わざるを得ません。
■資料を紙1枚にまとめると年400時間の残業がゼロに
お客さまは結果に対してお金を支払ってくださるのだということを忘れるな、というのがミリオンダラーピッチが意味するところです。分厚い資料を読んでもらうのは、相当な負担になります。読み手の集中力が続かなくて重要なポイントを見逃す可能性もあるし、最後まで読んでもらえないかもしれません。それを考えると、A4・1枚にまとめられた資料は、読み手にとって大変価値のあるものです。
トヨタでは、業務上の書類はすべてA3またはA4サイズの紙1枚に収めるという習慣が企業全体の文化として根づいているというのは、有名な話です。
報告書、企画書、会議の資料や議事録、打ち合わせ資料、プレゼン資料、スケジュール確認用のリスト、考課面談の記録……。あらゆる種類の書類、そしてどんなに複雑な内容の書類でも、トヨタは原則「紙1枚」です。紙1枚にまとめるようになってから、年400時間を超えていた残業時間は、ほぼゼロになったと言います。
紙1枚にするだけで、どうしてそんな効果が出るのでしょうか?
1枚の紙にまとめるのは、かなり大変なことです。必ず伝えたいこと(幹)だけを残して、周辺情報(枝葉)は切り捨ててしまわなければなりません。だから、1枚に収めるための作業をすることで、内容に対する理解は自然と深まります。お陰でどんな質問をされても即答できるレベルになります。
資料を読む人は、厳選された情報だけが書かれている資料を見ることで、考えることに集中できます。だから、その場で結論を出せるのです。
とはいっても、いきなり資料を1枚だけにしたら、「これだけ?」と言われないか心配です。そんなときは、A4・1枚の「サマリー(要約)」を先頭に、その後ろにこれまで作っていた分厚い資料を「補足資料」として提出しましょう。
「サマリーがあるとわかりやすくていいね」と言われたら、「そうですよね!」と次回から提出はサマリー1枚だけにすることを提案してください。
■メモをとると脳が活性化する
一流はメモ魔です。会議はもちろん、上司とのちょっとした打ち合わせ、同僚との話し合いなど、どんなことでも、必ずメモをたくさんとっています。
スマホにはボイスメモがあり、TeamsやZoomなどのオンライン会議システムには録画機能があるから、メモなんて必要ないと言う人がいますが、一流がメモにこだわるのにはちゃんとした理由があるのです。
メモをするという行為は、脳を活性化させます。耳から入ってきた情報を右脳でイメージし、左脳で言語化するので、脳全体を使います。
さらに、書くことは覚えることにつながります。脳は何度も入ってくる情報を重要なものと判断し、記憶にとどめます。口頭で住所を教えてもらったときなど、無意識のうちに何度も復唱してしまうのは、この脳のメカニズムを利用して記憶しようとしているからです。聞いた内容を書いていくことは、復唱しているのと同じ効果があるのです。
それに、書くスピードは話すスピードよりも遅いので、話を漏らさず書き留めるためには、記号化や図式化をしなければなりません。記号や図式に置き換える過程で、自然と思考の整理も進みます。
画像=iStock.com/wenjin chen
※画像はイメージです - 画像=iStock.com/wenjin chen
録音や録画をすることは失礼な行為だと考える人もいます。発言の一言一句をほぼそのまま文字にしてインタビュー録を作るのであれば別ですが、通常の会議を録音や録画するのは、はじめから話を聞く気がないのだと受け取る人がいるのです。
また、録音や録画が独り歩きして、思ってもいない形で、意図しない人に話が伝わってしまうリスクを考えなければなりません。
■議事録作成は議論を構造化する奥深い仕事
普段からメモをとる習慣がないと、いきなり書こうとしてもうまくいかないので、大事な会議で録音や録画ができなければ慌てることになります。また、録音や録画があると、あとから聞き直せるという安心感から、漫然と話を聞いてしまいがちです。こんなことも考えて、一流はたとえ録音や録画をしていたとしても、必ずメモをとっています。
少し込み入った話だったり、自分では今ひとつ理解が進まなかったと感じたら、会議終了後に、メモを頼りに内容をまとめ直します。こうすると、頭の中で会議を再現できるし、ひとつひとつの発言が、どこでどうつながって結論が出たのかを確認できます。
メモを頼りに会議の内容をまとめるというのは、議事録を作成するようなものです。議事録作成は雑用だと思っている人もいますが、実は仕事を学ぶ絶好の機会です。
私が勤務していたコンサルティングファームでは、新人が最初に任される仕事は議事録作成でした。議事録を作成してみると、とても奥深い仕事だというのがわかります。会議の内容を正確に聞き取って、重要なポイントを抽出し、わかりやすくまとめるというのは、議論をちゃんと理解していなければ難しいものです。
実際、議事録作成は新人にとってはなかなか骨の折れる仕事で、提出すると先輩によって真っ赤に添削されて戻ってきます。しかし、めげずに書き続けていると、そのうちに赤文字が少なくなっていきます。それは、添削している先輩と同じレベルで議論を理解できるようになった証拠です。こうなると、会議に参加しても、他の出席者と互角に話し合うことができます。
ときどき「誰が何を言った」方式で会議の出席者の発言をそのまま書き留めている人がいます。会議の要点や決定事項をまとめた議事録よりも、国会会議録のような「発言録」のほうが、臨場感があっていいのではないかと考えるからです。しかし、国会会議録をちらっとでも見るとわかるように、発言録は書くのも読むのも時間がかかります。
試しに、生成AIに発言録を基に、議事録を作成してもらったことがあります。確かによくまとまった文書ではありますが、発言録の「要約」にすぎず、決定事項や結論までの議論のプロセスがわかるようなものではありませんでした。このことからも、議事録は会議の内容をちゃんと理解して構造化できなければ作れないことがわかります。
一流のすることは、ひとつひとつにちゃんと理由があるのです。
■紙の資料はスキャンしてシュレッダーに
「ほらほら、去年の秋くらいに一緒に行ったセミナーあったでしょ? あれは今やっているプロジェクトの参考になるんじゃない? あのときにもらった資料、どこいったかな」
何時間もかけて必死に探す人がいる一方で、「はい、これです」とお目当ての資料をものの数分で出してくれる人がいます。
一流の思考と行動を分析するとき、その方の仕事ぶりが第三者の目にどう映っているのかを知るために、上司や同僚に話を聞くことがあります。そのときに、必ず出るのは「一流は必要な資料をすぐに出してくる」というエピソードです。
一流は皆、配布資料から自分で書いたメモに至るまで、紙の資料は基本的にすべてスキャンして、その後はシュレッダーにかけてしまいます。「基本的に」というのは、法令で原本の保管が義務付けられているものもあるからです。
とはいっても、2024年1月の電子帳簿保存法の施行で、電子データで保存できる書類は増えたので、ほとんどの資料は電子媒体で保存可能になりました。
「会議の配布資料は必ず紙で」という企業はいまだにたくさんあります。事前にメール添付で電子ファイルを送信しても、それを印刷して会議の場に持参する人もいます。こんな理由で、オフィスには紙の資料があふれています。
写真=iStock.com/sekulicn
※写真はイメージです - 写真=iStock.com/sekulicn
紙の資料は、ランダムに保管していては探すのに一苦労するし、整理整頓して保管するには、穴をあける、ファイルに綴じる、インデックスをつけるといった作業が必要になります。
■一流は電子化した資料をフォルダに保存しておく
さらにファイルが増えてワークスペースに保管しきれなくなると、年に何度かは、資料をひとつひとつ見返して、保管し続けるか破棄するかを決めなければなりません。外部倉庫を利用する方法もありますが、それはそれでコストがかかるので、やはり資料を見返して、倉庫に送るものを厳選することになります。資料のファイリング作業は、頭脳も時間もたくさん使うのに何も生み出しません。
「電子媒体にするのなんていつでもできる。あとから紙の資料が必要になるかもしれないから、しばらくはそのまま取っておこう」と考える人がいます。
でも、現時点で使う予定がないものが時間を置いて必要になることは、まずありません。必要になったとしても、紙でなければならない理由はありません。万一、紙媒体が必要だったら、スキャンした資料を印刷すればいいだけです。いずれは電子化してシュレッダーするのなら、決断を先送りにせずに、すぐにやってしまうべきです。
ルールを決めて、電子化した資料をフォルダに保存しておけば、何度かクリックするだけでお目当てのファイルにたどり着けます。OCR(手書きや印刷された文字をスキャナなどで読みとって、デジタルの文字データにする方法)をかけておけば、キーワード検索だってできます。リモートでアクセスできるフォルダに保存すれば、急に在宅ワークをすることになっても、仕事が滞ることはありません。
もうひとつ、電子化は情報セキュリティ対策としても有効です。
佐藤美和『世界のハイパフォーマーを30年間見てきてわかった一流が大切にしている仕事の基本』(かんき出版)
資料にはさまざまなビジネス情報が載っています。会議で配付した資料には、限定されたメンバーだけに口頭で共有した情報の書き込みがあったりします。取引先名や担当者の氏名や連絡先などの個人情報が含まれている場合もあります。紙のままだと、こういう大切な情報が載った資料をうっかりどこかに置き忘れる可能性があります。
電子媒体にしてパスワード設定、暗号化、アクセス権限の付与などの対策を講じれば、情報漏洩リスクは低くなります。
だから、一流のデスクは、いつもきれいです。「ここ空席だったっけ?」と思うくらいに何も置いてありません。きれいなデスクで仕事をするのは気分がいいし、広々と使えるから仕事もはかどります。ここまで考えて、すべての資料を電子化している一流はさすがです。
----------
佐藤 美和(さとう・みわ)
ビービーエル 代表取締役 人事戦略・組織開発・人材開発コンサルタント/企業研修講師
一橋大学大学院国際企業戦略研究科修士課程修了。2023年度Asia Business Outlook誌が選ぶ「アジアの組織開発コンサルタントトップ10」に日本から唯一選出。アメリカン・エキスプレス・インターナショナルにて、アジア太平洋地域オペレーションセンター設立プロジェクトを担当。アーサーアンダーセン ヒューマン・キャピタル・サービス、IBMビジネスコンサルティングサービス(現日本IBM)戦略コンサルティング部門にて、人事戦略策定等のコンサルティングに従事。日本GEにて人事本部組織・人材開発責任者として、グローバルタレント育成等に従事。現在は、ビービーエルを起業し、組織・人事コンサルタントとして活動している。
----------
(ビービーエル 代表取締役 人事戦略・組織開発・人材開発コンサルタント/企業研修講師 佐藤 美和)