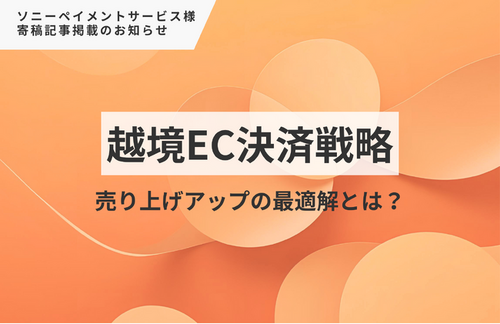【特別寄稿】ゴア、ハーレー・・・『フリーダム・インク』ゲッツ教授が解説する「解放企業」に共通の組織運営とは
2024年5月21日(火)4時0分 JBpress
これまで全6回にわたり、『フリーダム・インク——「自由な組織」成功と失敗の本質』(アイザーク・ゲッツ、ブライアン・M・カーニー著/英治出版)から、内容の一部を抜粋・再編集し、組織変革に成功したイノベーターたちの試行錯誤と経営哲学を紹介してきた。
第7回からは2回にわたり、本書の著者ESCPヨーロッパビジネススクールのアイザーク・ゲッツ教授の特別寄稿をお届けする。前編ではゴアとデュポンを比較し、イノベーションが生まれやすい組織の特徴を明らかにした。第8回となる後編では、革新的製品を生む土壌となるゴアの組織運営について解説する。
<連載ラインアップ>
■第1回 松下幸之助が40年前に喝破していた「科学的管理法」の弊害とは?
■第2回 金属部品メーカーFAVIの新しいCEOが目指した「WHY企業」とは?
■第3回 夜間清掃員が社用車を無断使用した“真っ当な理由”とは?
■第4回 13年連続赤字の米エイビス、新社長はなぜ経営陣を現場業務に就かせたのか?
■第5回 利益率9%を誇る清掃会社SOLには、なぜ「清掃員」が存在しないのか?
■第6回 なぜ経営トップは、5年以上職にとどまってはならないのか?
■【特別寄稿】『フリーダム・インク』ゲッツ教授が解説、ゴアがデュポンより多くのイノベーションを生み出す理由(前編)
■【特別寄稿】『フリーダム・インク』ゲッツ教授が解説、ゴアがデュポンより多くのイノベーションを生み出す理由(後編)(本稿)
※公開予定日は変更になる可能性がございます。この機会にフォロー機能をご利用ください。
<著者フォロー機能のご案内>
●無料会員に登録すれば、本記事の下部にある著者プロフィール欄から著者をフォローできます。
●フォローした著者の記事は、マイページから簡単に確認できるようになります。
●会員登録(無料)はこちらから
解放企業のアプローチ
タスクフォースという従来とは異なる組織運営のアプローチでは、継続的でコスト効果の高いイノベーションを実現するために、全ての社員がイノベーションのプロジェクトを立ち上げ、主導する自由と責任を担うことが重要で、中央集権的なR&D部門を設ける必要がなくなる。
その結果、組織は研究開発関連の管理費用を削減し、チーム中心の実現可能なイノベーションプロジェクトに直接投資できるだけでなく、 R&Dの専門家たちを、こうしたチームの支援と指導という付加価値の高い役割に再配置することができる。
この組織運営はコストを削減するだけでなく、イノベーションの成功率も向上させ、従来の3000分の1という比率を上回る成功率を達成している。このアプローチがいかに効果的かは、私が詳細に分析してきたゴアによって示されている。同社は米国、アジア、欧州を含む30カ国以上で事業を展開している。
ゴアがギター弦に参入し、静かに市場のリーダーとなったという事実は、同社のイノベーションへのアプローチを示す事例である。「エリクサー」ギター弦は、中央集権的な研究開発プロジェクトからではなく、社員の主体的な取り組みを奨励し、自由と責任を重んじる組織運営の副産物として生まれた。
開発はゴアの医療機器部門で働いていたアソシエートのデイブ・マイヤーズによって始められた。マイヤーズは自転車愛好家で、自分の自転車の変速用ギアに使用するケーブルが錆びやすいことに不満を持っていた。
改善策を追求する過程で、マイヤーは自由時間を利用してバイクのケーブルにテフロン加工を施す実験をした(ゴアの製品は全てテフロン製で、テフロンコーティングされた電気ケーブルは同社初のイノベーションだった)。このイノベーションは「ライドオン」バイクケーブルと名付けられ、商業的には成功しなかったものの、もっと利益の大きな取り組みの基盤となった。
ギターの弦が古くなるのは、錆びるからだ。しかも演奏者の指の汚れや垢で劣化は加速する。そこで、マイヤーズは弦をテフロンで覆えばこの問題は解決するのではないかと思いついた。
マイヤーズはギターを弾けなかったので、経験豊富なギタリストでもある同僚のチャック・ヒーバーシュトライトの協力を求めた。そして、二人は通常の弦よりも音質がよく、寿命が3倍のギター弦「エリクサー」を開発した。
この革新的な弦は、標準的な弦の3倍の価格にもかかわらず、発売後1年以内にギター弦市場の3分の1を占めるまでになり、エリック・クラプトンのようなトップ・ギタリストも使うようになった。「エリクサー」の成功に触発されて、「ライドオン」ケーブルも最終的には市場で成功を収めた。
これは、社員が自由にイノベーションプロジェクトに取り組むことを認めるゴアの組織運営によって生まれた、数ある製品イノベーションのうちのたった2つにすぎない。実際、数千もの革新的なプロジェクトから1000を超える革新的な製品が誕生した。
最終的には、継続的なイノベーションへの解決策は、さまざまな問題や機会に直面した社員が、それらを解決するために自発的に取り組める組織運営方式を築くことである。これは、会社全体の組織運営の根本的な革新に他ならない。
ブライアン・カーニーと私は、こうした企業を「解放企業」と名付けた。われわれの本、『フリーダム・インク』の初版は2009年に出版され、IDEO、ハーレーダビッドソン、クワッド・グラフィックス、FAVI、サン・ハイドローリックスをはじめとする数十社で実現した継続的なイノベーションに焦点を当てた。本書の出版以降、私はエアバスやミシュランを含む100を超える同じような変革を観察し、またそれらに貢献してきた。
重要な教訓
以上の議論をから得られる教訓は、驚くべきものかもしれない。イノベーションの実現に向けて従来型の研究開発(R&D)部門に頼ることは、カジノで運を天に任せるようなものだ。いや実のところ、「イノベーションルーレット」で勝つ確率は現実のカジノのルーレットよりもはるかに低いのである。
その限界に気付いたからこそ、ゴアやその他の未来志向の企業は従来の「R&Dカジノ」アプローチを捨てて、自社の社員が合理的なリスクを受け入れ、会社全体を巻き込んだイノベーションプロジェクトを始める機会を提供することにしたのだ。
これらの企業は、このアプローチを単に口にするだけでなく、「業務時間の20パーセントを個人的なプロジェクトに充てる」という表面的な仕組みを真似たりしたわけではない3。むしろ、組織運営方式の包括的な転換に本格的に取り組み、全社員が自ら率先して行動し、関心のある同僚たちと協力して、この取り組みをイノベーションに変えたのである。
3 B.M. Carney and I. Getz, “Google's 20% Mistake”, Wall Street Journal, Aug 27, 2013.
何よりも重要なのは、各社は他社のやり方を真似たのではない、という点だ。彼らは独自の文化的、組織的、そして人間的な文脈の中で、信頼、自由、責任という普遍的な諸原則を取り込んで自社独自の組織運営スタイルを確立した。
かつて大野耐一(トヨタ自動車工業元副社長。「トヨタ生産方式(TPS)体系化した)が「知恵を借りるのを止めて自分で考えよ。困難に真正面から立ち向かい、考え、考え、考え抜いて自ら問題を解決せよ。苦しみと困難は改善の機会を与えてくれる」と言った。私はこう付け加えたい。「それはイノベーションの機会でもある」と。
そのような組織運営方式の構築に向けて、この難しいが最終的には報われる旅を導き、持続的なイノベーションのための舞台を整える責任は企業のトップにあるのだ。
<連載ラインアップ>
■第1回 松下幸之助が40年前に喝破していた「科学的管理法」の弊害とは?
■第2回 金属部品メーカーFAVIの新しいCEOが目指した「WHY企業」とは?
■第3回 夜間清掃員が社用車を無断使用した“真っ当な理由”とは?
■第4回 13年連続赤字の米エイビス、新社長はなぜ経営陣を現場業務に就かせたのか?
■第5回 利益率9%を誇る清掃会社SOLには、なぜ「清掃員」が存在しないのか?
■第6回 なぜ経営トップは、5年以上職にとどまってはならないのか?
■【特別寄稿】『フリーダム・インク』ゲッツ教授が解説、ゴアがデュポンより多くのイノベーションを生み出す理由(前編)
■【特別寄稿】『フリーダム・インク』ゲッツ教授が解説、ゴアがデュポンより多くのイノベーションを生み出す理由(後編)(本稿)
※公開予定日は変更になる可能性がございます。この機会にフォロー機能をご利用ください。
<著者フォロー機能のご案内>
●無料会員に登録すれば、本記事の下部にある著者プロフィール欄から著者をフォローできます。
●フォローした著者の記事は、マイページから簡単に確認できるようになります。
●会員登録(無料)はこちらから
筆者:アイザーク・ゲッツ,鈴木 立哉