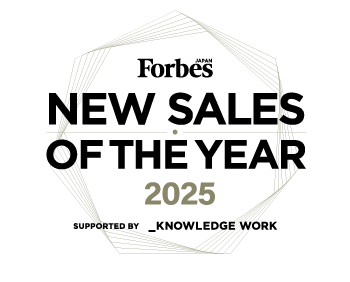ドラッカーが説く、企業の「第一の責任」とは?経営者が財務会計を理解しなければならない本質的な理由
2024年11月18日(月)4時0分 JBpress
企業を取り巻く環境が激しく変わる現代において、経営者は「社会課題への対応」や「新規事業の創造」など、前例がないようなさまざまな課題に向き合っていくことが求められる。そのような「変化の時代」にあって、意思決定のよりどころとすべき本質とは何だろうか。本連載では『成果をあげる経営陣は「ここ」がぶれない 今こそ必要なドラッカーの教え』(國貞克則著/朝日新聞出版)から、内容の一部を抜粋・再編集。「マネジメントの父」と呼ばれる経営学の大家・ドラッカーの教えを元に、刻々と変わり続ける時代において、会社役員がなすべき役割や、考え方の軸について論じる。
第2回は、財務諸表を構成するBS、PL、CSの「本質的な役割」について説明する。
<連載ラインアップ>
■第1回 「企業は社会の“器官”である」ドラッカーが指摘する、企業が果たすべき3つの役割とは?
■第2回 ドラッカーが説く、企業の「第一の責任」とは?経営者が財務会計を理解しなければならない本質的な理由(本稿)
■第3回 なぜ「配当」の仕組みを知らなければ、資本主義社会における財務会計の意味を理解できないのか?
■第4回 なぜROICはWACCと比較しなければ無意味なのか?ドラッカーが指摘する「資本のコストに見合うだけの利益」とは?(12月2日公開)
■第5回 スバルとマツダ、アサヒとキリン…業界のライバル同士は、いかに異なる戦略をとって成長してきたか?(12月9日公開)
■第6回 「自社の事業は何か」ドラッカーのシンプルな問いに答えることが、なぜ経営トップにとって極めて重要なのか?(12月16日公開)
※公開予定日は変更になる可能性がございます。この機会にフォロー機能をご利用ください。
<著者フォロー機能のご案内>
●無料会員に登録すれば、本記事の下部にある著者プロフィール欄から著者をフォローできます。
●フォローした著者の記事は、マイページから簡単に確認できるようになります。
●会員登録(無料)はこちらから
財務会計の全体像
ここで、ドラッカーの次の2つの言葉を紹介します。
1.「企業にとって第一の責任は、存続することである」
2.「社会と経済にとって必要不可欠なものとしての利益については、弁解など無用である。企業人が罪を感じ、弁解の必要を感じるべきは、経済活動や社会活動の遂行に必要な利益を生むことができないことについてである」
ここでもう一つ、「企業の第一の責任」に関するドラッカーの言葉を紹介しておきたいと思います。
「経済的な業績こそ、企業の『第一』の責任である。少なくとも資本のコストに見合うだけの利益をあげられない企業は、社会的に無責任である。社会の資源を浪費しているにすぎない69」(太字著者)
この文章の中の「資本のコストに見合うだけの利益」という言葉を聞いて、読者のみなさんは何を意味しているかピンときますか。資本のコストに見合うだけの利益をあげられていない経営陣は、「社会の資源を浪費しているにすぎない」とまで言われています。
会計がわかっていなくても経営はできます。しかし、プロの経営者として、責任を持って経営という仕事をしようと思えば、会計がわかっていないと話になりません。
私はこれまで約20年にわたって、日経ビジネススクールなどで財務会計の講師をしてきました。これから少し財務会計の話をして、その中で「資本のコストに見合うだけの利益」ということについて説明すると同時に、財務会計を使いながら、会社役員にとってのもう一つの重要な役割という話につなげていきたいと思います。
本書のベースになっている考え方は「大局観と本質論」です。ドラッカーの「大局観と本質論」とは比べものになりませんが、私も「全体像とその本質」ということをいつも大切にしてきました。私が書いた『財務3表一体理解法』がベストセラーになったのも、財務会計の「全体像とその本質」を示したからだと思っています。
会社役員が簿記や仕訳の細かいところまで理解しておく必要はないと思います。しかし、財務会計の「全体像と基本的な仕組み」は理解しておく必要があります。
69『ポスト資本主義社会』P・F・ドラッカー著、上田惇生+佐々木実智男+田代正美訳、(ダイヤモンド社)の5章
そういう意味で、財務会計の全体像というところから話を始めたいと思います。みなさんに質問です。
「そもそも財務諸表は何のために作るのでしょうか」
日本ではすべての企業が財務諸表を作らなければならないと法律で定められています。
財務諸表を作る目的はいくつもあります。みなさんのような経営陣が、会社の事業実態を数字で把握して、しっかり経営していくための道具として作られるという面があります。また、法人税を計算するための元ネタ帳になっているという意味合いもあります。
ただ、財務諸表を作る一番大きな目的は、会社の外の関係者に、みなさんの会社の事業実態を正しく伝えるためです。
会社の外の関係者とは、出資をしている株主、お金を貸してくださっている金融機関、これからみなさんの会社に出資をしようかと考えている投資家などです。つまり、会社の外の関係者とは、みなさんの会社に関係のある、もしくはみなさんの会社に興味を持っている人たちです。
では、会社の外の関係者は、みなさんの会社の何を知りたいと思っているのでしょうか。みなさんの会社はどういうデータを開示しておけば、会社の外の関係者は満足するのでしょうか。
経済産業省の調べによれば、いま日本には約360万社の会社があるそうです。実は、この360万社の会社は、業種が違おうと業態が違おうと行っていることは同じなのです。すべての企業が行っていることは、下図(図表3-1)で示すように、 [お金を集める]⇒[投資する]⇒[利益をあげる] という3つの活動です。
会社勤めをしている人は、この3つの活動をあまり意識することはないかもしれません。ただ、創業社長はこの3つの活動のことをだれでも知っています。
会社を興(おこ)そうと思えば最初に必ずお金が要ります。それを資本金か借入金といった形で集めてきます。何のためにお金が必要かと言えば、それは投資のためです。製造業なら工場建設、飲食業なら店舗調達のためにお金が要ります。そして、その工場や店舗を使って利益をあげるのです。
商社とか小売業は、集めてきたお金を商材に投資します。そして、その商材を販売して利益をあげます。私のような執筆業は会社を興すときにほとんどお金が要りません。しかし、私も事務所を持っていますし、事務所には大きな本棚を置いています。わずかばかりのお金ですが、それを事務所や本棚に投資して、それらを使って利益をあげているのです。
この[お金を集める]⇒[投資する]⇒[利益をあげる]という3つの活動は、すべての企業に共通する活動です。このすべての企業に共通する3つの活動を、「財務3表」 と呼ばれるPL(損益計算書)・BS(貸借対照表)・CS(キャッシュフロー計算書)で表しているのです。
BSは前ページの図表3-1のように、真ん中に線が引いてあって左右に分かれています。なぜ、左右に分かれているかというと、図のように、BSの右側には会社が「いままでにどうやってお金を集めてきたか」ということが記載されていて、BSの左側には「その集めてきたお金が何に投資されたか」が記載されているのです。そして、図の一番左のPLで「1事業年度にどのように利益をあげたか」が計算されているのです。
このBSとPLの中には、日本では円単位の数字がズラーっと並んでいます。円単位の数字が並んでいるのですが、このBSとPLの中の数字は必ずしも現金の動きを表す数字ではありません。売掛による売上、買掛による仕入、はたまた減価償却費など、現金の動きを伴わない数字が入っているからです。
私たちは子供のころから、円単位の数字が並んだ表は収支計算書しか見たことがありません。お小遣い帳も家計簿も収支計算書です。その中にある数字は、現金がいくら入ってきて(収入)、いくら出ていったか(支出)という現金の動きを表しています。
やはり、企業も1事業年度にどのような現金の出入りがあったかがすぐにわかるようにしておいた方がよいということで、日本では西暦2000年からCSの作成が義務づけられました。CSは “Cash Flow Statement” の頭文字をとったものです。この英語をそのまま日本語に訳すと、「現金・流れ・計算書」ということになります。そうなのです。このCSこそが、現金の流れを表す収支計算書なのです。
<連載ラインアップ>
■第1回 「企業は社会の“器官”である」ドラッカーが指摘する、企業が果たすべき3つの役割とは?
■第2回 ドラッカーが説く、企業の「第一の責任」とは?経営者が財務会計を理解しなければならない本質的な理由(本稿)
■第3回 なぜ「配当」の仕組みを知らなければ、資本主義社会における財務会計の意味を理解できないのか?
■第4回 なぜROICはWACCと比較しなければ無意味なのか?ドラッカーが指摘する「資本のコストに見合うだけの利益」とは?(12月2日公開)
■第5回 スバルとマツダ、アサヒとキリン…業界のライバル同士は、いかに異なる戦略をとって成長してきたか?(12月9日公開)
■第6回 「自社の事業は何か」ドラッカーのシンプルな問いに答えることが、なぜ経営トップにとって極めて重要なのか?(12月16日公開)
※公開予定日は変更になる可能性がございます。この機会にフォロー機能をご利用ください。
<著者フォロー機能のご案内>
●無料会員に登録すれば、本記事の下部にある著者プロフィール欄から著者をフォローできます。
●フォローした著者の記事は、マイページから簡単に確認できるようになります。
●会員登録(無料)はこちらから
筆者:國貞 克則