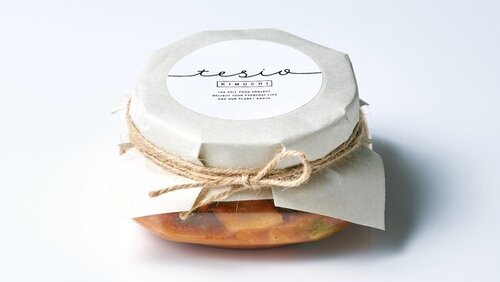朝起きたら白菜になっていた――緒方明監督が衝撃のデビュー作『東京白菜関K者』に込めた“社会への悪意”
2025年4月25日(金)7時20分 文春オンライン
〈 暴走族の集会に行ってエキストラを勧誘! 高校出たての緒方明監督が駆り出された『狂い咲きサンダーロード』の壮絶な現場 〉から続く
石井聰亙(岳龍)監督に出会い、『狂い咲きサンダーロード』の現場にチーフ助監督として放り込まれた緒方明監督。ピンク映画の助監督としても経験を積み、ついに撮った8ミリの初監督作『東京白菜関K者』は、「朝起きたら白菜男になっていた」という衝撃的な作品。ぴあフィルムフェスティバルで激賞されることになる。(全4回の2回目/ 3回目 に続く)
◆◆◆
『サンダーロード』の仕上げでプロの映画作りを学ぶ
緒方 『狂い咲きサンダーロード』はラッシュの段階で東映に見せたら評判がよかったので、全国の東映系で上映が決まって。だから、仕上げは後半から東映の大泉撮影所内の仕上げの棟でポスプロやるようになったんです。そこで編集とかダビング(注1)を手伝って。それは楽しかったですね。音楽も泉谷しげるさん、PANTAさんの曲を使えることになって選曲を僕に任せてくれたり。仕上げになると僕と石井さんの2人でやっていて。笠松さんはネガ編なんかをやってましたけど。その時に一番すごいなと思ったのは、プロの方たちのポスプロの音付けの仕方、効果音(足音や衣ずれの音)のアフレコやったりシネテープにマルを付けたりとか、編集の仕方とか、ダビングのやり方とか、「ああ、こうやってやるんだ」と。僕らが片隅で編集をやっていたりすると、他のテレビの組がお弁当を差し入れてくれたりとかね。映画人っていいなと思いましたね。

——そこが映画の学校でもあった。
緒方 そうですね。石井さんは精神みたいなことは教えてくれるけれども、テクニカルなことは教えてくれないんですよね。プロの現場というのはこうやってやるんだと。そこに来ている助監督さんなんかを見ていると、スケジュールというのはこうやって書くんだと。毎日予定表というものを出すんだと。映画のプロの世界というのはすごいなと思いましたね。ですので、『サンダーロード』が完成して、ちょっとお金もあって部屋も借りたりして、その時にピンク映画の助監督に行くんですよね。ピンクの助監督はわりと入りやすかったので。
——どの辺の監督の作品ですか?
緒方 たぶん言っても全然知らない、大蔵映画の監督。もうとっくに亡くなってますけど。ピンクの中でも序列があって、当時高橋伴明さんとか中村幻児さんとかあの辺は上なんですよ。普通はピンクは4日で撮ってましたけど、3日で撮りますみたいな、超低予算の現場に行って。助監督は1人ですよ。いろんな監督からやり方を教えてもらって。ロケハンなんかも全部自分でやって、ちょっと仕切れるようになった。そうすると、ピンクの中でも格上になって、新東宝の小水一男さん、ガイラさんのところにセカンドで付いたりするようになりました。そうして少しずつ仕事を覚えていくんです。それは楽しかったですね。
『東京白菜関K者』を監督
——『東京白菜関K者』を撮るのはその頃ですか?
緒方 『サンダーロード』を作って、ピンクの助監督をやったりしていたものの、自分が果たして映画界でやっていけるのか。今だったら大学に戻れるな、みたいに悩んでいたら、石井さんが「緒方も一回撮ってみろ」と。石井さんはそういう考え方の人で。撮るんだったら、ありがちな映研みたいな映画を撮ったってしょうがない、プロとして8ミリを撮れと。それで企画を考えて、「そんなんじゃ全然駄目だ」と駄目出しされて。で、ある朝起きたら白菜になっていたというアイデアを思いついて言ったら、「そういう自主映画はないぞ。それだったら俺はやってもいい」と。で、石井さんがキャメラをやってくれて。『東京白菜関K者』ってキャメラは石井聰亙ですから。
——そうですか。
緒方 あれ、全部石井さんなんですよ。「ちゃんと上映してお前は名前を世に出して、助監督をやりつつ作家として出ていけ」みたいなことを言われましたね。
——当時PFFで『白菜関K者』を見て衝撃を受けましたけど、今回見返して、すごくプロっぽいなと思ったんですよ。撮影も望遠レンズだったり。
緒方 それ、いろんな人に言われましたね。
——朝起きたら白菜だったという、そのアイデアから始まったんですね。
緒方 そうそう。
——アパートの名前が「認識荘」。
緒方 そうそう(笑)。ちょっと哲学系というか、インテリごっこが好きだったんでしょうね。石井さんはバイオレンス系というか、肉体系のマッチョな感じの映画を標榜してましたけど、僕は小説だと筒井康隆が好きでしたし、カフカとか、不条理ものとか好きだったので。ケン・ラッセルとか好きでしたからね。ちょっと癖のあるカルト系というか、そういうのを目指して。
——ケン・ラッセルっぽいところ、ありますよね。指を切っちゃって怒涛のように血が出るとか。
緒方 そうそう。ああいうことをやろうとしてるんですよ。まあ、それも時代の真似っこみたいな感じはあるんですけどね。
大林さんの撮った薬師丸ひろ子のプロモーションビデオをパクって
——途中でヒロインみたいな子が出てくる、あれはどなたですか?
緒方 あの方はもう亡くなられたんですけれども。
——ああ、そうですか。
緒方 あの子は俺と同じ年なんですよ。二十歳ぐらいで、写真集を出したばっかりの子で。
——監督が出てきてその子に「サインしてください」と迫る。あれは緒方さん?
緒方 ああ、俺だ。
——あそこはメタ的になりますね。
緒方 たぶん全部元ネタがあるんですよね。大島さんとかにも憧れてたよね。『帰って来たヨッパライ』とか『白昼の通り魔』とか。それから、寺山修司とかにも憧れてますし。そういう実験的作風というかメタ的な、それこそ石井さんじゃないですけど、映画の文法を破壊するみたいな。でも、やっぱりプロっぽさは残すみたいなね。
——あのパートで突然トーンが変わって、美少女ものみたいになる。
緒方 あれは完全に大林さんの撮った薬師丸(ひろ子)さんのプロモ映像パクった。フェチな感じとか。
——でも、悪意を感じるというか、パロディとしてやってますよね。
緒方 そういうことですよね。悪意ということで言うと、世の中に対する悪意というのはバリバリあるわけですよ。それはダイナマイトプロの当時の社会に対する恨みというか。「日本なんかなくなればいいんだよ、バカ野郎」みたいな、『十九歳の地図』的な、社会に対するね。そういういわれのない毒を吐き散らしたいみたいな。
——その匂いはありますね。女の子が爆発しちゃうんですもんね。
緒方 そうそう(笑)。
——あの作り物もよくできてましたけど。
自主映画の横のつながり
——特別出演の自主映画関係者も、見ていると「あの人だ」みたいなのがたくさんいましたけど、PFFとかで知り合った方々ですか?
緒方 そうですね。やっぱり石井組で助監督を一生懸命やっていると、「石井のところに新しい奴隷が入ったみたいだよ」みたいなことは伝わるので、それが長崎組(注2)にも伝わって。PFFの前ですね。それで山本政志(注3)とかに伝わっていったんじゃないですか。横のつながりはありましたよね。
PFFはその後になるんですけど、その頃、自主制作と同時に自主上映というものが社会の中で認められて広がっていくんじゃないかという予感があったんです。つまり、映画というものは全興連に入っている劇場で、窓口で1000円ちょっと払ってやる映画だけじゃなくて、ホール上映やもっと小さな会場、ライブハウスみたいなところで8ミリをやるということが広がって、プロもインディペンデントも関係なくなっていくんじゃないか、という。石井さんはそういうことを言ってましたし、僕もそういう予感はあったんですね。大森さんも亡くなる前に言っていたけど、自分たちで興行をやる、そういうレールがやがて敷かれていくだろうと信じて、『暗くなるまで待てない』以降は作っていたそうです。石井さんも、日活で『高校大パニック』を撮った後に、こんなことをやっていたんじゃ駄目だと。だから、自主映画が制作だけじゃなくて、興行の部分でも客を勝ち取ることが自分らでできるんじゃないかという幻想はありましたね。
——石井さんが日活版『高校大パニック』の後に8ミリに戻った時、『突撃!博多愚連隊』は8ミリだけれど商業映画として興行をちゃんとやろうとしたとおっしゃっていましたね。
緒方 大森さんも『オレンジロード急行』で、あれはものすごく持ち上げられて、ものすごく叩かれた映画なんですよね。その後、どうしようか迷った時に、「まだ8ミリはある」と思ったらしいんです。自分はプロとしてのローテーションピッチャーにはなれなかったけれども、8ミリという自主制作の世界でやっていければいいと思って、取りあえずお医者さんの大学に行こうと。その時に、ATGの佐々木史朗さんが大森さんのところに行って、「今、何をやってるんだ?」「今、学校に行ってます」「じゃあ、それを映画にしようか」ということで、『ヒポクラテスたち』になっていくんです。でも、自主上映は結局無理でしたけどね。そんな甘いものじゃないんですけれども。79年、80年あたりでは、興行形態、上映形態も含めて、革命ができるんじゃないかということをちょっと思ってましたね。
——そういう意味でも横のつながりは大事だった。
緒方 そうですね。その人たちとスタッフを横断したり。実際、僕は『アナザ・サイド』(注4)の応援助監督をやったり、長崎組を手伝ったりしていた。だから、撮影所の中、あるいは町場の中での、プロデューサー、監督、演出部がいてという動きとは別に、インディペンデントの中での演出部だったり制作部だったりというのが必要になってくると思っていましたから。
——『白菜』のクレジットでは山本政志さんがすごく大きく出てましたね。
緒方 あれは、山本がエキストラで来ていろいろ手伝ってくれて、お堀に飛び込んだんですよ。それを石井さんが映してなかったんですよね(笑)。しかも山本は足を脱臼して、そのまま救急車で病院に行ったんですよ。バカじゃないの? と思ってましたけど(笑)。
——その功績で(笑)。
緒方 そうそう。それだけです。
注釈
1)ダビング 台詞、効果、音楽をミックスして映画の音響を作る作業。
2)長崎組 長崎俊一監督の組。当時石井聰亙監督とは日大芸術学部の同期だった。
3)山本政志 映画監督。代表作:『闇のカーニバル』『ロビンソンの庭』『水の声を聞く』など。
4)『アナザ・サイド』 1980年16ミリ、山川直人監督作品。
〈 『爆裂都市』の現場で助監督・緒方明が石井聰亙(岳龍)監督を面罵した理由「映画監督というのは撮りたいものをただ撮りたいと言っているだけでいいわけ?」 〉へ続く
(小中 和哉/週刊文春CINEMA オンライン オリジナル)