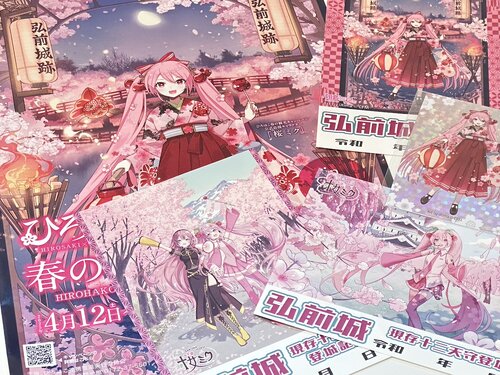アニメでも描かれる日本の自然との向き合い方にアイスランドの歌姫ビョークが共感「雪の日は温泉入ってうわさ話よ」
2025年5月3日(土)7時3分 読売新聞
ビョーク
ライブツアー映画公開、ビョークが語る祖国・音楽
天衣無縫の伸びやかな歌声と電子音を融合した独創的な音楽で、世界的な影響力を持つ歌姫・ビョーク。2019〜23年に世界各地で行ったライブツアーの一部を映画化した「ビョーク:コーニュコピア」が5月7日、TOHOシネマズ日比谷ほかで公開される。音楽とテクノロジーの関係や、これまでの作品への思いを聞いた。(文化部 鶴田裕介)
ビョークはバンド「シュガーキューブス」を経て、1993年、アルバム「デビュー」でソロデビュー。「ヒューマン・ビヘイヴィアー」「ハイパーバラッド」など、世界的ヒットを次々と生んだ。その間、ロンドンやニューヨークを拠点にしたが、近年は故郷のアイスランドに戻って暮らしている。
「とはいえ、1990年代にロンドンを活動拠点にしてた時にもアイスランドに60%、ロンドンに40%みたいな比率で暮らしていたし、ニューヨークにいた時もほぼ同じ。今まで一度も完全にアイスランドを離れたことはない。今、アイスランドですごく幸せだし、いい時期にこの国で生活させてもらっている。首相も女性なら、大統領も女性。女性の中にも人種差別的でファシスト的な思想を持っている人もいるから、手放しに素晴らしいってわけじゃないけれど、そうやって女性が当たり前のように組織のトップに立てている国に暮らせるってことは、すごく頼もしいし、新たな未来に対する希望が感じられる」
2019〜23年に世界各地で開催した、先鋭的な映像と音楽を組み合わせたライブツアー「コーニュコピア」が映画化される。舞台を覆う糸状のカーテンなどにめくるめくビジュアルアートが投影され、歌や演奏と、演劇の要素が高度に融合したショーとなった。
「VR(仮想現実)のヘッドセットの内側の世界を外に引っ張り出して、ステージで再現しようと思ったの。21世紀のVR作品を、19世紀の木製のステージで再現するみたいな感じかしら。今までで一番野心的なプロジェクトになると予感していた。何十枚ものカーテンが開閉する大掛かりな舞台装置を従えて世界を巡るのだから」
大事なのは「デジタルとアナログのバランス」
人の声や楽器の生演奏などアコースティックな要素とデジタルなテクノロジーは対立関係にあると捉えられがちだが、ビョークは以前から両者を「融和すべき要素」と位置づけており、その姿勢を体現するかのようなプロジェクトとなった。
「サムライの世界なら手と刀。手とノートパソコンの関係にも当てはまる。人と道具が重なり合うポイントは無数に存在していて、そのバランスを取るのが大事。私だって、こうして生身の肉体で外出したり、日の光を浴びたりしながらバーチャルでない実際の世界を生きている。一方で、スマートフォンを使ったり、電気自動車に乗ったり、ノートパソコンを開いたり映画を見たりしている。つまり、私たちは常に日々テクノロジーと共存しているわけで、そのバランスをどう取っていくかが大事なこと。
私はアルバムごとにそのバランスを変えてきたし、ライブでもそうしてきた。例えば50人の合唱隊を呼んでステージに立つなんて、まさに人力そのものでしょう? 同時にノートパソコンから放たれるビートはテクノロジーの力によって実現されているわけよね。ステージの中に音響ルーム的な空間を設けて、歌い手の身体から発せられる生身の響きを強調したり、デジタル・マスク的なお面を導入して、私のアバター(分身)のようにスクリーンに表示することで、顔の動きを連動させたりもできる。しかも、そのハイテクを駆使したマスクの素材は、太古の昔の時代から使われていた銀だったりする。
私は歌い手でもあるから、体が楽器でもある。思春期になり、恋に落ちたり、日々生まれ変わって変化していく。その変化が如実に表れるのが声であって、それを発してる本人の気持ちがおのずと伝わってしまう。デジタルとアナログのバランスを毎回、考え直すことが好きなの。これって私たちの生活そのものに当てはまるわけじゃない?」
今もレコード・ショップでDJ
米トランプ政権の誕生で、世界は分断の方向へと進み、気候変動への対応も滞っているように見える。音楽表現と、ライフワークである環境活動とを融合させた今回の映画が公開されるタイミングで、世界の現状をどう見ているのか。
「希望を持つこと、楽観的であることが大事。たとえトランプみたいな人が人類への思いやりや配慮を欠いた行動に出ているとしても、それが彼の哲学であり、物の見方を反映しているわけ。ただ、それは私の哲学ではないし、世界中の多くの人々はあれが決していい態度だとは思っていない。私はもっと人間らしさや魂の宿ったもの、自然や動物に価値を置いている。その自分の信念を支えるために、言葉だけでなく行動で示すことが大事」
ソロデビュー以降、ポップスターとして活躍してきたビョークは近年、理想郷を描いた「ユートピア」(17年)、土の中の世界を表現した「フォソーラ」(22年)と、前衛アートの側面を強めているようにも見える。
「いや、そこは昔から変化していないのでは。これまでのアルバムを振り返ってみても、ずっと前衛アート的な要素は存在していたはず。最近、ポッドキャストでこれまでの作品を一つずつ振り返る企画をした時も、最初からどのアルバムにもポップミュージックに負けないくらい前衛的な曲が含まれていることを改めて実感した。
例えば、1作目『デビュー』(93年)の『アンカー・ソング』は決してコマーシャルな曲とは言い難いし、その一方で、ものすごくポップな『ヒューマン・ビヘイヴィアー』みたいな曲も入ってる。最新作『フォソーラ』の『Ovule』もそう。『ヴォルタ』(07年)の『ワンダーラスト』は、『ポスト』(1995年)における(自身の代表的ヒット曲)『ハイパーバラッド』のような曲。自分の中でのポップとアバンギャルドのバランスって昔からそんなに変わっていなくて、昔から両方とも好きなのよ。
今も昔のパンク時代にみんなで一緒に経営してたレコード・ショップでDJをしていて、自分のアルバムと同じでパンクもダンスもポップも全部網羅している。さらにクラシックからワールド・ミュージック、テクノに能楽までプレーする。音楽ジャンルに関しては完全に民主主義よ」
今の時代に生きる実感を記録して伝え続ける使命
これまでに10枚のアルバムを発表した。とりわけ重要だと考えている作品は。
「私の中ではどれも同一線上のもので、同じくらい価値がある。20代の頃、作家のアナイス・ニンの日記をずっと読んでいたんだけど、10代の頃から晩年まで、40代、50代、60代、70代とずっと日記を残し続けた。どの時代も同じくらいに重要だと思い、私もすべて記録していかなくちゃという使命感を持ってやってきた。アイスランド人の女性として、その年代の女性として、今の時代に生きることの実感を真実のまま克明に記録して伝えていかなければと。世界は日々刻々と移り変わっている。自分は死を迎えるその日まで、この使命をまっとうできることを願ってる」
たびたび日本を訪れ、リスナーや日本文化への好意を伝えてきた。同じ島国で、時折大きな自然災害にも見舞われるというアイスランドとの環境の近さも影響しているのだろうか。
「それはあると思う。アイスランドと日本って、自然との向き合い方がすごく似ている。革新的で高度な技術力を持っているのに、テクノロジーと自然のどちらか一択を迫ることをしない。日本のアニメを見ていても、自然がたくさん描かれていて、自然に対するポジティブな姿勢が伝わってくる。ポジティブって言葉は違うかな。『受け入れる』みたいな。私たちのどちらの国も、いつ何どき噴火や地震が起こっても不思議ではない環境に生きていることも、絶対に関係していると思う。
アメリカ映画なんかによく登場する、すべてを破壊して奪い去りかねない悪や恐怖の対象みたいな敵対関係とは真逆の描き方よね。日本やアイスランドでは、自然を受け入れて共生しようという思想が生活の中に浸透している。つまり、自分もまた自然の一部であるという意識が働いているから、それを排除しようっていう発想がない。そもそも切り離すことなんて不可能だから、ただ受け入れて共存していく。さらに、テクノロジーの進歩や技術を取り入れて進化していくこともできる。
あと、共通点はお風呂文化よ! 日本に温泉があるように、私たちの首都のレイキャビクにはスイミング・プールがある。みんながワイワイ集まっておしゃべりしたり、特に猛烈な雪の日なんかは友達みんなで温泉に浸ってうわさ話に花を咲かせたりするの。日本式の『オンセン』とはだいぶノリや雰囲気が違うけど、日本もアイスランドも温泉文化があることは強みよね」
大規模なプロジェクトが一段落した。今後の音楽活動は。
「しばらくは曲作りに集中することになるかしら。書くこと自体は常にやっているけど、それが作品として形になるまですごく時間がかかるのよ。だから今の段階で話すのはまだ早すぎるけど、今度お話しする時にはお伝えできるはず!」
トップ画像クレジット photographer:vidar logi、dress:Stina Randestad、styling:edda gudmundsdottir、makeup:andrew gallimore、hair:hiroshi matsushita