食道がんで亡くなった兄……その時私の昭和は終わった
2025年4月23日(水)7時0分 文春オンライン
〈 70年代の新宿は眩しくて暗かった 〉から続く
イラストレーター・エッセイストとして長年活躍する沢野ひとしさんが、昭和100年・戦後80年を記念して書き下ろした全頁イラスト入りのエッセイ『 ジジイの昭和絵日記 』(4月23日発売)から、内容を一部抜粋してお届け。学問が好きでドイツに留学したものの、帰国後は大学で思うような活躍が出来ず、アルコールに依存していった亡き兄の思い出が綴られている。
◆◆◆
もともと強くなかった酒の味を覚えて
兄はもともと酒に弱かった。瓶ビールの半分も飲まないうちに手を横に振っていたくらいだ。
それがドイツで強い酒の味を覚えたのか、いつの間にか酒豪になり、兄が懇意にしている駅前の寿司屋でご馳走になった時、日本酒をぐいぐい飲み、追加を何本も頼むのに驚いてしまった。さらに店の主人と延々と「日本の貧困さ」について話すのにはうんざりしてしまった。何となく兄のどこかが崩れてきた感じを受けた。
「オヤッ」と強く思ったのは、毎年の両親の墓参りの時である。家族が集まると、兄だけ顔色が悪く、昔の精彩はまるでなく、足取りもふらついていた。会うたびに身分不相応な高級車に乗ってくるのも気になっていた。
帰りの食事会の時だった。全員が車で来ていたので、酒は常識的に頼まないものだが、兄はなんの躊躇もなく小瓶のビールを手にしていた。兄の嫁さんが来ていなかったので注意する人も横にいなかった。
妹が「車でしょう」と兄を軽蔑するような口調で言うと「平気だよ、昼間はすぐに抜けるから」と訳の分からないことを言った。私は大学の教師でありながら、モラルに欠けた兄に唖然としてしまった。仮に事故でも起こせば職を失うことは確かである。
酒が続くと失敗も多くなる。兄は自宅でいつものように酒を飲み、洗面所で転倒して、首の頸髄を痛めてしまった。可愛がっていた娘の嫁ぎ先の郡山の奥に、骨折や病に効く温泉宿があるというので、大学はしばらく休み、仕事の本とパソコンを車に積んで治療に専念したが、元に戻ることなく、元気に歩けるようにはならなかった。
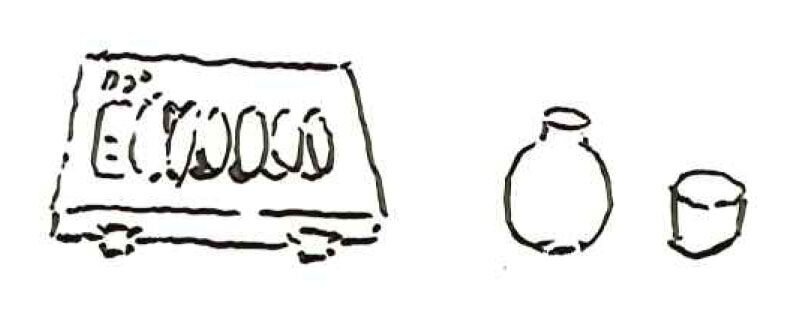
後年、兄の奥さんから聞かされた話は更に深刻だった。マンションの部屋の掃除に行くと、コンビニ弁当の食べカスと、酒類の瓶が転がり、明らかに昼間から酒を飲んでいた気配が濃厚だったという。
兄の弱った体が心配になり、「一度きちんと診断してもらったら」と電話してから半年を待たず、食道がんの疑いが濃厚となった。それまでしきりに「喉が痛い」とうがい薬を使っていたが、一向に具合が良くならず、兄も「もしかしたら」と不安に怯え、ついに病院に行ったのだ。おそらくその頃の数年というもの、アルコール依存症であったはずだ。奥さんが何度もお酒のことを注意しても「オレは平気」と全く耳を貸さず、最後は決まって修羅場になったという。
入院中の兄を見舞いに行くと、ベッドに横たわっている兄の顔が、亡くなった父にそっくりになっていて驚愕した。何だか確実に死に近づいている気配を感じた。
そして半年の治療も虚しく、12月の寒い朝に亡くなってしまった。お葬式の時に祭壇に飾られた、山をバックに笑っている兄の写真を見た途端思わず号泣した。屈託なく眩しそうにして笑っている本来の兄の姿だった。通夜の日は涙が涸れるほど泣き崩れた。
斎場の帰りの坂道を妻と歩きながら「惜しいな、惜しいな」と何度も繰り返していた。
親しい友たちが高原の風になっていった
兄が鬼籍に入ったのは、私が58歳の時で、とっくに昭和は終わり、2003(平成15)年になっていた。だが今更ながら「昭和は終わった。兄と一緒の昭和は終わった」という言葉が何度も頭の中でぐるぐる回っていた。
私は長い間山歩きをしてきたが、一番好きな山は八ヶ岳の峰々だ。とりわけ野辺山高原から見た裾野を伸ばした山の姿に見惚れる。
ある時耳にした「千の風になって」(作詞:不詳 日本語詞・作曲:新井満)というテノール歌手、秋川雅史が歌う曲が、歳と共に身に沁みて聞こえるようになった。
この曲を初めて聴いた時は不思議な気持ちに陥った。すでに亡くなった人が、まだ存命している人に「私のお墓の前で泣かないでください」といい、「そこに私はいません」「千の風になってあの大きな空を吹きわたっています」と歌う。身内の死はいつまでも身に応えるものだ。ふとした時に思い出し涙が出る。でもこの曲を聴いてからはいくらか楽な気持ちになってきた。
晴れ渡った八ヶ岳高原を歩く時、「風」を感じる。風は目に見えず、手で触ることができない。だが「千の風になって」を耳にしてから、風が見えるようになった。
親しい友たちが高原を千の風になって流れていくのをはっきりと認識できるようになった。透明な薄いセロハンのような風が山から次々に流れてくるのだ。
「あっ今の風は兄が笑っているな」「ああ、あの風は穂高で亡くなった彼だ」「あのふんわりした微笑む風は、若くして亡くなった彼女だ」
唄はさらに「秋には光になって畑にふりそそぐ」「冬はダイヤのようにきらめく雪になる」と歌う。
小さな声で口ずさむと本当に亡くなった人に会える。あの頃の兄の元気な声が聞こえる。涙は少し出るが自分が生きている実感も感じる。
昭和の時代から、高原には千の風が爽やかに流れていたのだ。
(沢野 ひとし/ノンフィクション出版)













