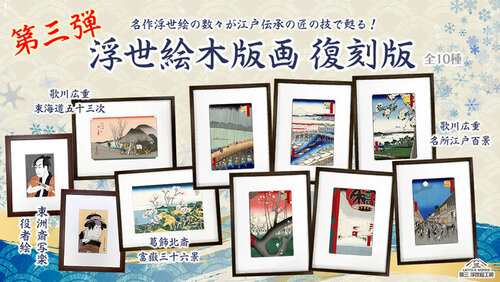「ゴッホよりニルヴァーナに憧れて人生間違った」芸人・永野の“笑いのルーツ”は90年代ロックにあり(インタビュー)
2021年11月13日(土)16時0分 tocana
「孤高のカルト芸人」と呼ばれる永野の初めての著書『僕はロックなんか聴いてきた〜ゴッホより普通にニルヴァーナが好き!〜』(リットーミュージック)が9月25日に発売された。この本では、永野が独断と偏見を交えて自分の好きなロックミュージックについて思い入れたっぷりに語っている。永野はロックから何を学んできたのだろうか?
■90年代の悶々とした思い
——この本を出されたきっかけは?
永野 最初のきっかけは、「JASON RODMAN」というウェブメディアで「コラムを書いてみませんか」と言われて、自分の好きな洋楽や映画の話を書いたことですね。(出版社の)リットーミュージックの方にそれを面白がっていただいて、本を書くことになりました。
もう1つのきっかけはYouTubeです。僕はもともとYouTubeに偏見があったのでやりたくなかったんですけど、コロナ禍になって営業が全部飛んだので、大人の人たちに言われてやり始めたんです。
でも、お笑いっぽいことをやったら思ったほど再生回数が伸びないんですよ。ただ、メントスコーラとか、今さらみんながやるようなことはしたくないからどうしようと思っていて。ネタがないから仕方なく、自分の好きなバンドのニルヴァーナについて話したんですね。その後、YouTubeでそういう90年代のバンドの話をするようになったら、少しだけ見られるようになって。それも本を書くきっかけになりました。
リットーミュージックの方には「自伝を書くか、ロックについて書くか、どっちにしますか?」と言われて。自伝を書くのは別に興味なかったので、それだったらロックについて書こうと。でも、こっちは音楽ライターでも何でもないから、ただ自分の思いで語ってるだけなんですよ。おすすめの音楽というわけでもなくて。
——この本を読むと、90年代のバンドのことだけじゃなくて、その頃の永野さんの悶々とした感じとかがよくわかりますよね。
永野 僕は1974年生まれなので、90年代に入った年に16歳だったんです。だから、90年代が一番多感な時期でした。僕には兄貴がいて、その影響で洋画や洋楽に触れていたんです。当時の若者はみんなアメリカやイギリスの文化に目を向けていて、そのとき聴いていたのも白人のバンドばっかりだったんです。
だから、いま自分でこの本を読み返すと、尖ってるし、闇がある感じだし、90年代的な思想に染まってるなあと思いますね。僕はアニメには興味がなかったので『エヴァンゲリオン』とかは通ってないんですけど、同じような部分がある気がします。後輩に「その感じ、古いですよ」って言われたことがあるんですけど、たぶん90年代で止まってるんですよね。ずっと闇で、露悪系、鬼畜系(に傾倒している)というか。
——当時はそういう空気がありましたよね。
永野 ありましたよ。ロフトプラスワン(で開催されるイベント)もそうだったし、『Quick Japan』も今みたいなお笑い雑誌とは違ったから。『完全自殺マニュアル』とか『羊たちの沈黙』とか『マーダー・ケースブック』とか、ありましたよね。あの頃はみんな無理していたんですよ。この本を読み返して思ったのが、俺、ずっと無理してたんだな、って。
——自伝を書くつもりはなかったそうですが、結果的に自伝みたいなものになっていますよね。
永野 なりましたね。やっぱり音楽って、聴いていたときのことを思い出すじゃないですか。ニルヴァーナの話をしていたら、だんだん中学校の頃を思い出してきて。その前にセックス・ピストルズを買ったな、とか。結構気持ちが入った本になりました。
あと、自分で読んでいて「こいつアホだな」って思いました。とにかく洋楽しか聴かないっていうのも、ここまで来たら意地じゃないですか。「俺、洋楽聴いてる」っていうのがアイデンティティだったんだな、って。柔らかくいけばいいのに。だって、苦痛でしたからね。全然楽しくなかったですよ。
——苦痛だったんですか?
永野 映画もそうなんですけど、無理をしちゃうんですよね。それこそ無理してキューブリックの映画を見るみたいなことをしていました。今考えたら何も楽しくなかったです。
普通の歌謡曲とかも聴けば良かったな、って思います。そのマインドが自分のやっているお笑いにも出ているんですよね。もうちょっと普通にやればいいじゃないですか。だけど、この人たちの影響で“オリジナリティ”を覚えて、いや、オリジナルじゃないとダメでしょ、みたいになったんですよね。
■ニルヴァーナに憧れて人生間違った!?
——私は洋楽には疎いんですけど、この本を読んでいて面白かったのは、そういうバンドの中に永野さんの笑いのルーツみたいなものがあるということです。影響を受けているという話が随所に出てくるんですよね。
永野 ニルヴァーナは特にそうですね。ニルヴァーナがテレビに出演する時、すごくかったるそうにしてたんですよ。あれが格好良いと思って。あと「レイプ・ミー」という過激な歌詞の曲があるんですけど、MTVの授賞式で「リチウム」という曲をやってほしいと言われていたのに、冒頭でちょっとだけ「レイプ・ミー」を弾いて、その場の空気が一気に緊張したりするんです。いま考えたらクソ生意気な20代のバンドなんですけど、そういうのがいいなと思っちゃって。
あと、ニルヴァーナと並んでグランジの双璧と言われるパール・ジャムというバンドがいて。ニルヴァーナはパール・ジャムの悪口を平気で言っていたんですけど、パール・ジャムは他人のことを悪く言わないんです。
パール・ジャムは今でもやっていて、(米国の)国民的な人気バンドになっているし、仲間もいっぱいいて、家族も大事にしているんです。昔はニルヴァーナが格好良いと思ってたけど、ボーカルのカート・コバーンは最後は自殺してるじゃないですか。パール・ジャムは富を得て幸せに暮らしている。だから、いま考えたらパール・ジャムの方が正しかったのかな、って思うんです。ニルヴァーナに憧れたもんだから人生間違っちゃったのかな、って。
それがあったから、僕はテレビに出るようになってからも、『PON!』で生放送中に俳優にビンタしちゃったり、『とんねるずのみなさんのおかげでした』で落とし穴に落とされて不機嫌な態度を取って、変な空気にしちゃったりしたんです。
——落とし穴に落とされたときの芸人のリアクションってだいたい決まってるものなのに、永野さんはそれを無視して本気で嫌がってるみたいな感じを出していたから、とんねるずのお二人も戸惑っていましたね。
永野 その後、同じ番組でラッセンの絵を買わされるというドッキリがあって、和解はできたから良かったんですけどね。
でも、かますのが格好良いと思っているのはやっぱりニルヴァーナの影響です。
■オアシスは『M-1』決勝進出コンビと同じ!?
——永野さんはバンドの好き嫌いもはっきりしていますよね。この本の中で印象的だったのは、オアシスのことをあまり評価していなかった点です。
永野 でも、オアシスはいい曲を作るんですよ。彼らは労働者階級で、言っていることは反体制みたいなことだったりするから、普通の人から見たら応援しがいがあるんですよね。
一方、ライバルと言われていたブラーには何もないんですよ。中流階級だし、結構お上品なんです。アートスクール出身で、ふざけた曲ばかり歌っていて。その人をナメている感じが僕は好きだったんですよね。
本にも書きましたけど、オアシスは『M-1(グランプリ)』で決勝に行くようなコンビに見えるんです。決勝に行った後で、テレビに出るようになって「こいつ、借金があって」とか「実はこんなキャラで」とか言うやついるじゃないですか。そのつまらなさね。
お前、『M-1』に出るために一生懸命練習してきて、決勝の日も朝ちゃんと起きて会場に来たんだろ、って。本当のクズはビビって来なかったりするじゃないですか。
ブラーがクズというわけじゃないですけど、今もそういうのが好きなんですよね。でも、周りを見回したら僕のように考えてる人が誰もいなかったんです。
——俺だけだった、と(笑)。
永野 『猿の惑星』みたいな状況ですね。まさにディストピア小説そのものだった。僕は「自分はこういう感覚だけど、それってお笑い好きだったらみんなそうだよね」っていう自信を持って生きてきたんですよ。
でも、最近ちょっと自信がなくなってきて。「サブカルっぽいね」と言われることもあったんですけど、サブカルの方も頭いい人たちに囲まれていて、もうよくわからないし。本当にどこにも居場所がなくなってきたんですよね。
〜つづく〜
※ 永野の生い立ちと“お笑い観”が明かされる中編(14日16時に公開)はコチラ!