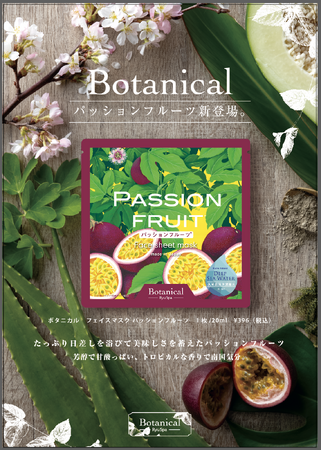「沖縄県民は飲み会のシメにステーキを食べる」という真っ赤な噓はナゼ生まれたのか?《都市伝説を作った“ヤラセ満載のテレビ番組”》
2025年4月20日(日)12時0分 文春オンライン
警察からは「土人」と呼ばれ、1970年代には結婚差別や「琉球人お断り」を掲げる飲食店も——こうした「沖縄差別」は、今も形を変えて残っている。仲村清司氏による書籍『 日本一ややこしい京都人と沖縄人の腹の内 』(光文社)から一部抜粋し、解説する。(全2回/ 続きを読む )

◆◆◆
「沖縄県民は飲み会のシメにステーキを食べる」という真っ赤な噓
沖縄に在住していたときに、沖縄の飲食をとりあげた番組を制作したいということで、僕も番組担当者からコメントを求められたことがある。その人いわく、
「沖縄の人たちは酒を飲んだあとにラーメンでなく、ステーキを締めで食べながらまた飲み直す」
というものだった。僕が沖縄で文筆活動を続けていたから依頼があったのだろうが、はっきりいう。沖縄人がアルコールを飲んだあと、締めにステーキを食べるなどという食習慣は断じてない。沖縄には飲み友達もたくさんいるが、飲んだあとにステーキで締めるなんてことは一度もやったことがない。
なぜ、そんな都市伝説が生まれたのかを解明するのはたやすい。沖縄のステーキハウスは深夜も営業している店が多く、早朝まで開けているところも少なくない。つまり、ステーキハウスながら、遅くから飲み始めた人たちや、飲食店などのシフト制で夜遅く勤務を終えた人たちの飲食の場にもなっているのだ。
事実、メニューもステーキだけではなく、フライドチキンやフライドライスやタコスなどの単品もあるし、ドリンクもビールはむろんのこと、ワインや泡盛までそろっている。
「沖縄のシメステーキ」という“都市伝説”が生まれた理由
出所は知っている。日本各地の居酒屋をめぐる旅の本の沖縄編で、ステーキハウスを案内した人の会話が掲載されている。
ただし、「沖縄では締めはステーキですよ」などとは書かれていない。「沖縄に来たからにはステーキも食べないと」という意味で誘っただけなのだ。その会話文がどう読み違えて広まったのか、いつのまにか、沖縄では締めはステーキという都市伝説が根づいてしまった。実のところ、僕はその本に登場したステーキを食べようと誘った人の友人なので、この件の真実についてはよ〜く知っていたのだ。
なので、担当者には、
「それは作り話ですからコメントできません。そんな番組が放送されたら沖縄の人たちの酒癖の嘘がまかり通るので、番組制作も再検討してください」
そうはっきり述べたが、結局はヤラセ満載の内容で放送されてしまった。
それどころか、沖縄人は酒飲みから始まって、沖縄人は酒にだらしない、終電のない沖縄は朝まで飲んでいる人が多いから働かない、などという悪意に満ちたデマがまかり通るようになった。まあ、100パーセント嘘ではないが県民全員がそうであるはずがないし、だいいち酒に溺れている人間はどの都道府県にもいる。
国税庁統計情報 (2016年)の都道府県別アルコール消費量調査によると、トップ3は上から、東京都、鹿児島県、宮崎県で沖縄県は4位である。
先の番組制作者は東京人がいちばん飲んでいることをお忘れなく。付け加えておくと、ハイセンスでオシャレな飲み方をしているはずの東京のサラリーマンの飲み方なんぞはいちばんだらしない。
わたしゃ東京にも長く住んでいましたから、そのへんの事情は聖書に誓えるほど真実を述べている。本書をお読みの方も心当たりがあるだろう。
警察が市民を「土人」呼ばわり
沖縄についても容赦のないバッシングをたたきつける人もいる。
「沖縄料理はまずい」「泡盛は臭くて悪酔いする」程度なら好みの問題だからとやかくいうつもりはない。そんなにまずくて臭かったら、「あんたは食わねばいい、飲まねばいい」と返せるが、穏やかでないデマを投げつける人も半端なく多い。
排他的、反日、沖縄人は中国人、第三国人、本土人をヤマトンチュと区別する、野蛮人、はては大阪府警の機動隊が市民を「土人!」呼ばわりした事件まで、差別発言はあとをたたない。
実のところ僕は子どもの頃、大阪で育っているのだが、そのときのあだ名は「土人」「外人」であった。昭和40年代初頭の頃だが、差別表現に対する意識が高くなったいまでも「土人」と叫ぶ警察官がいるとは夢にも思わなかった。
あるいはもしかすると、警察内ではいいつがれているのではないかとも疑ったりしたが、差別は解消しないどころか連鎖することをまざまざと思い知らされた。
これらの差別発言は辺野古の新基地建設などいわゆる沖縄問題が起源になっていて、政治的な意味合いが深く刻み込まれている。
1970年代まで「沖縄差別」が当たり前にあった
しかし、戦前から沖縄差別は社会問題化するほど顕在化していて、沖縄人のことを「琉球人」「リキ人(琉球人)」と呼んで結婚差別をしたり、「琉球人お断り」という札を下げたりした飲食店が70年代まであった。
2016年には東京に異動になった琉球新報の記者が住居を探していたときに、家主から「琉球新報の人間には貸したくない」と入居を断られたことがあった。
本書の主旨である「ややこしい京都人と沖縄人の真実」を書くきっかけになったのは、京都人へのバッシングや沖縄人に対する偏見も大きな要因になっている。
「ややこしい人たちやなあ」ですめばお笑いにもなるが、他府県人に対する偏見やメディアによる真実のねじまげが激化すれば差別に発展する。
たとえば「京都人はイケズ」というフレーズは都市伝説を超えて日本全国にあたかも真実のように蔓延している。これが曲解されれば社会問題になるおそれもある。
仮に京都出身の人が他府県に引っ越しをし、子どもが転校した場合のことを考えていただきたい。「おまえ、京都人か。だったら性格もイケズだろう」と茶化され、イケズというあだ名でもつけられたら差別事件に発展する。
「沖縄人は中国に帰れ!」「朝鮮人は朝鮮に帰れ!」というデモ行進が現実に起きている世の中である。残念ながら日本は差別や偏見の自浄能力の低い国で、それゆえ個人的には民度の低い国と思っている。
本来なら、京都人がイケズというならその根拠を示せといいたい。沖縄人が反日で土人というなら、なぜそう思うのか証拠をあげなさいといいたいのである。
〈 「京都は陰湿で排他的」と思い込んでいる人に伝えたい“京都人よりケチでセコいあの県民”〈「茶漬けが出たら…」の本当の意味〉 〉へ続く
(仲村 清司/Webオリジナル(外部転載))