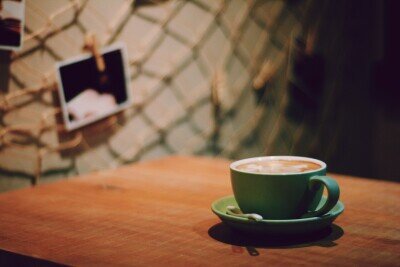東京は「憧れの街」から「行かざるをえない場所」になった…令和の若者が「消極的な上京」にすがるワケ
2025年3月4日(火)17時15分 プレジデント社
1936年、東京台東区の上野駅の内部(写真=桑原 甲子雄/PD-Japan-oldphoto/Wikimedia Commons)
1936年、東京台東区の上野駅の内部(写真=桑原 甲子雄/PD-Japan-oldphoto/Wikimedia Commons)
■東京は未知の世界、憧れの街だった
東京なんて——。そう思いながらも、上京せざるをえない。令和になり、いえ、今世紀に入ってから、若者たちの上京の動機や東京に対する意識が明らかに変化しました。
かつて東京は未知の世界であり、憧れの街でした。地方に住む若者たちは、東京に幻想を抱き、希望ともにふるさとをあとにしました。
たとえば、弘前市出身で、劇作家の寺山修司は、1954年に早稲田大学への進学とともに19歳で上京しました。少年時代から東京に憧れた寺山は『誰か故郷を想はざる』で次のように書いています。
私は人知れず、「東京」という文字を落書きするようになった。仏壇のうらや、学校の机の蓋、そして馬小屋にまで「東京」と書くことが私のまじないになったのだ。
東京東京東京東京東京東京東京
東京東京東京東京東京東京東京
東京東京東京東京東京東京東京
東京東京東京東京東京東京東京
東京東京東京東京東京東京東京
東京東京東京東京東京東京東京
書けば書くほど恋しくなる
■家賃や生活費が高くても、行かざるをえない
70年前に上京した寺山修司に対して、現代はどうでしょう。
ネットが発達し、SNSがこれだけ普及した令和のいま、若者たちは東京が地方に比べて、家賃や生活費が高いことを知っています。とはいっても、地元には職がなくて、仕事を選べない。東京に行かずに済むなら地元に残りたい。けれど、仕事について考えたら、上京せざるをえない。地元に残るよりは……と仕方なく消極的に地元を離れる。令和は東京への幻想や憧れが消え去った時代といえるかもしれません。
■憧れだった東京が、現実のものに
戦後80年を振り返ると上京には3つのピークがありました。
1つ目が戦後の高度経済成長期。
寺山修司が上京した10年後に開催される1964年の東京オリンピックに向け、東京の再開発が一気に加速しました。オリンピックの競技施設だけではなく、高速道路が延び、空港が造られ、新幹線が開業し、高層ビルが林立していく。
この時期に「金の卵」と呼ばれた中卒の集団就職や、進学で上京したのが団塊の世代です。メディアの急成長により、夢想するしかなかった東京から、ブラウン管の向こう側に存在する具体的な憧れに変わったといえるでしょう。
次のピークが1980年代。80年代後半からのバブル経済で、人とお金がどんどん東京に集まりました。
写真=iStock.com/voyata
※写真はイメージです - 写真=iStock.com/voyata
大阪出身の私が上京したのは、バブル前夜の1984年。そもそも私には上京する気がなく、京都大学に進学しましたが、東京に本社がある広告代理店への就職が決まりました。私にとってのはじめての上京となった1カ月半の研修で実感したのが、マスコミの東京一極集中です。地方の支社を希望しようものなら、「やる気ないの?」と問い詰められるような雰囲気もあり、東京本社を希望し、配属されました。
オンラインで取材に応じる難波功士教授
■ぜいたくしなければ「東京で家が持てる」と思っていた
その頃、地方に暮らす若者たちには、切実な業界幻想がありました。音楽に詳しかったり、オシャレだと自負したりする地方の若者たちは、東京に行かないとオシャレな人たちのネットワークに入れない、という切迫感の反面、期待感も持っていました。上京すれば、憧れの人や、オシャレな人たちとの接点ができて、自分も成功できるのではないかと。
戦前は文学を志す青年たちの上京がありました。それが、演劇や映画、音楽へと広がっていき、やがて80年代のテレビや雑誌などのメディア業界、ファッション業界、音楽業界などのいわゆる「ギョーカイブーム」への憧れからの上京という流れにつながっていきます。
またこの時期には、バンドブームも起きました。「三宅裕司のいかすバンド天国」や、原宿のホコ天(歩行者天国)での演奏を夢見て、バンドマンたちが東京を目指すようになりました。
私が上京した当時、基本的にみな正規雇用でしたから、給料は右肩上がり。終身雇用でもあったので、変なぜいたくさえしなければ、いずれ東京で持ち家を建てられるか、マンションを購入できると自然に思えた時代です。アメリカの経済がボロボロで「ジャパン・アズ・ナンバーワン」が続くと、みんなが疑いなく信じていました。
現在のように身の回りのプラットフォームのすべてがアメリカ製になるなんて、誰も考えもしていなかったのです。
■イオンモールができても雇用のほとんどはパート、非正規
そして最後のピークが2000年代以降です。
私が関西に戻り、関西学院大で教鞭をとったのは1996年。着任した頃、20人から30人のゼミ生のうち、関西に残る割合はほぼ半分でした。しかし現在、関西に残るのは3分の1程度で、3分の2近くが上京します。関西で創業し、発展した商社や、電気機器、繊維、薬品などのメーカーも本社機能を東京に移していますし、学生に人気のIT企業やベンチャーは東京に集中しています。
こうした産業構造のなかで、学生たちが上京するのは自然な流れです。この流れで拍車がかかったのが、地方の衰退です。
上京の第1次ピークとなった高度経済成長期に、若者が首都圏に流出した影響で、地方は疲弊しました。
それでもまだ80年代の地方は、寂れつつあったものの、地元の商店街や中小の商工が生き残る余地が残されていました。大規模なスーパーなどの進出と周辺の商店との利害を調整する大店法(大規模小売店舗法)があったからです。その後、2000年に大店法の廃止などにより、地方は衰退の一途をたどります。商店街はシャッター通りになり、地場産業も痩せ細っていきました。
シャッターが閉まった商店の代わりに郊外に誕生したのが、イオンモールなどの大型ショッピングセンターです。なかには、イオンモールがあれば、満足という人もいるでしょう。
ただイオンモールの出店によって創出される雇用のほとんどがパートや非正規です。昔のように公共事業での雇用は期待できない。イオンモールまでクルマで1時間以上もかかるような過疎地域に暮らす若者の受け皿が地元にあるのか。問題はより切実です。
■圧倒的な首都圏への転入超過
総務省が公表した2023年度の各都道府県の転入・転出で、転入が転出を大きく上回ったのは、首都圏の東京、埼玉、神奈川、千葉。大阪や福岡でも若干上回っていますが、大阪の隣にある兵庫や京都では転出が増えています。
総務省統計局「住民基本台帳人口移動報告 2023年結果」より
ちなみに、東京は約45万4000人の転入に対し、転出は38万5000人。転入が約6万9000人も上回っています。首都圏全体では、約12万6000人の転入超過に上りました。ただ大阪では約1万人、福岡では4000人ほどに過ぎません。地方中核都市がある宮城や愛知、広島では転出の方が多い。
■非正規で食いつないでいる上京者もたくさんいる
このグラフは、新型コロナの感染拡大や、災害などによって凹凸はあるものの、東京一極集中への流れが押しとどめようがない現実を可視化させます。
確かに、コロナを機に、リモートワークが増えました。地方にいながら、東京と同じ仕事ができると謳いながらも、リモートワークを可能にする通信産業の中心は東京です。その構造はそう簡単に変わりません。
一方で、上京したとしても、都内で高額な家賃を負担しながら生活基盤を築くのはハードルが高い。誰もが家賃補助をもらえるような企業に就職できるとは限りません。きょうだいや知り合いのアパートに転がり込んで、非正規の仕事で食いつなぎながら東京での生活をスタートさせる人もたくさんいるはずです。
写真=iStock.com/Wachiwit
※写真はイメージです - 写真=iStock.com/Wachiwit
もちろん80年代の若者たちも生活は決して楽ではなかったかもしれませんが、好きでやっているんだという意識はあった。東京には、「ギョーカイ」に憧れた若者たちの居場所があった。
■上京の負の側面を象徴する「秋葉原通り魔事件」
その点で、00年世代における上京の負の側面を象徴するのが、秋葉原事件を起こした加藤智大です。
1982年生まれの彼は寺山修司と同じ名門青森高校を卒業しましたが、北海道大学に入学できず、岐阜の短大へ進学します。その後、派遣会社に登録し、非正規の労働者として、埼玉県上尾市、茨城県つくば市、静岡県裾野市などの工場を転々とします。
加藤の足跡からは東京へのこだわりは感じられません。オタク気質から秋葉原には通ったのでしょうが、大阪の日本橋などでも代替できたのではないかと思います。それに、彼にとって、地元や家族は忌避すべき場であり、存在でした。職場にもネット上にも、そして東京や地元にも居場所を見つけられずに、2008年に秋葉原で、凶行に及んだ。
■CMに見る「上京の価値観」の変化
反面、日本社会のポジティブな変化を感じたのが、2022年に上京を扱った2つのCMです。
1つ目が、サントリービールの「ザ・プレミアム・モルツ〈香る〉エール」のCM。川口春奈さんと山田裕貴さんが遠距離をするカップルを演じています。地元に残った山田さんが、上京する川口さんを駅のホームで見送ったり、東京でバリバリ働く川口さんからの愚痴を電話で聞いたりする。
2つ目が深津絵里さん主演のJR東海のCMです。関西で働く深津さんがコロナ禍に新幹線で上京し、ビジネストークをして新幹線に再び乗り、関西に帰る。実は、深津さんにとって33年ぶりのJR東海のCM出演でした。33年前のCMでは、クリスマスイブの新幹線ホームで帰省する男性を待ち続ける女性を演じました。
CMが現実を投影しているとは言いませんが、社会の変化を感じずにはいられませんでした。私が男女雇用機会均等法以前に就職した世代だからなおさらです。私たちの世代では、ジェンダー規範がまだまだ強かった。「女の子が東京の大学に進学して一人暮らしするなんて」と抵抗を覚える人は少なくなかった。
しかしいまは経済的に余裕がある親は娘を東京に出すことをいとわない。学生を見ていても、女性のほうが東京志向が強く、前のめりになって、どんどんチャレンジしているように見えます。
■「成功するとは限らない」けれど上京する
実際に、2023年の内閣府の調査でも、地元を離れて首都圏で就職した理由を〈職場となる地域に憧れがあったから〉〈私生活(趣味や娯楽など)を充実させたかったから〉と答えた割合は男性よりも女性のほうが高いという結果が出ました。
私は明治以降の上京をたどった『人はなぜ〈上京〉するのか』の執筆の動機をこう記しました。
時代ごとに人々の「上京」にこめた思いを、その背景と照らし合わせつつたどることで、この国の近代化の一側面を描き出していきたい
令和のいま。東京に行ったからといって、何か素晴らしいことがあるわけでも、みんながみんな成功できるわけでもない、という現実を経験則として知っています。けれど、それでも、上京せざるをえない。
上京は社会や時代、何よりもその人の生き方と切り離せません。だからこそ、令和の時代に込められた、それぞれの上京の思いが、きっとあるはずです。
プレジデントオンラインでは、「令和の上京」の体験者を募集しています。
本連載は、個々の上京を通して、令和という時代や、東京と地方の格差、社会の変容を浮かび上がらせる目的で取材を続けています。
取材をお受けいただける方は、生年や出身地、ご職業、上京の時期や動機、思い出やエピソードなどを添えて、右のQRコードのアドレスもしくは〈reiwa-jokyo★president.co.jp〉(★を@に変えてください)までお送りください。
----------
難波 功士(なんば・こうじ)
関西学院大学教授
1961年大阪市生まれ。1984年から1996年まで博報堂に在籍。1996年より関西学院大学社会学部教員となり、2006年より現職。現在「広告文化論」「ポピュラー・カルチャー論」といった講義を担当している。『社会学ウシジマくん』(人文書院、2013)、『就活の社会史』(祥伝社新書、2014)、『広告で社会学』(弘文堂、2018)ほか著書多数。
----------
----------
山川 徹(やまかわ・とおる)
ノンフィクションライター
1977年、山形県生まれ。東北学院大学法学部法律学科卒業後、國學院大学二部文学部史学科に編入。大学在学中からフリーライターとして活動。著書に『カルピスをつくった男 三島海雲』(小学館)、『それでも彼女は生きていく 3・11をきっかけにAV女優となった7人の女の子』(双葉社)などがある。『国境を越えたスクラム ラグビー日本代表になった外国人選手たち』(中央公論新社)で第30回ミズノスポーツライター賞最優秀賞を受賞。最新刊に商業捕鯨再起への軌跡を辿った『鯨鯢の鰓にかく』(小学館)。Twitter:@toru52521
----------
(関西学院大学教授 難波 功士、ノンフィクションライター 山川 徹 取材・構成=フリーライター・山川徹)