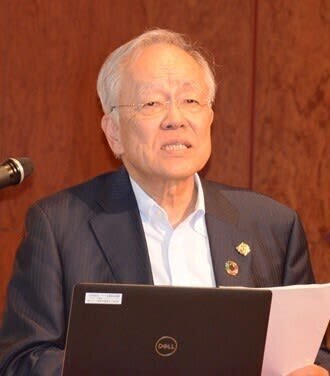だから政府や財務省への不満が高まる…「賃上げ」と言われているのに「生活が苦しい」本当の理由
2025年3月25日(火)16時15分 プレジデント社
財務省の外観=2025年2月4日、東京都千代田区 - 写真=時事通信フォト
■雇用者の7割が働く中小企業の賃上げが進まない
今年の春闘も大幅な賃上げで決着するところが増えている。連合が3月21日に発表した第2回集計結果によると、ベースアップと定期昇給を合わせた賃上げ率は5.40%と、昨年の第2回集計時の5.25%を上回り、34年ぶりの高水準を維持した。
一方で、組合員数300人未満の中小組合の賃上げ率は4.92%と5%に届かなかった。連合は今年の春闘では「5%以上の賃上げ」を要求すると共に、中小については「6%以上」の目標を掲げている。業績が好調な大企業の賃上げが進む中で、雇用者の7割が働く中小企業の賃上げが進まないことが大きな問題となっている。
総務省が発表した2月の消費者物価指数は、生鮮食品を除いた指数が前年同月に比べて3.0%上昇した。コメの価格が大幅に上昇するなど、食料品の値上がりが激しく、消費者の生活に打撃を与えている。
もちろん、数字の上では、物価上昇を上回る賃上げが実現しているわけだが、生活者の感覚としてはますます生活が厳しさを増している。いったいこれはどうしたことなのか。
写真=時事通信フォト
財務省の外観=2025年2月4日、東京都千代田区 - 写真=時事通信フォト
■人件費を価格に転嫁できていない中小企業
ひとつは大企業はともかく、中小企業や零細事業で働く人たちの給与がなかなか上がらないこと。連合の芳野友子会長も記者会見で「中小は労務費を含めた価格転嫁が重要だ」と述べていたが、大企業の下請け企業などが思うように納入価格を引き上げてもらえないという実態がある。値上げを受け入れてもらえても、原材料価格やエネルギーコスト分を上乗せするのが精一杯で、中小企業で働く人たちの人件費を価格に転嫁できていないわけだ。
そうは言っても人手不足の中で従業員を確保するためには一定の賃上げは必要で、ここ数年は中小企業経営者も賃上げを進めてきたが、そろそろ限界だという声も聞こえる。
政府は、発注者が不利な取り引き価格を一方的に決める行為を禁止することなどを盛り込んだ「下請け法」の改正案を3月11日に閣議決定した。発注者が受注者と協議をせずに受注者にとって不利な取り引き価格を一方的に決めることを禁止する内容で、物流業界での荷主企業と運送業者の間の委託業務も含めるとされている。
■賃上げ分がそのまま手取り賃金の増加にはならない
現実には発注者側が提示した価格を受け入れなければ、仕事をもらえないという力関係にある中小企業が圧倒的に多く、この法律がどれだけ効果を生むかは不明だ。さらに、この改正法案では「下請事業者」という言葉を「中小受託事業者」に、「下請代金」を「製造委託等代金」に変えることが盛り込まれているが、「下請け」という言葉を無くしたからといって「下請け」が消えるわけではない。中小企業庁や公正取引委員会が躍起になって下請けイジメの撲滅に力を注いでいるが、人件費分まで含んだ価格の引き上げはそう簡単ではない。
また、こうした価格転嫁ができたとして、大企業はそれを最終価格に転嫁するわけで、そうなると物価上昇に弾みがつくことになる。賃上げをしても物価上昇がさらに進めば、生活は楽にならない。
もうひとつ、大きな問題が、賃上げ分がすべて、可処分所得つまり手取り賃金の増加に結びつかないことだ。
写真=iStock.com/PeopleImages
※写真はイメージです - 写真=iStock.com/PeopleImages
■「子ども・子育て支援金」に「防衛特別所得税」
岸田文雄前首相が目玉政策として掲げた「子ども・子育て支援金」の原資は社会保険料へ上乗せすることに決まっていて、2026年度に月額平均250円、2027年度に350円、2028年度以降450円が上乗せされる。これはあくまで平均額で、会社員などは2028年度に月800円、年間1万円近くの負担増になる。しかも同額を雇用している企業なども負担することになっている。
当時の岸田首相が、賃上げで所得が増えるので、実質的に負担は増えない、と強弁していたのが記憶に新しい。賃上げ分が社会保険料に回ってしまっては、一向に生活が豊かになるどころか、物価上昇の影響をモロに受け続けることになる。
さらに、5年間で43兆円という防衛費を賄うための増税も決まっていて、2027年1月からは「防衛特別所得税」が課される方向だ。所得税に1%の付加税を課す一方で、時限的に導入されてきた「復興特別所得税」の税率を1%引き下げ、課税期間を延長することとなっている。つまりは、1%の付加税がほぼ恒久的に続くということだろう。加えて、たばこ税の段階的増税も予定されている。
■「国民負担率」がなぜか低下した理由
国民の負担はどんどん増えているわけだが、これを示す数値がある。「国民負担率」というもので、租税負担と社会保障負担の合計が国民所得の何%を示すかという指標だ。毎年2月に財務省が公表しているが、今年は予算成立が遅れた関係か、3月にずれ込んだ。
実は、その「国民負担率」の2023年度の実績数値が8年ぶりに低下した。46.1%と、過去最高だった22年度の48.4%から低下したのだ。前年と同率だった年度はあったが、低下したのは2015年度以来だ。毎年、国民負担率が過去最高を更新し続けてきたことを考えると、画期的な出来事だと言える。
だが、どうして負担感が増えているという消費者の感覚とは食い違った数値が出てくるのか。このズレは何が原因なのか。
前述の通り、国民負担率の計算は分母が国民所得、分子が租税負担と社会保障負担だ。率が低下するには分子が小さくなるか、分母が大きくなるか、2通りの要因があり得る。
実は、2023年度の実績で、国民所得は409.6兆円から437.8兆円に6.8%も増えているのだ。つまり分母の国民所得が大きく増えたことで、国民負担率は低下したのである。
写真=iStock.com/takasuu
※写真はイメージです - 写真=iStock.com/takasuu
■「国民所得」には企業の所得も含まれる
決して分子の租税負担と社会保障負担が減ったわけではない。租税負担は120.4兆円から122.1兆円に1.4%増加、社会保障負担も77.8兆円から79.6兆円に2.3%増えている。租税負担と社会保障負担の合計では198.2兆円から201.7兆円に1.7%、金額にして3.5兆円増えているのだ。つまり、国民負担「率」は低下したが、国民負担「額」は増えたということだ。3.5兆円と言えば、消費税1.5%分に相当する。
もうひとつマジックがある。「国民所得」は個人の所得だけでなく企業の所得も含まれていることだ。企業の儲けが増えても、その分給与が払われなければ、見た目の国民負担率の低下と個人の実感はかけ離れたものになる。企業収益の何%を給与として払っているかを「労働分配率」と言うが、これは低下を続けている。
■高まる政府や財務省への不満
東京・霞が関の財務省の前には連日のように「財務省解体」を叫ぶ人々が集まる。その数は増え続けて1000人を超える規模になっている。SNSでの呼びかけが徐々に広がっていると見られるほか、亡くなった森永卓郎さんの著書『ザイム真理教』の影響もあると見られている。物価の上昇で人々の生活が厳しさを増している一方で、社会保障費の増額や増税を着々と進める政府・財務省への不満が高まっているのは間違いない。
物価が上昇すれば、同じものを買っても支払う消費税は増える。財務省にとっては物価上昇は税収増につながる追い風とも言える。本来は消費が落ちないように減税するなど対策を取るが、一部の野党が主張する消費減税などには一向に応える様子はない。「103万円の壁」引き上げやガソリン税の引き下げを求める国民民主党が大きく支持を伸ばしたのも、共通の「怒り」があるように見える。
賃上げをするかどうかは本来、企業自身の問題で、政府が口を出す話ではない。「官制春闘」と言われて久しいが、政府が民間の賃上げに頼る一方、社会保障費増や増税に動くのは、政府として無策に等しいのではないだろうか。
----------
磯山 友幸(いそやま・ともゆき)
経済ジャーナリスト
千葉商科大学教授。1962年生まれ。早稲田大学政治経済学部卒業。日本経済新聞で証券部記者、同部次長、チューリヒ支局長、フランクフルト支局長、「日経ビジネス」副編集長・編集委員などを務め、2011年に退社、独立。著書に『国際会計基準戦争 完結編』(日経BP社)、共著に『株主の反乱』(日本経済新聞社)などがある。
----------
(経済ジャーナリスト 磯山 友幸)